近年、音の表現がこれまでにまして多様になってきています。かつては音の表現といえば、レコードやCDのジャケット、さらにはミュージックビデオのような映像が主でした。しかし、それだけにはとどまらず、工場の音を視覚化した「INDUSTRIAL JP」のような表現、また音楽をさまざまなな構造物として取り上げた「音のアーキテクチャ」のような展覧会、さらには音と美術の領域を行き来して表現するアーティストたちの活動の活発化など、その表現には広がりが生まれています。なぜ今、こうした形で音の映像・ビジュアル表現に新しい兆しが見られるようになったのか。
今回、クリエイティブディレクター 木村年秀さん(DJ MOODMAN)、蛍光灯の楽器「オプトロン」を自作して、演奏するアーティスト 伊東篤宏さん、そしてライブストリーミングスタジオ「DOMMUNE」を運営する宇川直宏さんが「体感」ということをキーワードに、いまに至る音の表現について話をしました。

Photo:parade/amanagroup for BRAIN

解像度と計算速度が起こした革命
宇川:アートと音楽の領域を横断するアーティストが増えたり、そのような活動が活発になっていることの背景には、モニター、そしてプロジェクターの進化があると思います。つまり映像は同じく時間芸術なので音楽と大変相性がよいのは自明ですが、映像のキャンバスにあたるモニターの画素密度が歴史上考えられない速度でUPDATEされた。僕は2010年からライブストリーミングスタジオ「DOMMUNE」をはじめ、巷では2011年がアナログから地デジへの放送フォーマットの完全移行ですが、それ以前、映像作家はキャンバスの段階で、画家や彫刻家に負けていたんです。地デジ以前は当然アナログで640x480ピクセルがそのキャンバスの解像度です。では、絵の具側はどうか?その後、CANONのEOS 5D Mark II移行、フルハイビジョン(1920x1080ピクセル)で一眼レフを使って動画が撮影できるようになり、そこから急速に進化して35ミリフィルムで撮影した劇場映画と同クオリティを、家電テクノロジーで撮影できるようになりました。並行で、テレビモニターの解像度が急激に上がり、液晶プロジェクタの解像度も4Kから8Kに変わりました。8Kつて7680x4320ピクセルですよ。1953年の地上波テレビ放送開始から、65年が経過しましたが、それまで58年間進化しなかったのに、ここにきてたった7年間で解像度が10倍。つまり2011年以降、過去の劇映画クオリティを優に超越した世界をデスクトップで編集できる時代になったんです。
木村:編集ソフトも速くなりましたからね。
宇川:2010年以前は映像の解像度を上げるにはビデオでもフィルムでも多額の予算がかかったので、非常にハードルが高かった。だから急激に映像がパワーを持つようになり、計算速度と解像度を最大限に使ったクリエイティブとして、チームラボやライゾマティクスのようなキャンバスを超えたマルチプロジェクションとしての空間表現が生まれました。
そして今、映像は誰もが手軽に利用できる、いい意味でも悪い意味でもコンビニエンスな表現になっている。もはや、映像業界こそがファミリーマートです(笑)。だからチームラボに驚異的な動員があるのです。
木村:計算速度。解像度。テクノロジーの進化が、今さまざまなシーンで求められている体感性の高いコンテンツを可能にしています。それが、ライブの価値が上がっている世の気運とも合致しています。
伊東:でも体感でいうと、映像は人間の限界値を超えていますよね。秒速で動いているものを人間が把握する速度よりも、映像ではさらに速くクリアに撮ることができます。それを僕らは普段から見ているのだけれど、実際には見たことがなくて、それを映像を通して見ている、ということになっていますよね。
宇川:そうなんです。さらに言えば、VRの奥行きがAR、MRと広がっていて、MRでは現実と非現実の世界が混然一体化して空間に浮かび上がるので、現実だろうが、バーチャルだろうが体感値さえ変わらなければそこにヒエラルキーはないという表現が生まれています。その表現軸を日々研究しているのがデジタルネイチャーというマニュフェストを掲げる落合陽一くんです。映像の世界は終焉を迎え、環境に溶け込んだメディアが偏在する「魔法の世紀」が訪れると彼は論じています。
例えばそこに脚立が置いてありますけど、本当にあるかどうかなんてどっちでもよくて、目に見えているから「ある」と体感すればいい、しかし反面、足をかけると魔法は解けて脱臼する(笑)。
木村:その変化の中で「音」がフィーチャーされています。その理由として、音に関するテクノロジーが先んじて進化し、浸透していたことも大きいのではと思います。
伊東:音は芸術の中でも商用的な使い方が当たり前にあるものだから、ソフトやデバイスが充実し、映像と同じで誰でも扱えるコンビニエンスなものになってきました。
宇川:MOODMAN(木村さん)が始めた町工場音楽レーベル「INDUSTRIAL JP」と伊東さんが自作した蛍光灯の楽器「オプトロン」の活動は、まさにそういう背景もあって生まれてきたものじゃないかと思っていますよ。
木村:「INDUSTRIAL JP」は、日本の町工場をクリエイティブの力で盛り上げるという目的から始まりました。これまで町工場の活動を紹介するとき、その多くは匠の技や人情の世界、つまり人から技術を伝えていくというストーリーを描きます。このプロジェクトのアプローチはその逆で、技術のコアをまず体感してもらう。体感から、町工場への興味を引き出そう、と考えました。
伊東:素晴らしいですよね。僕は自分を匠とは言いませんが、人間スタート、人間発信で、オプトロンを使ったパフォーマンスを続けています。今、木村さんが言ったことは、近くに行って見なければ体験できない匠の世界を音楽と合わせることで、今まで僕らが知らないところにまで広げて見せている。一般に「マルチメディア」と言われているものって、つまり本来はそういうことですよね。
木村:映像と音楽。一つひとつのコンテンツの体感性を高めることと並行して、このプロジェクトではコミュニケーションの構造自体についても体感性を高めたいと考えました。そこで、音楽レーベルという仕組み、受け手との接点を提案しました。
宇川:INDUSTRIAL JPのプロジェクトメンバーに、下浜臨太郎くんがいますよね。彼が2014年に文化庁メディア芸術祭で受賞した「のらもじ発見プロジェクト」は、地方都市のストリートにあふれている無名の文字職人=フォント・グラファーが描いた野生の看板文字、つまり"野良文字"を保護し、後世に残すという運動です。
彼はこれを柳宗悦以降の「民藝運動」と呼んでいて、野良文字をトリートメントしてフォント化。そしてネット上で配布し、そのフォントを使ってデザインした商品から得た収入を商店街に還元しました。だから、INDUSTRIAL JPに彼が関わっている理由は文脈としてすごく理解ができて、つまりストリートとサイバースペースを接続し、全く新しいエコシステムをつくろうとしているんですよね。
同じようにINDUSTRIAL JPは昭和の高度経済成長期から止まることなく働き続けて、我々の生活を支えてくれた機械の声に着目し、それを現代のテクノDJが解体して、楽曲として再構築してという"ポスト・ポストモダン"なプロジェクト。ここでも近代的な物語の解体と、現代的な再構築が行われ、新しい生態系のようなものが生まれている気がします。
木村:下浜くんをはじめ、各メンバーが各自のフェチを体感化させていくプロジェクトと言えるかもしれません。
TOSHIHIDE KIMURA'S WORKS
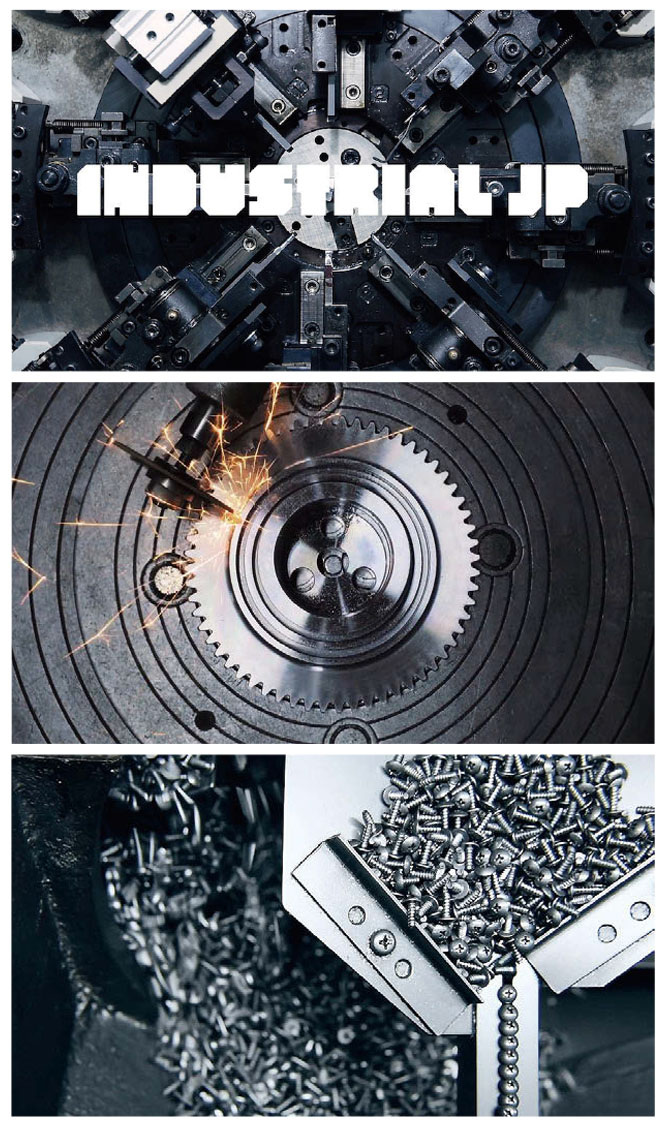
日本の町工場をレーベル化するプロジェクト「INDUSTRIAL JP」町工場の緻密な製造過程から生み出されるノイズを、気鋭のトラックメーカーがリミックスし、ミュージックビデオとして作品化。

「INDUSTRIAL JP」DJ NOBU×東洋化成
レコードの制作過程から生み出された音を再構築した7インチシングル。レコードストアデイ限定。初のアナログリリース。

DJ MOODMANミックスCD「SF」
アートワークはby Will Sweeney。
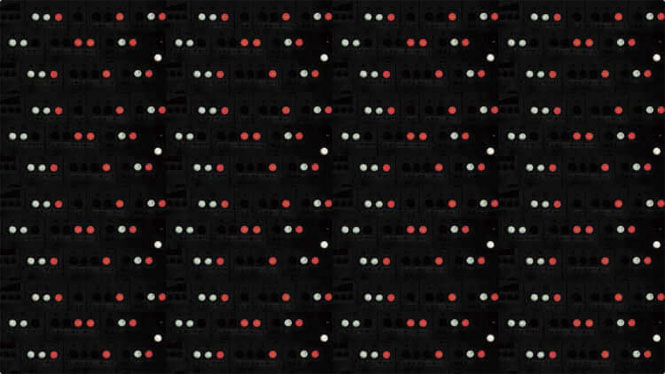
「INDUSTRIAL JP」新栄工業×DJ Gonno
PENとのコラボによりリリースされた、フランスの気鋭トラックメーカーVOISKIによるRemix VerのMV。

DJ MOODMANリミックスワーク「OGRE YOU ASSHOLE/SOMEONE'S DREAM」(7インチシングル)

マガジンハウス70周年記念事業のひとつとして行われた雑誌「relax」復刊プロジェクトを企画。クリエイティブ・ディレクションを担当。

「relax」復刊プロジェクトのプロジェクトムービー。音楽はpepe California。

DJ MOODMAN リミックスワーク「うつくしきひかりと惣田紗希」(7インチシングル+ブックレット)

総勢30人のDJがレコードのみでクラシックを演奏したテクニクスのWebMovie「THE PHILHARMONIC TURNTABLE ORCHESTRA」。サウンドディレクターを担当。
アートとコマーシャルのバランス
宇川:インダストリーという意味において考えると、第一次産業革命が蒸気、二次が電気、三次がコンピュータ制御のオートメーション、四次が人工知能とインターネット、IoTで、現代は「インダストリー4.0」と言われていますよね。
そしてAIが人間の仕事を担っていき、この産業革命の最果てとして政府が国民に最低限の生活に必要なお金を定期的に支給するという所得保障、ベーシックインカムの文脈がありますね。この第四次産業革命はもうはじまっていて、さらに進んでいくと、人間の職業の49%はAIに代替可能と聞きます。そこで人間は何をするかというと、労働でも仕事でもなく、ようやく「活動」をできる時代が来ると。
伊東:予定ではね(笑)。これだけ情報流通が高速化して、データの圧縮率が上がった今、その目的って何だったの?と考えると、宇川さんが言った「活動する時間を増やすため」だったはず。でも、僕らは一向に活動時間が増えているとは思えないけれど。
宇川:僕は2010年から過去のキャリアをすべて絶って、全仕事をほぼ停止しました(笑)。そこで2010年にライブストリーミングスタジオ「DOMMUNE」を開局したわけですが、これは紛れもなく仕事ではなく活動です。だから現在僕の24時間/365日は、9割が活動で、1割しか仕事をしていない状況。つまり全くマネタイズしてないから開局以来8年間赤字の、大量出血ストリーミングです(笑)。しかし、お陰様でイノセントな人生観を垣間見れ、大変人間味にあふれた社会貢献ができています。
伊東:僕は活動が5、6割かな。そのマネタイズを超えたところが重要だと思っていて、それは単純に「人生お金じゃないよ」という安っぽい意見ではなく、そこについてはもう少し真面目に考えるべきだと思っています。マネタイズできないもので活動と繋げて考えるのは基本的にはアートの文脈で、日本でも以前は酔狂な人たちがお金を出して何となくできていた文化圏が、今ではほとんど消えていますからね。
宇川:本当ですね。DOMMUNEの活動はアートとコマーシャルのバランスを考えるための思考実験でもあって、僕が日常やっていることの半分は地下広報活動、半分は"ファインアート"です。INDUSTRIAL JPのすごさは全くセルアウト(売れ線)せずに純度を高めているところ。感動しました …



















