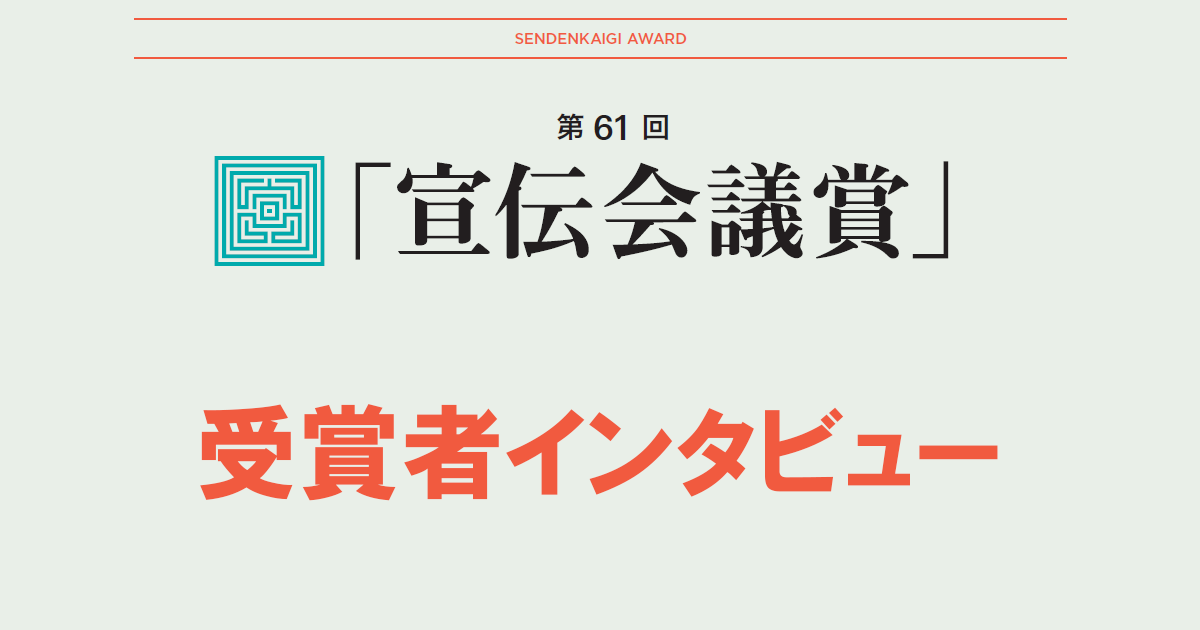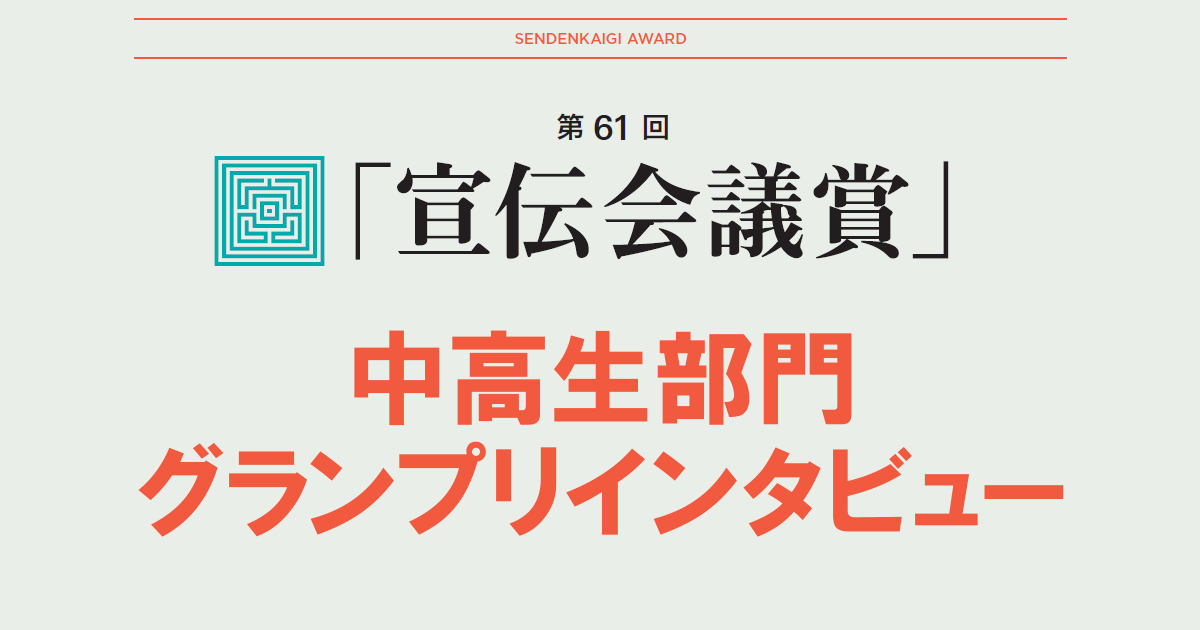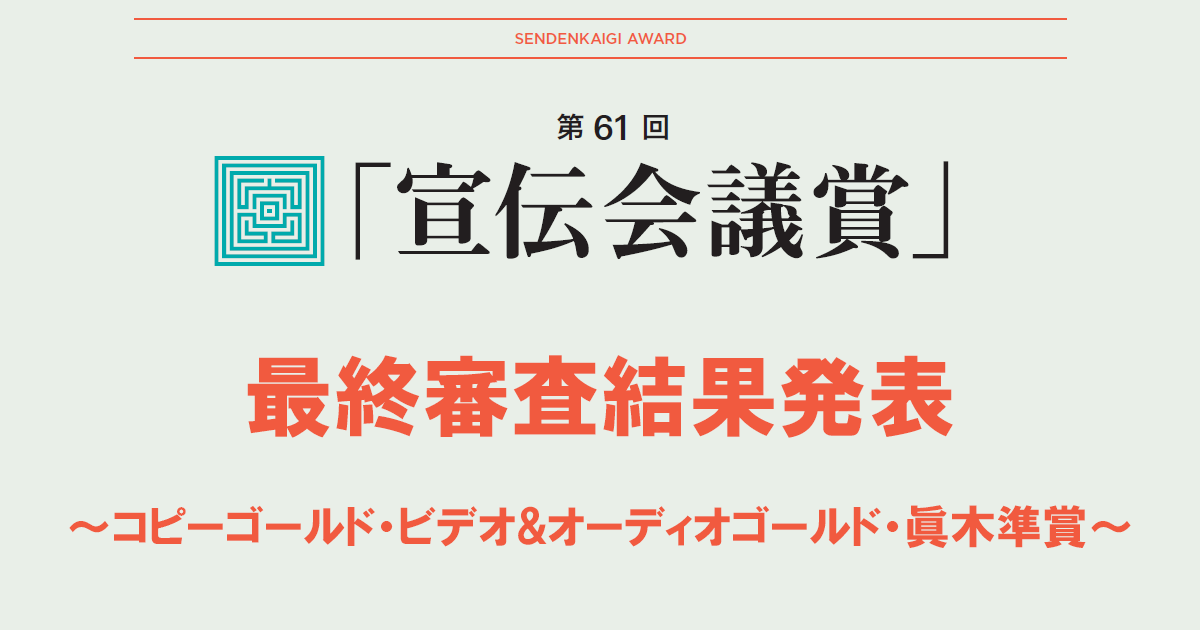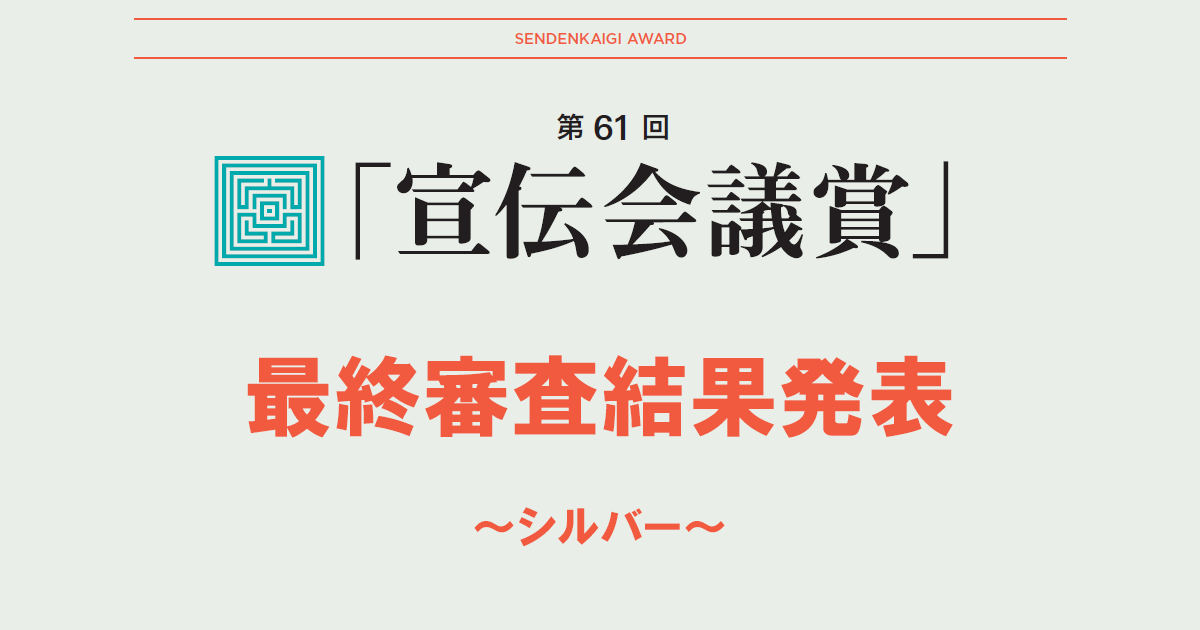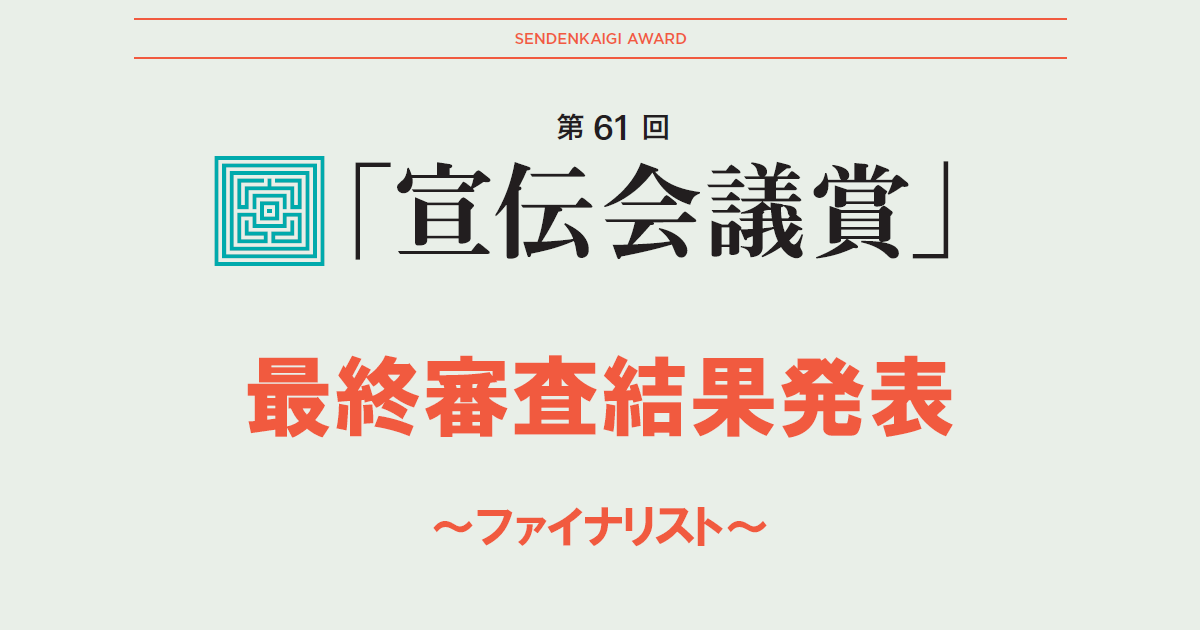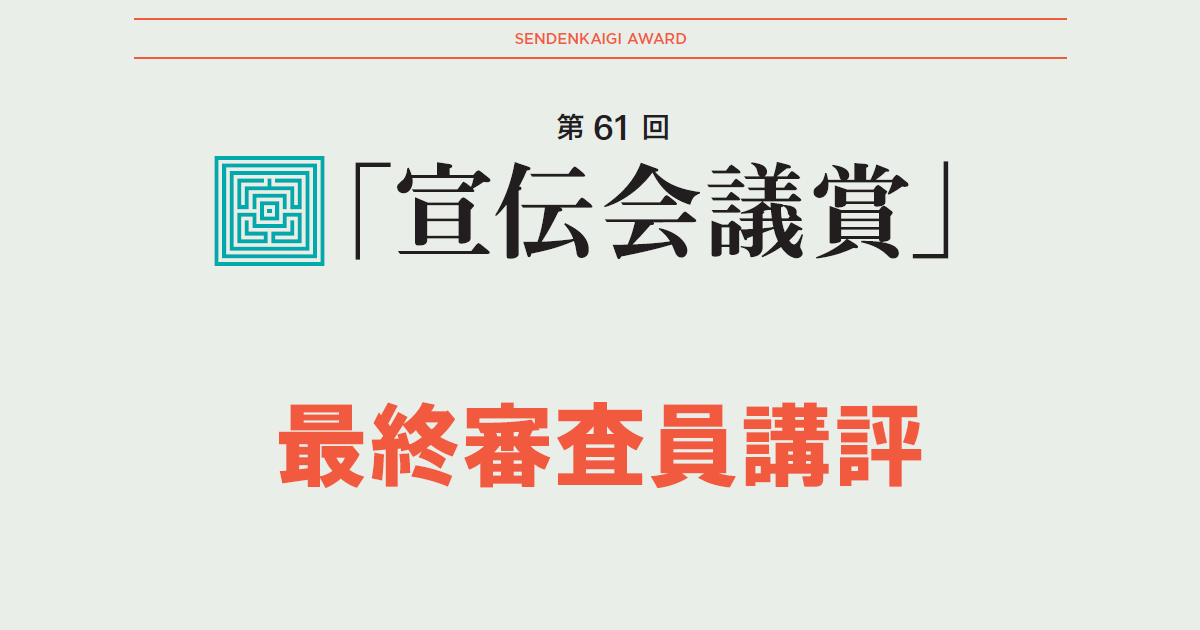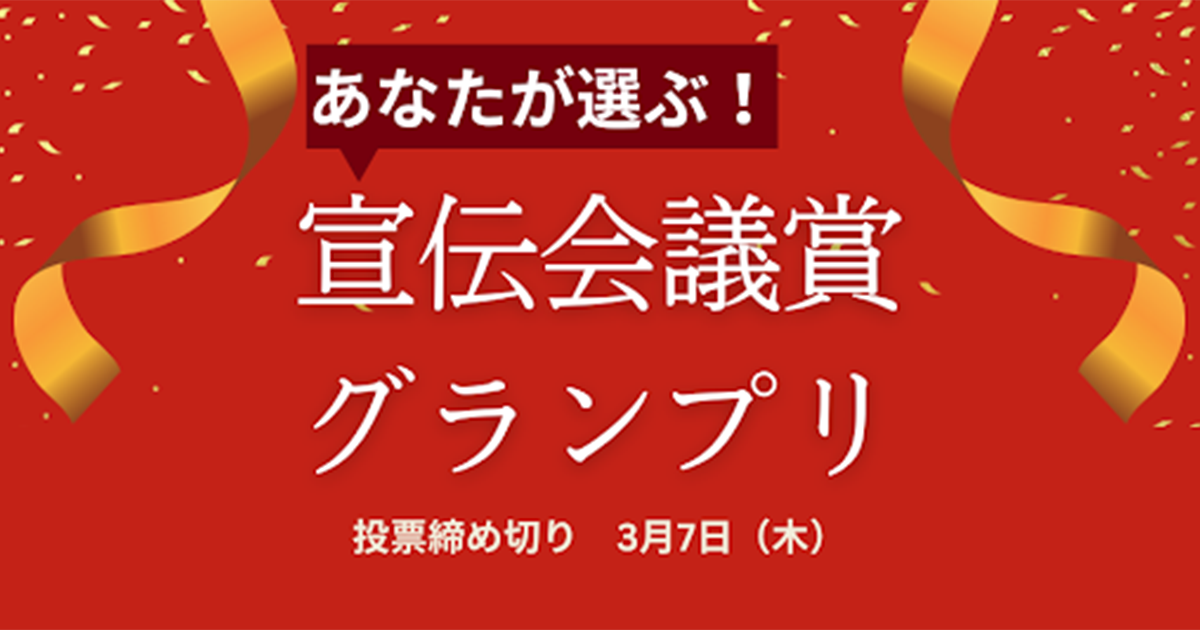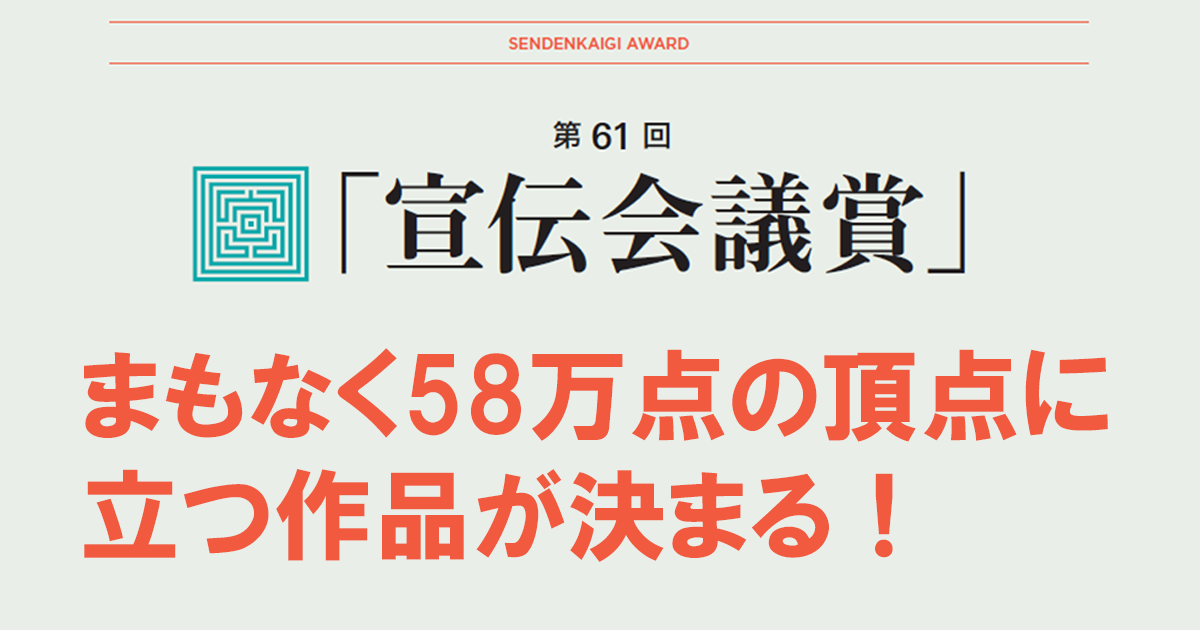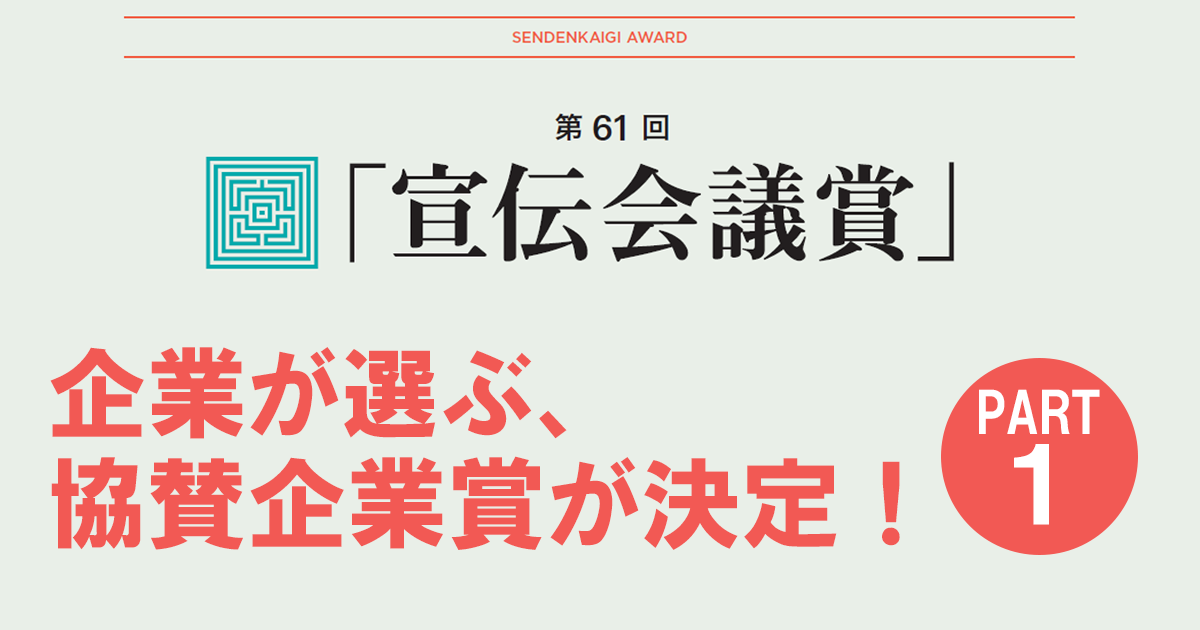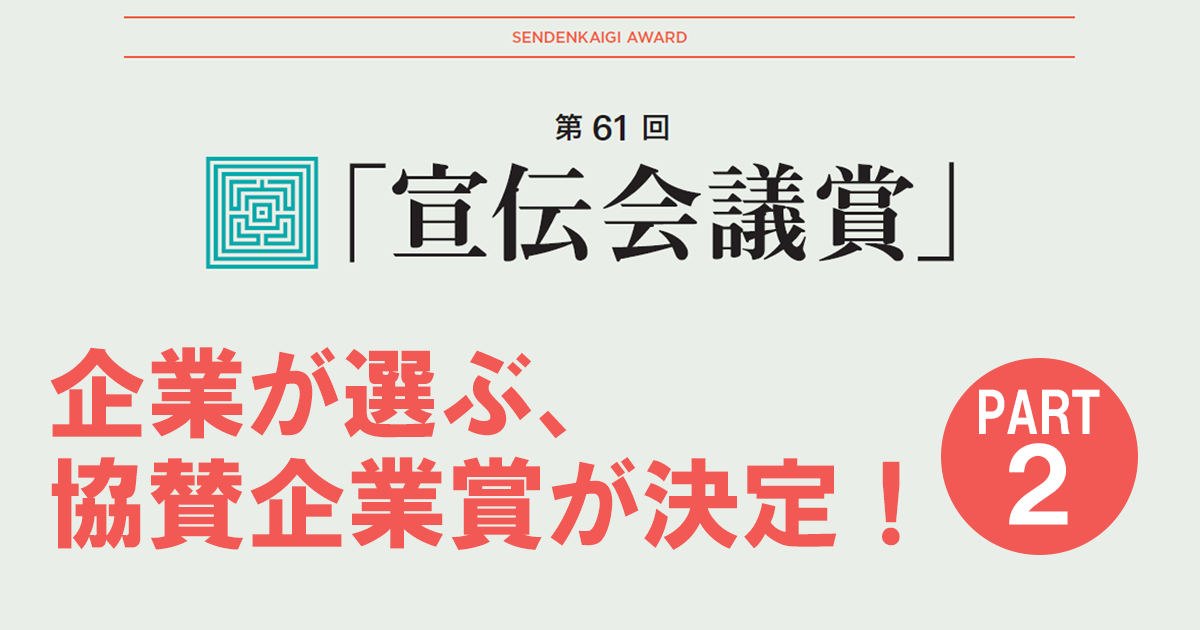3月8日に行われた第61回「宣伝会議賞」の最終審査会。グランプリには、赤ちゃん本舗の課題に対する、貝渕充良さん、森脇誠さんのコピー「泣く子と育つ。」が選ばれた。過去にない2名同時のグランプリ受賞。コピーが生まれた背景や今後の展望について聞いた。




“社会が子どもと一緒に育っていってほしい、
という想いを込めました。”
“「母親目線」というのは一切やめよう、
ということは最初に決めていました。”
10年前にファイナリストに選ばれもっと上に行きたいと思った
―改めて、受賞への想いを聞かせてください。贈賞式で名前を呼ばれた時、どのような気持ちでしたか。
貝渕:とにかく驚きました。嬉しかったのはもちろんですが、「宣伝会議賞」には20年近く取り組んできたので、やっと終われる…という想いもありました。
森脇:私も最初の応募から24年くらい経ちました。応募を始めた当時はコピーライターとして働いていましたが、今は別の仕事をしながら趣味として続けていたんです。楽しみながら毎年挑戦していたので、貝渕さんと同じようにようやく終わったという安堵と、終わってしまったという寂しい気持ちもあります。
―これまで「宣伝会議賞」にはどのように取り組んできましたか。
貝渕:この20年間で、「宣伝会議賞」を始めとした広告賞に共に取り組む仲間がたくさんできました。だから、なかなかやめられなかったのですが(笑)。ひとつの転機は、10年前にファイナリストまで選ばれた時。…
あと81%