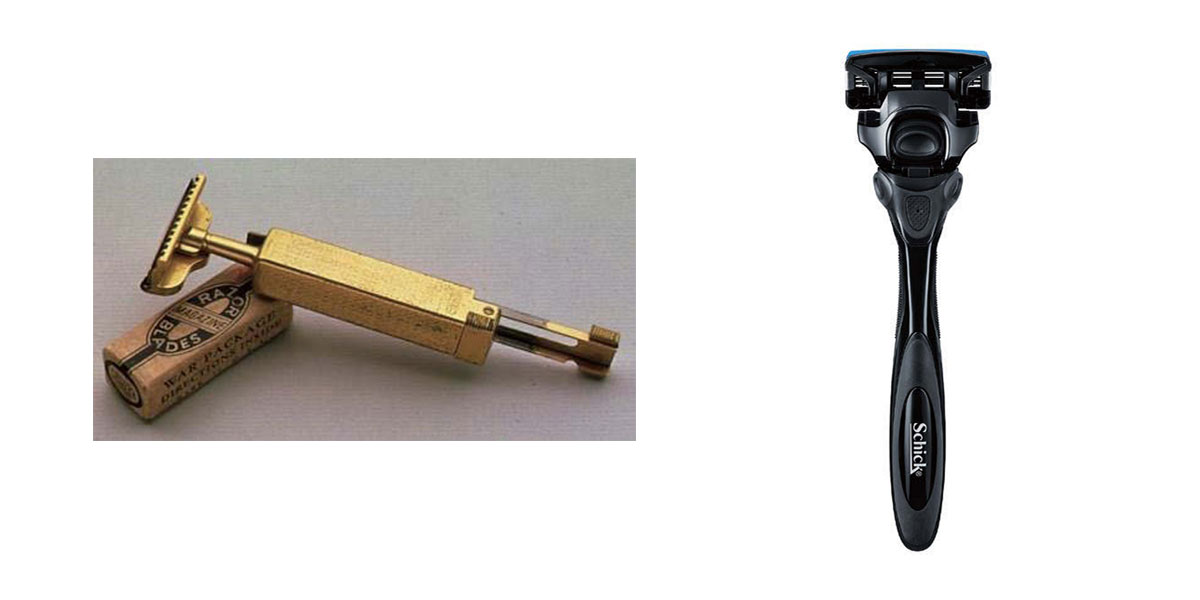(左)1971 (右)2021
1971年9月に森永製菓が販売を開始したチョコレートブランド「小枝」は、2021年で50周年を迎えた。
1970年に社員が出張でヨーロッパに訪れた際に出会ったイギリスのお菓子から着想を得て開発された小枝。当時の日本は工業化の反動で環境問題が深刻化しはじめた時代であったことから「高原の小枝を大切に」というスローガンのもと発売された。
発売時、チョコレート菓子で和名の商品は市場に少なく、社内では「和名で大丈夫なのか」との声もあがったというが、珍しさが逆に話題に。同社ではその後、「栗」や「森のどんぐり」といった和名をネーミングに使用するケースも増え、小枝はその先駆け的な存在となった。
50年愛されてきた小枝の魅力について、ブランド担当の信田直毅氏は食感と形状にあると考えを話す。
「小枝の強みのひとつは2種類のパフとアーモンドによる独特な食感。もうひとつは、枝の形です。この50年間、同様の形状のものはほとんど発売されていません。多くの具材を入れて、細長い形に加工するには特殊なノウハウが必要」と信田氏。小枝も発売当初は、手作業と言っても過言ではないほど製造に苦労をしていたが、改良を続け品質・製造効率ともに向上させてきたという。
小枝の主なターゲットは30〜50代の女性。このターゲット層を中心に考えつつ、男性や若年層の新規顧客も取り込むため、50年の間に小枝では様々な商品ラインナップの拡充をしており、期間限定フレーバーのみでその数は150種以上にものぼる。
そんな小枝が現在、注力しているのがブランドとしてのサステナブルな取り組み。50周年キャンペーンでも、「レッツ サステナブル」をテーマにキャンペーンを展開している。
「このような取り組みは、一過性では意味がないもの。50周年をきっかけに今後、継続的に発信をしていきたい」と信田氏は構想を語った。
視点01 ラインナップ・パッケージ
時代に応じた拡充により愛され続ける存在に
1978年から2001年においては、画家の笹倉鉄平氏がパッケージイラストを手掛けていた歴史も持つ小枝では、1979年の「白樺の小枝」、1985年の「メープルの小枝」を皮切りに、多くのフレーバーを展開。また、フレーバーの拡充のみならず、時代に応じてパッケージや包装形態においても変化・拡充を続けてきた。
これまでに「箱タイプ」「ティータイムパック」「小袋」「バータイプ」などを販売しており、信田氏は、このようなラインナップの拡充も、小枝がロングセラーブランドとなった要因ではないかと話す。
「メインユーザー層の30〜50代の購入に加え、直近では...