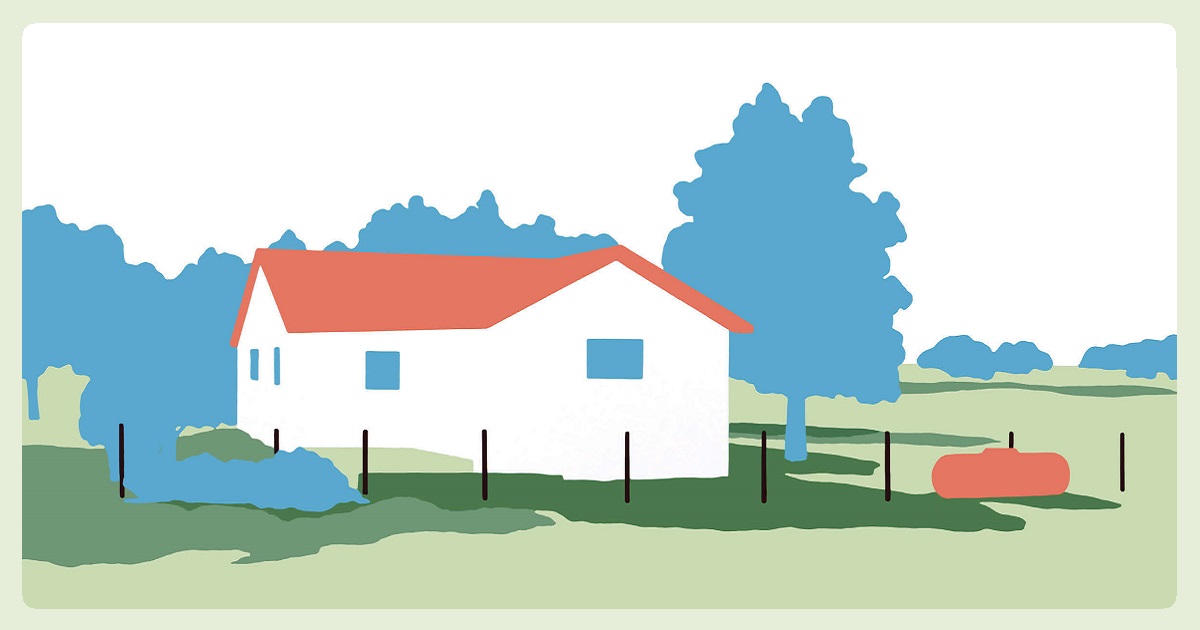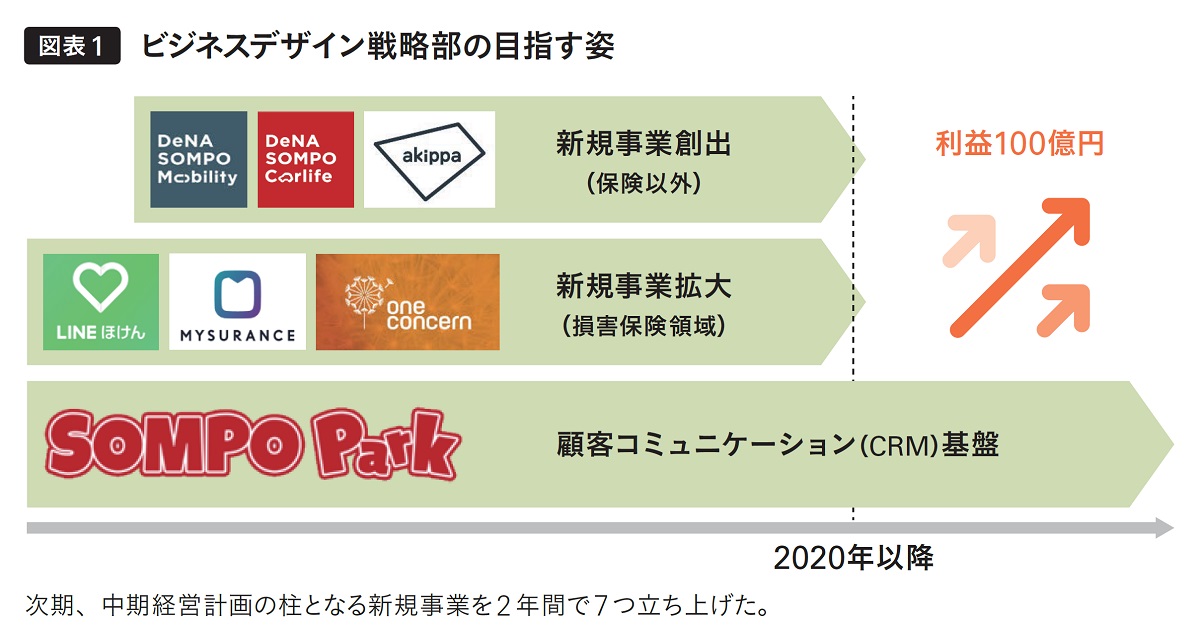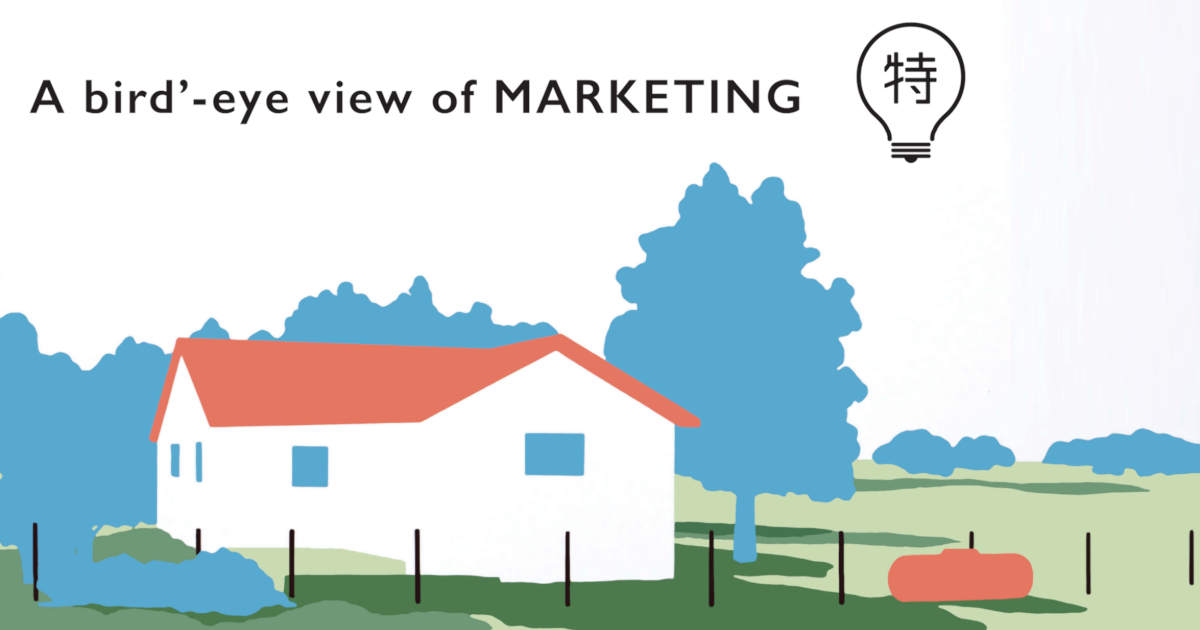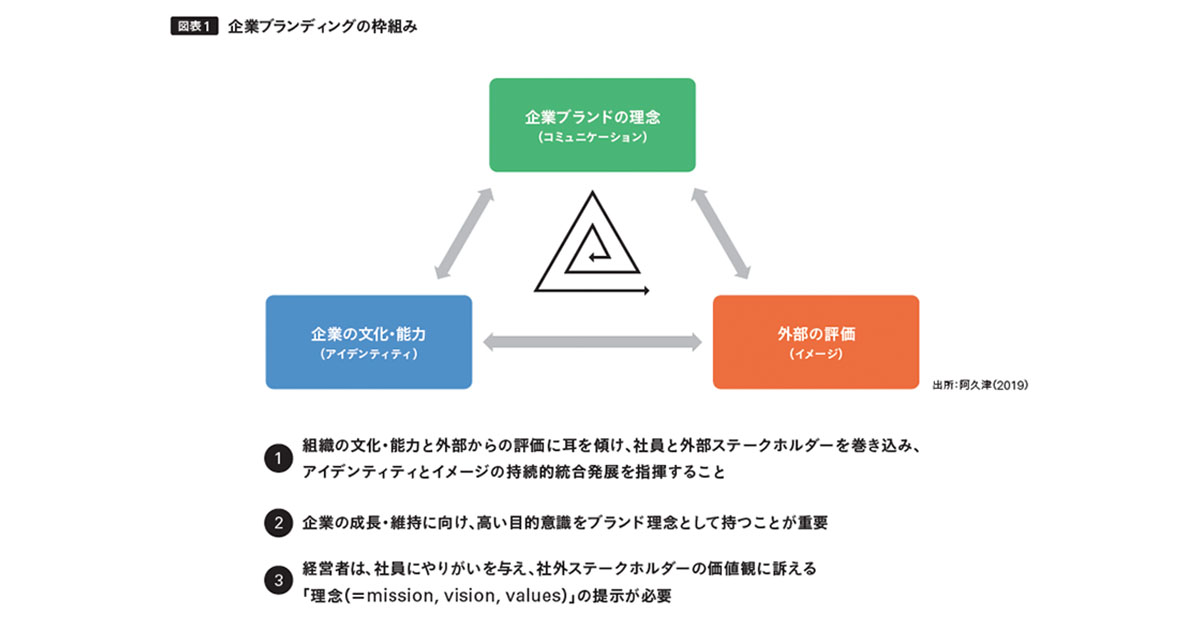マーケティング実務に携わりながら、京都大学大学院経営管理大学院博士課程で研究を行い、さらに社会情報大学院大学の客員教授を務め、マーケティングのみならずパブリック・リレーションズにも精通する高広伯彦氏。多様な視座から企業のコミュニケーション活動を考察する同氏が、いま考えるマーケティングの全体知とは?
課題が発生したとき、人々はなぜ「検索」できるのか?
課題発生時に人々はその課題解決の方法を見つけようと「検索」するのだということが、GoogleがZMOTという概念を発表して以降知られています。しかしその「検索」に用いた言葉はどこから来たのでしょうか。
おそらく検索の前段階で、人々は何かしらの「文脈」に基づき、関連する言葉を思いついているのだろう、と推察されます。
この文脈は人々の知識や経験によって編み上げられているものと考えられますが、その文脈があるからこそ、検索に必要な言葉が思い浮かび、さらには商品・サービスの価値が判断できると言える。そう考えると、文脈が構築されるに至る、人々の「学び」のプロセスを理解し組み込むことが、次の購買行動モデルを考える上で必要でしょう。
この、文脈にまつわる問題は購買行動モデルを考える時のみならず、マーケティング・コミュニケーションやパブリック・リレーションズなど、企業のコミュニケーション活動すべてにおいて意識すべきことです。
例えば、広告の炎上案件を観察していると、メッセージの送り手と受け手の間における「文脈」の違いから生まれる「齟齬」が要因となっているとも考えられます。情報の送り手と受け手の間で、共有できる経験や知識(文脈)があれば、コミュニケーションは円滑になるはずなのです。
例えばP.F.ドラッカーはコミュニケーションのあり方に関する記述で「大工と話をするときは大工の言葉を使え」というソクラテスの言葉を引用し「相手の言葉を使って話をすること」を指摘しています。そしてこの時に使われる言葉は、経験をベースにしたものでなければ、適切には受け取られない可能性が高く、つまり、完全なコミュニケーションにおいては「共有体験」が必要だと説いています。
ドラッカーの指摘は、経営マネジメントにおける人と人とのコミュニケーションの話ではありますが、企業活動としてのコミュニケーションにおいて、関係する企業や人々における文脈、および相互の関係において共有される文脈については、同様の注意を払う必要があるでしょう。
顧客側のナレッジがなければ価値は提案できても創出できない
このように考察を進めていくと、企業の文脈と顧客の文脈が交わるところに「価値」が発生しているといえるのではないかとも考えられます。こう考察するに際しては「サービス・ドミナント・ロジック」の視点が参考になります。
サービス・ドミナント・ロジックとは...