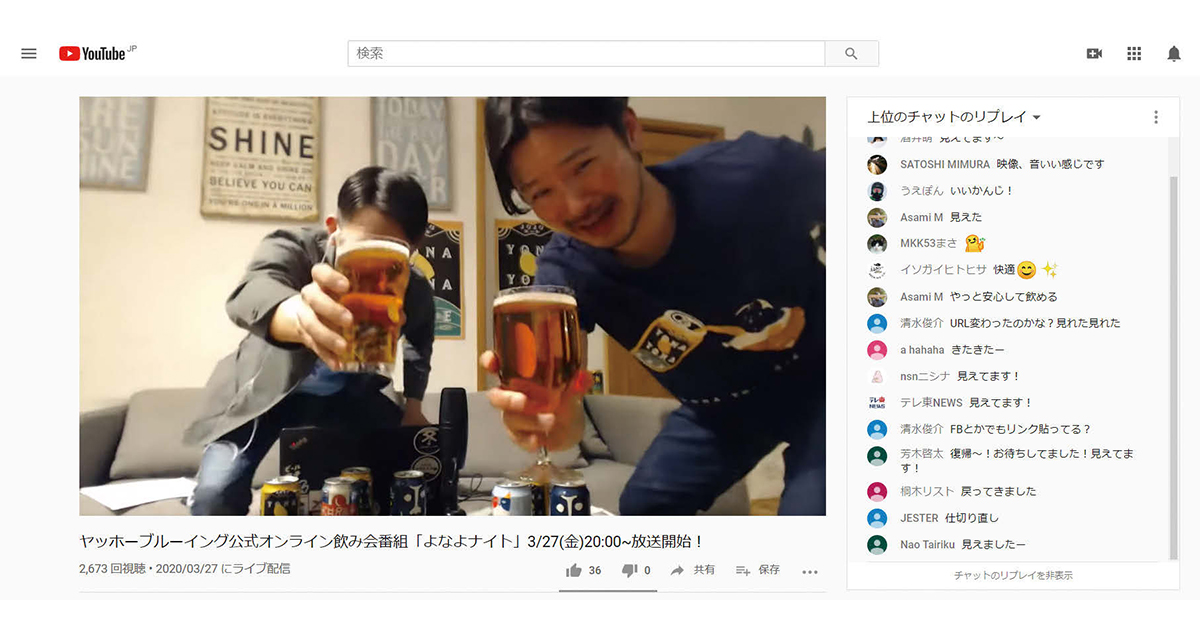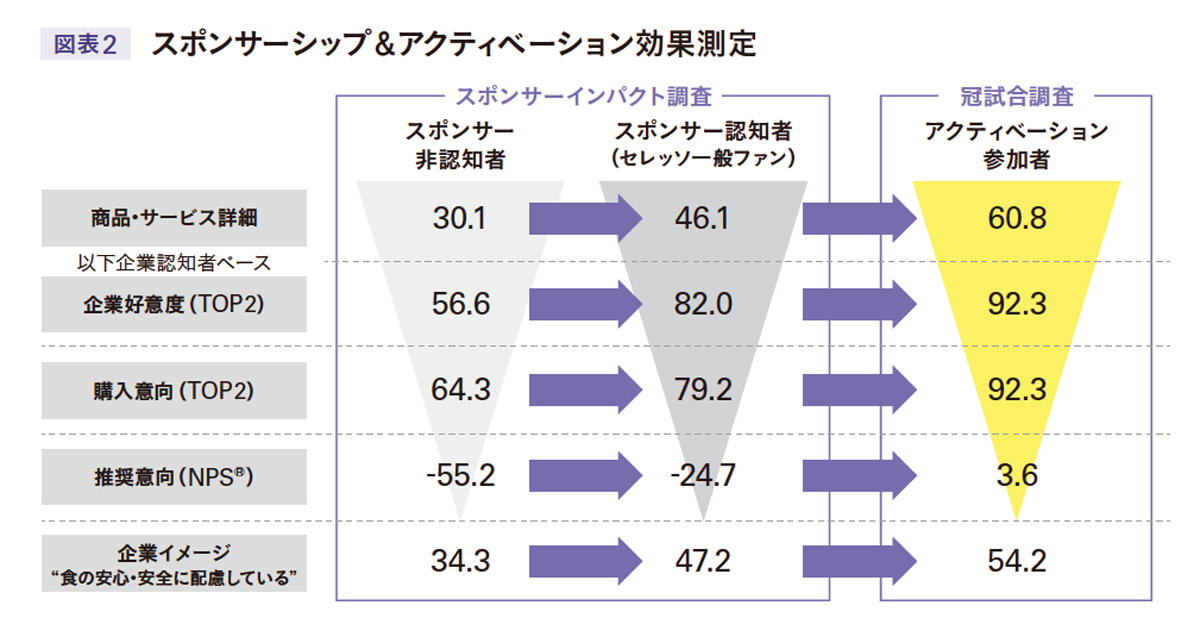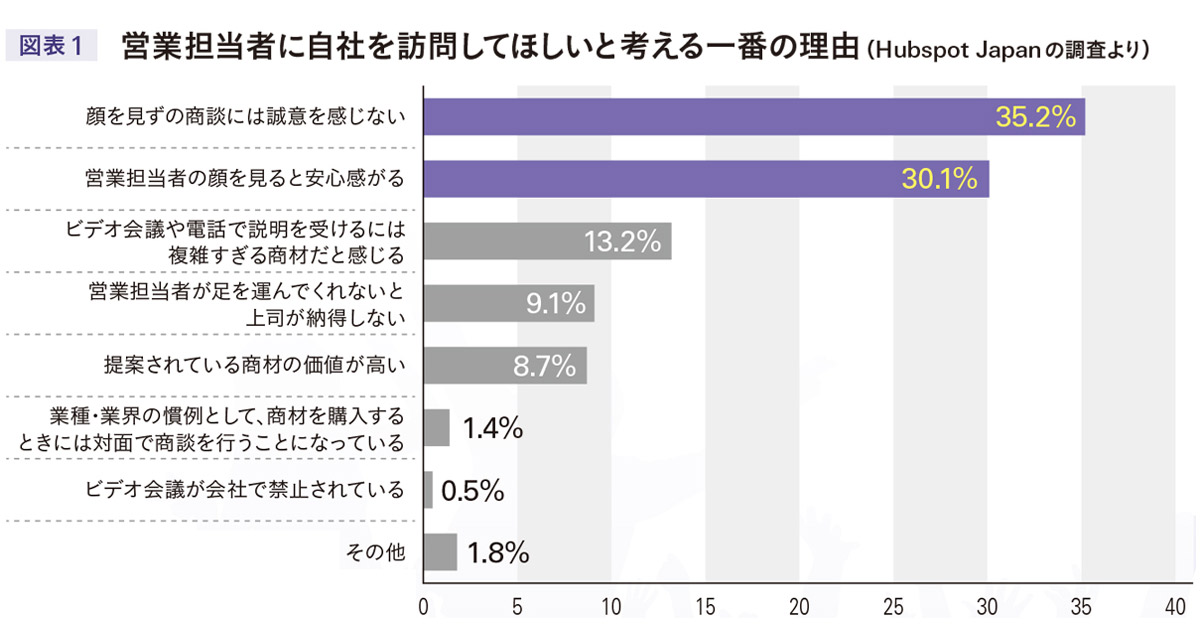新型コロナウイルスの感染拡大の影響下、仕事においても生活においても非対面でのコミュニケーションが急激に浸透しています。テクノロジーの活用で「リアル」を超えるコミュニケーションは、今後さらなる進化があるのでしょうか。VRやARを専門とするプロジェクト「hakuhodo-VRAR」を牽引する須田和博氏が解説します。

●MR-CM
日本テレビと博報堂が共同開発した未来のCMのプロトタイプ。既存のテレビCMの人物などが画面からリビングにMRで現れる。
当たり前は突然、変わる コロナでXRが必須の時代に
私は、緊急事態宣言が出される少し前からテレワークになり、オンラインミーティングばかりやっています。リアルで会社に出勤しなくても十分に仕事ができるとも言えるし、リアルで動かないことにだいぶ飽きてきたとも言えます。この経験を経て、はっきりと気づいたことは、今まで「東京にいないと自分がやっているような仕事はできない」と思いこんでいましたが、そんなことは全然ないというシンプルな事実でした。
2018年、XR系の事業を起案した際、社内から「VRとかMRとか、そんな時代いつ来るのか」と何度も聞かれました。その都度、「5年以内に来ると言われますが、正確には誰にもわかりません。ただ技術も社会も大きくはその方向に進んでいるから、準備はしておくべきでしょう」と答えました。しかし、まさか、こんなにすぐ、しかも突然に「そんな時代」が来るとは、今年の正月にさえ想像しなかったでしょう。
「当たり前は突然、変わる」という言葉を、今までは「予想もしなかったイノベーションが、その利便性をユーザーに支持されて、気がつけば昨日まで当たり前ではなかった生活習慣が明日から当たり前になっている」という意味でよく使っていました。加えて、その変化の結果「昨日まで当たり前に存在していた産業が、ある日、突然なくなる」という警句として。
しかし今回、この2月以降のパンデミックで経験したことは、イノベーションと関係なく、降って湧いた突然の災害でも日常生活の「当たり前は突然、変わる」という実感でした。まさか会社や学校に行けなくなるなんて、全てのイベントが中止になるなんて、その状態がいつ終わるかわからないなんて、誰が予想したでしょうか。
意識変化と技術変化でテレプレゼンスが前倒しに
パンデミックや地震など大きな災害を経験すると、社会の有り様はそれ以前とは変わり、二度と戻ることはないとよく言われます。ペスト以後のヨーロッパ社会での宗教や農村労働者の変化。311以後の日本社会での共感や共有へ向かう消費の変化。技術進化がもたらす利便性の生活変化と、災害に対して耐性を獲得することでの集団変化。この2つが相互に影響し合って、人間社会は決定的に不可逆的に変化していきます。
では、いま起きている「アフターコロナ」または「ウィズコロナ」の時代に向かう決定的で不可逆的な変化とは、一体何なのでしょうか...?