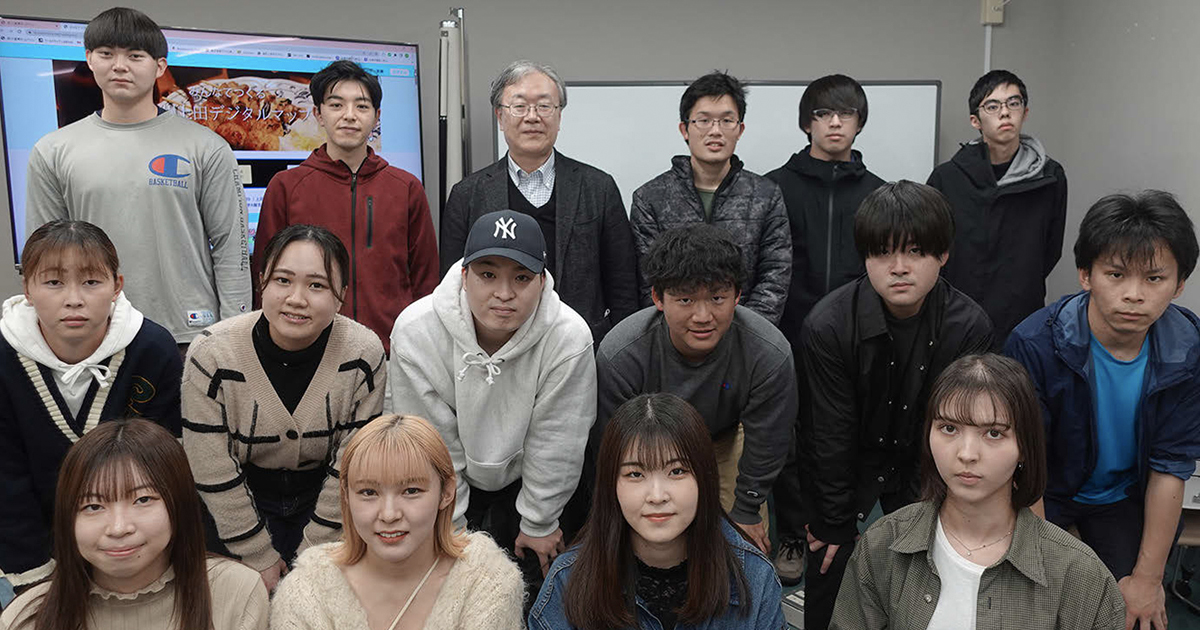メディア研究などを行っている大学のゼミを訪問するこのコーナー。
今回は静岡文化芸術大学の加藤裕治ゼミです。

加藤裕治ゼミのメンバー
| DATA | |
|---|---|
| 設立 | 2012年 |
| 学生数 | 3年生7人、4年生4人(2023年度) |
| OG/OBの主な就職先 | 広告代理店、番組制作会社、求人情報誌企画・編集会社、ITソリューション系企業、地方銀行など |
静岡文化芸術大学では、学部・学科・学年を越えたコラボレーションを通して、自分とは異なる感性や考え方に出会い、互いを刺激し合う創造的な学びを行っている。文化政策学部では、人々が「豊か」だと感じる社会の実現を目指し、いきいきとした社会生活を送るための理念や政策を見つけ出す人材を育成。さらに、文化政策学科では、地域社会や企業の課題を総合的に捉え、持続可能で包摂的な社会の実現に向けて、行政施策・企業戦略・市民活動などを構想し、それを有効に実現できる人材を養成している。
テーマは自由、研究作法を学ぶ
「メディア論」を研究する加藤裕治教授のゼミでは、メディアやコンテンツに関わることであれば、4年次の卒業論文も含めて研究テーマは自由。ただし、研究の作法はしっかり身につける必要がある。「仮説の設定や先行研究の参照、理論および方法論の検討、調査手法の習得、執筆のための論文作法などは、3年次のゼミで一通り学べるようにしています」と加藤教授。
3年の前期は、1人で読むと挫折しそうなメディア論の古典や解説が必要なメディアに関わる最新の論文などを輪読する。研究とは何か、論文とは何かを理解するためだ。夏休み明けの後期からは、ゼミ生全員で1つのテーマを調査・分析する「ゼミ論研究」を実施。ここ3年はデジタルメディア文化について調査している。
例えば2022年度は、YouTubeにおいて「目立つサムネイル(視認性)」と「クリックしたくなるサムネイル(誘引性)」は必ずしも一致しないのではないかという仮説を立て、調査を実施した。ゼミ論研究は、学生間で役割分担を行うため、チームビルディングや集団コミュニケーション、共同制作作業の学びにもなるという。その後、4年次のゼミ生は、各人が自らテーマを決めて調査・研究し、卒業論文を執筆。加藤教授はアドバイザー、サポート役に徹している。
斬新な発想で「圧」の少ない紙面を制作
加藤ゼミは地域のメディアとも接点があり、2020年には、中日新聞・静岡新聞の2社合同で「メディアとしての新聞/社」講座を開講。地域のライバル紙である2社が合同で連携授業を実施するのは珍しい試みだったそう。ゼミ生は全員参加した。
また、両社との結びつきを活かし、2021年度から2022年度にかけて「次世代型新聞制作プロジェクト」という実践型の研究を行った。前述の連携授業内で、学生から「新聞の紙面に圧を感じる」とコメントがあったのを機に、新しい紙面レイアウトをデザインし、実際の新聞に掲載することをプロジェクトの最終目標とした。
レイアウトデザインについては、同大学デザイン学部の学生にも参加を依頼。紙メディアの紙面調査から新聞制作の理解、印刷工場見学、新聞社の意向聞き取り、大学生のニーズ調査、紙面デザインの実制作、掲載記事の執筆など、約1年間かけて制作から新聞社への納品まですべて学生が実施した。その新しいレイアウト紙面は、2022年9月2日発行の静岡新聞(17面)、中日新聞東海本社版(19面)に掲載された。
記事の見出しは控えめに、内容自体も短く、用語解説や図表を充実させ、写真はインスタグラム的にスクエアタイプにし、フォントの工夫や余白を多く取るなど、見やすくユニークな発想に満ちた紙面となった。紙面にはQRコードを付け、読者からの意見をウェブで収集したが「読みやすさの考え方が新鮮」など、狙い通りの意見に加え「若い視点でのチャレンジに好感が持てた」と同プロジェクトの試み自体を評価する声も寄せられた。
加藤教授は「学生の自主性や行動力、紙面レイアウトの新鮮さには驚かされたと同時に、今後の紙メディアのあり方を学生から学ぶ機会にもなりました」と話す。「好きなことには大変な熱量で没頭し、情報取得にも熱心なゼミ生ですが、関心外のものには冷淡なことも。しかし、デジタルテクノロジーの進展により、異なる他者と知り合い、深く理解するための条件は整っているはずです。ゼミ生には、他者への理解を深め、自らも高めるためのツールとしてメディアを活用できる人になってほしいと願っています」。

新聞制作への理解を深めるため、中日新聞社浜松都田工場を見学。「新聞が出来るまで」を間近で見聞きし学んだ。

取材の様子。要点をまとめながらメモしている。
研究のきっかけは
ゼミの楽しさと人々の意見を社会に届けるプロセス体験
「大学で出会った社会学の教員たちの社会や文化、メディアへの考え方に惹かれ、この分野でもっと学びたいと考えるうちに、博士課程まで進学していました」と話す加藤教授。
メディアを研究対象に選んだ理由は2つ。1つは、海外の映像理論に関する文献を読みながらメディア現象を分析する自主ゼミがたまらなく面白かったこと。時間を忘れて議論をし、昼頃始まったゼミは飲み会まで続いた。2つ目は朝日新聞社千葉支局(当時)で世論調査を手伝ったバイト経験だ。ゼンリンの住宅地図を片手に、買ったばかりの中古車を走らせて県内のさまざまな場所を戸別訪問。
時に怪しまれながらも時間をかけて対面調査を行い、その結果が社会に届く体験もできた。これらの経験がメディア論の研究に結びついたと考えている。

加藤裕治(かとう・ゆうじ)教授
千葉大学社会文化科学研究科博士課程修了(2002年)博士(学術)。文化科学研究所(旧ぴあ総研)研究員などを経て、2012年より静岡文化芸術大学。研究分野は文化社会学、メディア論。趣味は映画館で映画を見ること、鉄道(特に乗り鉄)。