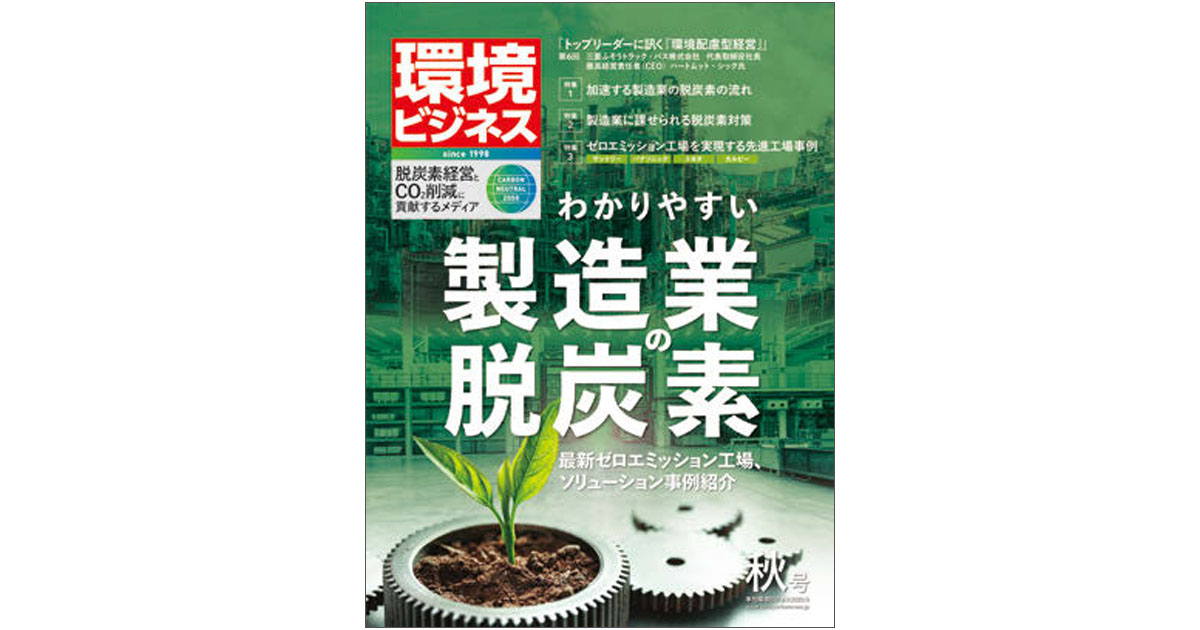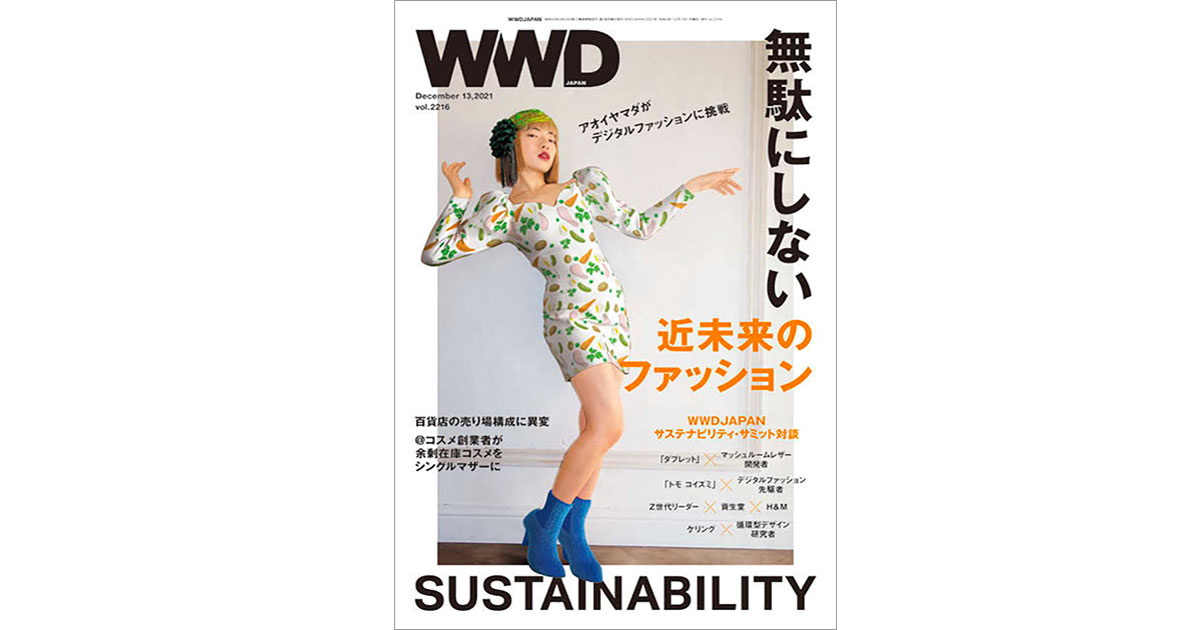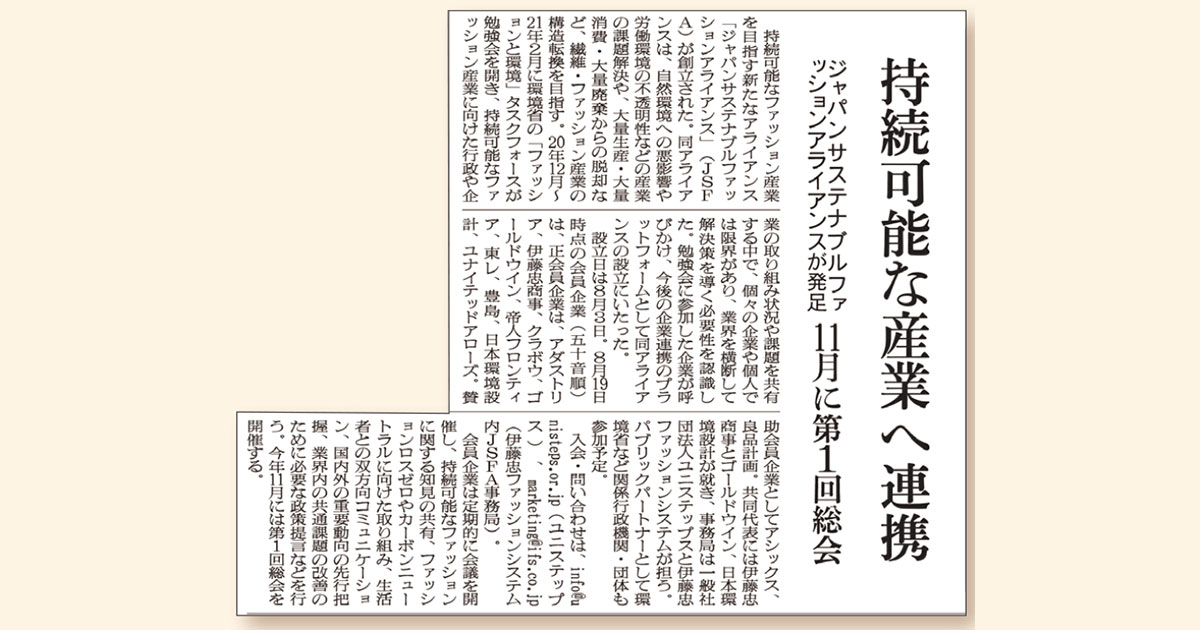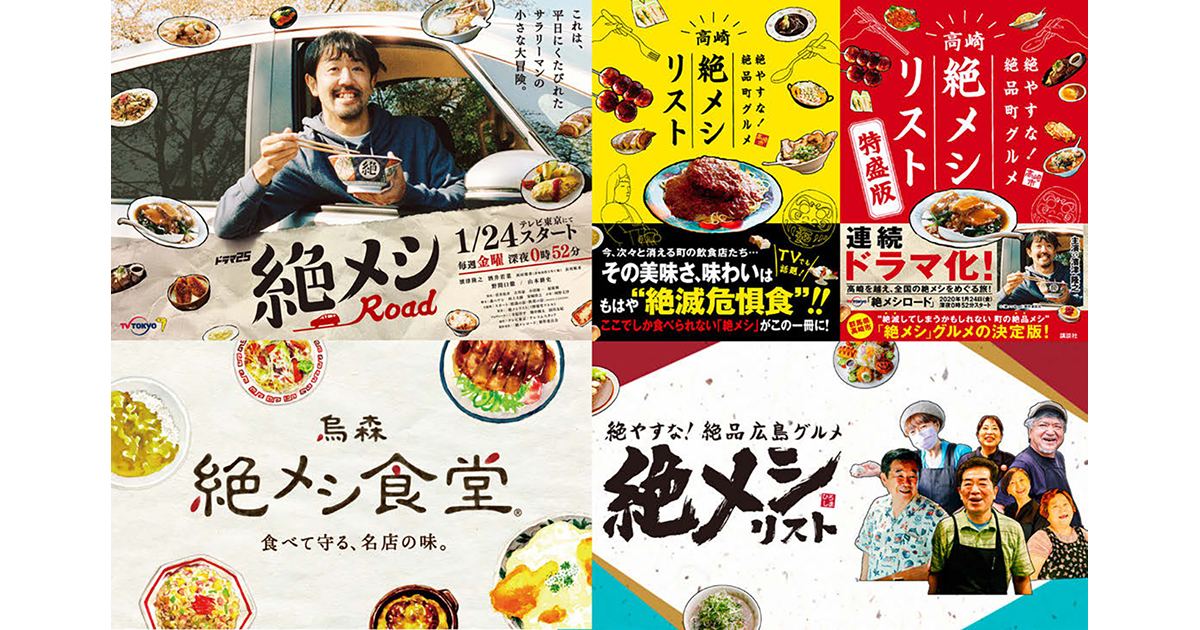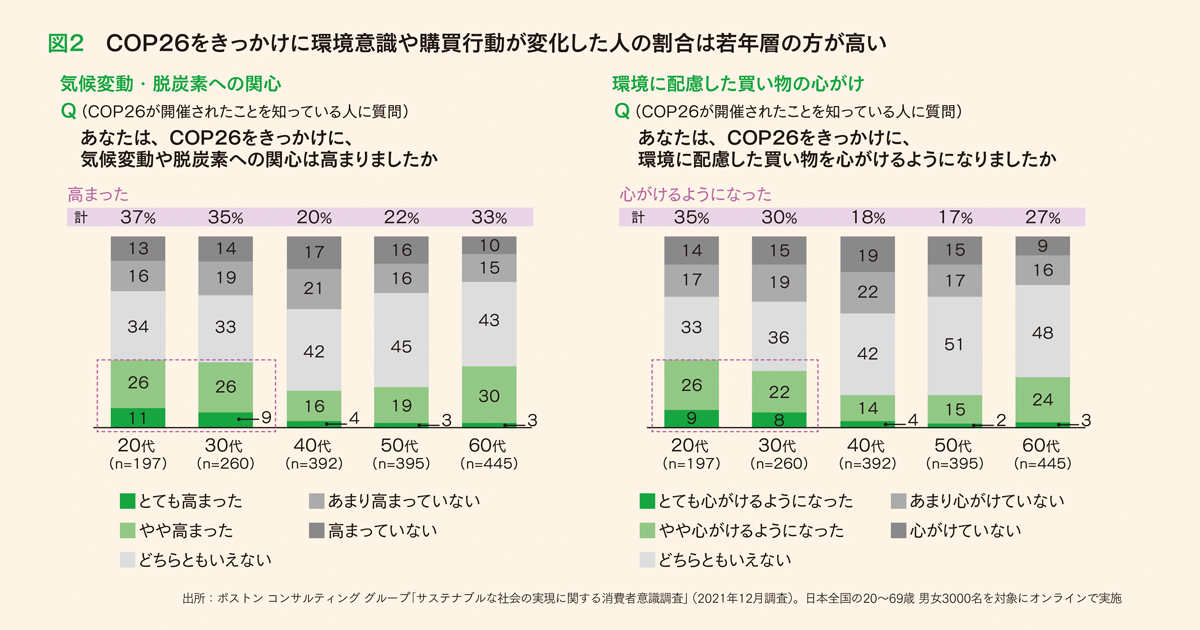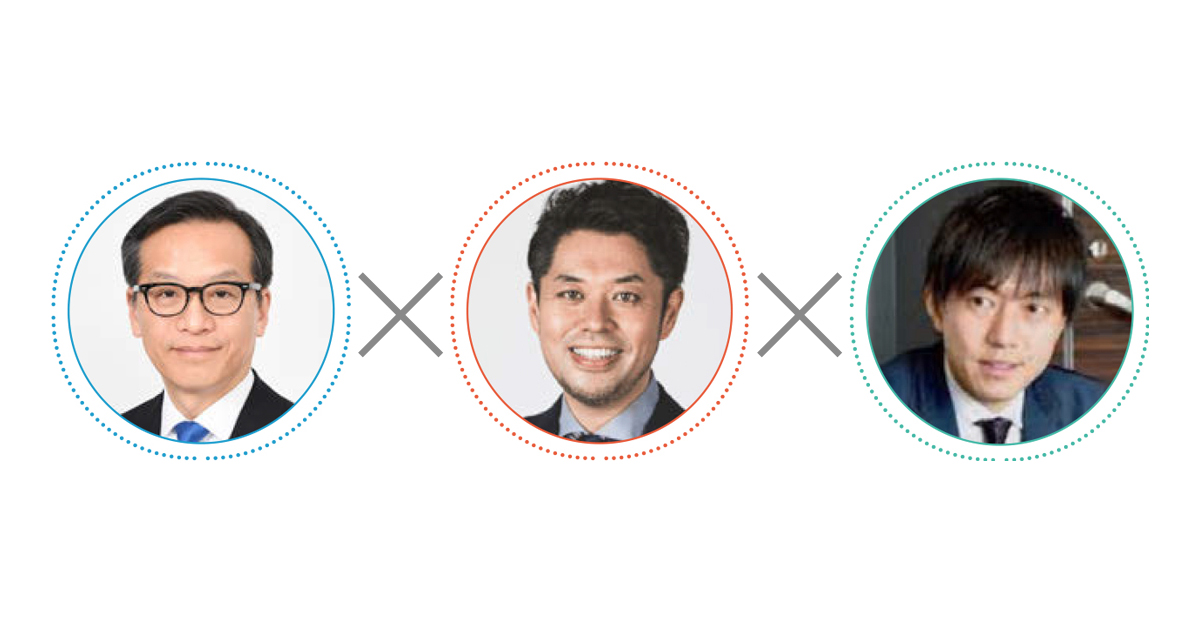今やあらゆる企業がサステナビリティをうたうように。その結果、誠実に取り組んでいることを誤解なく伝えることが逆に困難にもなってしまった印象だ。一方で、真偽を見抜くプロである記者は企業のメッセージの例えばどこを見ているのか。各メディアの編集長陣に忌憚ない意見を聞いた。

化学工業日報社
編集本部 編集局長
渡邉康広(わたなべ・やすひろ)
1971年生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。整理部を経て2001年から記者。シンガポールとバンコクにも駐在。昨年から編集局長。
──サステナビリティに関する最近の記事で、読者からの反響が特に多かったものを教えてください。
『化学工業日報』の読者のほとんどが化学関連企業や研究機関、大学、行政の関係者などですが、一般の方々からも反響があったのは、積水化学工業が開発した技術の記事です。これは微生物を使い、可燃ゴミを原料にして、化学品の原料であるエタノールを取り出す技術です。
この技術の何が革新的かというと、処理問題で悩んでいる膨大なゴミを、都市油田へと変えられるのです。日本の燃えるゴミの排出量は、年間約6000万トンと言われていますが、この技術を使えば、理論上、現在の石油化学原料を上回るエネルギーを産出できます。
この技術は実証試験が進み、2020年代の普及を目指しています。実現されれば、サステナブルな社会を現実化する大変ユニークな技術であるため、大きな反響がありました。
あと61%