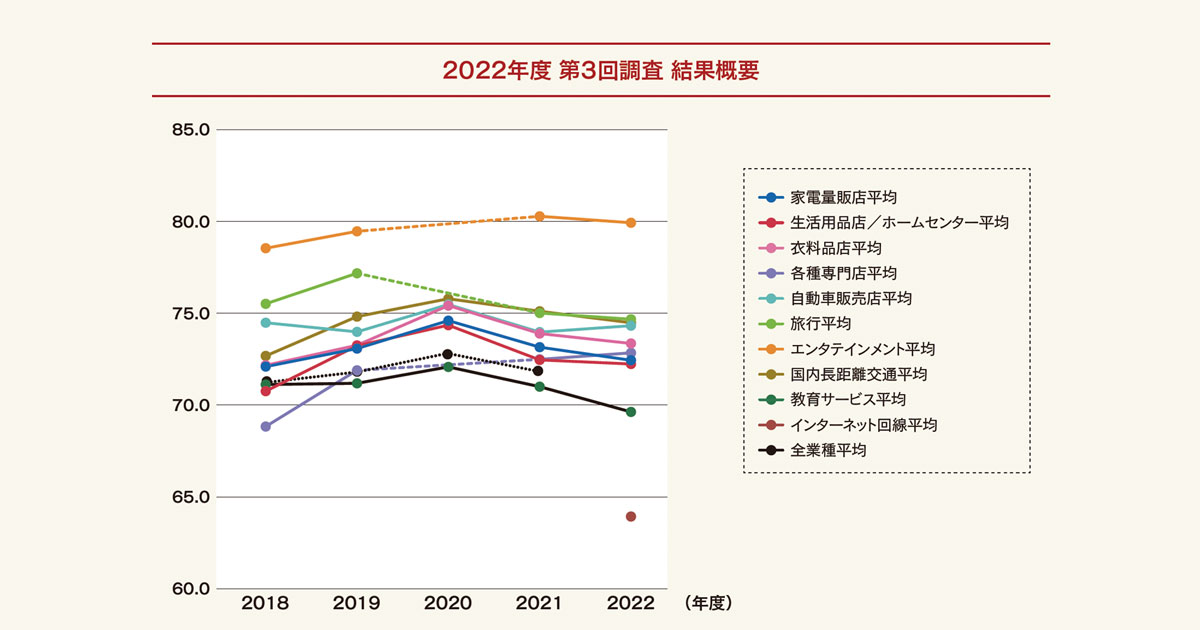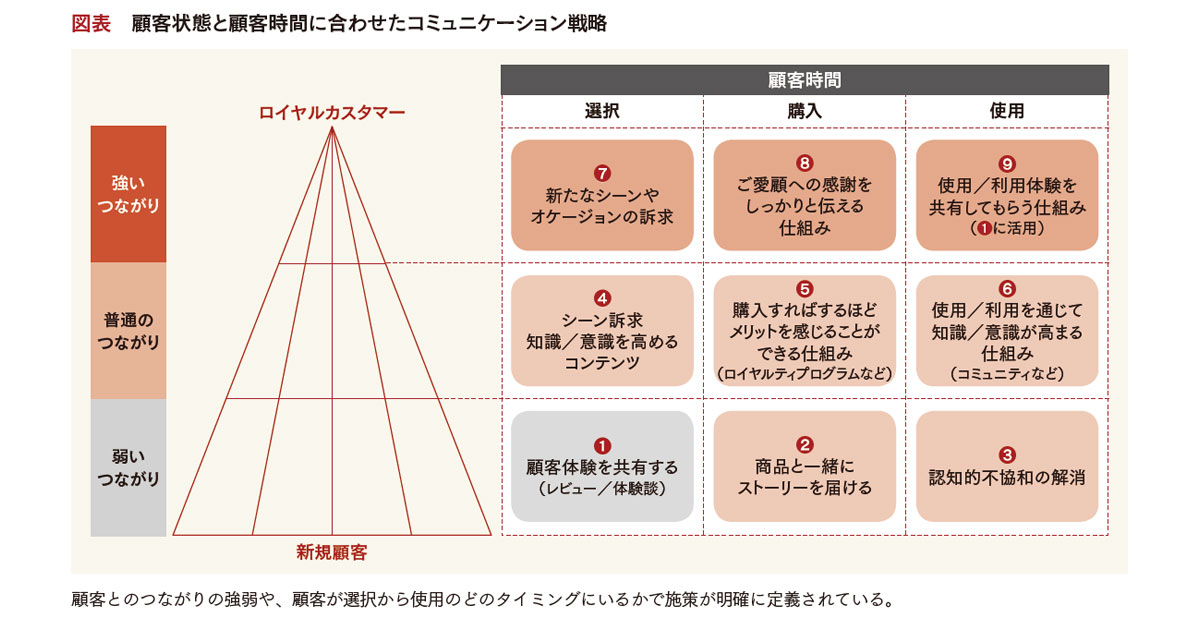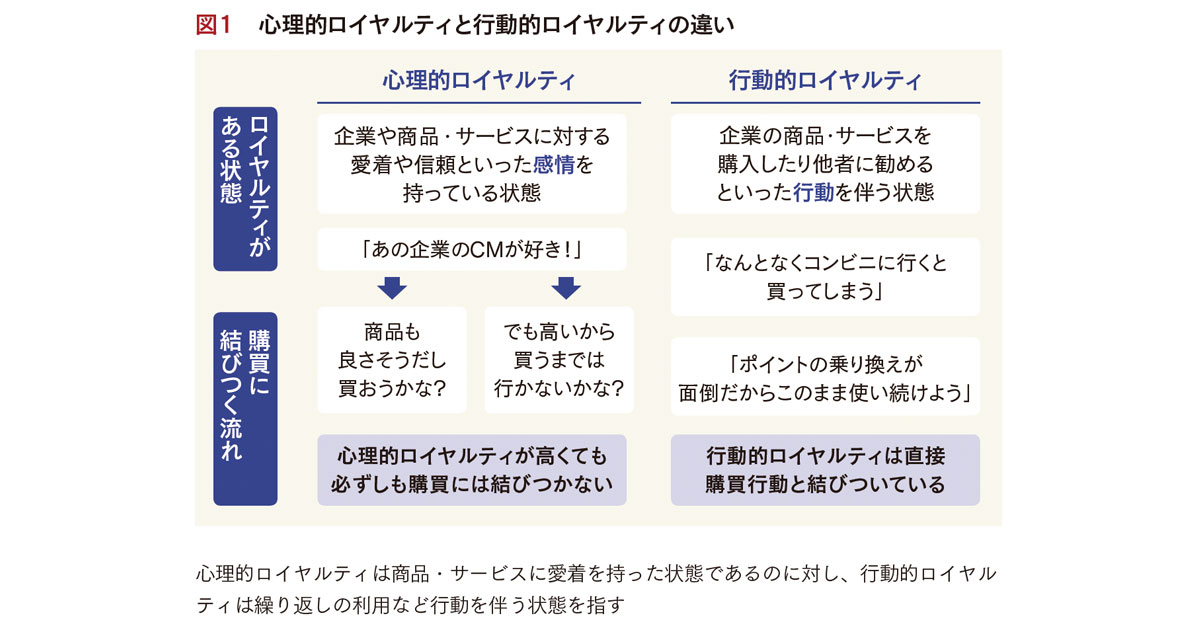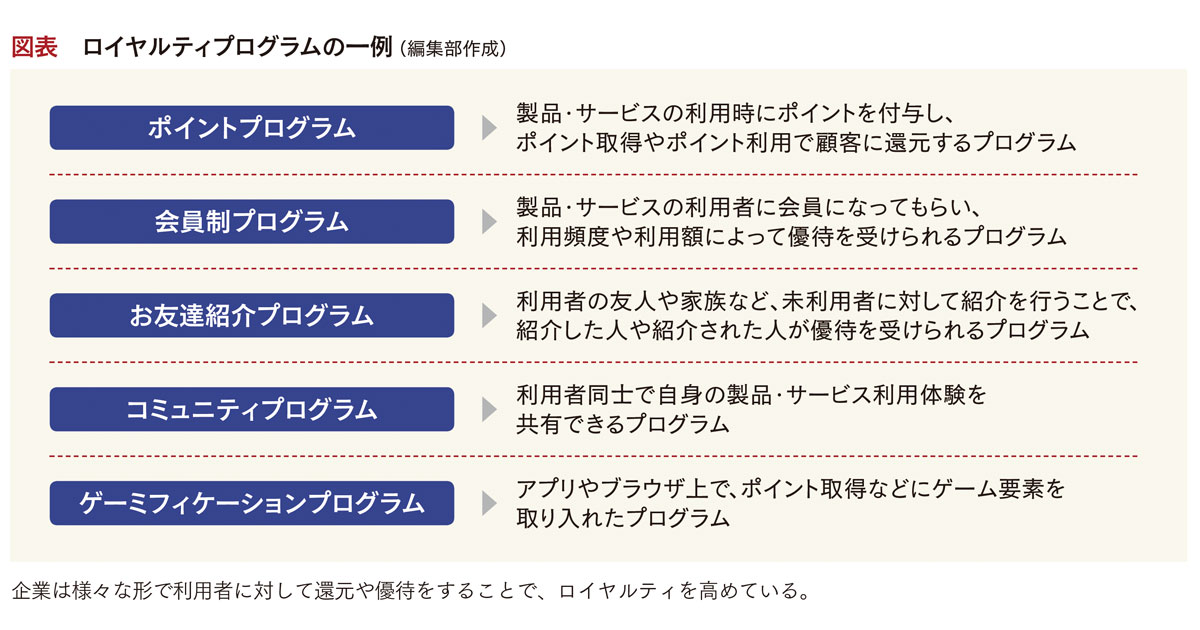共通ポイントサービス「Ponta(ポンタ)」を運営するロイヤリティ マーケティングは、2019年よりSDGsの達成に向けた活動を開始。2021年には日常生活で気軽にSDGsを学べるアプリ「Green Ponta Action」をリリースした。その経緯と狙いを新規事業開発部の佐藤智仁氏に聞いた。

Green Ponta Actionの運営を担う佐藤氏は「SDGsを目指すブランドという立ち位置で、他社との差別化を目指した」と語る。
SDGsをテーマにブランドを差別化
──「Green Ponta Action」について教えてください。
共通ポイントサービス「Ponta」を運営する当社は、SDGsの達成に向けた活動として、2019年より「Green Ponta Project」を展開しています。
この一環として、2021年4月にアプリ「Green Ponta Action(グリーンポンタアクション)」をリリースしました。日常生活の中で気軽に取り組めるSDGsにつながるアクションを積み重ねることで、「持続可能でより良い世界を目指す」活動を知ることができるアプリです。
この企画を立ち上げた背景には、単純にポイントだけでユーザーに魅力を訴求していくのは、昨今の競争環境の中で難しいこと。またPontaというブランドに愛着を持ってもらうにはどうしたらいいのかという課題がありました。その中で、SDGsは今後ますます重要になると予想。アプリのテーマをSDGsとすることにしました。テーマとするにあたり、「持続可能でより良い世界を目指す」ための課題に気付くには、各自が「何がサステナブルか」を認識する必要があると考え、そこに意識を向けるような仕組みを取り入れることにしました。
そこには「私たちはSDGsの達成を目指していくブランド」という立ち位置で他のポイント事業者と差別化していこうという狙いと共に、「SDGsに共感してくれるユーザーと共に課題に取り組んでいく」というブランディング戦略もありました。
──アプリ開発について教えてください。
アプリの開発にあたっては、ユーザーと企業それぞれに対して狙いがあります。
まずユーザーに対しては、「SDGsは意識が高い人がやること」というイメージを変えたいという思いがあり、ユーザーに意識変容や行動変容をもたらすアプリを目指しました。
一方企業に対しては、その企業の商品やサービスのファンになっていただけるような、ユーザーと企業がマッチングするプラットフォームになるように企画しました。