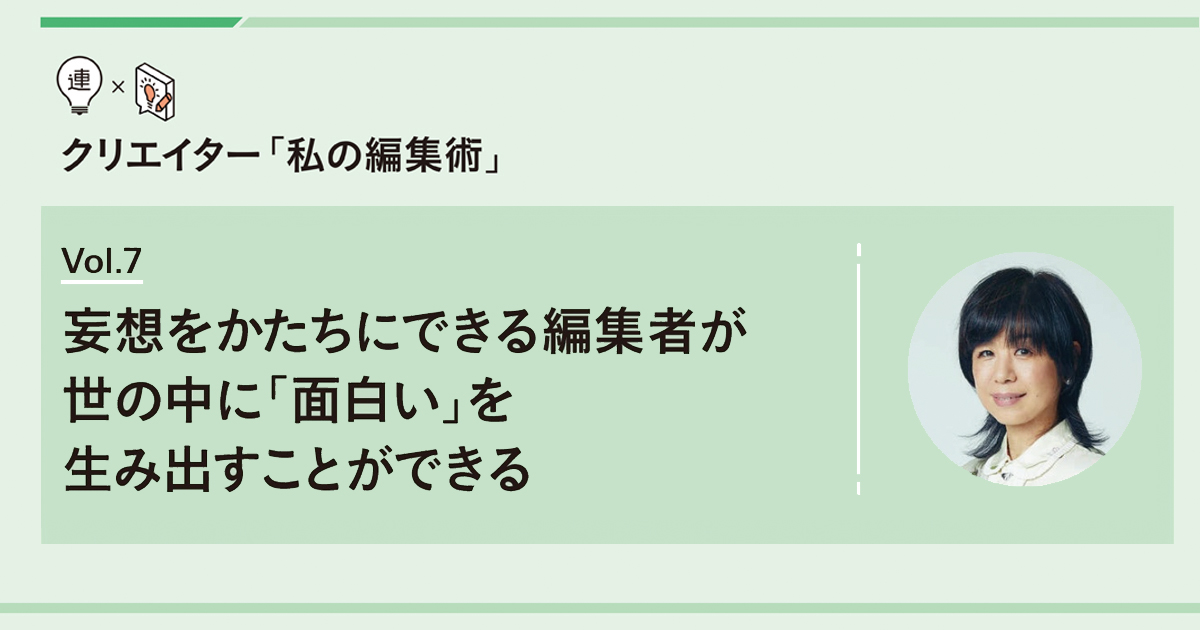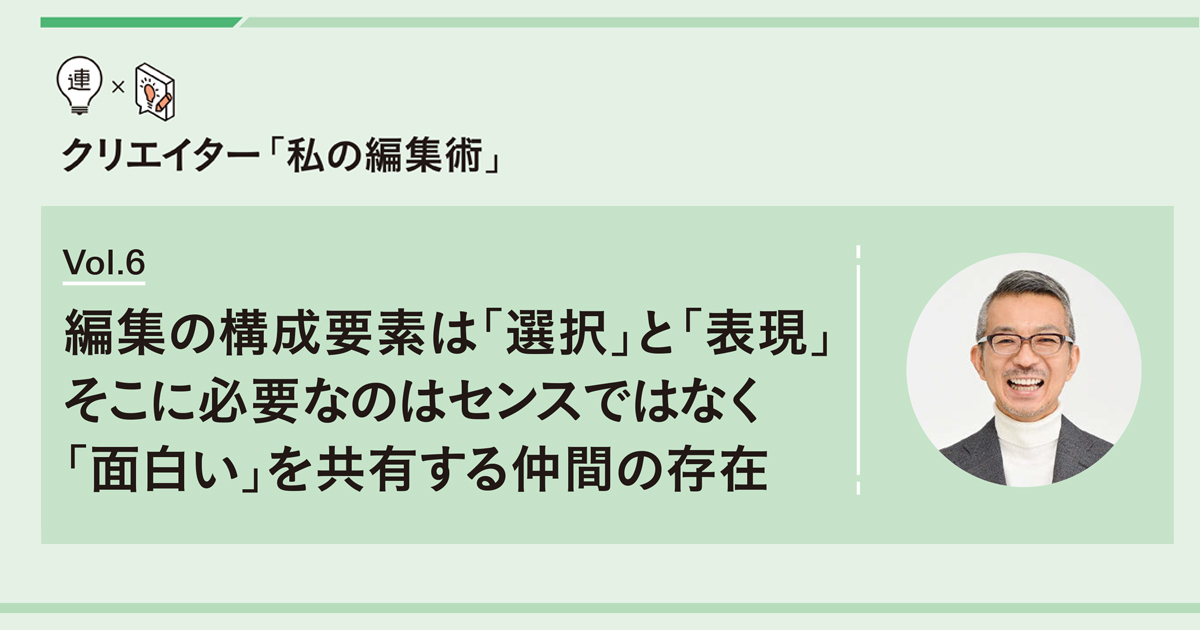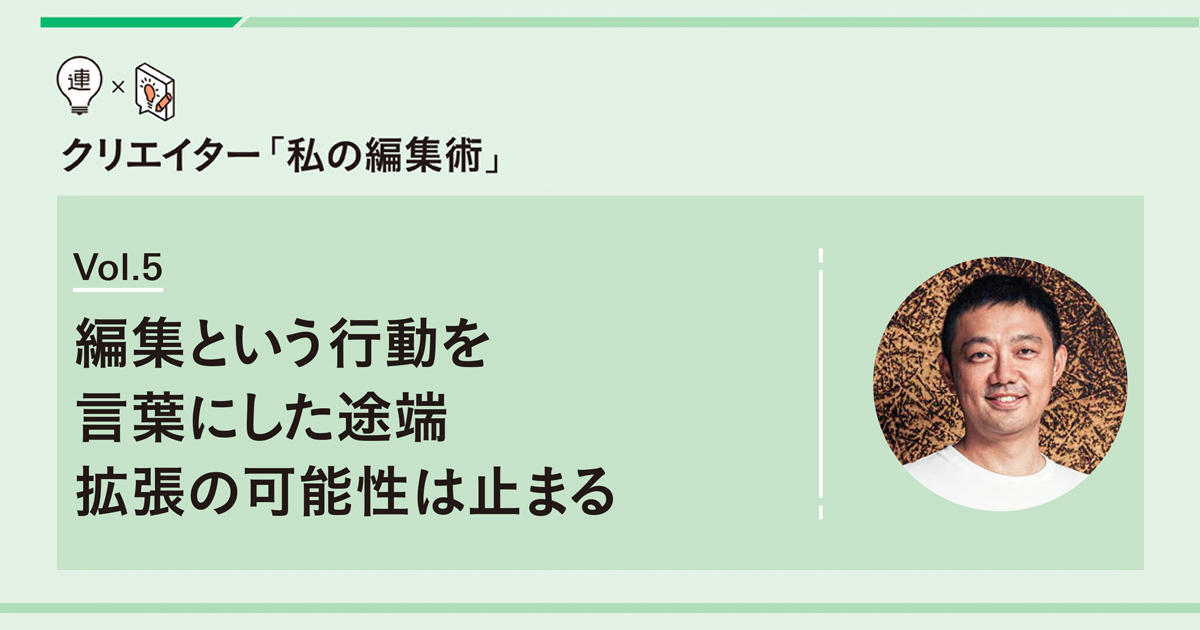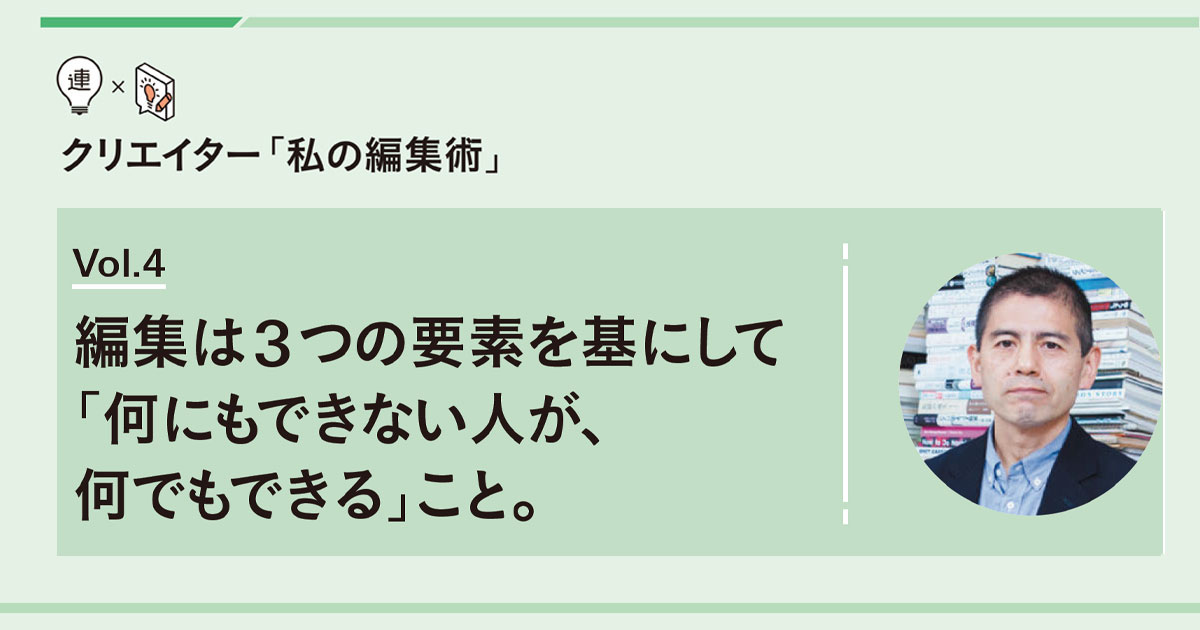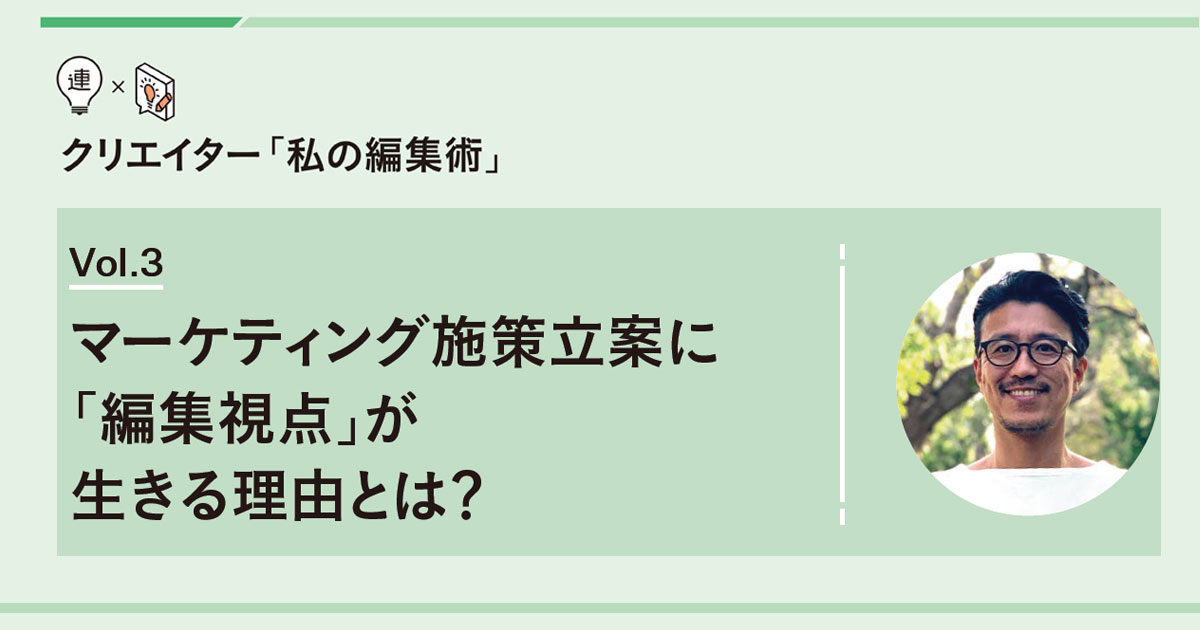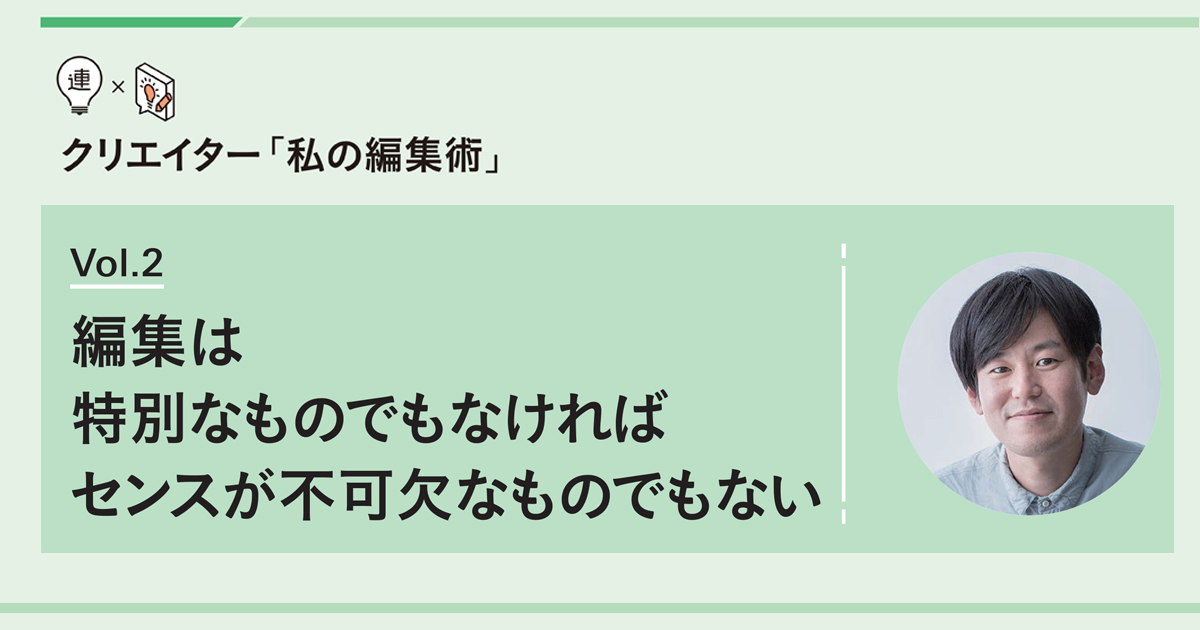出版・メディアで仕事をする人にとって必要な能力のひとつ「編集力」。しかし、ビジネスの世界の意思決定はすべて適切な情報編集の先にあると考えると、広告・マーケティングの領域においても、表現力だけでなく情報の取捨選択・整理といった編集力が必要なのではないでしょうか。本連載では、出版業界の編集者の方はもちろん、広義の意味で編集力を生かしている方に、編集術に対する考えを聞きます。
内田秀美が考える「編集」とは
☑異質なもの同士を掛け合わせ、新しい価値を生み出すこと
☑やりたいことを最大スケールで考える「妄想力」が必要
☑大事なのは企画を実現する「推進力」と「瞬発力」
妄想をかたちにできる編集者が
世の中に「面白い」を生み出すことができる
「A+B=C」の方程式で新しい価値を世の中に提案する
私が考える編集とは、「A+B=C」というように、何かと何かを掛け合わせて、新しい別の何かを生み出すこと。さらに異質なもの同士を掛け合わせることによって思いがけない化学反応を起こし、世の中に新たな価値を提案することです。
この自分なりの編集の定義にたどり着いたのは、仕事の領域が雑誌をつくるだけではなくなったときでした。もちろん雑誌をつくっているときも、例えばカメラマンとスタイリストの掛け合わせ、いわゆるA+B=Cの方程式で新しい化学反応や価値を生み出している自覚はあったのですが、雑誌編集で行ってきたことが広くビジネスでも生かせると気づいたきっかけとなる出来事がありました。それは『SPUR』の広告企画として実施した、漫画『ジョジョの奇妙な冒険』とラグジュアリーブランドの「GUCCI(グッチ)」のコラボレーションです。
異なる両者を掛け合わせることで実現したこの企画は、『SPUR』から集英社全体に。そして集英社から世界に拡がり、漫画の作者である荒木飛呂彦先生によるグッチのための描き下ろし作品が世界約80店舗のグッチのお店のウインドウを飾る企画にまで成長しました。
雑誌の編集で行ってきたことが、思いがけない企画を生み、ハイブランドと漫画の新しい可能性を提案できた事例だったと思っています。
「やれそうなこと」ではなく「やりたいこと」を考える
『宣伝会議』の読者であるマーケティング担当者や広告を制作するクリエイターの中には、まったく別のものを掛け合わせると言われても、企画の実現可能性が低くなってしまうのでは? と考える方もいらっしゃると思います。先述のようなコラボであれば、コラボ相手との親和性を見つけてきて、どうにか「できそうな」企画をつくるのが得策だと思う方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、そうやって完成した企画は、世の中に新たな価値を提案する面白いものになったでしょうか。私は企画を考える時に、「やりたいこと」と「やれそうなこと」は別ものとして捉えるべきだと...