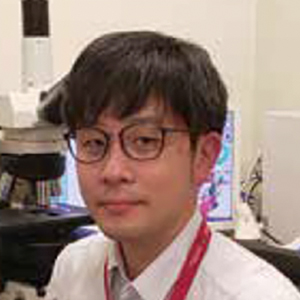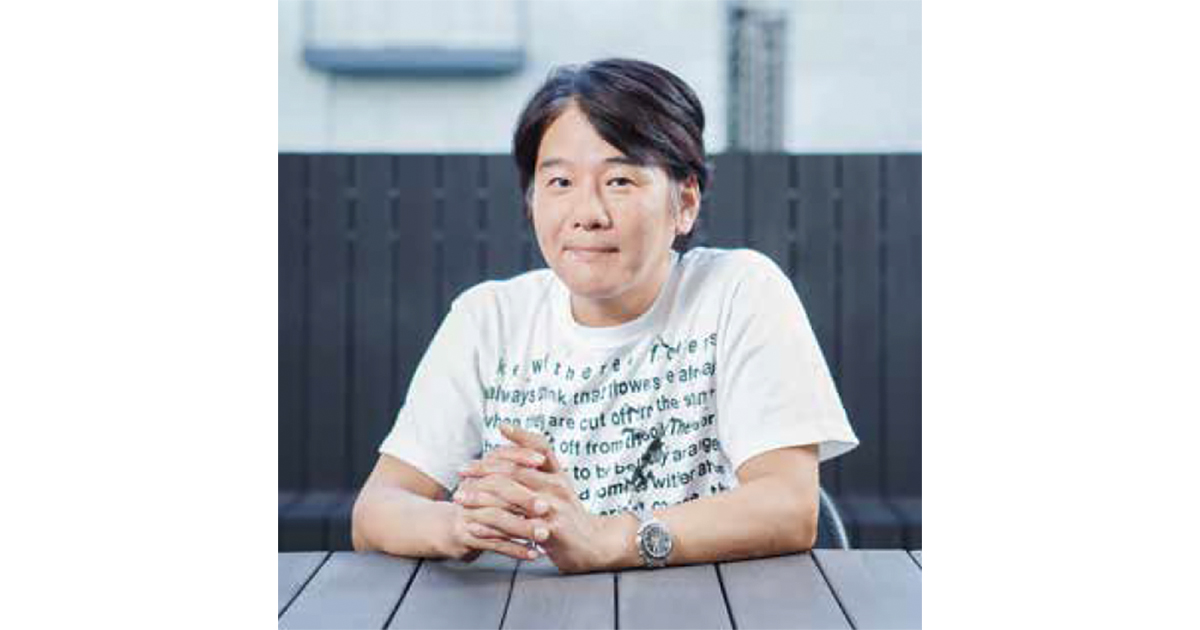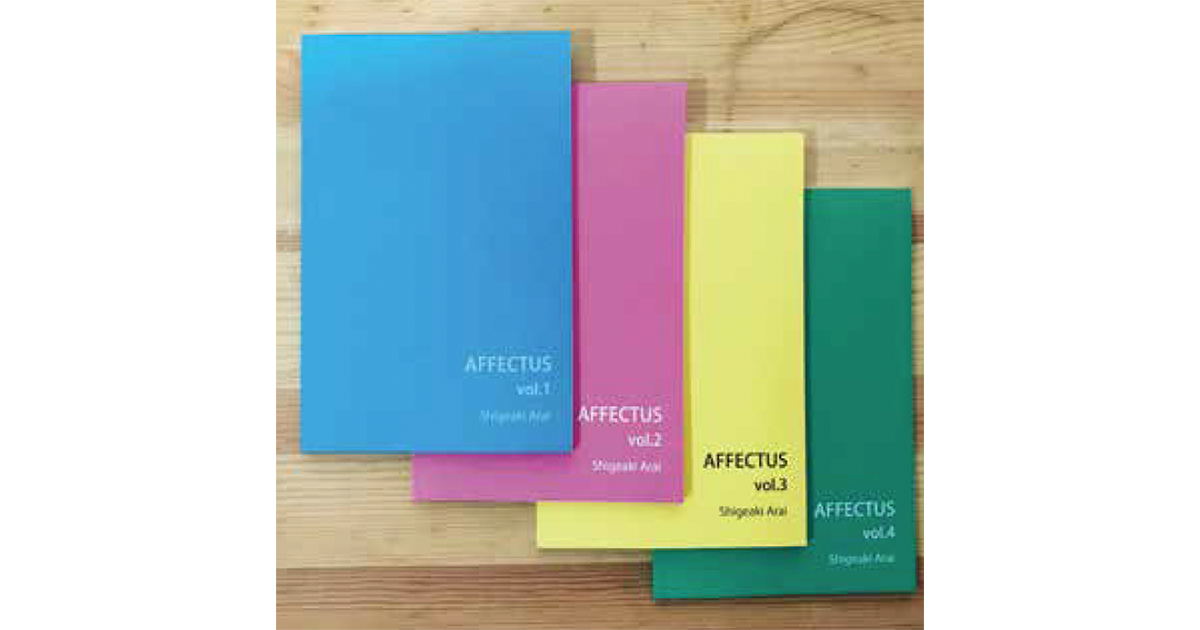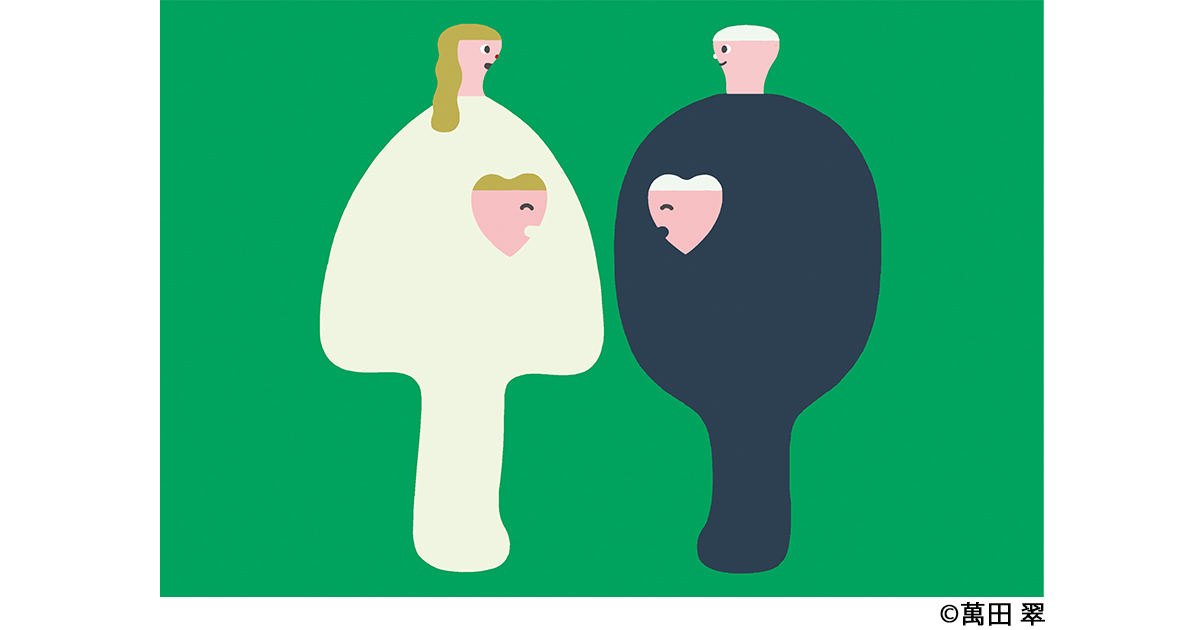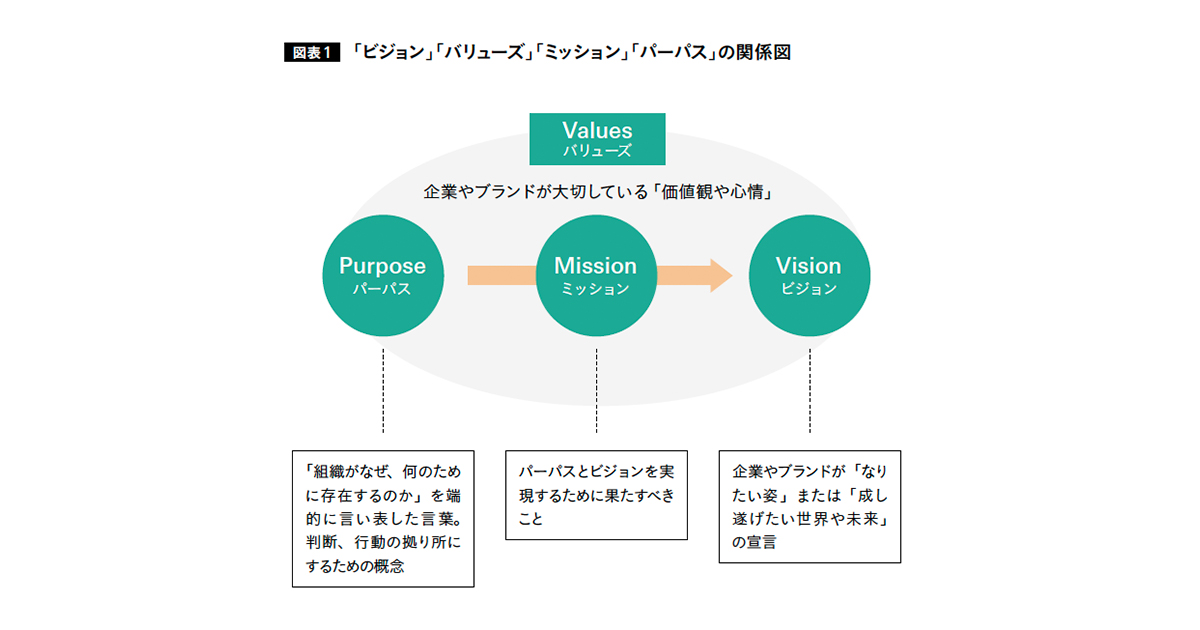「病理医ヤンデル」として、本業の病理医の傍らTwitter、執筆活動を続ける市原真氏。言葉を使って診断結果が「伝わって」初めて仕事が成り立つと話す“病理医”としての市原氏と、Twitterで多くの人に発信する“ヤンデル先生”としての市原氏がもつ、「言葉観」を聞いた。

病理専門医
市原 真氏
1978年生まれ。医師、博士(医学)。病理専門医・研修指導医、臨床検査管理医、細胞診専門医。ツイッターでは「病理医ヤンデル(@Dr_yandel)」。著書に『いち病理医の「リアル」』(丸善出版)、『Dr.ヤンデルの病院選び ヤムリエの作法』(丸善出版)、『病理医ヤンデルのおおまじめなひとりごと』(大和書房)、『どこからが病気なの?』(ちくまプリマー新書)ほか。
伝わって初めて業務完了する仕事「病理医」
私は大学時代、学内で自分が一番頭いいと思っていたんです。自意識過剰ですが。新たな病気の発見や、治療法の発見に精を出したくて、臨床医ではなく研究職に就こうと考えていました。結局そこまで頭が良くなかったので(笑)、研究職は諦めることになるのですが、ベッドサイドで患者さんと向き合うことを目指してはこなかったので、臨床とはひと味違う病理診断の世界に飛び込むことになりました。これが天職だったので、わからないものです。
皆さんは、病理医の仕事ってご存知ですか?検査で採取した患者さんの細胞を調べ、医師に病名と結果を「伝える」仕事です。メインは医師とのコミュニケーション。今、「伝える」ことが仕事だと申し上げましたが、病名を「伝える」過程で認識の齟齬が生まれるようなことがあれば、患者さんの命に関わりかねません。
その意味では、診断結果を「伝える」だけでなく、医師にしっかりと「伝わって」初めて病理医としての仕事が完了すると言えます。
病理医以外のあらゆる医療職においても、「言葉」によるコミュニケーションは発生しますが、とりわけ病理医の仕事においては、「伝える」だけでなく、「伝わる」ことが第一に求められるのです。「伝えた」で一方的に満足してしまってはいけない。
Twitterのフォロワーとは「敵同士(笑)」な関係性で
病理医が業務時間内にTwitterをマメに更新するのって珍しいですよね(笑)。日中にツイートしている医者がいる、と驚かれることもあります。私は2011年頃から「病理医ヤンデル」としてTwitterを始めました。ヤンデルという名前はハーバード大学のサンデル教授をもじって、病理の「病(やむ)」を掛け合わせたもの。皆さんからは「ヤンデル先生」と呼ばれることが多いです。
Twitterを始めたきっかけは、病理医の広報活動でした。当時の病理医の人数は日本で2100人程度。そこで、目標フォロワー数を...