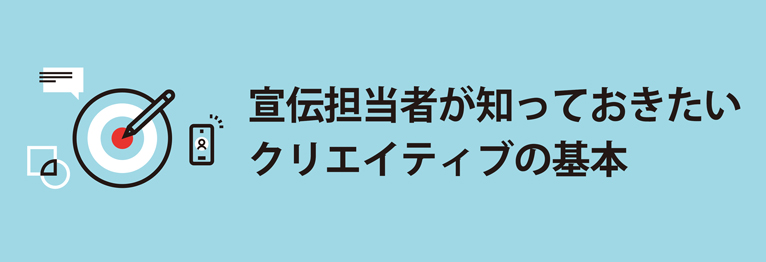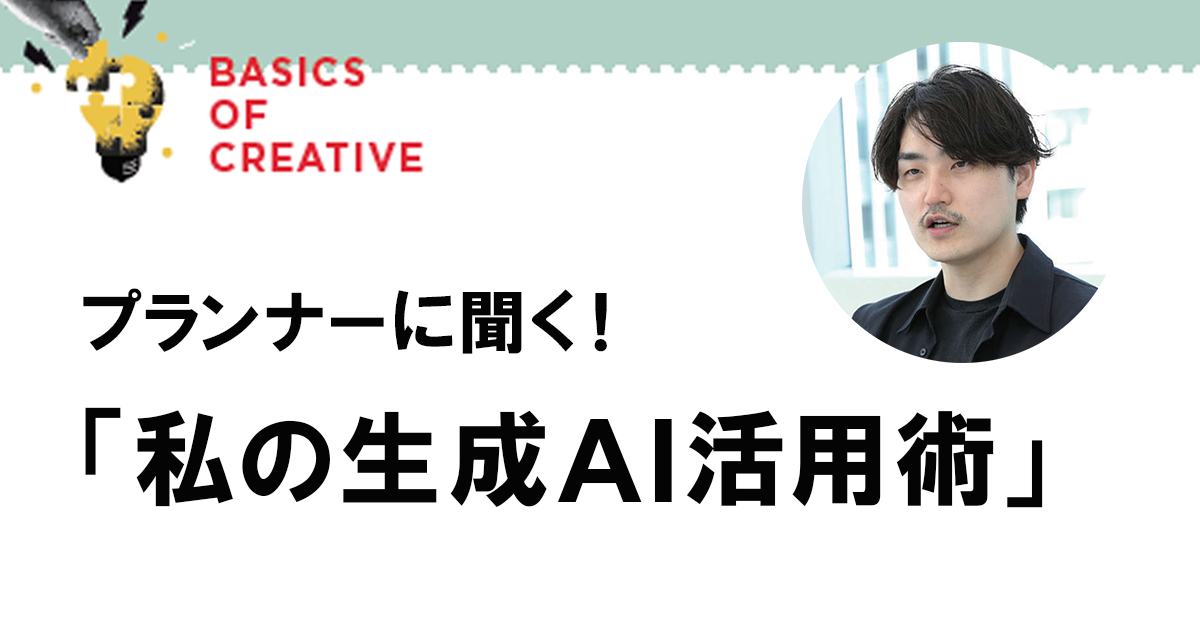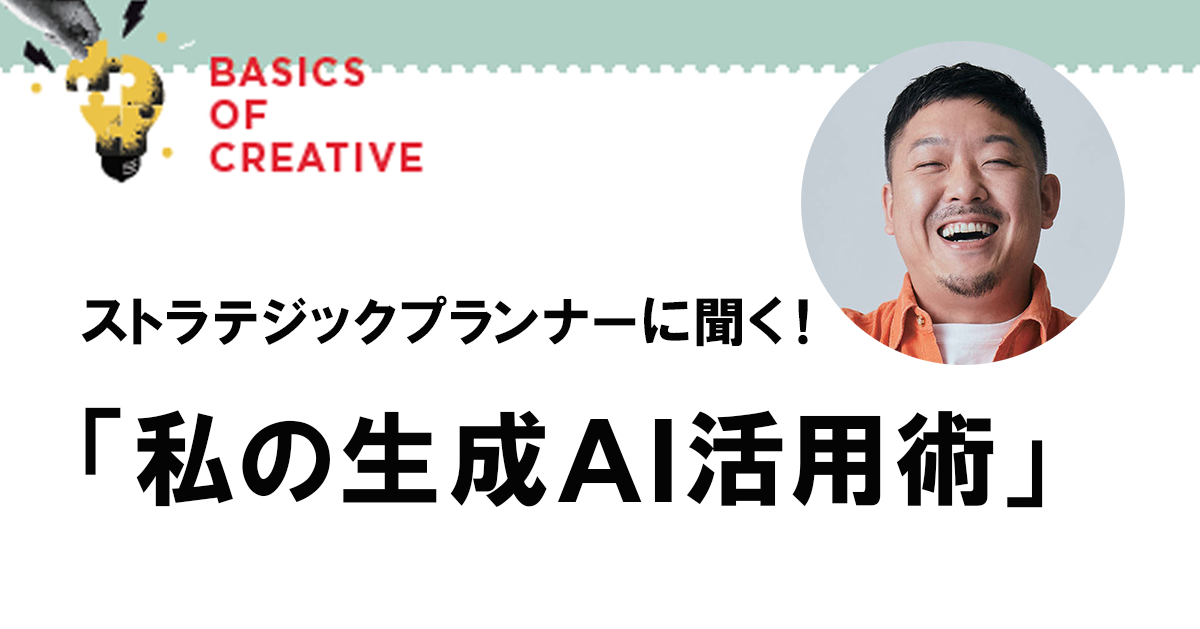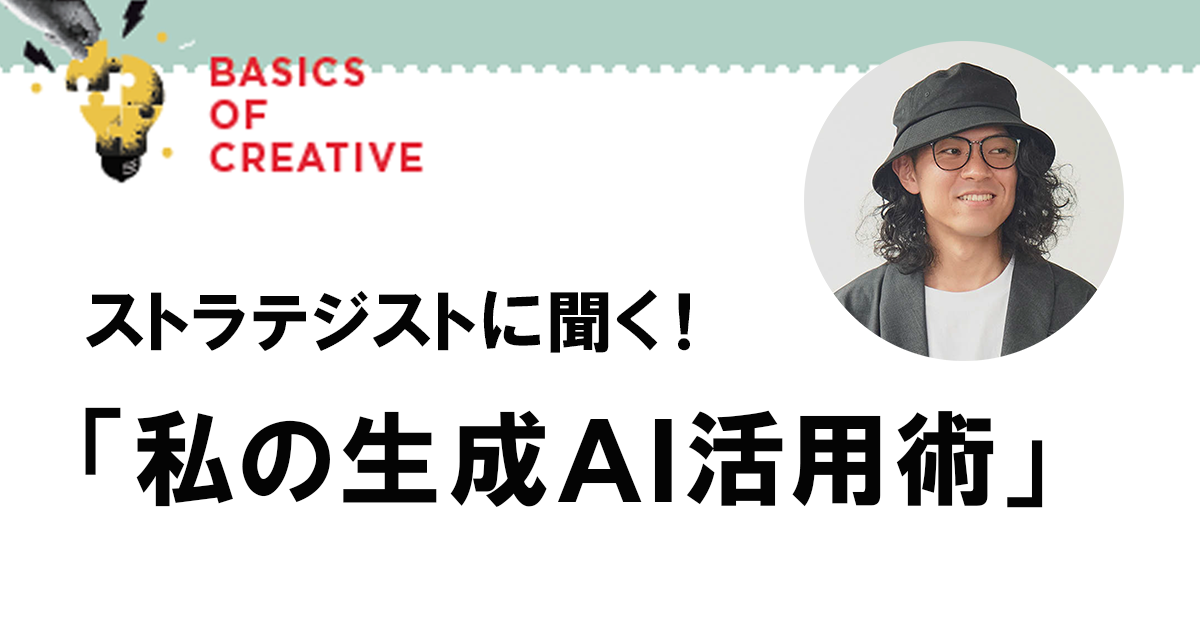| [SEMINAR DATA] | |
|---|---|
| ゼミ名 | 藤村和宏ゼミ |
| 設立 | 1988年 |
| 学生数 | 3年生:5名 |

香川大学 経済学部
藤村和宏教授
博士(商学)。学習院大学経済学部卒業後、花王を経て、1988年神戸大学大学院経営学研究科に進学。1990年広島大学経済学部助手、1993年香川大学経済学部講師、2001年より現職。「平成16年度(第二回)助成研究論文 吉田秀雄賞 第1席」(2004年)、「第71回 日本商業学会賞 優秀賞」(2021年)等を受賞。
自由なテーマ設定で、自ら問いをつくる力を身に付ける
藤村ゼミではまず、共同研究を通して仮説立案や調査票のつくり方、分析の仕方を学ぶ。4年次の卒業研究については、マーケティング領域に限らない、自由なテーマ設定が可能だ。「なぜ“バズる”のか」「なぜ自分探しをするのか」「カッコいいとは何か」。「問いのつくり方や仮説の立て方は、どんな業界に行ってもビジネスで役立てることができる。好きなことを研究しながら、そうした手法を身につけてほしいと思っています」と藤村教授は話す。
週に1度のゼミ活動には、社会人も定期的に参加しているそうだ。
「卒業生の他には、60代の会社社長も。以前は毎年、ゼミ生として企業から数人参加してもらっていたこともありました。研究や懇親会を通じて、実際に働いている人の考えを知り、コミュニケーションの中から学びを得ることが狙いです」。
またこの2年間はコロナ禍で中止しているが、毎年1週間の海外旅行を活動に組み込んでいることも特徴だ。オーストラリアやフィンランド、中国など行き先は様々。それをきっかけに語学を始めたり、公務員志望だった学生がグローバル企業に勤めたりと、価値観を変える、大きなきっかけになっているのだという。

現在、通常の授業は対面とリモートのハイブリッド形式、ゼミ活動は対面で行っている。
市場拡大に必要なのは育てるという視点
藤村教授の研究テーマのひとつが、サービスマーケティングにおける「便益遅延性」だ。特に医療や教育の領域において、サービスを消費する時点と、その結果として...