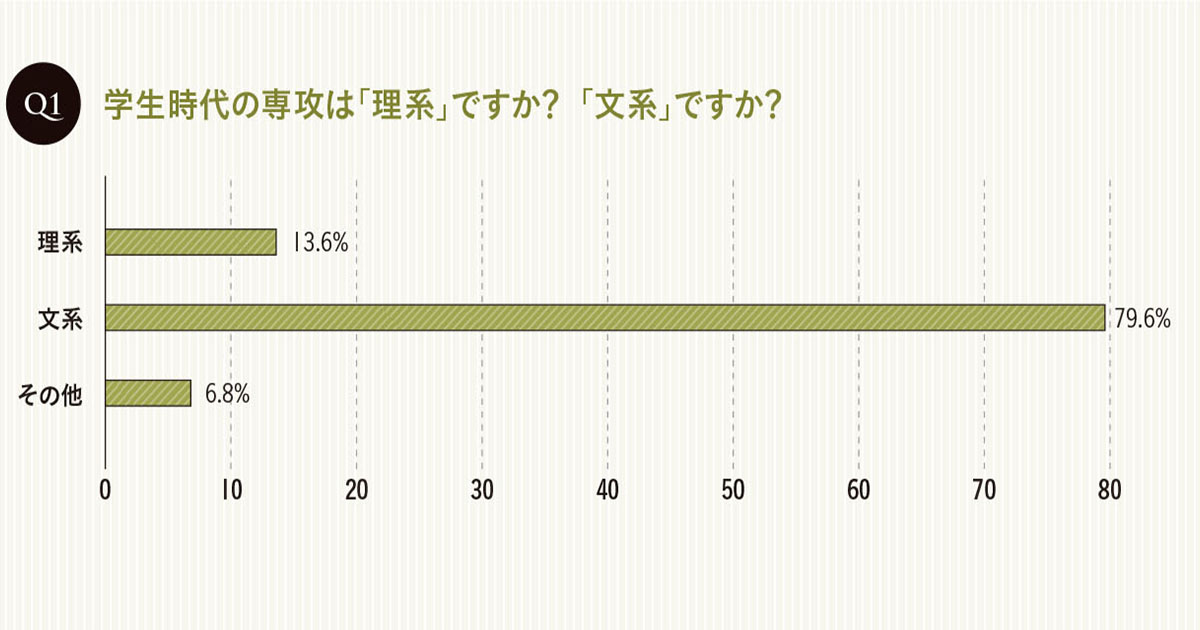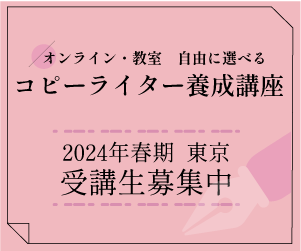1834年に水菓子の露天商として創業し、今年で184周年を迎える「千疋屋総本店」。現在で6代目店主となる大島 博氏は、社長就任後20年で売上高を5倍に拡大させた。老舗ブランドとして、どのようにブランドを捉え、戦略を立てたのか。その考えを紐解きます。

上からスペシャルパフェ、フルーツサンド。
高価なブランドイメージから手の届くおいしいブランドへ
老舗高級フルーツブランド「千疋屋総本店」の現・代表取締役社長の大島 博氏は6代目店主となる。高級なイメージが強くなりすぎてしまった千疋屋ブランドを時代に合わせるため、「ブランド・リバイタル・プロジェクト」を立ち上げ、ブランドコンセプトである「ひとつ上の豊かさ」をコアバリューとしたブランド経営を大島氏は行ってきた。
「私は1985年に入社し、1998年に代表取締役社長に就任しました。就任後の3年間は、前代の父の経営方針を継いでいたのですが、今の時代に合っていないのではないかという思いを抱くようになり、プロジェクトを立ち上げました」と大島氏は振り返る。
バブル景気時に高額で高級品のイメージがつき、「千疋屋の名前は知っているが、敷居が高い」というイメージを持たれるようになってしまったのではないか、というのが大島氏の考えたブランディングの問題点。ただ、高級品というイメージはブランドに対する信頼にもつながっている。質に対する信頼感は保ちつつ、手を伸ばせば届くブランドというイメージに転換していこうとの考えからプロジェクトは始まった。
まずはスイーツやケーキ類を入口としてお客さまに親しみを持ってもらおうと考え、スイーツ事業を立ち上げた。現在は全体の売上の中で生のフルーツは2割。8割をスイーツなどの加工品が占める。
また、フルーツは単価が高いうえに、遠方のお土産には適した商品とは言えない。そこで、新しいギフト商品の開発に目をつけたという大島氏。ブランドのイメージを強く打ち出し、おいしいフルーツを使ったスイーツを購入しやすい金額で販売。「東京お土産戦略」として駅や空港で販売を始めたのが売上拡大につながった。
「こうした戦略により、これまで千疋屋のお客さまではなかった方に『千疋屋っておいしいね』と知ってもらえるようになり、母の日などの特別な日に高価格帯のフルーツも売れるようになってきました。特別な記念や自分へのご褒美につながればと思います」と大島氏は話す …