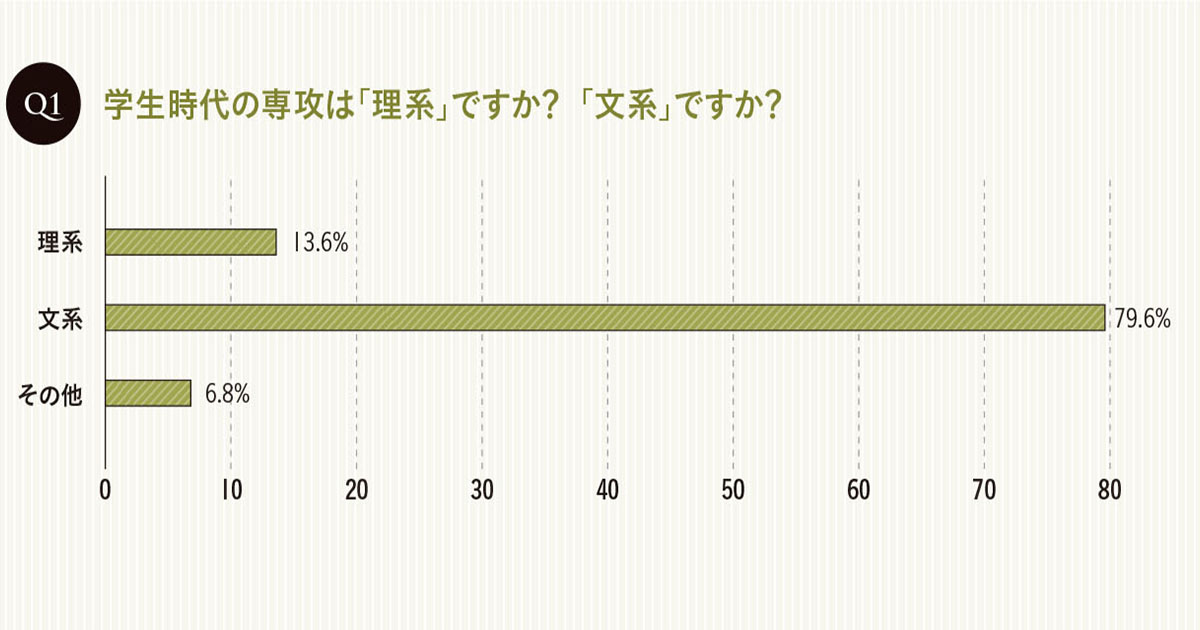今からおよそ200年前の江戸時代、1825年に創業したのが総合化粧品メーカー「伊勢半」の前身だ。そして明治初期の1887年にはかの「浅田飴」が誕生している。両社はジャンルこそ違えど、変わらぬ真摯なモノづくりとユーザーからの確かな支持があったからこそ今に続いている。急速なデジタル化が進む現在に立ち向かう、老舗企業の主軸ブランドを担当している3人に話を聞く。

(写真左から)伊勢半 開発本部 商品戦略部 副主事 小栗万祐加氏
浅田飴 商品開発部 市場開発課 課長 兼 社長室 広報課 小杉寛之氏
浅田飴 取締役 総務部 部長 兼 社長室 室長 玉木 卓氏
歴史の積み重ねを生かし次の一歩へつなげる
―現在担当されている商品や仕事の領域について教えてください。
小栗:私は伊勢半の展開するブランドの中でも若年層向けの化粧品ブランド「ヒロインメイク」や「ヘビーローテーション」などを担当しています。見ている領域はブランドの中長期計画の策定から商品周りの市場データ分析・調査などによるブランド管理などです。
玉木:私は浅田飴で総務部長と社長室長を兼務しています。当社では社長室が広報的な役割を担っており、主に社長室では社外と、総務では社内とコミュニケーションを図り、ブランディングについて、さらに会社の方向性について考えています。
小杉:玉木と同じく広報を担当していますが、中でもWebやデジタルでの活動が中心となります。商品開発も兼務しているため、開発企画から販促まで一通り担当しています。当社はもともと水飴タイプの薬から始まった会社です。持ち運び用にキャラメルタイプをつくり、次に暑さに強い飴型へと改良しました。医薬品ですから、商品開発といっても処方を大きく変えることはありません。効き目はそのままに、今の時代に合った製品づくりを心がけています。
―ブランドを通じてどのようなコミュニケーションを目指していきたいとお考えですか。
小栗:ヒロインメイクは「天まで届け!」でおなじみのマスカラが主軸です。少女漫画風のパッケージに加えて高い耐久性がお客さまからご好評をいただいています。このパッケージ=高い耐久性というイメージがお客さまに認識されているので、新商品やリニューアルなどの際はコミュニケーションに齟齬が生じないように配慮しています。
ちなみに、このパッケージのテイストにしたのはプランナーのアイデアによるもの。最初は「こんなパッケージでは受け入れられない」と社内の反対もあったようですが、熱意とやる気で発売までこぎつけたと聞いています。
玉木:当社も2015年から「ドラえもん」をパッケージに起用した商品展開をしています。今の「浅田飴」の顧客層は、50代以上が中心。だからこそ、若年層へのアプローチをどうするかが長年のテーマでした。
浅田飴の特長は、医薬品なのに服用しやすいという点。お子さまの多くは苦い薬が苦手ですから、その特長を生かせるのではと考えました。お子さまに親しんでもらうために「伝統」や「老舗」といった今までのイメージに加え、親しみがあり、世代を越えて長く愛されている「ドラえもん」を起用することになりました。
小栗:歴史で言えば、当社も1825年創業の江戸の「紅屋」がルーツです。モノづくりの原点は江戸時代からずっと受け継がれているんですね。例えば「ヒロインメイク」では、機能性が担保されないうちは発売の延期もザラです。きっと老舗企業には「モノづくり精神」と「チャレンジ精神」の2本柱がとても重要なのだろうと思います。ブランドの核は守りながらも、型にはまらないこと。その両方が求められますね。
小杉:おっしゃる通りだと思います。突飛なことをすれば一時的な認知は上がるかもしれませんが、長期的に見ればこれまで築いてきた信頼を壊すことになりかねない。基本的な姿勢はブレないまま、そこから少しずつ広げていくということはすごく意識しています …