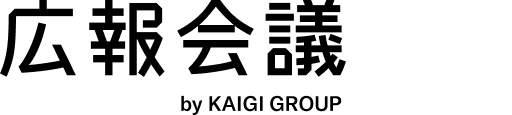【あらすじ】
海に面した、小さなまちの市役所で1年前に生まれた市民サービス課。各部署に届ける市民からの“声”は、ほとんどが苦情メールだった……。ある日、職員の佐原兼四郎は「告発」というタイトルのメールを目にする。そこには、産業廃棄物処理の受託入札にまつわる贈収賄について、詳細な内容が書かれていた。

やるべきことを忘れるな
画面に映し出された文字を読みはじめる。「今日はどんな声をいただいているかな」市のホームページには毎日のようにお叱りや苦情の声が届く。褒められることはまずない。人口4500人余りの小さな市だが公務員に向けられる厳しい眼は他の市町村となんら変わらない。
〝職員の対応がぞんざい〞〝市民サービスなんてかけ声だけでなにもしていない〞〝給料はぜんぶ税金から出ていることを自覚しろ!〞などの苦情メールがほとんどだった。市民サービス課の職員は五人。文字どおり市民へのサービス向上を図ろうと一年前に市長の肝いりで設置された部署だった。
「今日も同じか。どんなに丁寧に対応したってイメージは変わらないっつうの」当番の佐原兼四郎が画面を見てつぶやく。市民の声をすべて聴き、関係部署にその声を届け、行政サービスに反映させていく。市民サービス課の仕事は〝声〞を届ける仕事だった。五人が交代で朝のメールチェックを欠かさず行ってきている。今日も一三件の声が寄せられていた。
職員の態度に対する苦情、手続きの煩雑さに対する苦情、対応の遅さに対する苦情。「はあ……こんなのばっかり読んでいたらこっちのモチベーションが下がるよ」机に片肘をつき、画面をスクロールしていく。
「ん?何だこれ」画面に顔を近づけた佐原が怪訝な表情をつくる。「告発」というタイトルが画面に表示される。クリックして文面を確認する。「これって……」周囲を見渡しても市民サービス課の職員はまだ誰も出勤してきていない。
厄介そうなメールはひとまず保留にし、読み終えたメールを対応部署へ振り分けていく。「もう一回、あのメールを確認しないとな」いたずらかも知れないと思いつつ、佐原の頭の中から「告発」という文字が消えない。
海に面した鳥取県の田舎町で、きな臭いことなどありそうには思えない。それでも初めて届いたタイトルに心がざわつく。メールの振り分けを終え、問題のメールをあらためて開いてみる。文面には事細かく告発の内容が書かれていた。いたずらにしては手が込みすぎている。
メールには、資料まで添付されていた。「議員と産業廃棄物処理会社?本当なら大変なことになるぞ……」市だけでなく、県を巻き込む事件になってしまう可能性すらある。
「今朝、うちの課に届いていた」市民サービス課の課長を務める東川幸作が会議室のテーブル越しに紙を差し出してくる。「今日はどんな苦情ですか」君津凌士が盛大な溜息を吐く。「忙しいだろうけど、まあ読んでみてくれ」
「毎日忙しいのに市民の声にいちいち付き合っていられませんよ。市民サービス課で対応できないんですかね」「うちは届いたメールを各部署に振り分けて、どうしても必要ならうちが対応する決まりになっている。我々の上司が決めたことだろ」上司とは市長のことだった。
君津は〝忙しい〞を口癖に、いつも余裕なく動き回っている。昔、あるテレビ番組で、認められたい、自分を見てほしい、話題の中心でいたいという自己顕示欲の強い人間は、いつも〝忙しい〞を口癖にしていると聞いたとき、君津の顔が浮かんだのを思い出す。君津は東川の二年後輩にあたるが、役職はともに課長だった。
市の業務を仕切っているのが企画課で、その課長である君津は「自分がいなければ業務が滞る」と誤解している典型的な自信家である。東川から受け取った紙を読み進める君津の表情が強張っていく。もともと感情が表情に出てしまう男だ。広報も担当し、地元のマスメディアとの関係も深い企画課で、よく課長が務まるものだと不思議でならない。
「イタズラじゃないですか?」「だといいけどね」東川は抑揚のない声で応じる。君津がまた溜息を吐く。「市民サービス課で裏付けを取っていただけませんか」「うちは担当部署に情報をあげるのが役割だったよな。調査をするのは担当部署。そうじゃなかったか?」東川が淡々と言葉を継ぐ。
「毎日忙しいのに調査をしている時間なんてありませんよ」「今の言葉、そのまま返信しておいていいか?担当部署の企画課長が言っていると」はあ?と君津の声が裏返る。「メールの内容はかなり具体的だ。事実だとしたらこの町を揺るがす大事件になる。調査してイタズラだったらそれはそれでいいんじゃないか。何も起きていないことが証明される。ただ、調査もしない、しようともせず見て見ぬふりをして告発の内容が事実だったときは、どうなる?」
君津は目を合わせようとしない。「事実関係を調べる。市民の声に耳を傾ける...