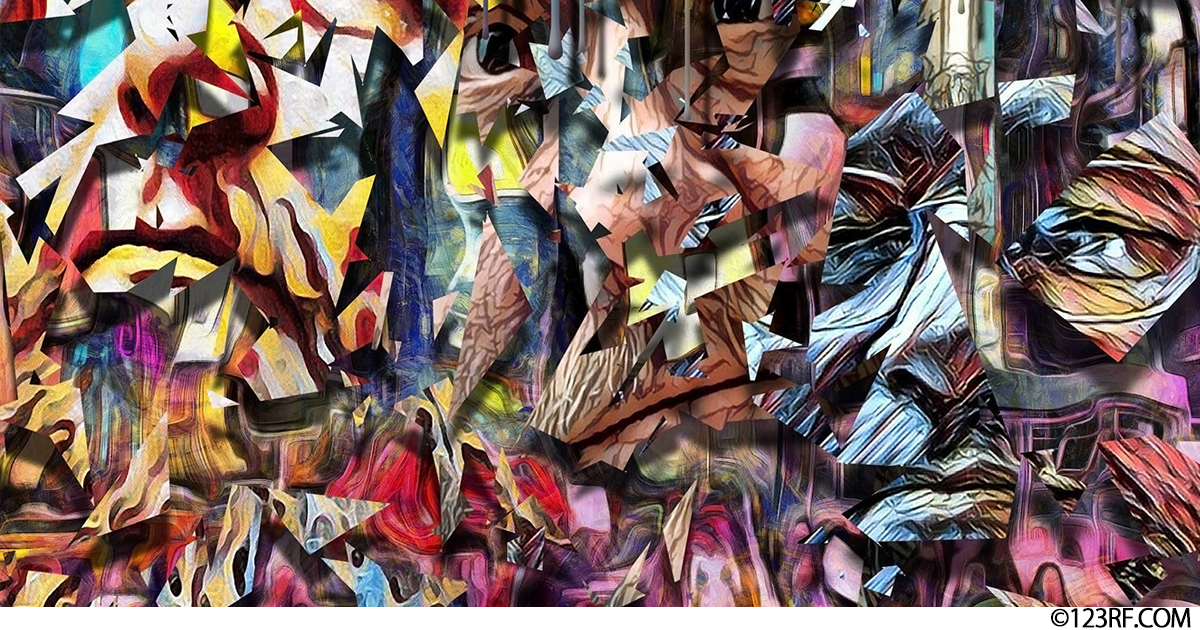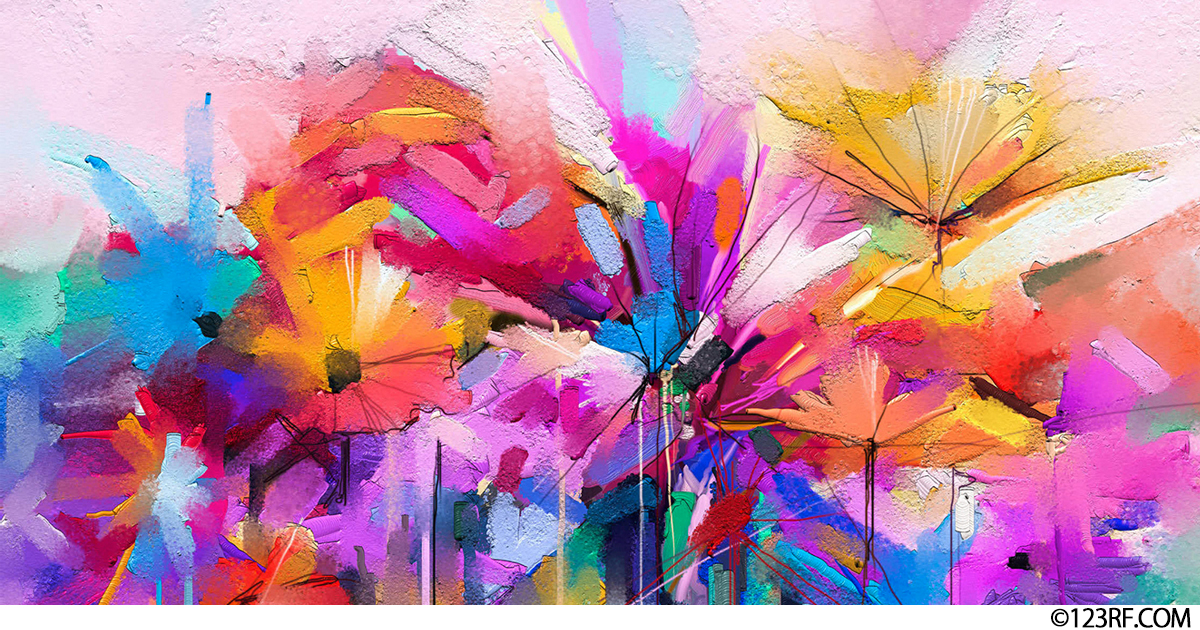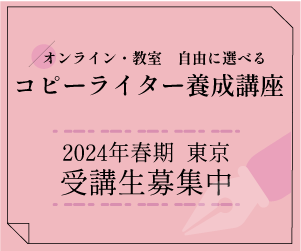【あらすじ】
宮城県石巻市にある小さなかまぼこ屋「川上蒲鉾」。4代目社長の川上有希は、営業の井沢真也と二人、降って湧いた商品偽装の疑惑に頭を悩ませていた。社長室で一人になった有希は、今は亡き義母・佐知子と夫・諒太の写真に思わず話しかけた。そこに一本の電話が入る。相手は、テレビ東北の中丸という記者だった。

©123RF.COM
私が守ってみせるから
摺りガラスがはめ込まれたドアが開く。「おかえりなさい」パソコンに向かっていた高瀬真子が、営業の井沢真也に声をかける「はい、これ」井沢が手にした紙袋を高瀬に差し出す。塩大福が美味しいと評判の店だった。「これ食べたかったんだあ」「工場の人たちにも渡してくれよ」包みを開けると二〇個ある。「了解!」声を弾ませる高瀬の姿に微笑みながら、井沢は社長室のドアをノックする。社長室といっても事務室と扉一枚隔てただけの簡易なつくりだった。
「どうだった?」社長の川上有希が不安げな声で訊く。「ダメでした」「そう……」「責任の所在はともかく、商品が偽装されていたことに変わりはないだろうって」井沢は小声で話すと、大きな溜息をつく。「何を言っても仕方ないわね……ありがとう」有希が落胆の感情を隠して井沢を労う。
「ほかの取引先にもお願いしてきます」井沢が腰をあげてドアノブに手をかける。「待って、今日はもういいわ」有希は微笑みを浮かべていた。「でも社長、このままだとどんどん取引を打ち切られますよ」「今は我慢よ。ちょっと考えさせて」諭すように言う。「分かりました」納得はできないが社長が言うなら仕方ない。井沢は自分に言い聞かせた。
一人になった有希は、椅子に座りなおすと机の上にある2枚の写真立てに話しかける。「こんなとき、どうすればいい?」一枚には義理の母親である佐知子が、もう一枚の写真立ての中では夫の諒太が微笑んでいる。「笑ってばかりいないで、なんとか言ってよ……」有希がわざとふくれっ面をつくり怒ってみせる。次第に諒太の顔がぼやけてくる。
「二人ともたまには相談させてよ」二枚の写真立てを顔に近づけるとそっと目を閉じ、ゆっくりと深呼吸をする。「このまま終われない。お義母さんが守ってきたお店を諒ちゃんと受け継いだんだもん。守ってみせるから……見ていてね」
返事がないことは分かっている。それでも有希は、二人が空から見守っていると信じている。井沢をはじめ頑張ってくれている従業員もいる。〝弱気になっちゃだめだぞ〞諒太の声が聞こえた気がした。
黒南風(くろはえ)の日が続いていたが、ここ数日は穏やかだった。鹿島御児神社で手を合わせてから太平洋を一望できる場所まで歩く。梅雨の晴れ間から降りそそぐ光が水面を照らしていた。「きれい」尾田原有希がつぶやく。「諒太はここで育ったんだね」石巻に有希を連れてきたのは二回目だが、この場所を訪れるのは初めてだった。嬉しそうな笑顔を向けてくる。有希と交際してまだ一年だった。
高校卒業まで地元で過ごした諒太にとって、東京の生活は驚くことばかりだった。生活のリズムが違うのは仕方ないが、なにより食材の豊富さに驚かされた。野菜、肉、魚介類。全国の食材がいつでもどこでも食べられた。〝恵まれた環境は、工夫の知恵を後退させる〞と小さい頃から父親に言われてきた。恵まれた環境のほうがいいに決まってるじゃん。父親の言葉の意味が理解できなかったし、理解しようともしなかった。東京に出た頃には頭の片隅にも残っていなかった。
「おかえり」母親の佐知子が玄関で出迎える。「ただいま」「有希ちゃん、いらっしゃい」「お邪魔します」お辞儀をした有希が玄関の三和土で靴を脱ぐ。「いらっしゃいじゃないよ」佐知子をみて諒太が微笑む。「あらそうだったわ。今日からよろしくね」「こちらこそよろしくお願いします」
「玄関先でやってないであっちに行こうよ」まだお互いによそよそしい二人をみて、諒太がリビングを指さす。リビングに飾られた祖母と父親の遺影に手を合わせる。結婚式は行わず、籍を入れるだけにしようと二人で決めた。「二人で決めたことだろうからいいんじゃない」佐知子は諒太と有希の考えを尊重してくれた。
諒太の中で震災の傷はまだ癒えていない。佐知子も、そして被災地の誰もが同じ想いを抱いている。「お店は?」「今日は定休日」諒太の実家はかまぼこの製造販売を手がけている。二人のパート従業員を雇い、何とか切り盛りしている。毎朝四時には自宅と棟続きの小さな加工場に入り、九時の開店に間に合わせる。小さい頃から見てきた光景だった。変わったのは祖母と父親の姿がないことだった。
「おじいちゃんとおばあちゃんが始めたこの店を終わらせたくはないからね」以前、佐知子がポツリと言ったことがあった。家業を継ぐことなど想像もしていなかった学生時代を思い出す。「これからよろしくお願いします」諒太が言うと有希も改めて母に向けて頭をさげる。「三人でこの店を守っていこう」佐知子が笑顔になる。
有希とは同じ学部だった。大学を卒業して二年が経った頃...