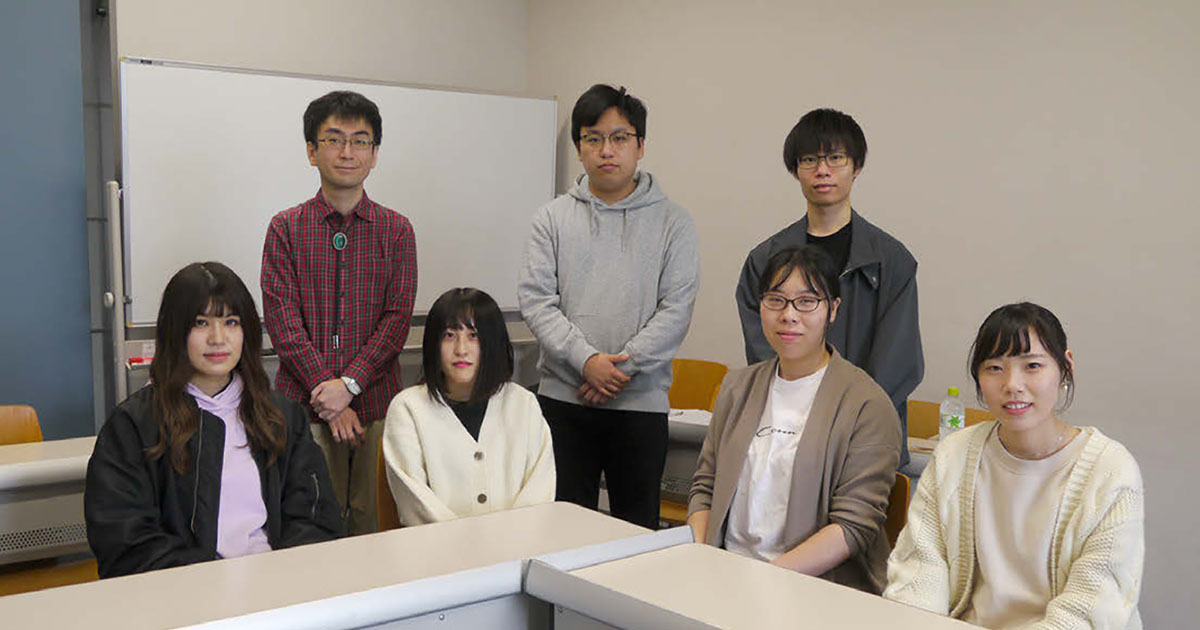メディア研究などを行っている大学のゼミを訪問するこのコーナー。今回は香川大学の西成典久ゼミです。

西成典久ゼミ室のメンバー。
| DATA | |
|---|---|
| 設立 | 2011年 |
| 学生数 | 3年生13人、4年生12人 |
| OB/OGの主な就職先 | 国家公務員(四国財務局、四国経済産業局など)、地方公務員(高松市、丸亀市、岡山市、倉敷市など)、JR四国、四国電力、メディア関係、その他 |
前身である高松高等商業学校の時代を含めると、2023年で創立100周年を迎える香川大学の経済学部。四国でも唯一の経済学部として、中四国における経済界のリーダーを数多く輩出してきた。
想いを具現化するデザイン
学部5つのコースのうち、西成典久教授は観光・地域振興コースに所属しており、ゼミでは香川県のフィードワークを中心に「まちづくり・デザイン」をテーマに活動している。
「ここでいう『デザイン』とは、絵を描いたり、モノをつくる行為のみを指しているのではありません。地域の現場で起こっている様々な社会問題の解決に向けて、想いを具現化させていく行為そのものを『デザイン』と呼んでいます。より分かりやすく言えば、前者を『モノづくりのデザイン』というのに対して、私たちが目指しているのは『コトおこしのデザイン』とも言えます」。
問題解決への共感者を増やす
具体的な取り組みのひとつに、「人と人がつながる場をつくる」コミュニティデザインプロジェクトがある。
これまでに、観音寺市の五郷地区(2010-2012年度)や、三豊市の積地区(2013-2015年度)、東かがわ市の水主地区(2016-2018年度)にてコミュニティの主体づくりに取り組んできた。2019年度からは、高松市の庵治地区のプロジェクトに取り組んでいる。
「まちづくりでは、自分たちだけで完結する『コトおこし』だけでなく、自分たち以外の人たちが継続して出来事をおこしていける状況を意識的につくっていくことが求められています。『状況をデザインする』『出来事をデザインする』といえばやや不遜な言い方かもしれませんが、“人と人がつながる場をつくる”ことで、地域や人は変わっていきます」。
初年度の五郷地区では、ゼミでの活動をきっかけに、“五郷里づくりの会”が結成され、最近では水車の復活活動、耕作放棄地にこんにゃく芋や蕎麦を植えるなど、新たな活動や魅力づくりが芽を出してきているという。
地域の魅力を掛け合わせる
他にも、2015年度から取り組むプロジェクトに、香川の老舗観光地である屋島の観光再生をテーマとしたものがある。
ゼミでは「日本の夕日100選にも選ばれている屋島の夕夜景が活かしきれていない」という観光課題に着目し、そこに香川の伝統工芸である「讃岐ちょうちん」を掛け合わせ、「世界でここでしか見ることができない風景をつくろう」というアイデアが生まれた。
2016年度には、「屋島の夕夜景」と「讃岐ちょうちん」のコラボを楽しめる場づくりに取り組み、社会実験として「屋島山上ちょうちんカフェ」を夏季限定で開始。初年度は10日間で1027人、2年目には10日間で2279人の方々が来場するなど、盛況を得た。2019年度には全国学生観光論文コンテストにて「屋島山上ちょうちんカフェ」の取り組みが観光庁長官賞を受賞することとなった。

屋島山の夜景を楽しみながら「讃岐ちょうちん」の灯りのもとで食事を楽しめる「屋島山上ちょうちんカフェ」。オリジナルメニューやちょうちんづくりのワークショップも開催。
共感されるビジョンを描くスキル
「社会が多様化・混迷化するなかで、地域活力の低下という問題は個別的な原因で生じているのではなく、様々な分野の原因が連関して生じている総合的な問題です。個別的な問題解決に終始せず、総合的な問題解決を目指し、多くの人に共感されるビジョンを描ける能力。ゼミ生にはこの『デザイン的教養』を高めてもらい、卒業後も当事者意識をもって解決に向けた行動を続けてほしいと思っています。まちづくりや地域活性の中核を担う人材に育ってくれたらうれしいですね」。
地域都市の複合的な社会問題に学生とともに挑む
東京出身の西成教授。地域開発のコンサルタント会社にて地域づくりのプロジェクトに携わるなかで、大都市ではなく、地方都市や田舎で多くの社会問題が横たわっていることを体感し、自分自身も課題解決に向けて貢献したいという想いが生まれたという。
「香川には就職というご縁で移住してきましたが、もともと田舎暮らしがしたいと思っていたので、とてもいい自然環境のもとで仕事ができています。学生たちも素直な学生が多く、とてもやりやすいです。地域に対して問題意識を持った状態で入学してくる学生が増えてきており、既得権益でがんじがらめになっている地域を少しずつ変えていってもらいたいと思います」。
今後は「持続可能な暮らし方を実践したい」と西成教授。そのための実験的な場所を得て、教育と実践を交えた暮らしに取り組んでみたいと語った。

西成典久(にしなり・のりひさ)教授
専門は都市計画。まちづくりの実践家として、地域の潜在的な魅力や活力を活かしたプロジェクトを手掛ける。「屋島山上ちょうちんカフェ」にて観光庁長官賞、「五郷里づくりの会」が農林水産省の中四国農山漁村の宝に選ばれる。NHK『ブラタモリ』にて高松編案内人を担当。