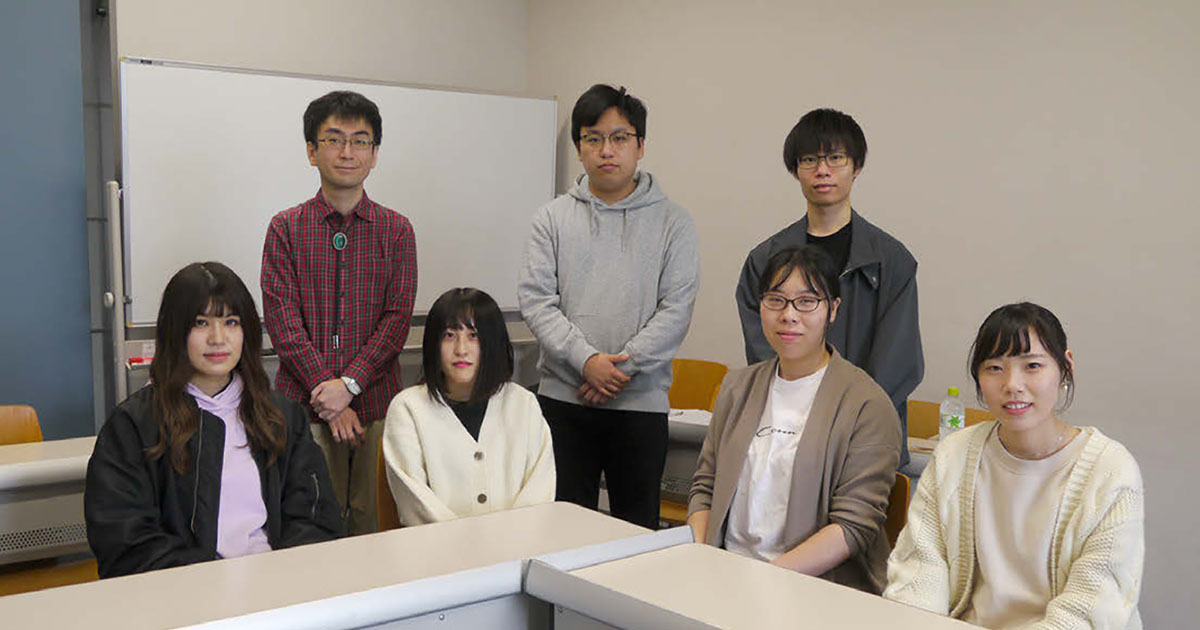メディア研究などを行っている大学のゼミを訪問するこのコーナー。今回は千葉商科大学の勅使河原隆行ゼミです。

ゼミで開発した商品のPRの一環としてラジオに挑戦する勅使河原ゼミのメンバー。
| DATA | |
|---|---|
| 設立 | 2014年 |
| 学生数 | 3年生20人、4年生21人 |
| OB/OGの主な就職先 | 千葉県警察、防衛省海上自衛隊、君津市農業協同組合、ちば東葛農業協同組合、社会福祉法人佑啓会、医療法人財団IMSグループ、エヌ・シィ・ティ、BRAISE、RICOH、Audi柏の葉 |
2014年の学部の開設と同じく、スタートした勅使河原 隆行教授のゼミ。主に千葉県山武市をフィールドとして「地域活性化」に関する研究を行っている。研究テーマに関する基礎知識を身につけるだけではなく、アクティブ・ラーニングを通じて、学外に出て企業や地域と連携した、実践的な活動を行っている。

地産地消の商品開発を通じて、千葉県山武市の活性化による持続可能な地域づくりに貢献。ゼミ生は「山武市応援学生隊」に任命されている。
人のつながりでの地域活性化
「地域活性化を目指すための方法には様々なものがありますが、ゼミでは、地域住民が主役になり、人と人とのつながりを大切にしながら盛り上げていく方法について研究しています。地域に大学生などの若い力を加えることによって斬新なアイデアが生まれたり、地域が明るくなったりすることを期待しています」と勅使河原教授。
商品開発、被災地支援など様々な取り組みを行うゼミだが、「2つのビール(ルビール・ネギラエール)をつくったことが印象深いです」と、長谷川瑞貴さん(4年)は話す。まず2021年に、障害者福祉施設で栽培されたトマトを使用した「ルビール」を開発。そして2022年は、山武市の名産品である海水ネギを使用した「ネギラエール」を開発した。「商品名は、ネギだけに『ねぎらい』と『エール』を掛け合わせました。すべての人に向けた『どんな困難も乗り越えていこう!』という思いを込めています」(長谷川さん)。
開発のきっかけのひとつには、コロナ禍があったという。「『お酒を飲む交流ではなく、お酒をつくることで交流をしよう!』という発想は面白いと思いました。学生自身もコロナ禍で活動が制限されている中、出来ることを見つけて、前向きに進んでいる姿が印象的でした」と勅使河原教授も振り返る。

ゼミ生が企画・試飲・味の調整・PRまで行ったビールづくり。2021年は障害者福祉施設で栽培されたトマトを使用した「ルビール」
メディア向けに商品発表会も実施
商品開発では、商品のテーマ・コンセプト・商品名・ラベルデザイン・販売先の決定、生産者との打ち合わせなどすべてゼミ生が主導。完成後にはゼミ生が手作業でラベルを貼り、販売先への納品、商品のPR、販売イベントなどの一連の作業を、ゼミ生全員で2~3カ月かけて行った。商品のPRの際には大学の事務局と連携をしてメディア向けに商品発表会も開催したという。
「学生たちには、単発での商品開発で終わらせず、継続性、成長性、発展性を考え、意外性から話題性につながることを意識するように伝えています。メディア取材もたくさん経験することになるので、スケジュール調整も含めて、打ち合わせナシでも対応できる力が身につくと思います」(勅使河原教授)。
商品開発はビール以外にも継続的に行っており、地域の特産品(主に農産物)の旬の時期に合わせて、2022年は5月にネギ、いちご、菜の花を使ったドレッシングを開発、販売した。
「単に時期だけではなく、地域住民、農産物の生産者、道の駅の方などからの聞き取り調査や、社会的課題(災害など)を視野に入れて企画を立案していきます。そのため、毎年何月に何を実施するということは決まっておらず、その時の状況に合わせて継続的に行っています。学生たちには、先輩が実践してきたことをただ受け継ぐ(引き継ぐ)のではなく、バージョンアップさせていってほしいと話しています」(勅使河原教授)。
既存の活動やひとつの学びに捉われず、幅広い経験が積める勅使河原ゼミ。岡田陽奈子さん(4年)は、「地域活性化に関する取り組みはもちろんですが、商品のPR方法を実践的に学ぶこともできます。そして商品開発の企画を通して、食品ロス問題や障害者の就労支援などSDGsも意識するようになりました。これらの活動は、社会に出てからも役に立つと思いますし、卒業後も大学と継続して関わりながら、一緒に社会課題の解決を目指すための取り組みを行っていくことが私の夢です」と話す。

2022年は山武市のネギ・いちご・菜の花を使用したドレッシングを開発・販売した。
2014年に人間社会学部が新しく設置されたことを機に、千葉商科大学に着任しました。人間社会学部の学生は、とにかく素直ですし、何事にも挑戦してみようという前向きな学生が多いです。大学ではアクティブ・ラーニングを通じて実践的に学んでいますので、社会に出てからも即戦力で活躍できると思います。

勅使河原 隆行(てしがわら・たかゆき)教授
千葉商科大学大学院政策研究科政策専攻博士課程修了。博士(政策研究)、社会福祉士。主な著書に『入門社会保障』(ミネルヴァ書房、2021)、『これからの「共生社会」を考える』(福村出版、2020)、『はじめての人間社会学』(中央経済社、2020)、『地域福祉の原理と方法第3版』(学文社、2019)など。