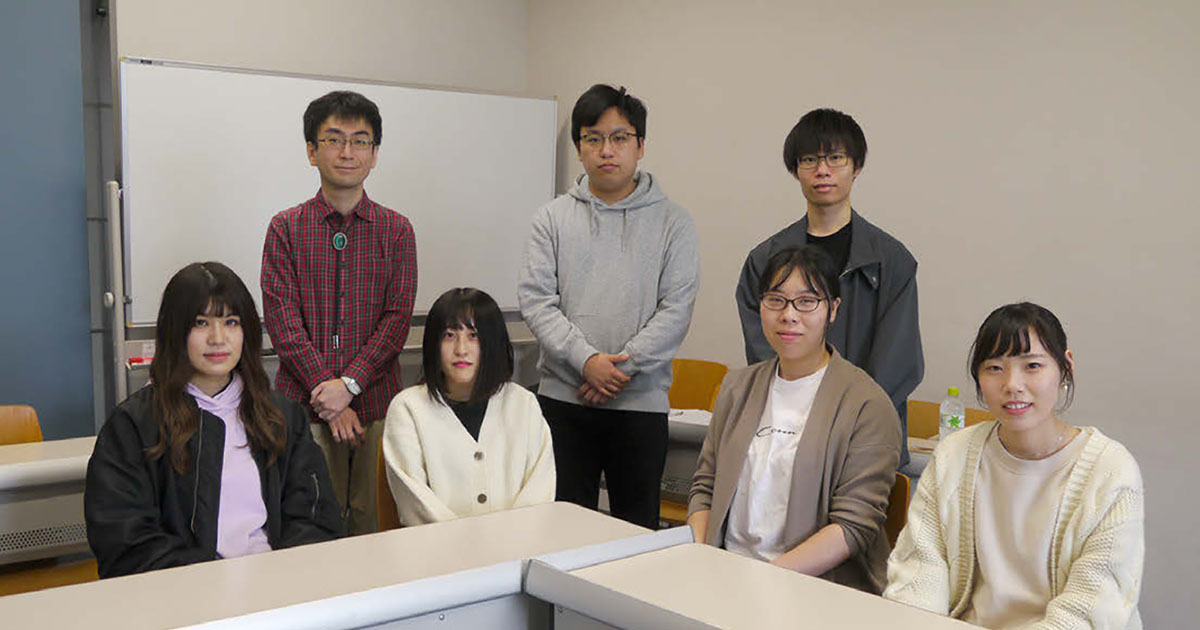メディア研究などを行っている大学のゼミを訪問するこのコーナー。今回は北海学園大学の下村直樹ゼミです。

下村直樹ゼミのメンバー。
| DATA | |
|---|---|
| 設立 | 2006年 |
| 学生数 | 2年生8人、3年生6人、4年生6人 |
| OB/OGの主な就職先 | ナシオ、サツドラ、ツルハ、コープさっぽろ、デイリー・インフォメーション北海道(現:イースト・デイリー)、日本特殊陶業、北海道中央バス、三菱電機ビルテクノサービス、アルページュ、損保ジャパンなど |
北海学園大学 経営学部 下村直樹教授のゼミでは、北海道内の経済・経営・商学部のある社会科学系の大学で唯一、マーケティング・コミュニケーション(プロモーションとも呼ばれる)や広告をメインに学ぶゼミだ。
大学生の頃にしかできない「研究」に重き
ゼミは2年生から4年生までの3年間。「マーケティング・コミュニケーションに関する知識を身に付けて、世の中に氾濫するメディア(とその情報)を冷静に捉えることができるようにするのが目標です。メディア(とその情報)に踊らされない人間になってもらいたいと考えています」。
ゼミの内容としては、広告、セールス・プロモーション、パブリック・リレーションズといったマーケティング・コミュニケーションを構成するものに加えて、消費者行動、ブランド、口コミ、それらを分析するためのデータの集め方と分析までを範囲として、教科書や論文を使って学んでいく。
「近年の大学では、企業と協働して何かに取り組むことが求められていますが、このゼミでは大学生の頃にしかできないこととして『研究』を重視しています」と下村教授は説明する。
研究のため、学生自ら動画も撮影
3年次からは、2~3名の学生を1グループとして、学生自らがマーケティング・コミュニケーションにかかわる問いや、仮説を立て、それをデータや文献を集めて検証するというグループ研究を行う。
とあるグループが取り組んだのが、「YouTube動画広告におけるスキップボタンの有用性」というテーマ。
「検証するために使う動画をどうするかを検討していたところ、既存の動画を用いてもすでに印象や評価ができ上がっているため、有用性に対する正しい評価がされないという結論に至り、新たに自分たちで撮影することになりました。中立的な態度を持つものを選んだところ、札幌の観光名所の動画を撮影することとなり、秋から冬の寒空の下で学生たちが撮影した動画は、学生の自主性と、研究に妥協せず向き合った結果からできたもので、とても記憶に残っています」。
グループ研究で学んでほしい心構え
ゼミの基本はグループワークやグループ研究など、複数人での活動。「メンバーに対する思いやりや助け合い(自分のことを優先させすぎて、他のメンバーの足を引っ張らない)、足りないところを補い合う、という社会人になら当たり前のように思われることが大切。ひとりで行えることには限界もあるので、こういった協力して行うことの心構えと行動をしっかりと身に付けてほしいです」。
4年次には、ゼミ活動の集大成として、自分たちがお気に入りの製品やサービスを取り上げた広告戦略を企画。具体的な広告物を作成する取り組みを卒業制作として行う。

ゼミでの活動は、少人数グループでの研究がメインとなっている。自分たちで問いや仮設を設定する。
受動的、学びっぱなしではダメ
そのほかゼミでは、学生自ら街中に行って撮影してきた広告について、その広告で訴求されているものや目的などを考え、広告周辺の様子などを交えてのプレゼンテーションも、時折行っている。
「普段、道を歩いていても広告を自分から見ることがなかった学生たちが、この発表の後になると『地下鉄の車内にある広告に目が行くようになった』『自分の目の前にあるこの広告は何のために行っているのだろう?』とその広告の目的や効果について考えるようになるんです。受け身ではなく、ポジティブに情報を取りに行く意識を持ってもらいたいと考えています」。
サイエンスとアート 両面から研究できる魅力
当初、商学や流通を専門に研究しようとしていたという下村教授。しかし、指導教官からの提案で広告に関して学んでいく内に、次第に広告分野に魅力を感じていった。「広告効果は消費者の心理や行動といったサイエンス、また、広告戦略の中でもコピーやグラフィック・映像などはアートにかかわるという、(両極端でもある)サイエンスとアートの両面から研究できることに大きな魅力を感じました」。
現在進めているのが、物語をどのようにマーケティングに取り入れるかの研究だ。
また、それと平行させて、昨今インターネット広告においても問題となっている広告表現や広告媒体の倫理に関する研究にも取り組んでいるという。
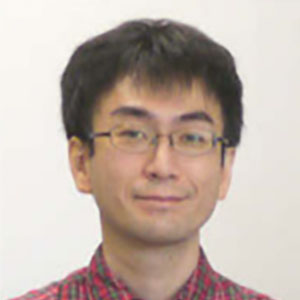
下村直樹(しもむら・なおき)教授
北海道大学大学院経済学研究科博士後期課程修了(博士・経営学)。北海道大学大学院経済学研究科助手、愛知学院大学商学部専任講師、北海学園大学経営学部専任講師・准教授を経て、2013年から現職。共著に『マーケティング・コミュニケーション』など。