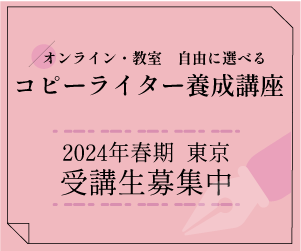文具メーカーでの粉飾決算 踏みにじられた従業員の誇り〈後編〉
【あらすじ】
創業50周年を迎えた文具メーカーBANIWAで粉飾決算が判明。社長の橋川亨が財務部長の富樫雄介に指示し、不正操作された額はおよそ35億円。橋川の背後には香港の投資グループの影。追及に開き直る橋川をよそに、常務執行役員の荻原磯路を中心に広報部長の舟屋総司、広報部員の吾妻晋太郎らは対策を協議する。

つぶされてたまるか!
自社で粉飾が行われていたことに、広報部の吾妻晋太郎はショックを受けていた。愛され続けるBANIWAを目指し、マスメディアへの広報活動を精力的に行ってきた。ほかの従業員もそれぞれの現場で思いをともに動いてきたはずだ。
世界に一三〇店舗を構える"BANIWA"。十二カ国に進出し、人々の日常に寄り添う文具として浸透している。そのブランドに傷がついてしまった。先ほどまで開かれていた役員会議室での紛糾がすべてを物語っていた。
三年前の秋から行われていた粉飾会計処理。社長の橋川亨が主導し、財務部長の富樫雄介が経理を操作していた。それが突然明るみに出て、社内は混乱していた。
銀行出身の橋川が役員らに相談せず、独断で行った売上の水増しや商品在庫の書き換えといった利益操作は許される行為ではない。「ブランドだけで生き残れる時代ではない。積極的に海外に出て行かなければ取り残されてしまうことは明らかだ。仲良しグループのままでは早晩結果は見えている」橋川が会議の場でもっともらしく嘯(うそぶ)いたが、香港を拠点とする投資グループの影を隠す口実にすぎない。影を隠すための粉飾であることはもはや誰の目にも明らかである。
常務執行役員で店舗統括責任者でもある荻原磯路は、役員たちが出席した会議で、たたき上げの迫力をみせた。「今は、当社の不適切な会計処理、つまり粉飾会計の事実を把握して適正な会計処理に戻す。その対策を考える場であるべきだ。口喧嘩などしている無駄な時間はない」社長の橋川は口から泡を飛ばしながら抗弁したが荻原が一蹴した。今は粉飾公表の対策を考えねばならない。
"ブランドの失墜"。その言葉が脳裏から消えない。会社に裏切られたという思いが体に重くのしかかり、鉛の塊が足にまとわりついているようだ。一歩進むたびに靴底でBANIWAを踏みつけている錯覚にさえ陥る。前を歩く男たちはどう思っているのか、その背中に問いかけたくなる。
怒りを我慢しているように見える広報部長の舟屋総司に比べ、粉飾操作の当事者である富樫の背は丸く、力がない。先導する形で歩いていた荻原が歩をとめ、部屋に入る。舟屋、富樫に続いて吾妻も足を踏み入れた。「今からここが対策本部だ。BANIWAは何がなんでも守り抜く。全員で守り抜くんだ」荻原の言葉をかみしめるように三人がうなずく。「BANIWAはつぶさない」舟屋が口角を上げる。
「富樫さん」「……はい」荻原の呼びかけに富樫が掠(かす)れた声で返事をする。「さっき舟屋さんが言った言葉がすべてですよ」「えっ……」「原点回帰。誰かを責めている時間はない」荻原が舟屋の言葉を引用した。
吾妻がふと壁に目をやると、会議室のものと同じ墨書の額があった。"お客様の笑顔を想像しろ やるべきことが見えるはずだ"。荻原も額に目をやり、柔和な顔になりながらつぶやいた。「これがすべてだよ」「馬庭貞三の顔に泥は塗れない、ですね」舟屋が続く。「ほんとに……申し訳ありませんでした……」富樫が嗚咽を漏らしながら、膝につくほど頭を下げた。
五十を過ぎた男が目の前で泣く姿に、吾妻はかすかな怒りを覚えた。しかし同時にサラリーマンという立場の悲哀も感じていた。「頭を下げる相手は全従業員だ。私じゃない。頭の下げ方は改めて考える……今は前に進むぞ」荻原が富樫を見据えた。
「三十五億円か……」椅子に身体をあずけた荻原がつぶやく。富樫は"粉飾"にいたった経緯、橋川からの指示内容、粉飾の詳細、加担した者などを事細かに説明していく。全容が明らかになるにつれ、部屋の空気が重くなる。
昨年は創業五十周年の行事で賑わい、千百人の従業員はやる気にあふれ、社内は熱気に包まれていた。馬庭貞三がつくったブランドは次世代に引き継がれ、新たなステージに向かうはずだった。しかし今、対策をひとつ間違えれば消滅させてしまうかもしれない …