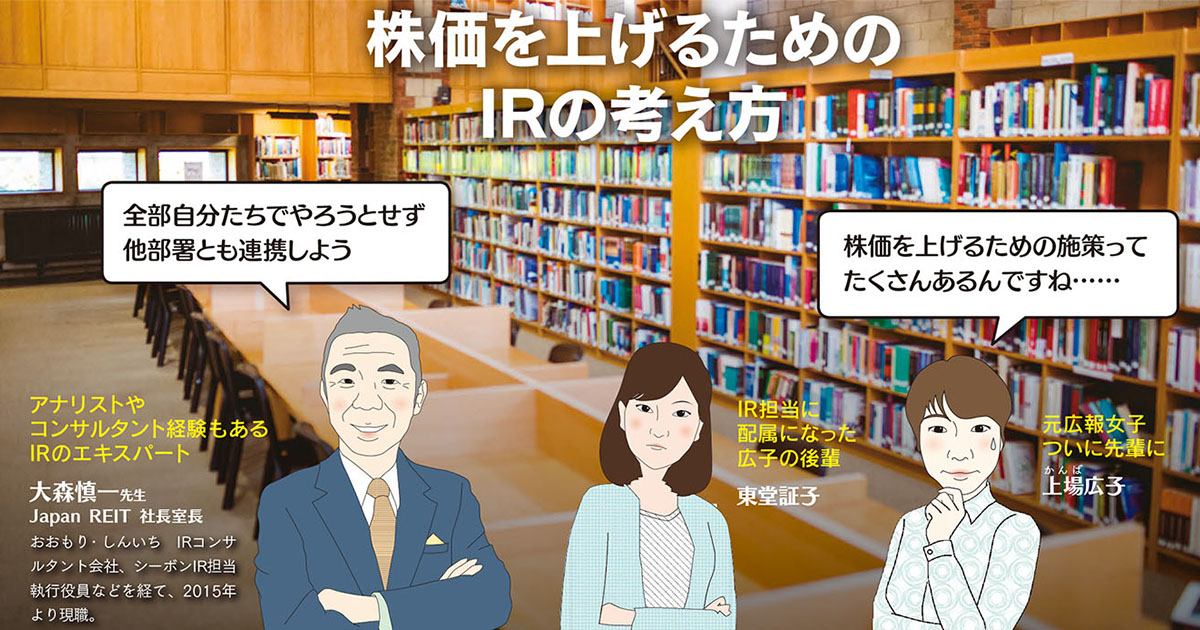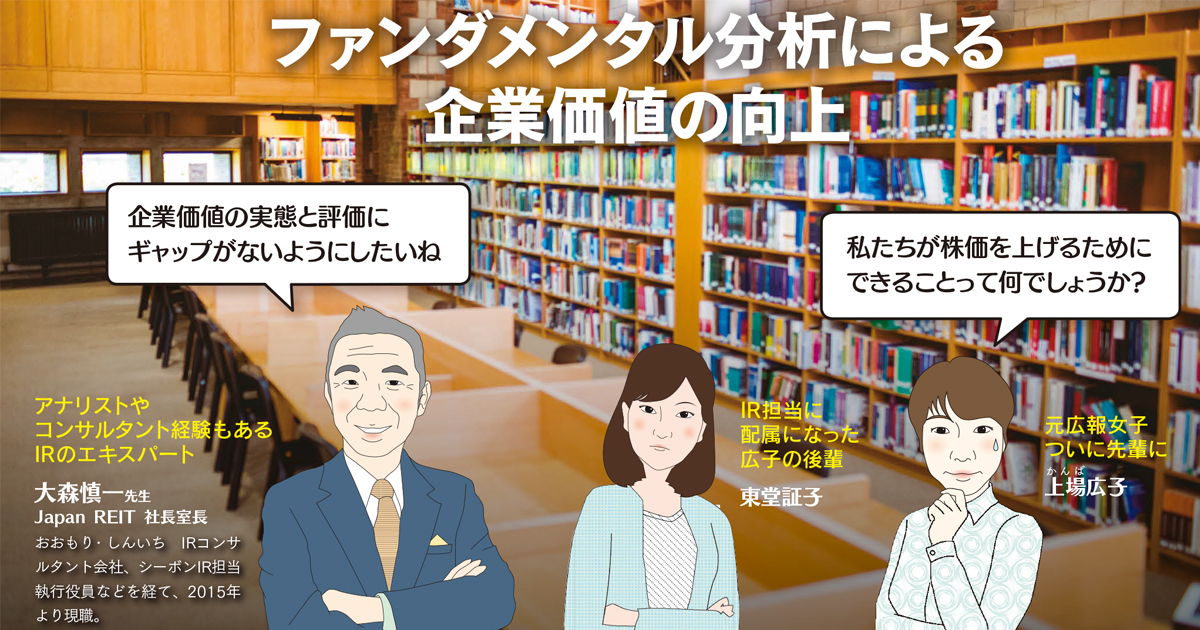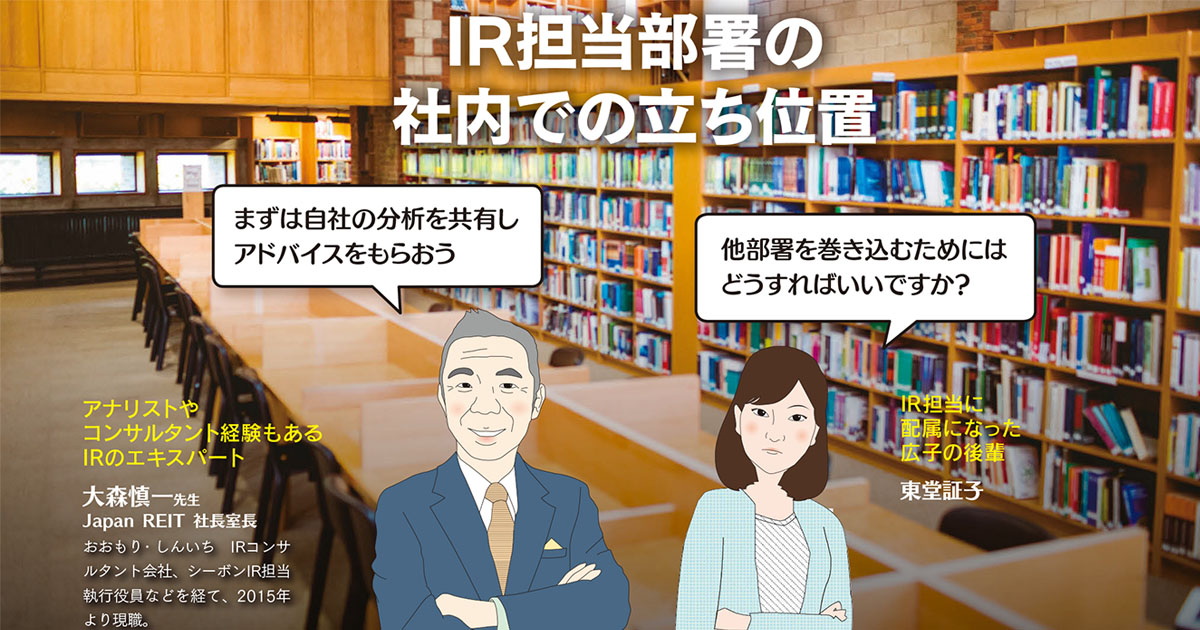IRの効果測定についての社内発表を無事終えた広子たち。そのフィードバックを受けようと大森先生の元を訪れたが、いつしか「株主数」を指標にした効果測定の話題に。

広子・東堂:こんばんは。
大森:こんばんは、今日はなんだか軽やかだね。
広子:はい、全社マネージャー会議、無事乗り切りましたから。
大森:おお、それはよかった。どう乗り切ったんだい?
東堂:時価総額と業績推移のグラフに、主なIRトピックスの発表タイミング、各種会社説明会の回数などを組み合わせて説明しました。
広子:業種別トピックスで指数化した時価総額の推移も反応がよかったです!業界内での弊社の実力みたいなものですから。
大森:なるほど、けっこう頑張ったね。
広子:おかげで、社長も喜んでくれて。
東堂:喜んでいただいたまではよかったのですが、科学的分析による「効果測定」の手本として、今後も同様に発表してほしいって。
大森:おやおや、大変だね。
広子:そうなんです。この作業量を毎回続けるのもつらいですし……。なので、株主関連の数値で効果を測定する、という前回のお話の続きをぜひお聞きしたくて。
株主数を指標にする意味
大森:オッケー。じゃあ、僕の考えを披露しましょう。それはずばり、「株主数」だ。
広子:えっ、株主数ですか?
大森:意外かい?
東堂:正直意外です。
大森:では、僕の考えを説明しましょう。
広子・東堂:はい!
大森:効果測定の数値としての条件を覚えている?
東堂:はい。まず、❶測りやすさですよね。客観的に効率的に測れるかどうか。次に❷行動・施策、因果関係のある測定値かどうか、でしたよね。
広子:そういう意味だと、株主数は測りやすいですね。株主名簿も専門の会社が管理して定期的に報告してくれますから、簡単ですし第三者の目が通っています。
大森:そうだね。
東堂:でも、2つ目の施策と因果関係の部分はどうでしょうか?
大森:問題はそこだね。効果測定をするんだから、IR活動の目的・目標の段階別に整理しつつ確認しよう。
広子:まず、❶開示義務を果たすですね。次に ❷認知度を向上させる ❸実際に投資してもらう ❹ファンとして定着してもらう、でどうでしょうか。
大森:いいね。じゃあ適時開示という基本がしっかりできたら、何が変わると思う?
東堂:情報が株価にきちんと反映されて、適正な株価になる、というところでしょうか。
大森:そうだね。だから日々の新しい情報に対する反応が小さくなるとともに、買い・売りの判断が同時に出てきやすくなる。なので、株価の動きも小さく、売買株数が増えるという理屈なんだ。結果、株式が分散され、株主数が増加する、というのが僕の考え方だね。
広子:なるほど……。なんとなく分かるような気はします。
大森:いまひとつ納得していないようだね?
東堂:理論的にはそうなるとは思うのですが……。
大森:でも逆に考えて、情報開示が偏っていたら、いい情報を持っている一部の株主が買い増しするから株主が減っていく、というのは想像がつくよね?
東堂:たしかにそうですね。
大森:株主数を直接増やすような施策、株式分割や株主優待の変更などを行った場合の影響も大きいから万能ではないけど、ひとつの指標としては有効だと思うよ。
株主の「属性」に着目
大森:もうひとつ言うと、株主には属性があるから、自分たちのIR目標に応じてアレンジすればいいんだよ。広子さんたちの会社だと、「ファン株主を増やす」という目標もあったね。
広子:そうですね。製品の愛用者に株主になってほしい、という社長の想いを受けて。
大森:じゃあ、少し手間はかかるけど、ファン株主の数を追ってもいいんじゃない?
広子:株主の中のファン株主って、管理したことないですね……。
東堂:株式は夫の名義で妻が購入者だったりする場合もありますし …