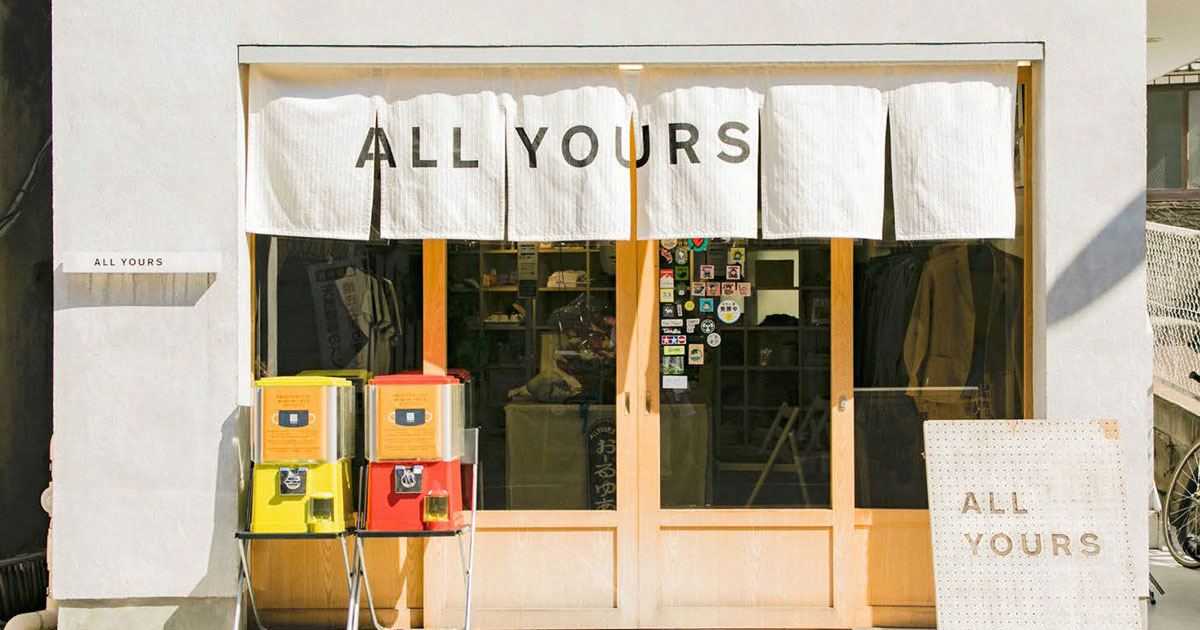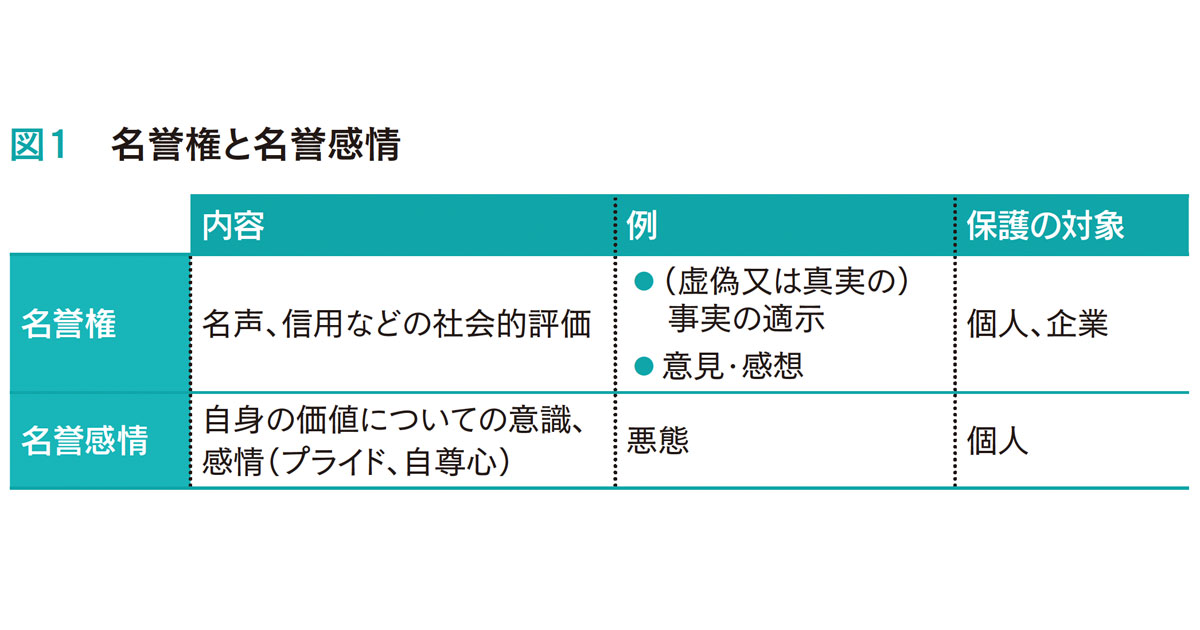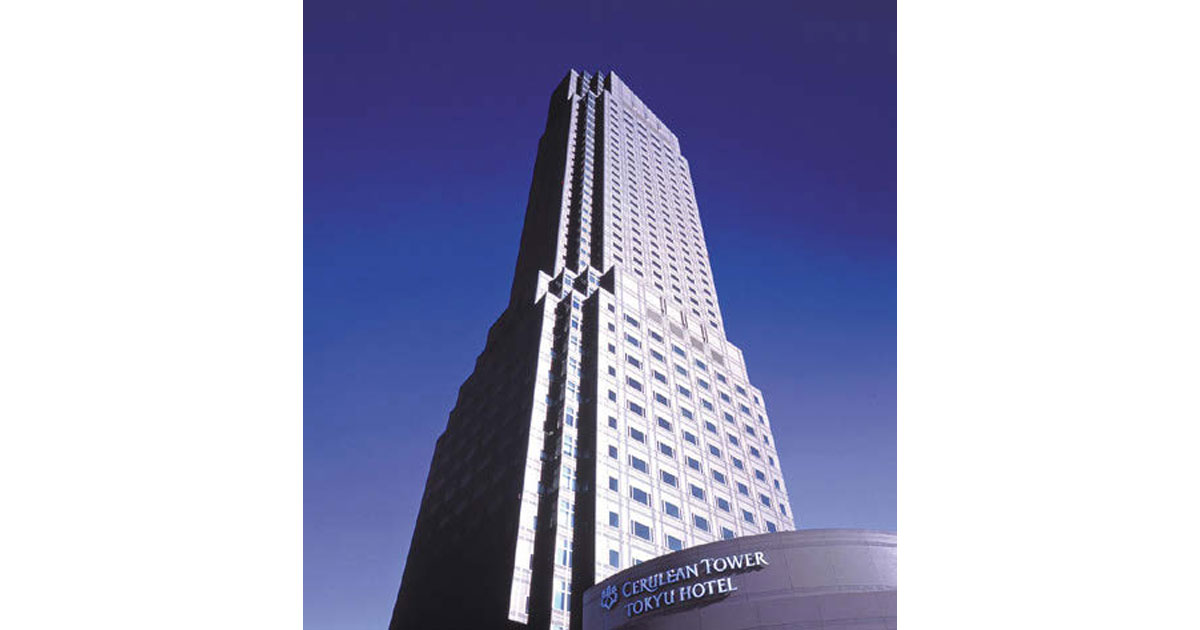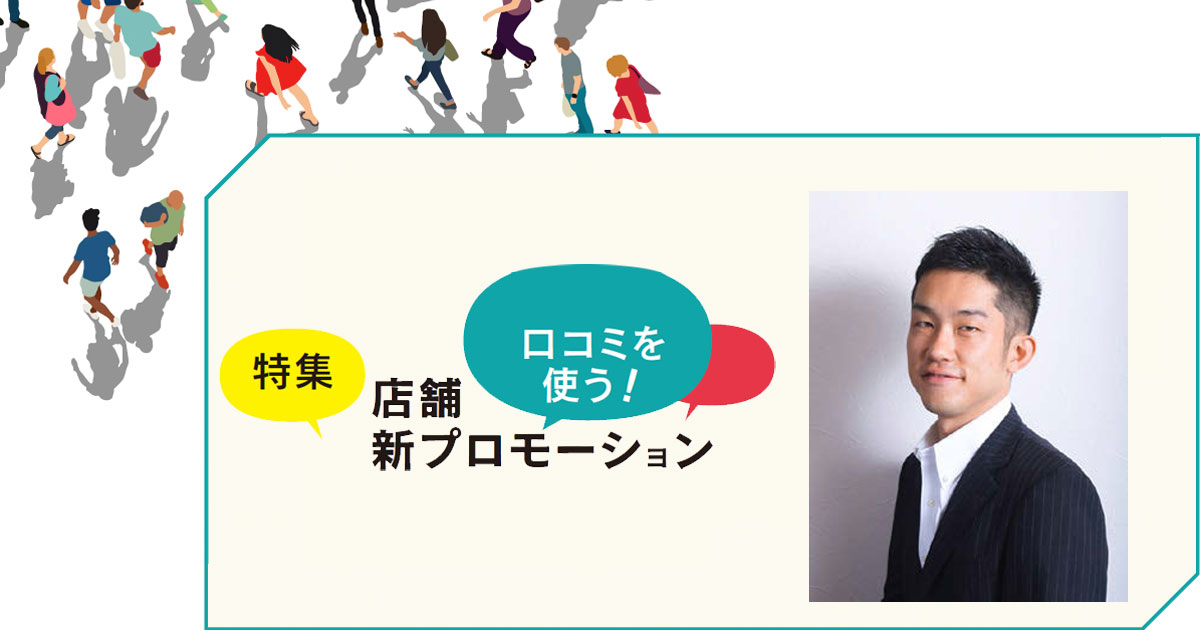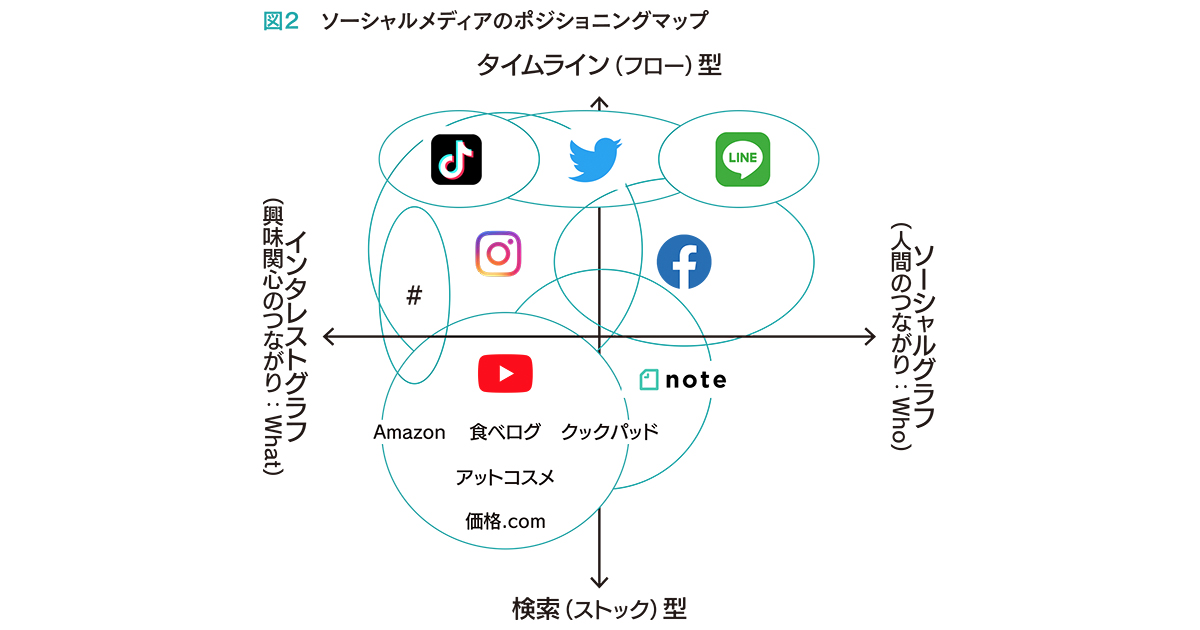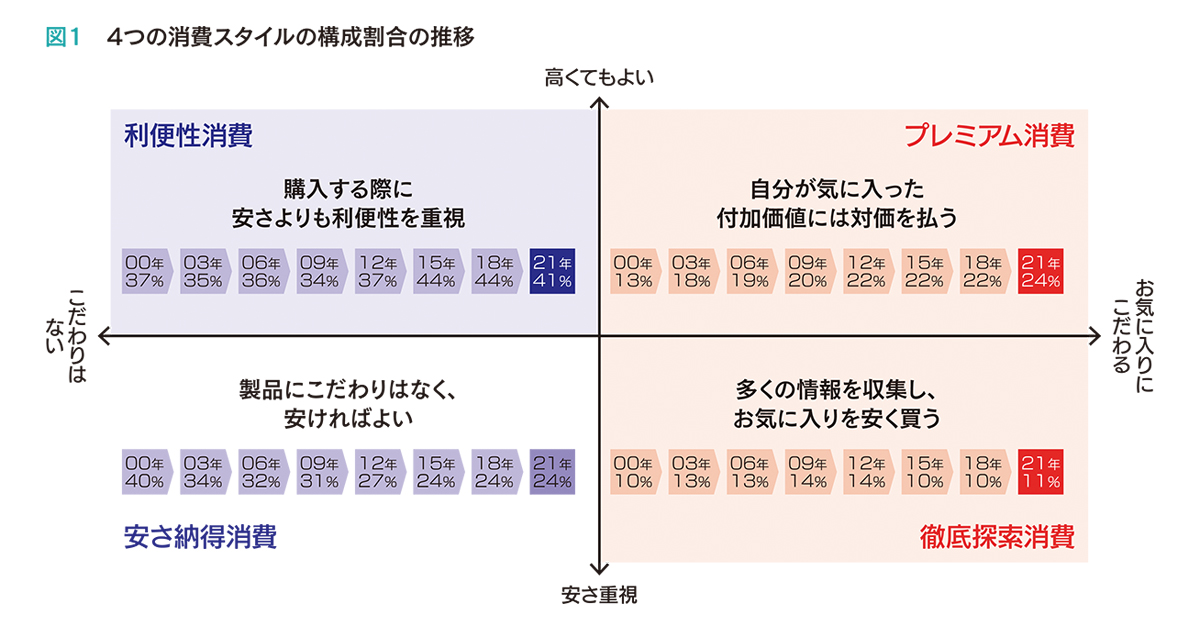宿泊から食事まで、滞在した顧客に上質な体験を約束する「セルリアンタワー東急ホテル」。同ホテルは2017年より顧客コミュニケーションの強化施策を多く実施しており、いわゆる「口コミ対応」についても、専任担当者を配置することで満足度の向上に寄与している。
口コミ返信は具体的な内容で
──カスタマーリレーション部の設立目的について教えてください。
毛利:当社のカスタマーリレーション部は、2017年4月に発足しました。従来は「マーケティング」という大きなくくりの中で、主として企画宣伝業務を行っていたのですが、時代の流れに対応できるように特化したかたちです。口コミ対応以外には、会員組織の企画運営や、販促業務にも携わっています。
──特に口コミ対応に力を入れていくようになったのはなぜなのでしょうか。
毛利:やはり、お客さまの生の声の影響力を強く感じたからですね。自分自身の経験に照らしてみてもそうなのですが、来館するか否かを決定する際に、「すでに利用している方の感想」というのは、とても参考になります。その点から見ても、各種Webサイトで触れることのできる口コミや点数というのは、新しいお客さまとの大事な接点になるものだと考えています。
もちろん、口コミはお褒めの言葉だけではないこともあります。「これがあったら良かったのに」といったお声も多く、特にハード面に関係するご要望はすぐには対応できないこともあるのですが、いただいたお声は全て現場と共有して、できるものから着実に改善していけるようなPDCAサイクルを作っています。
──現在、対応されている口コミサイトはいくつありますか。
弘田:国内、海外を含めて15以上のサイトに対応しています。1カ月あたり150件以上は口コミがありますね。各種業態の稼働率によって口コミ数も上下するので、週頭の月曜、火曜などは特に口コミが多く入ってきて、対応に少し手間取るときもあります。
──返信の際のフォーマットはあるのでしょうか。
毛利:フォーマットというものは、特に決めてはおりません。口コミ対応をする私と弘田の中で「なんとなく、こうすればいいかな」という感覚は共有していますが、定型文のようなものはないですね。大切にしているのは、「どんなことへ感想を寄せてくれているか」をしっかり読み込み、返信することです。例えば「景色が良かった」とあれば、「季節や時間によっても見える景色が変わってくるので、ぜひまたご来館いただき楽しんでほしい」といったように、具体的な内容に...