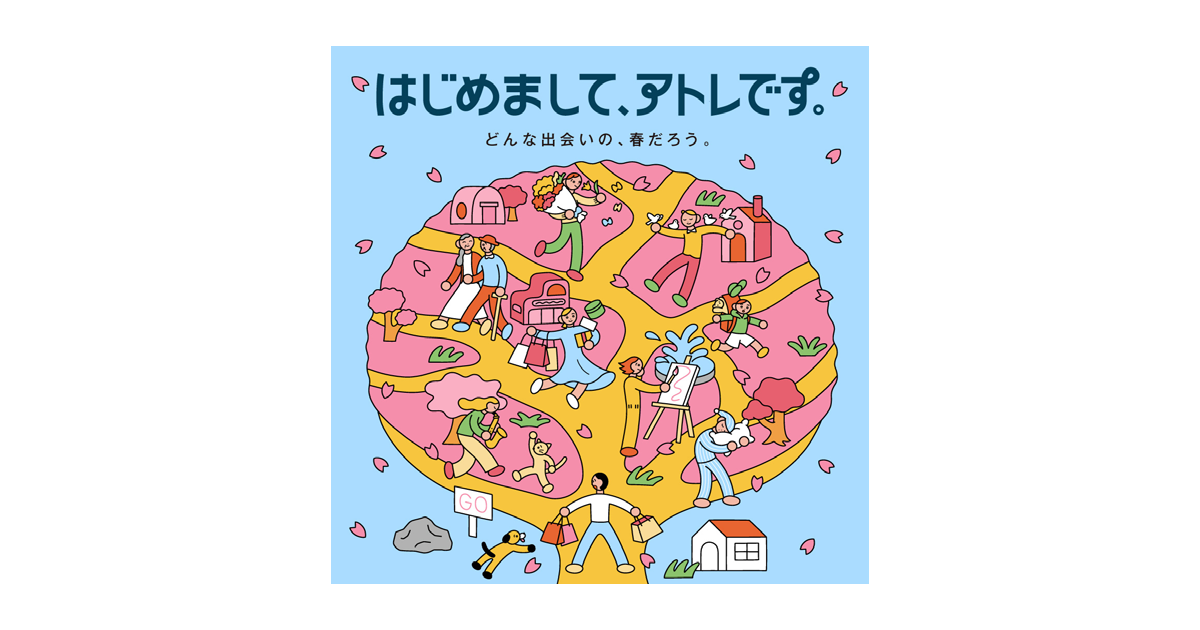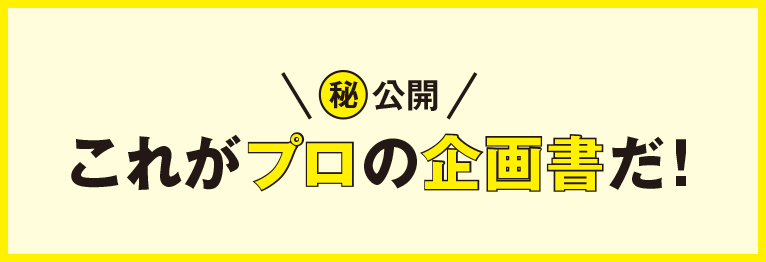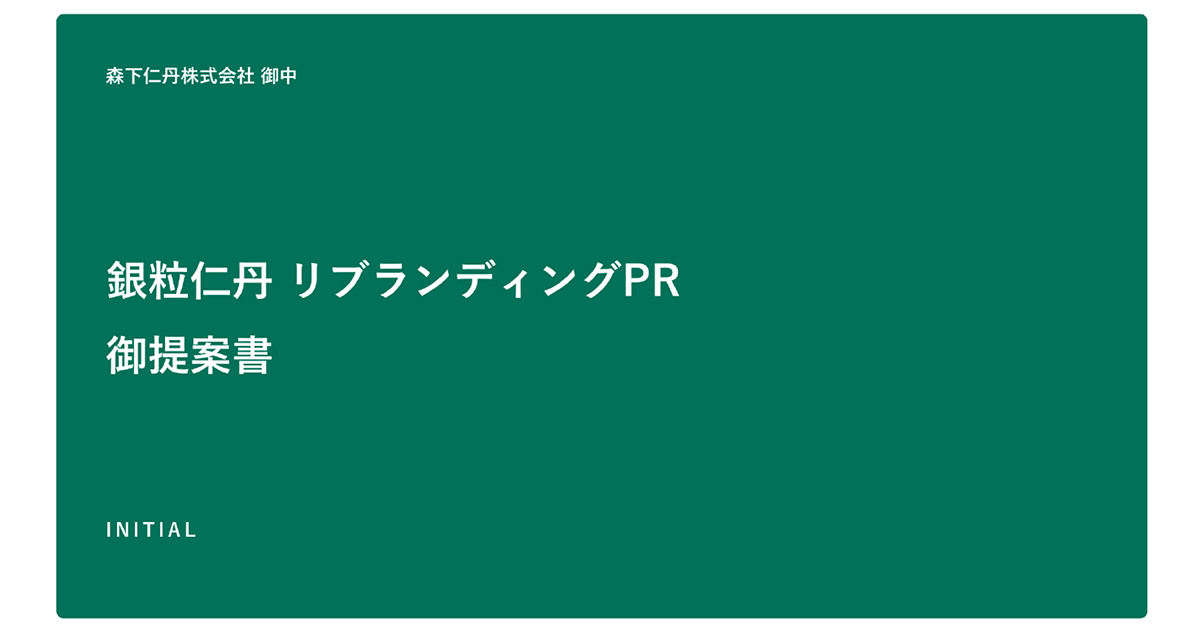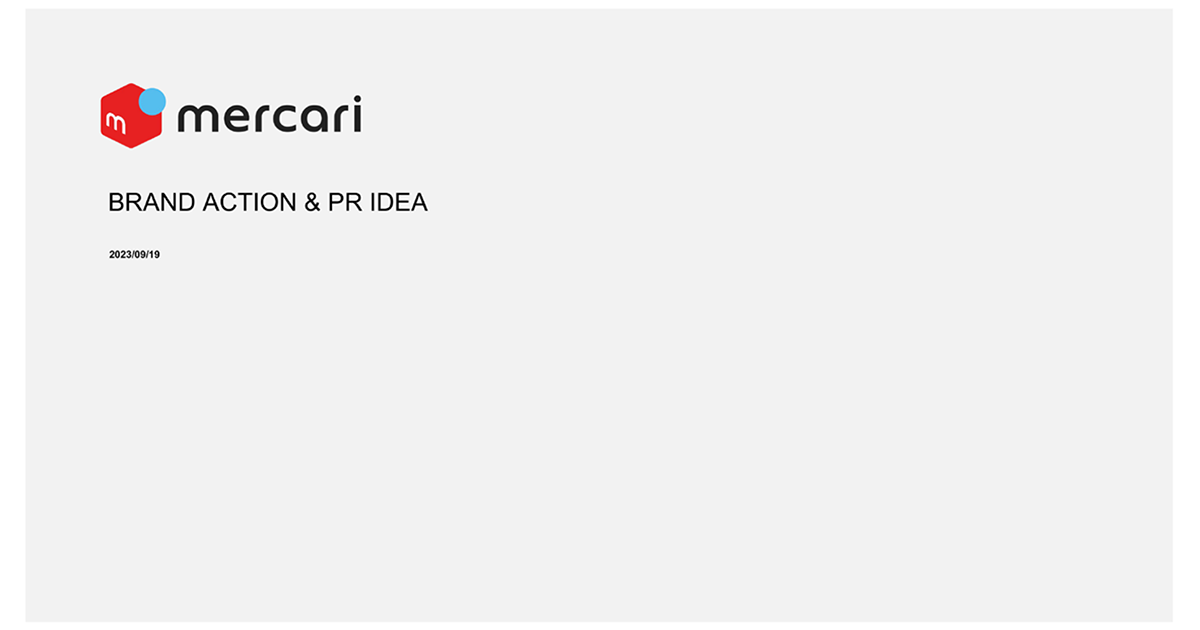純文学の映像化実習で言葉への感度を高める
中京大学文学部は、三年次よりゼミ活動が始まる。数あるゼミの中でも甘露ゼミの活動は、文学作品を精読し映像化する、というユニークなものだ。
ゼミの最初に取り上げる作品は、夏目漱石の小説『三四郎』。各ゼミ生は、作品の時代背景を調査研究し、作品を自分なりに解釈した上でリメイクした映画を制作する。
映像化といっても、原作に沿ってただ撮影すればいいわけではない。甘露教授によれば、小説の一語一語を精読し、作者が言葉に込めた意味や仕掛けを紐解き、行間に込められた物語を、映像で表現することが重要だという。
「言葉を尽くして説明しようとしても、観る側は感情移入しません。余分な言葉は、できるだけ削ぎ、情景や登場人物の表情、しぐさ、音楽、カメラワークなどの要素との組み合わせで表現することが必要です」
マーケティングコミュニケーションの領域でも昨今、企業の動画活用が広がっている。行間を映像で表現することで、音声やテロップなど言葉を詰め込むのではなく、研ぎ澄ませていく。こうした考え方は、受け手に伝わるコミュニケーションを考える上でも参考になりそうだ。
「例えば名作と言われるコピーにも、人の記憶に残る、シンプルながら力強い言葉がたくさんあります」と甘露教授は言う。
生活者の触れる情報量が爆発的に増加し、メールやソーシャルメディアを通じたコミュニケーションによって、誰もが言葉の送り手になった今、「ゼミの実習を通じ、学生には言葉に対しセンシティブになってほしい」と言う。甘露ゼミでは映像制作というアプローチで、言葉一つ一つの重みを学生に噛みしめさせている。
映像制作を通じ身に付ける社会性とチームワーク
甘露ゼミでは、学生同士でプロジェクトを進め、コミュニケーションをとらせることに重点を置いている。映画の撮影がコミュニケーション実習の一環でもあると甘露教授は話す。
映画を撮影するにあたっては、まず全体を5人のチームに分ける。チームの決め方として、甘露教授は事前に学生に交友関係を聞き、あえて居心地の悪いメンバー同士でチームを組ませるという。5人のチームは、監督を一人ずつ順番に交代しながら、撮影を行っていく。
監督は決められた期限までに撮影を終えるため、スタッフやスケジュールの管理を行わなければならない。
このような経験をリアルに積むことこそが重要だと甘露教授は指摘する。社会に出れば、スケジュール管理や価値観の異なるチームでの作業が、当然のように行われるからだ。社会に出て、初めて体験するのではなく、ゼミ活動を通じ疑似体験させることで、社会人としての基礎を身につけてもらう狙いがある。
また、チームで活動する上で、人間関係のトラブルも起こる。その際 …