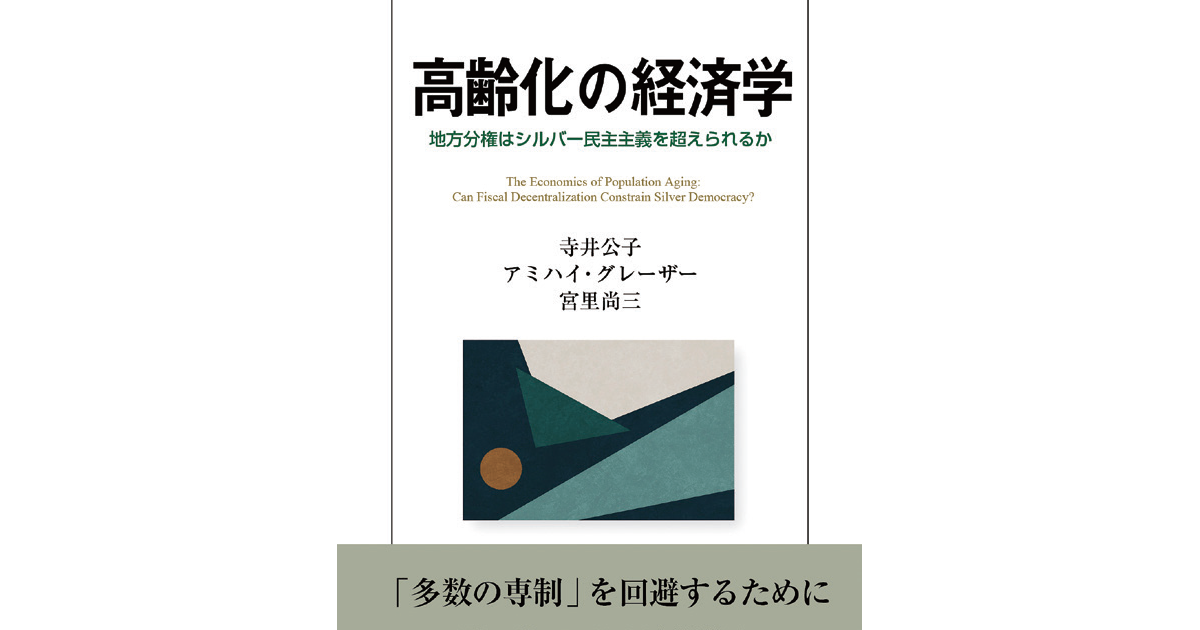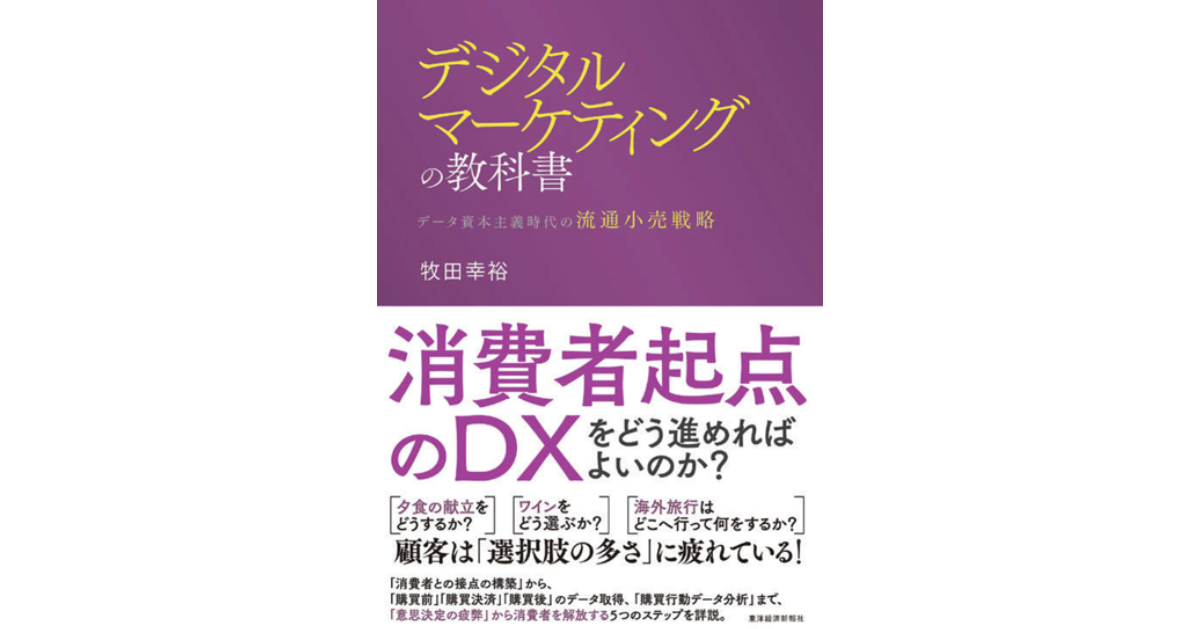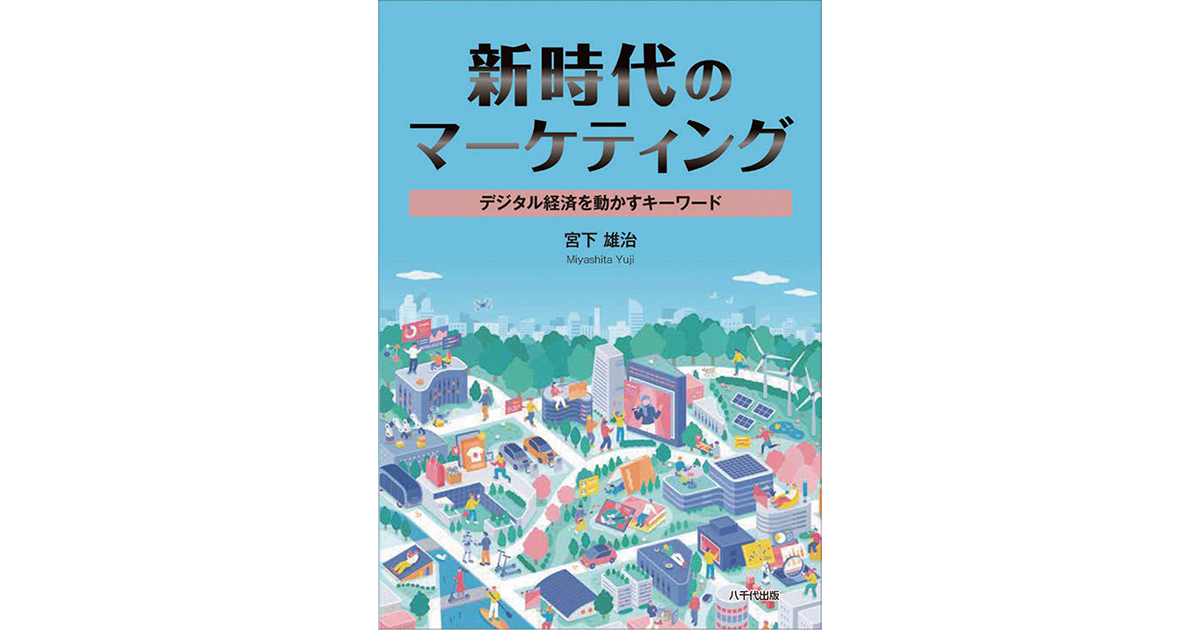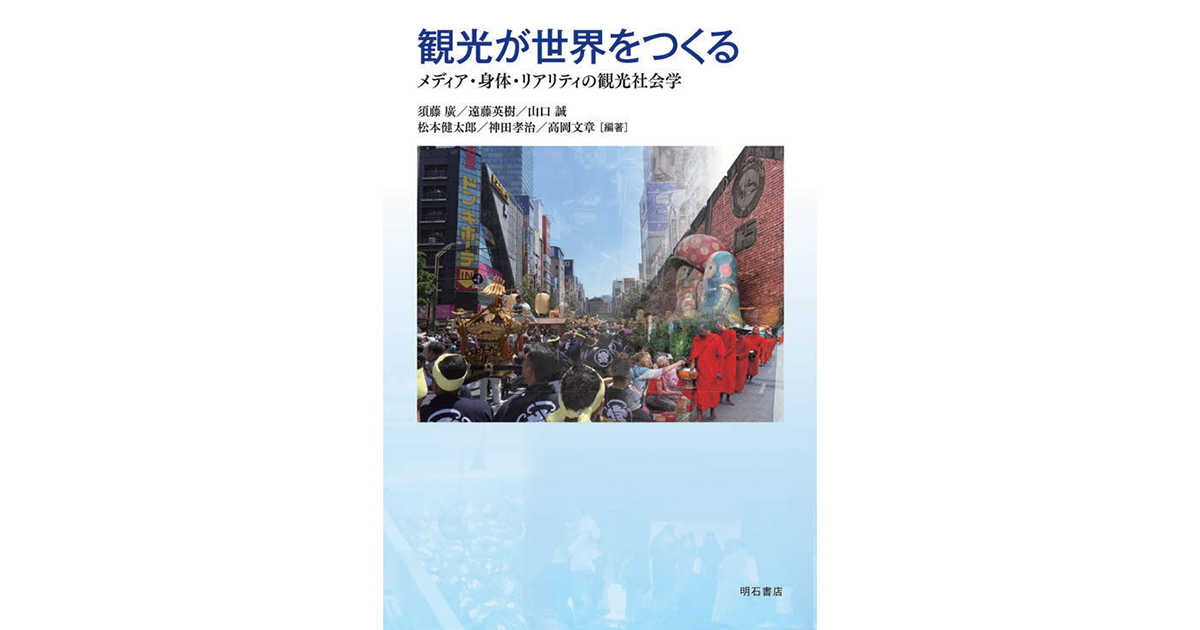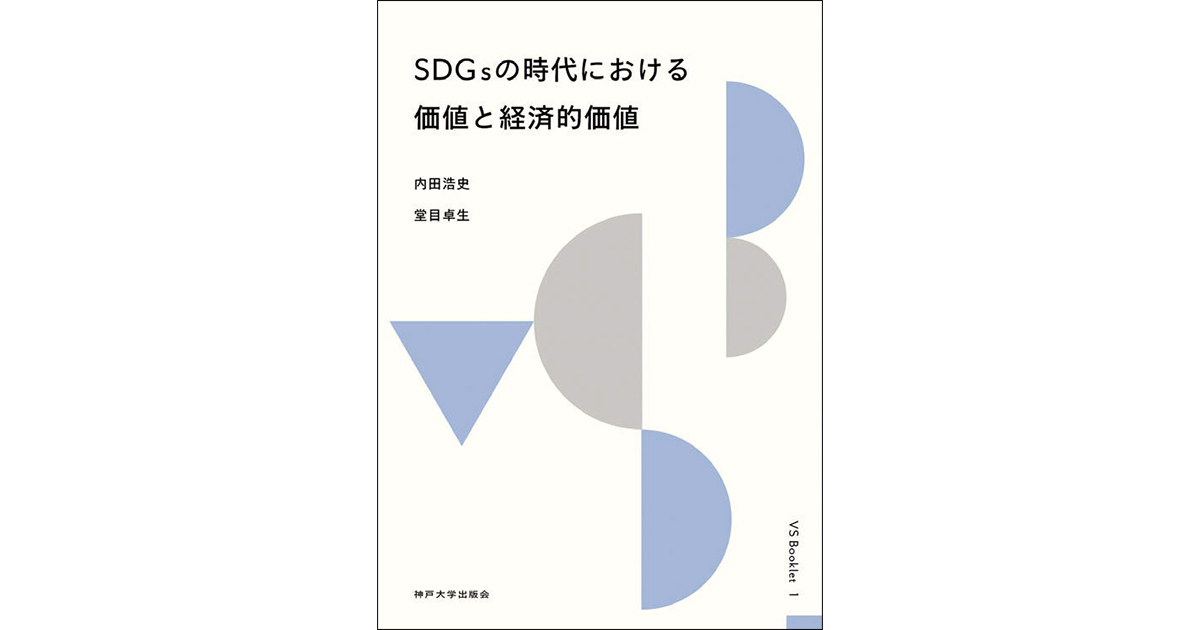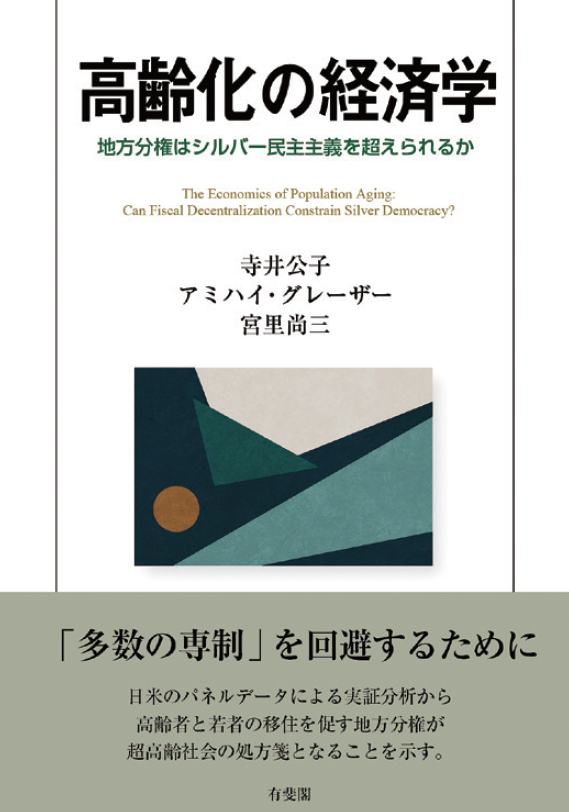
●著/寺井公子、アミハイ・グレーザー、宮里尚三
●発行所/有斐閣
●価格/4400円(税込)
人口問題が日本の重要な課題となって久しい。人口減少が続き、有権者の年齢構成が高齢化すると、高齢者が政策決定に与える影響が増す。高齢者がその影響力を行使することは、「シルバー民主主義」と呼ばれている。日本の地方分権は、地方分権一括法による権限移譲により大きく進展した。しかし、国の地域政策の主眼は若い労働力の地方分散に置かれている現状にある。本書『高齢化の経済学地方分権はシルバー民主主義を超えられるか』では、人口高齢化が政治過程を経て経済成長に与える負荷を、財政支出、税、労働市場政策を通して考える。そのうえで、人口移動を促す地方分権が成長への負荷を軽減する可能性を示す。
まず序章では、「高齢化を考える視点」を整理する。ある世代の得になる政策が、違う世代の損になることがたびたびあるなど、政策の効果が世代によって異なることは稀ではないという。高齢者の政治的影響力が増すことで、長期にわたって便益を生み出し、現在の若い世代や将来世代が主な受益者となるような政策よりも、短期的に集中的に便益を生み出す政策の方が実施されやすくなるという仮説を設定した。
第1章では、日本の経済政策の変遷を振り返ったうえで、ティボーの「足による投票」、オーツの「分権化定理」を中心に、これまでの地方分権理論研究の成果を紹介する。
あと57%