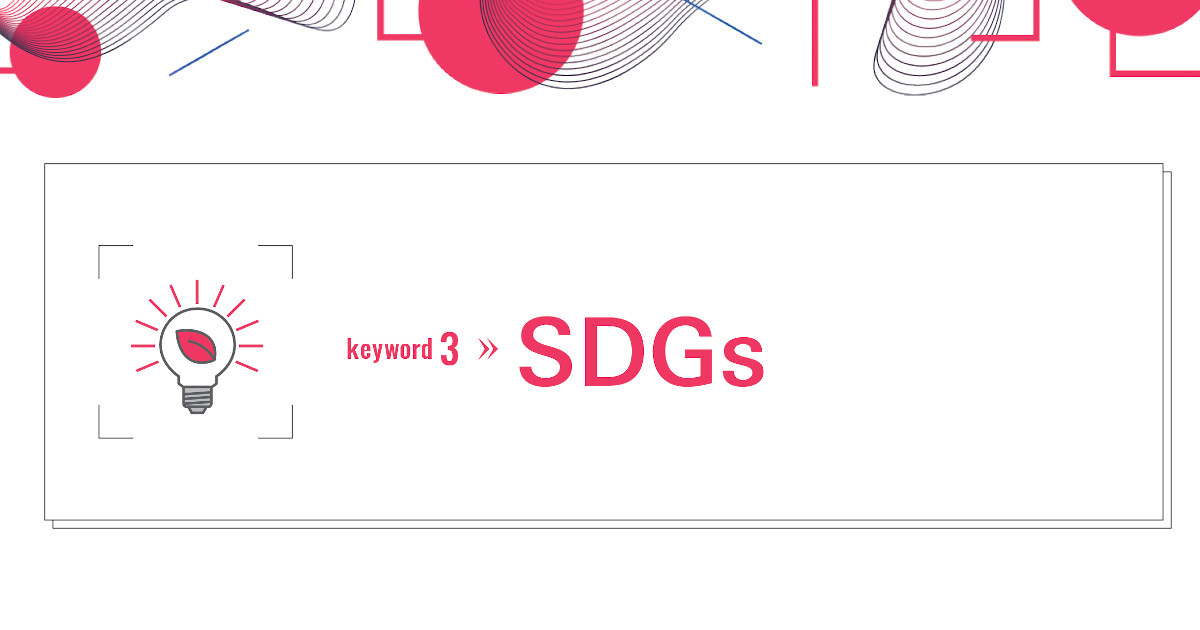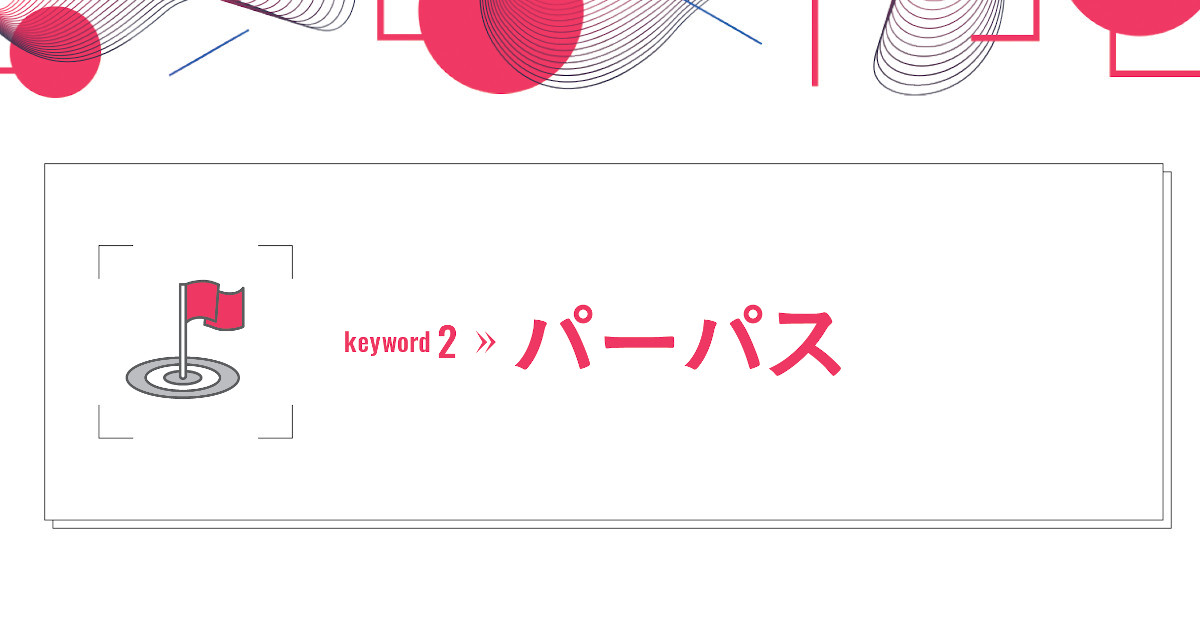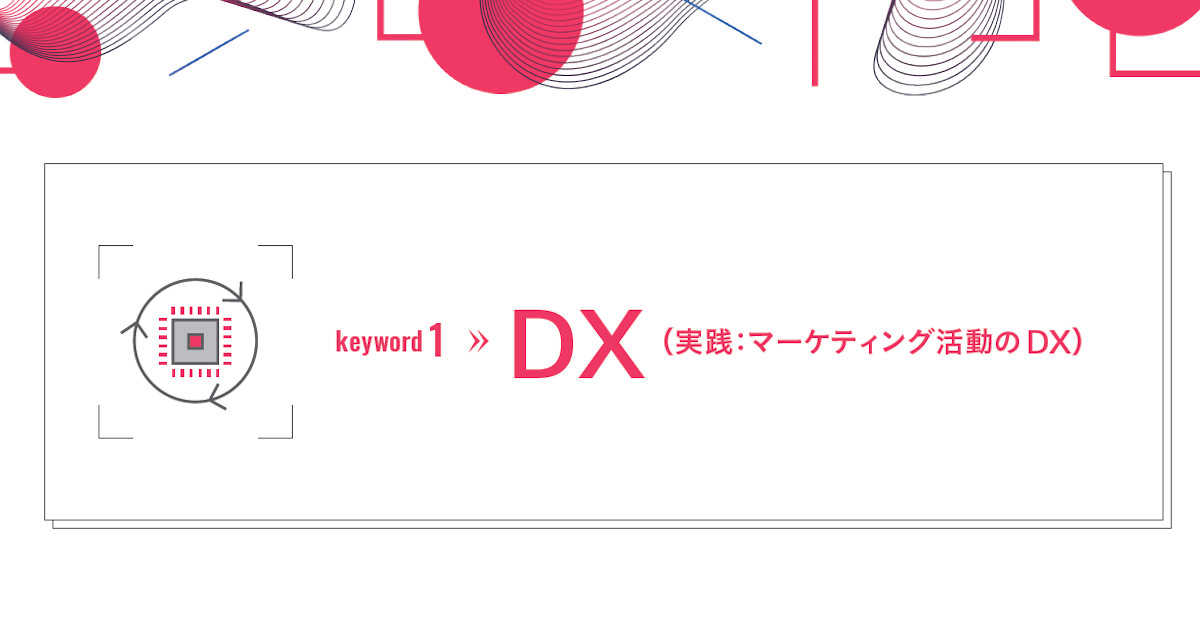昨今、マーケティング領域においても「SDGs」というワードを耳にする機会が増えている。ブランド担当者の中にも、「SDGs」を取り入れたブランドづくりやコミュニケーションを考えている人がいるのではないだろうか。本当に、SDGsでブランドづくりはできるのか。33年のブランド担当経験から、ダイキン工業 広告宣伝グループ長の片山義丈氏が解説する。
keyword 3 » SDGs
「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称。2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っている。企業、自治体、NPO法人、教育機関などで取り組みが進んでいる。
ブランドづくりの目的は「お金を儲ける」こと
昨今、「SDGs」という言葉を目にする機会が増え、ブランドづくりやコミュニケーションに取り入れようと考えている人も多いのではないでしょうか。
このようなバズワードに踊らされ、バズワードを使ったところで、時間をかけて取り組む必要があるブランドづくりはできません。そもそも、どんな目的を達成したくてSDGsでコミュニケーションをしているのでしょうか。あなたは、その目的を明確に説明できますか?
まずは、そもそもブランドづくりの「目的は何か」に立ち戻って、考えてみましょう。
ブランドづくりの目的とは、一言でいえばお金儲けです。世のため人のため地球のため(社会貢献・CSR・SDGsなど)ではありません。専門家が「ブランドづくりの目的は『金儲け』などではなく、『世のため人のため地球のため』である」とか「これからの時代はSDGsに積極的に取り組む企業しか生き残れない」とか言っていることを皆さんは素直に信じています。しかし専門家の結論には、彼らからすれば自明のことなので省略している言葉があり、専門家ではない私たちはそのことに注意を払う必要があります。
省略の部分を省かずに書くと、「(一部の大企業の)ブランドの目的は、『世のため人のため地球のため(しか選択肢がないことが多い)』です」となります。この( )の部分の省略に気付かず素直に読むと、「ブランドの目的は、『世のため人のため地球のため』です」となります。しかし、あくまでも大企業という一部の企業に限った特殊な事例で、すべての企業・商品には当てはまるものではないのです。
企業を好きになるポイントは時代によって変化する
では、なぜ大企業においては、「『世のため人のため地球のため』=SDGsでブランドづくり」が正しいといえるのでしょうか?