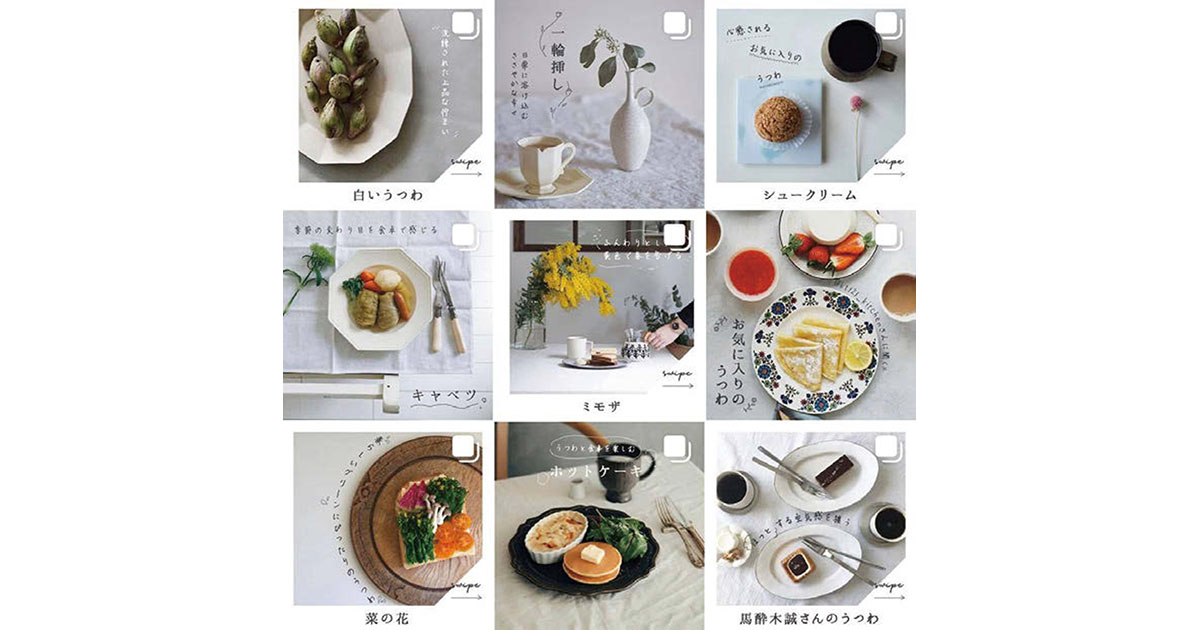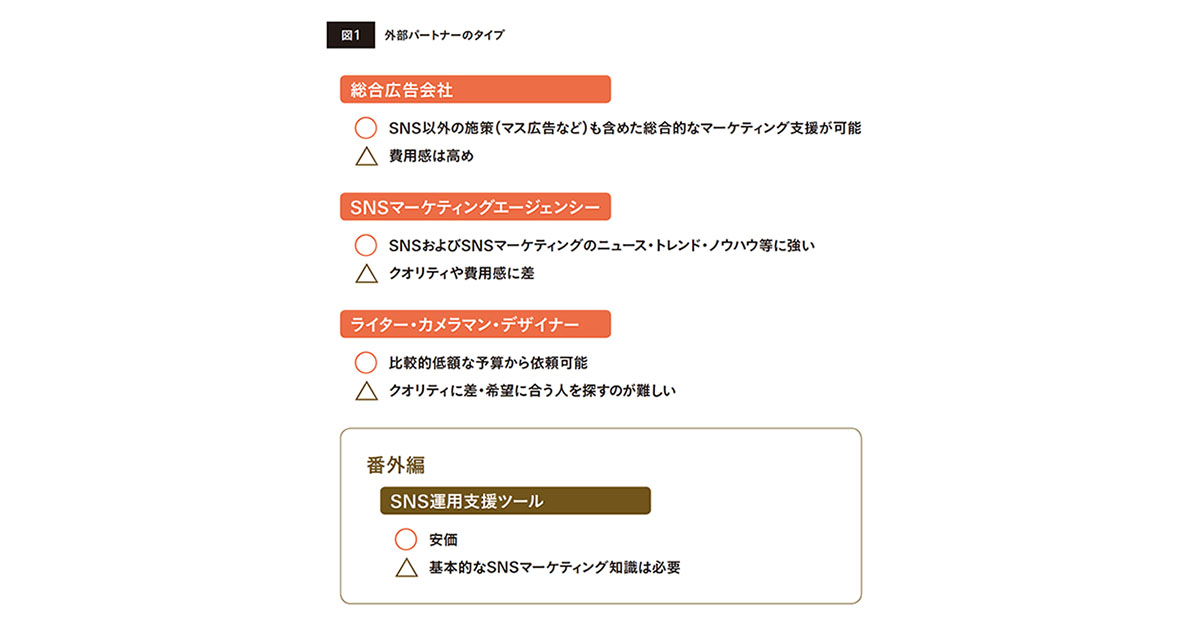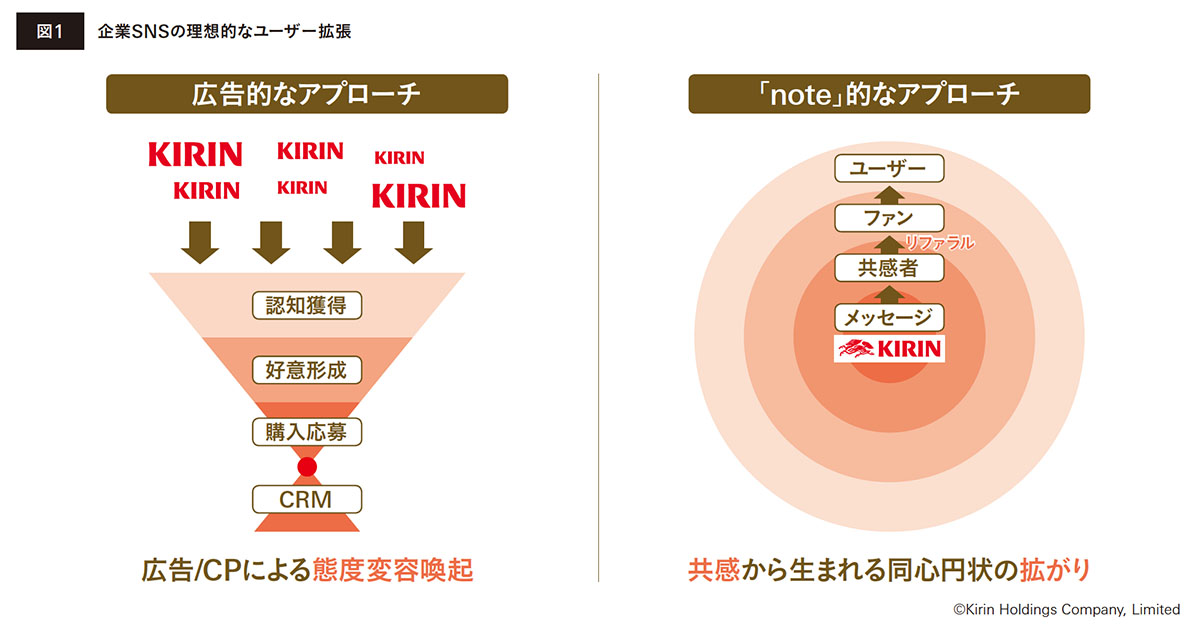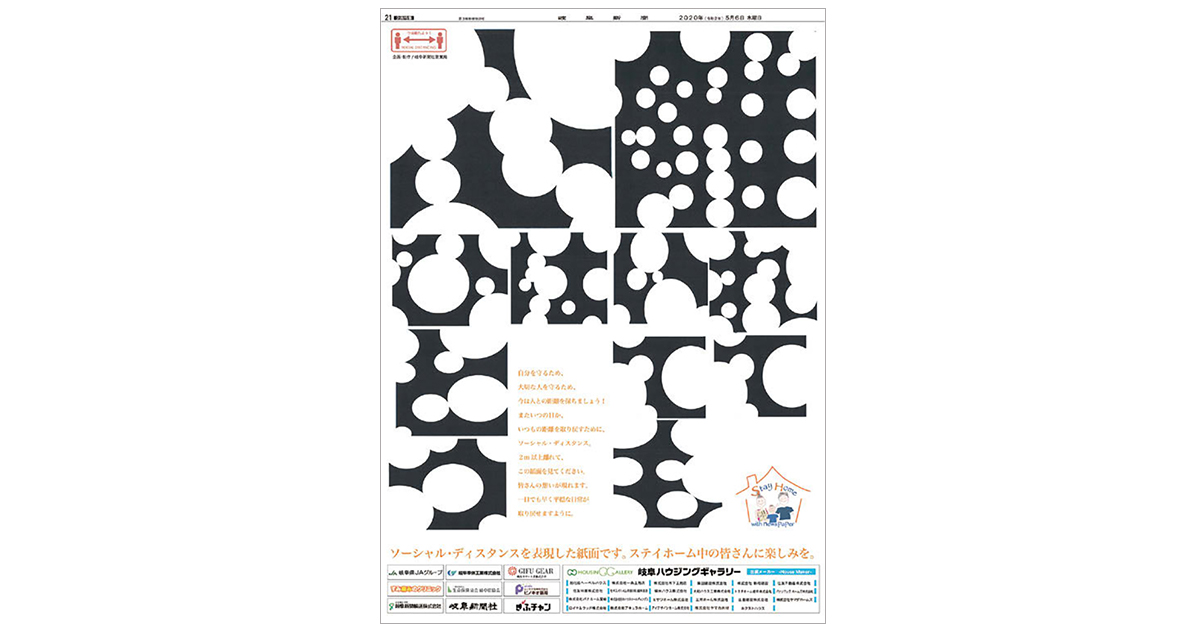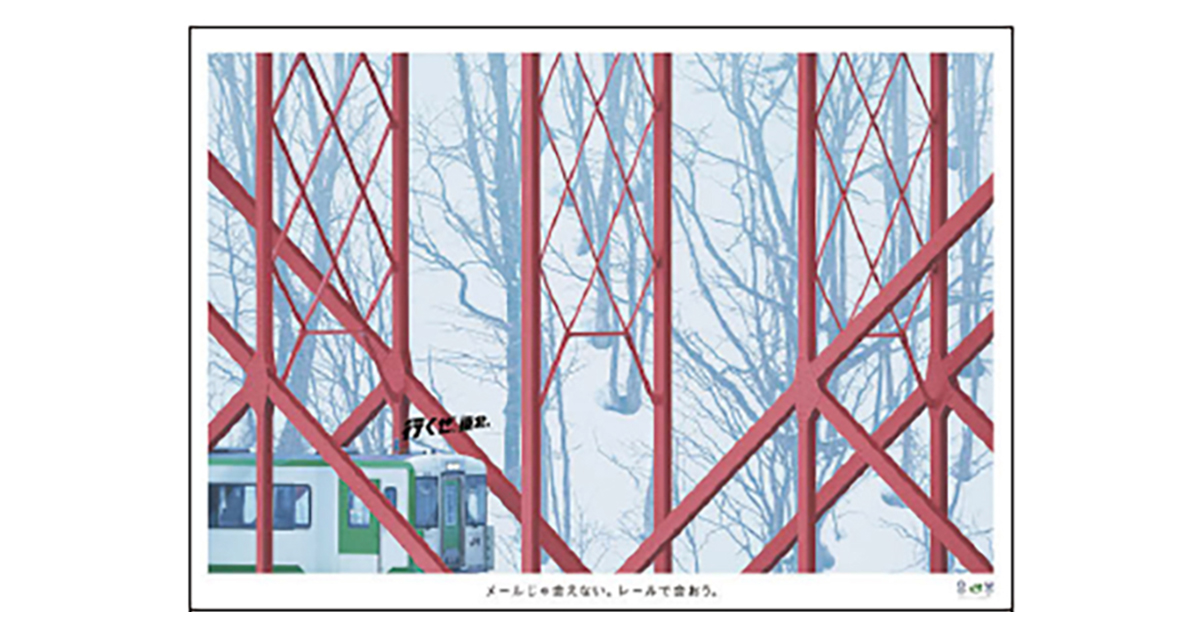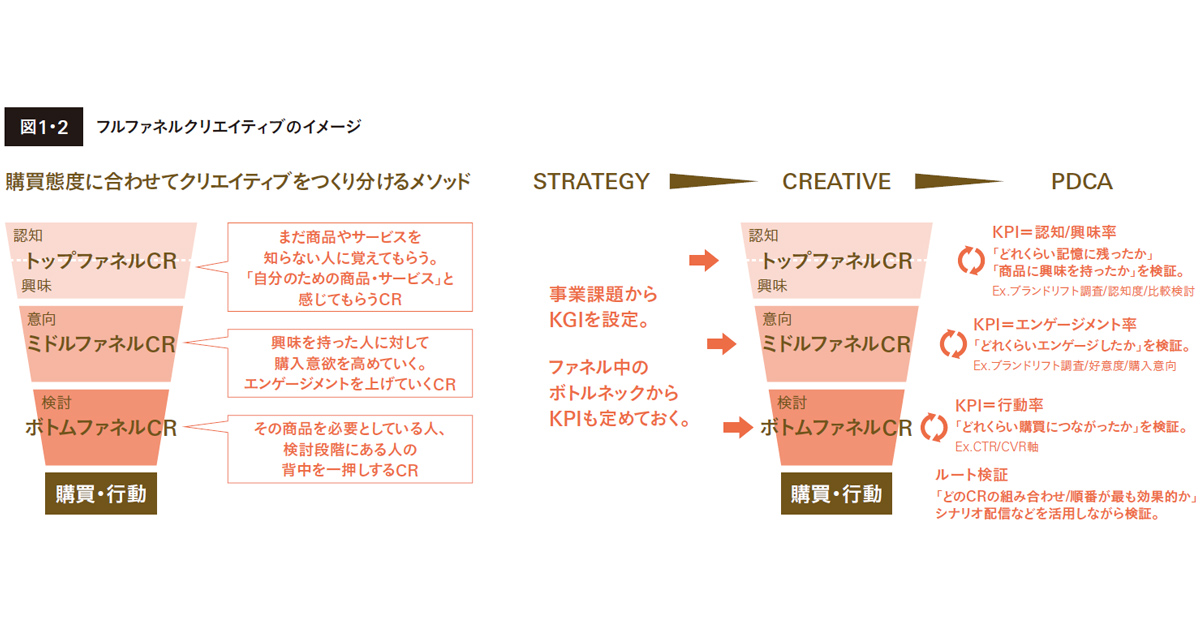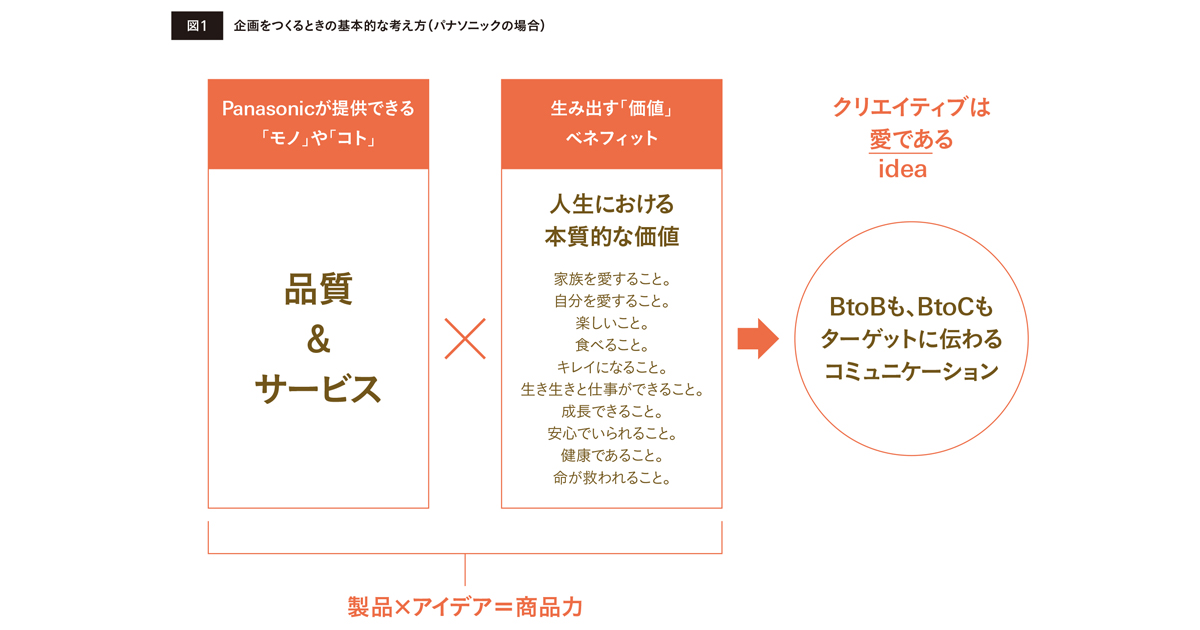自ら直接、消費者に情報を届けられるオウンドメディアを活用する企業が増えています。広告と異なり、企業が伝えたいメッセージを自分たちが適切と考える文脈のなかで届けることができるオウンドメディアは、これまでにない形で消費者とブランドの出合いの場を創出します。一方で、定期的なコンテンツの制作と発信が求められるオウンドメディアには、従来の広告にはない制作のノウハウも求められます。その実践論を、オウンドメディアの企画・運営のプロフェッショナルが、現代の潮流も踏まえながら解説します。
- 「課題解決型」と「発信型」の2種類の記事で消費者との接点をつくる。
- オウンドメディアは「情報収集装置」。自然な流れでデータを取得する、綿密なサイト設計が重要。
- 企業の目的優先ではなく、生活者に役立ててもらう姿勢が必要。
オウンドメディア企画・運営の極意
生活者との“接点”となるオウンドメディアの役割とは
現在、オウンドメディアを持ち、運営をしている企業は数多くあります。私が所属するライオンでも、2014年に「Lidea(リディア)」という生活情報メディアを立ち上げ、リニューアルを重ねながら運営をしています。
取り扱っている商品のカテゴリーや、ブランドが抱える課題によって、企業がオウンドメディアを活用する目的は異なりますが、私はオウンドメディアとは、広告などの商品の販売活動におけるコミュニケーション以外で、生活者と持つことができる“接点”として、貴重な存在であると考えています。「リディア」を通して私が考える、オウンドメディアの価値や運営におけるポイントについてお話ししていきます。
生活に役立つ情報を届ける「コミュニケーション装置」
私が「リディア」を運営する上で、オウンドメディアの役割として考えていることが2つあります。その内のひとつが、生活者の暮らしの中に入り込み、役立つ情報を届ける「コミュニケーション装置」としての役割です。
「リディア」では、生活の中で困りごとがあった際に解決策を提示できるようなHow to記事を配信しています。例えば「白いシャツに醤油のシミがついてしまった」といった困りごとが発生した際、ユーザーが検索エンジンで「白いシャツ」「醤油」「シミ」などで検索し、「リディア」の記事を見つけ、読んでいただくといった流れになります。
当社は、衣料用洗剤やオーラルケア用品など、生活の中に溶け込む身近なプロダクトを扱っているため、さらにこの傾向が強いのかもしれませんが、自社のプロダクトが、生活の中で人々の役に立てる場面を想像して記事をつくることが重要です。生活者との接点を生むような記事を配信することで、人々の生活に寄り添うメディアとなり、それがブランドファンを創出することにつながるのです。
しかし、それだけでは生活者に困りごとが発生し、探してもらうまで受け身の状態になってしまいます。How to記事には、困りごとがあるときにしかサイトに読者が来訪しないという課題があるのです。そのため、能動的に発信できるようなコンテンツも必要だと考えています。
「リディア」では、2019年の6月に大規模なリニューアルを実施しました。それまでも配信していたHow to記事に加え、より“知的好奇心”を追求した読み物コンテンツなどの「発信型記事」も用意し、読者がザッピングする中で興味に合ったおすすめ記事がレコメンドされるような仕組みもつくりました。このような読み物コンテンツはTwitterなどのSNSでシェアされることも多いので、生活者に困りごとが発生せずとも、人々の目に触れるチャンスを得やすいのです。
オウンドメディアの記事では、キャンペーンの告知広告のようにすぐに効果は出ないかもしれませんが、記事を読んだ人が売り場で商品を見かけた際に「そういば、あの記事に書いてあったな」と思い出してもらえるような、コミュニケーションが取れると考えています。
読者にもメリットをもたらすデータ収集装置としての機能
オウンドメディアの役割として、もうひとつ私が考えているのは、「データ収集装置」としての役割です。記事のクリックやサイトへの会員登録により、オウンドメディアを介して読者のデータを集めることができ、そのデータの価値は非常に高いと思います。
前章で、「発信型記事」により、ユーザーに課題が発生する前に能動的に働きかけることも必要であると述べましたが、データ収集という面でも、「発信型」の読み物コンテンツを配信することは、読者の興味関心を知る上で非常に参考になります。
オウンドメディアを通してデータを取得する上でのポイントは、いかに自然な流れでデータを取得するのか、その設計を考えることです。「リディア」での例を挙げて説明します。
「リディア」では、記事への感想を回答することで、プレゼントが当たるキャンペーンを毎月実施しています。応募方法は、リディアに会員登録をした後、各記事の感想を2択から選択し、回答するだけ。月ごとに最大10記事へ回答することが可能で、回答記事が多いほど、プレゼントの当選確率が上がります(10記事に回答した場合、応募口が10口になるという考え方です)【図1】。この仕組みにおけるポイントは次の3点です。