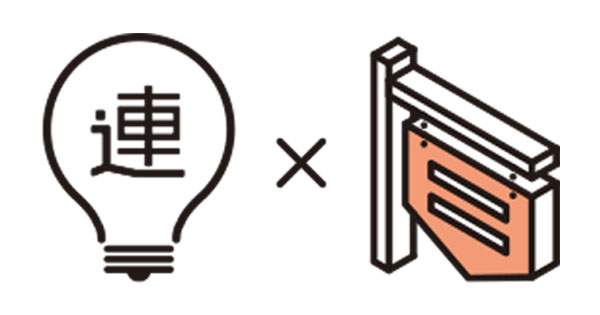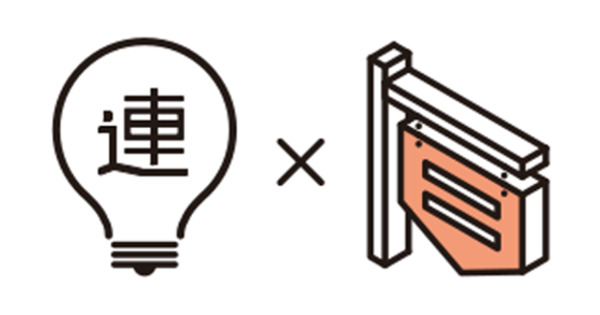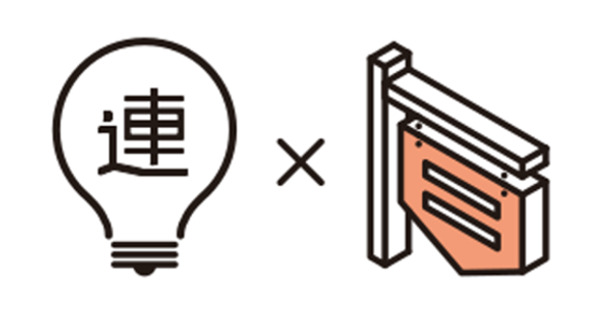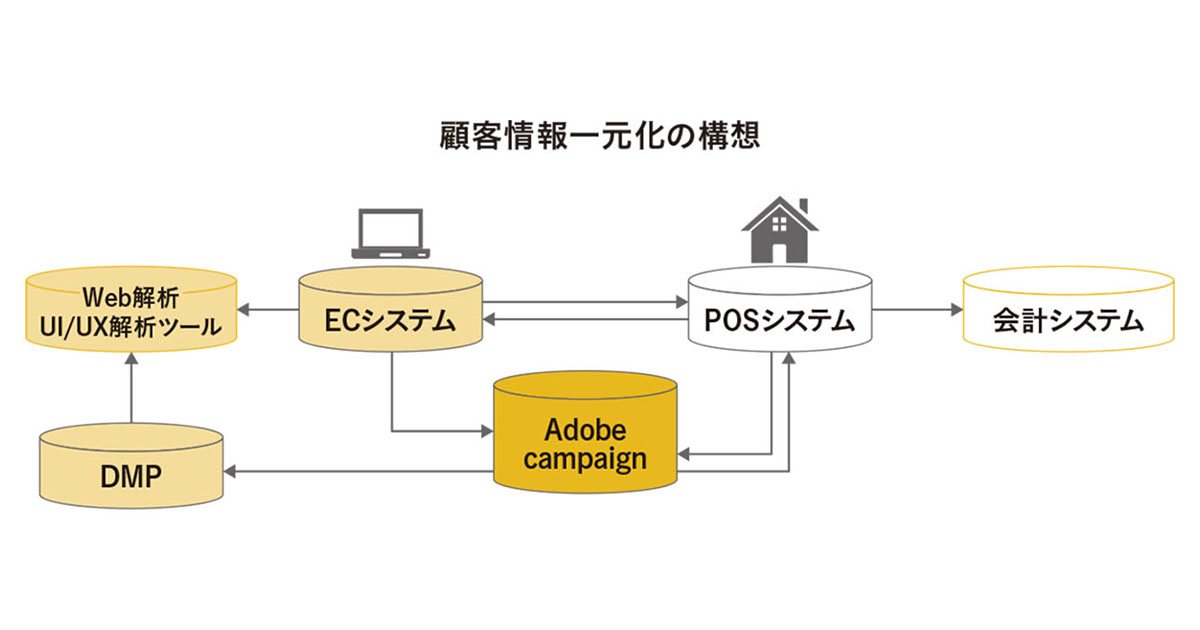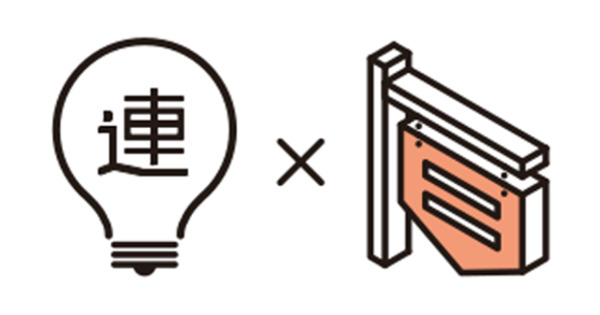価格や機能の差を超え、ブランド力が重要要素となるブランドビジネスの世界。その世界において、デジタルテクノロジーはどう活用できるのか。定量化しにくいブランド力をデジタルテクノロジーの活用によって現代に合わせたアップデートをしていく戦略を全6回で解説します。
コールセンターの改善が収益改善の大きな鍵に
これまでの4回の連載ではテーマに従って、それぞれのデジタルやテクノロジー、ソリューションを活用したブランドビジネスのアップデートについて方法論を説明してきました。5回目となる今回はコールセンターという、ひとつのチャネルに絞り、データの整理から意識の変化までを一連の流れで説明していきます。
私が着任した当時、ロクシタンにおけるコールセンターのビジネスは、投資に対して十分なパフォーマンスが上げられず、投資見直しの対象に含まれていました。しかし、Webでの売上比率が高まっているブランドであってもコールセンターの運用を細かくマネジメントしているケースは少なく、私は、この領域の改善は比較的実績を出しやすいとう読みをしました。そこで1年と期限を区切り、やりきるというスタンスで深堀りを進めていきました。
当時のコールセンターは、組織で言えばE-comの部門が管轄していたものの、KPIは受電からの売上しか追いかけていませんでした。例えば要員の生産性、具体的にはCPH(Call Per Hour=1時間ごとにオペレーターが受けるコール数)やコンバージョン率などは計測できておらず、IVR(Interactive Voice Response=自動音声応答)も初期設定のまま活用されていない状況。より売上を高めるためには、マーケティング予算を増額し、コールセンターに入るリードを増やすしか、選択肢がない状況でした。
また、メディア予算もDM送付者からの購入マッチバックでしか効果測定をしていなかったため、本当にメディアの効果で購入に至ったのか、メディア自体の効果がどれくらいあるのか、正確には把握できていませんでした。
そこで、まずは過去3年程度の月別・日別のコール量の把握を行いました。当然ですが、DM到着日や新聞広告などが出稿されるタイミングにコール量の山ができます。ここでは、山ではなく出稿がないタイミングでのボトムを把握することで、概算ではあるものの、それぞれのメディアのインパクトを理解することができました。
ここまでで見えてきたのは、クリスマス時期以外はマーケティング予算を増額しても、大きなコール量を呼び込むことはできないという事実でした。そこで、それまで各月に均等に配していたメディア予算をクリスマス商戦に近い月へ集中投下し、チャネル全体での予算投下を最適化するプランを作成 …