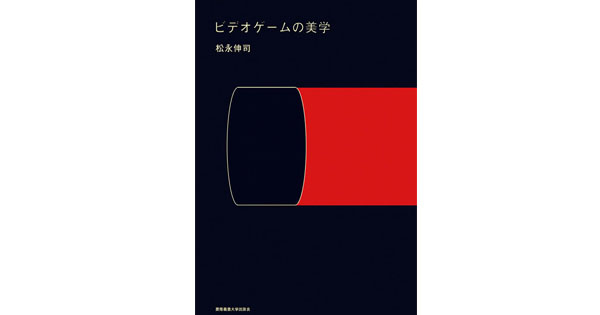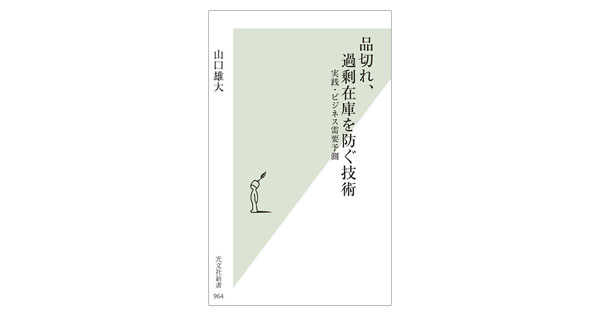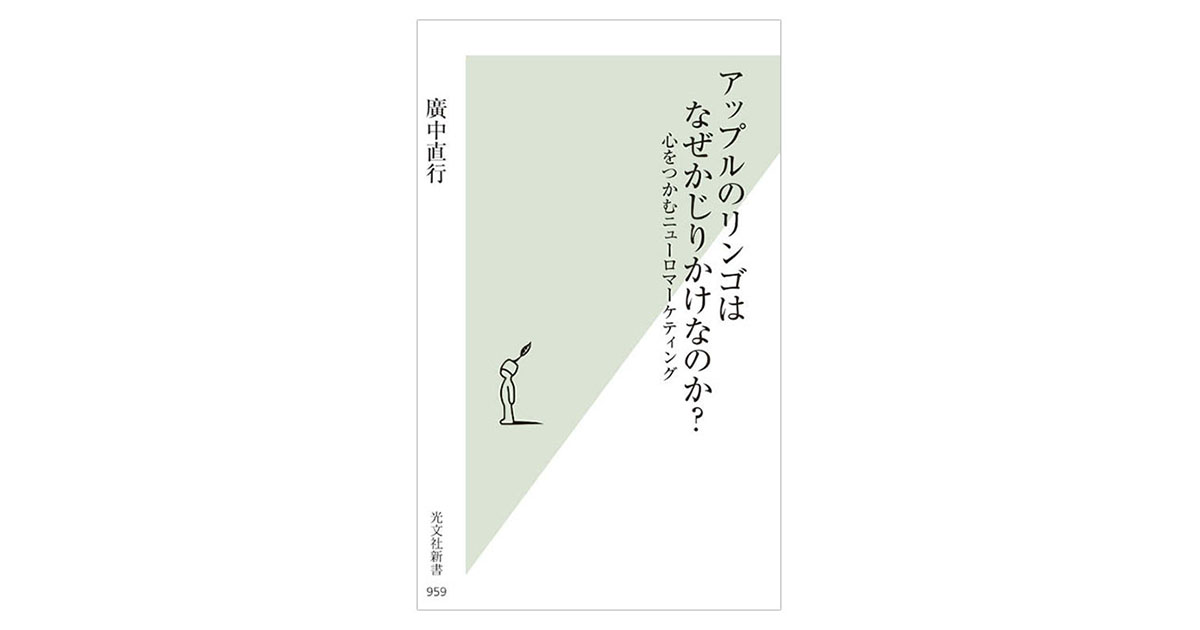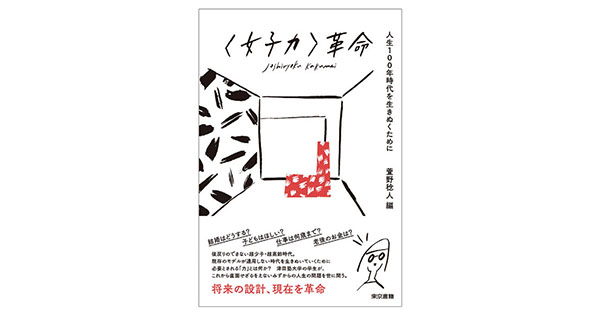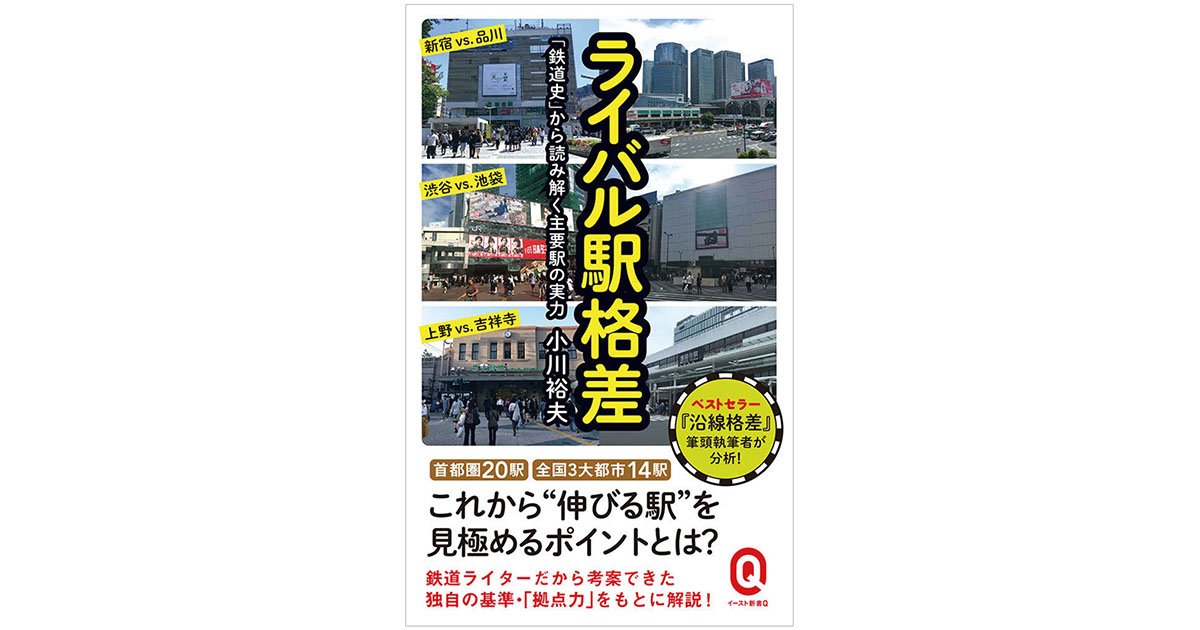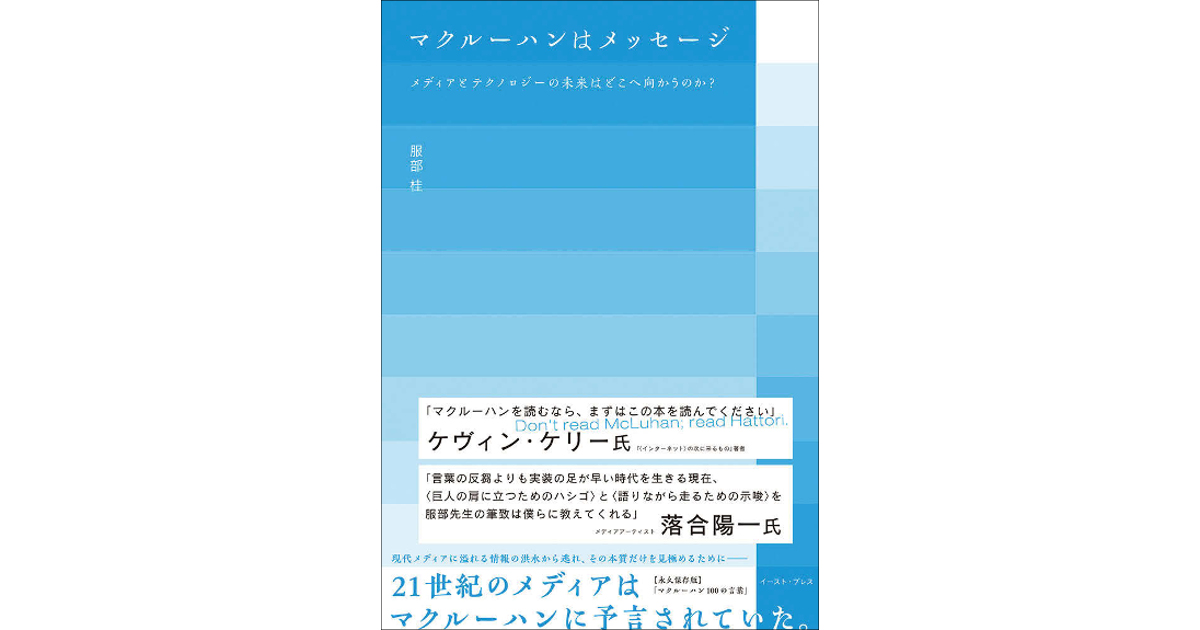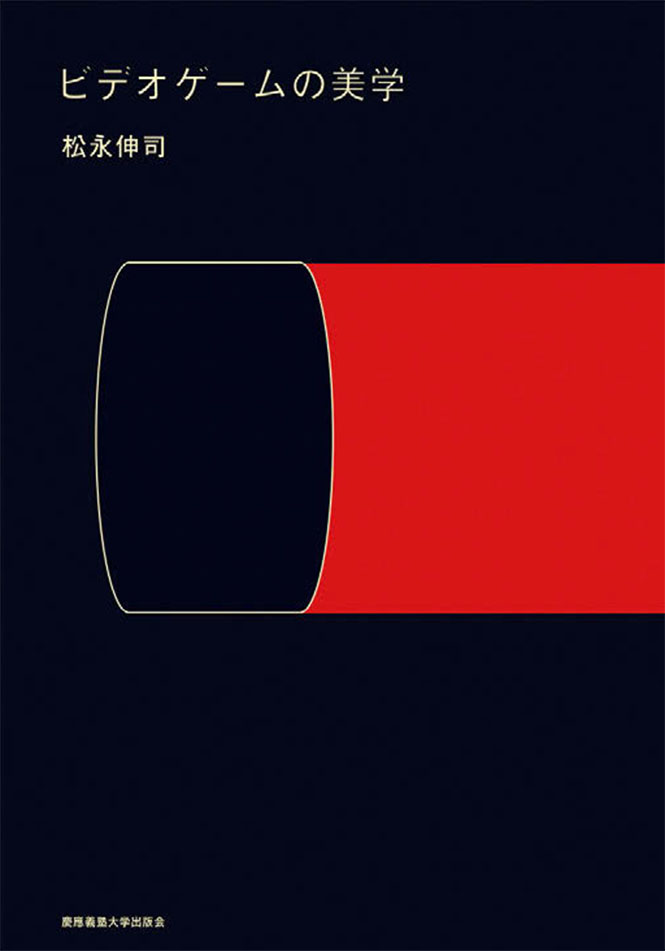
ビデオゲームの美学
● 著者/松永伸司
● 発行所/慶應義塾大学出版会
● 価格/3200円(税抜)
対戦型ゲーム競技「eスポーツ」が世界的に盛り上がりを見せ、市場拡大が進むゲーム産業。日本のゲームは世界的にも広く受け入れられており、近年は政府からもゲームの文化的重要性とその経済波及効果を認められている。
本書「ビデオゲームの美学」はビデオゲーム(視覚ディスプレイを用いるゲームの総称)を、絵画や映画などと並ぶひとつの芸術形式として捉え、ビデオゲーム"ならでは"の特徴を明らかにすることを試みた一冊。
芸術哲学の先行研究を踏まえつつ、スペースインベーダー、パックマン、スーパーマリオブラザーズ、テトリス、ドラゴンクエストなど多くの作品を事例として取り上げながらゲーム研究の理論的枠組みを提示する。
著者の松永伸司氏は本書の読みどころについて、「この本ではゲームを『行為のデザイン』として捉え、それをさらに『目的のデザイン』『信念のデザイン』『現実のデザイン』に分解して論じています。この見方は、人は何によって動くのか、人を動かすにはどうすれば良いのかを考えるヒントになると思います」と話す。
通常、ビデオゲームにおいてプレイヤーが操作を入力すれば、その入力に応じて何らかの"反応"がディスプレイを通じて返される(この意味で、芸術形式としてのビデオゲームが持つ特徴として"インタラクティブ(相互作用)性"が挙げられている) …
あと56%