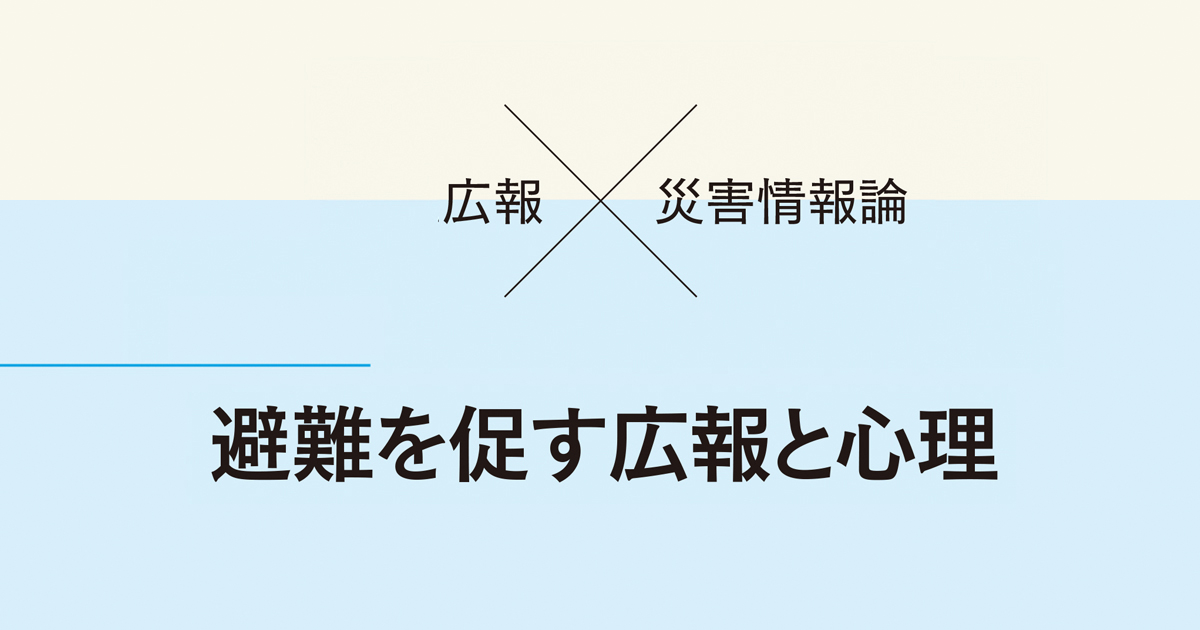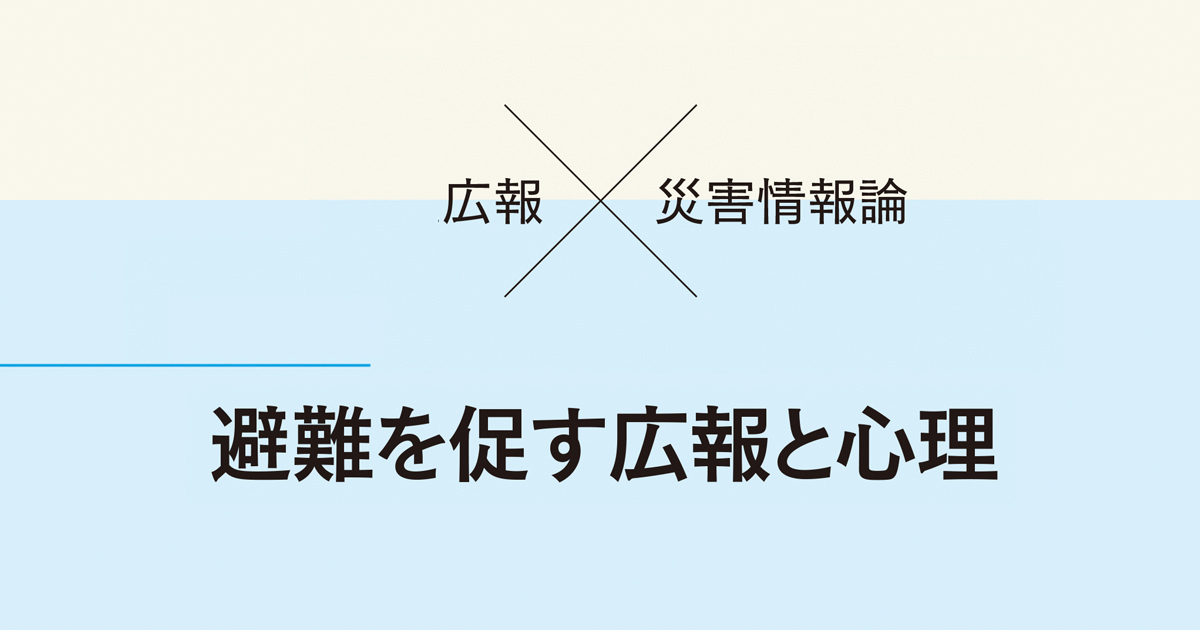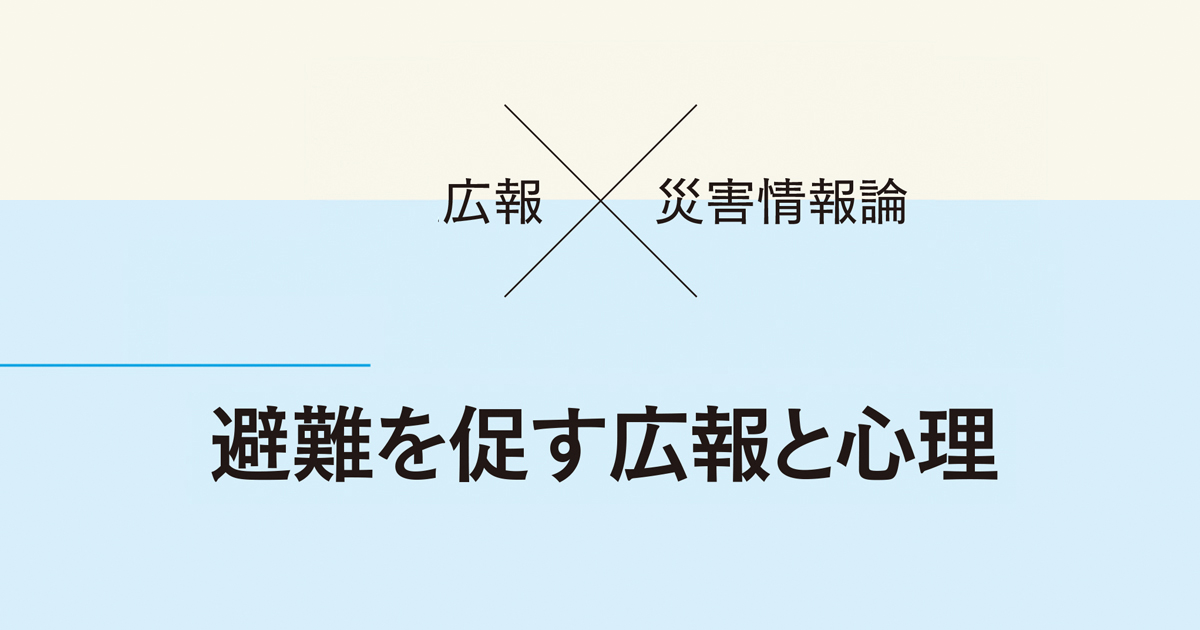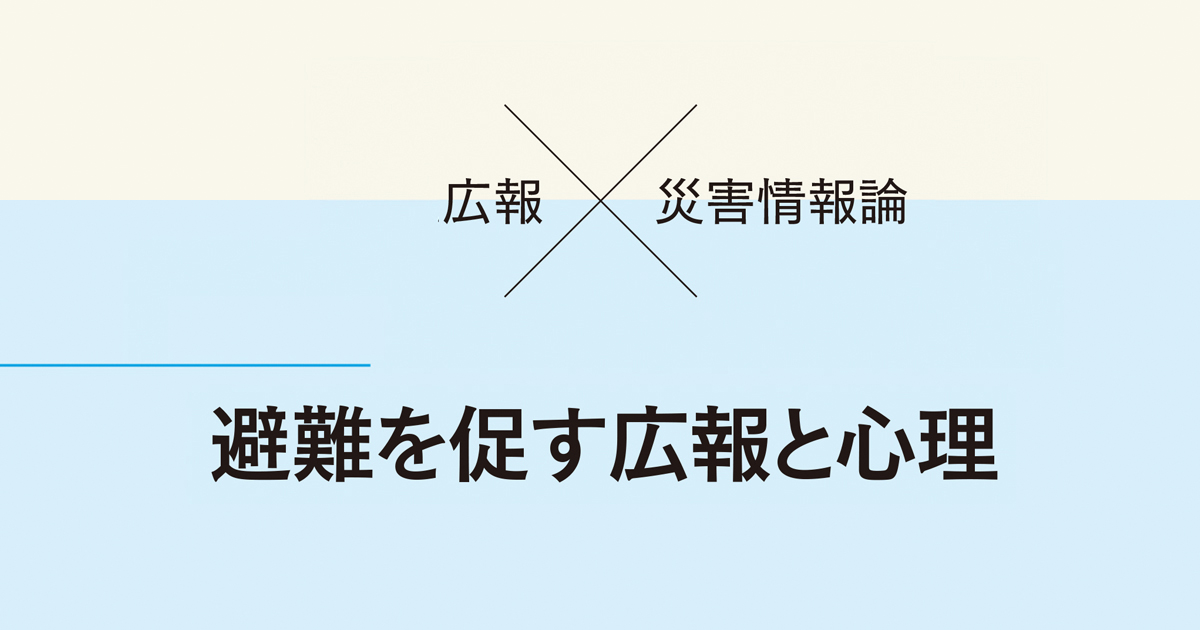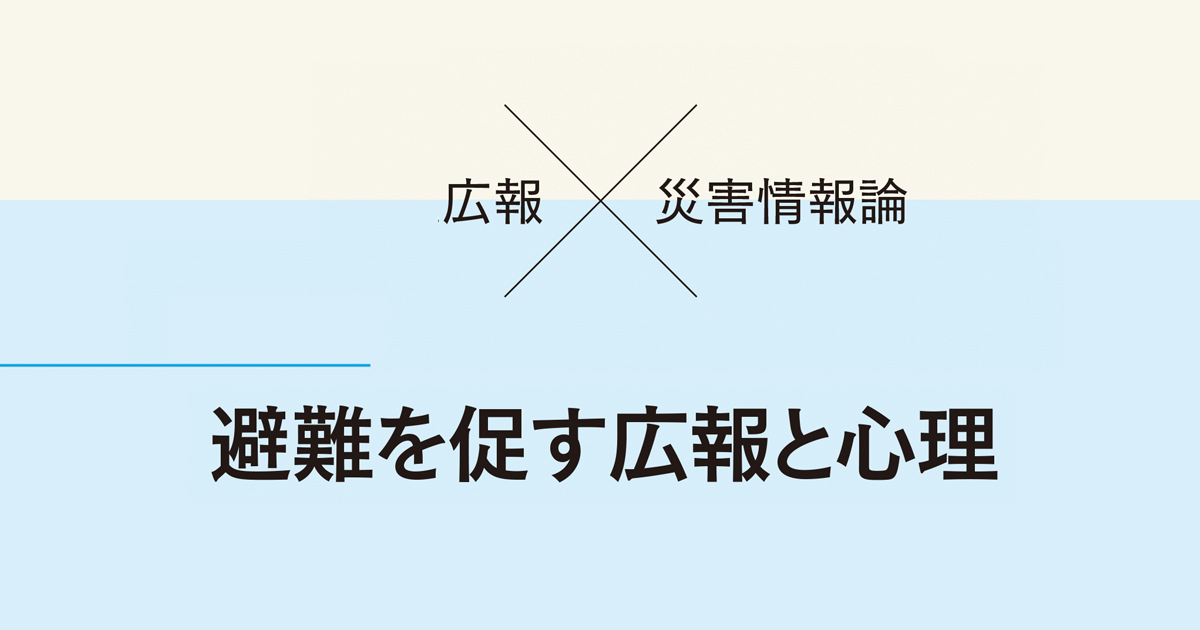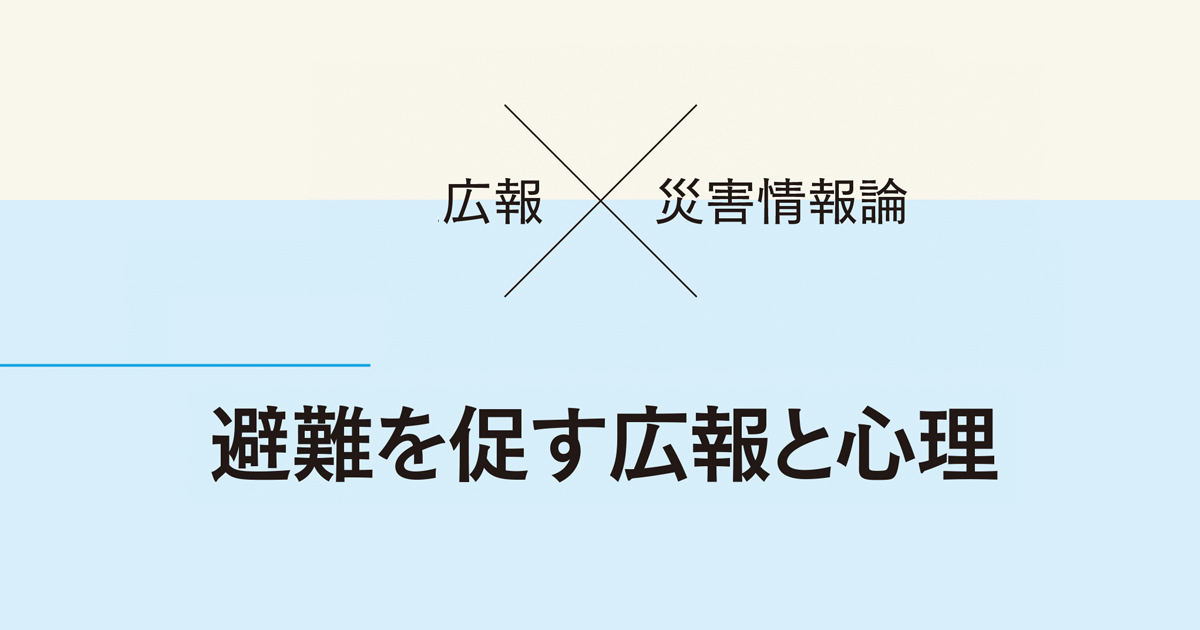迅速な行動喚起が必要な避難指示。その伝達は一刻を争うこともあります。災害情報論の視点から、情報の受け手の心理について考えます。
今回は、無関心層へ防災情報を伝達するにはどのようなメディア(手段)を使ったらよいか、について考えます。その原則には、①接触可能性(accessible)を確保すること ②注意を引くこと(noticeable) ③記憶に残らせること(memorable)の3つが重要です。
すなわち、興味のない人々に対して、まずはいかに防災情報に接してもらうかが問題となります。しかし情報に接するだけではダメで、注意を引いて認識してもらわなければなりません。さらに繰り返し接触するなどして記憶に残るようにする必要もあります。では具体的にはどのようなメディア(方法)があるでしょうか。
平時の啓発メディア
平時の啓発としては、学校の防災教育が、興味のない人にも接触させることができる基本的な手段ですが、対象は子どもに限られます。また大人向けには自治体がつくるハザードマップ(紙版・ウェブ版)がありますが、興味のない人は配布されても中身を見ることはありません。
一方、テレビ・ラジオ・新聞といったマスメディアも時機をとらえて啓発情報を出しており、こちらは関心のない人にも接触可能性が出てきます。しかし日ごろからマスコミに接しない人も増えており、限界があります。無関心層にアクセスする他の...
あと60%