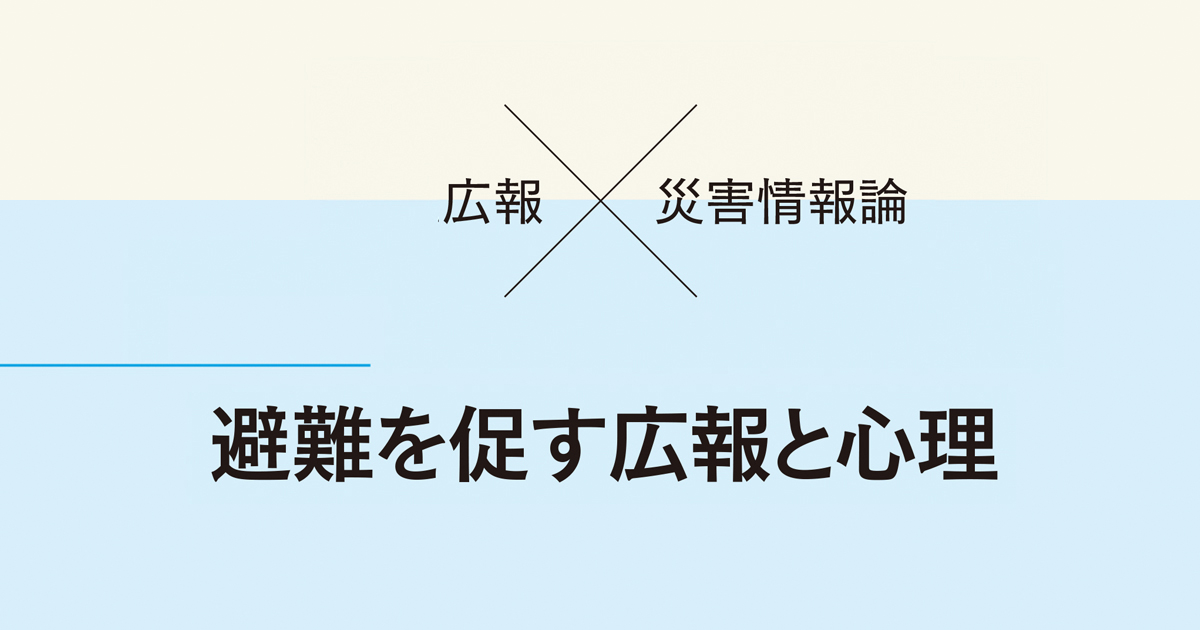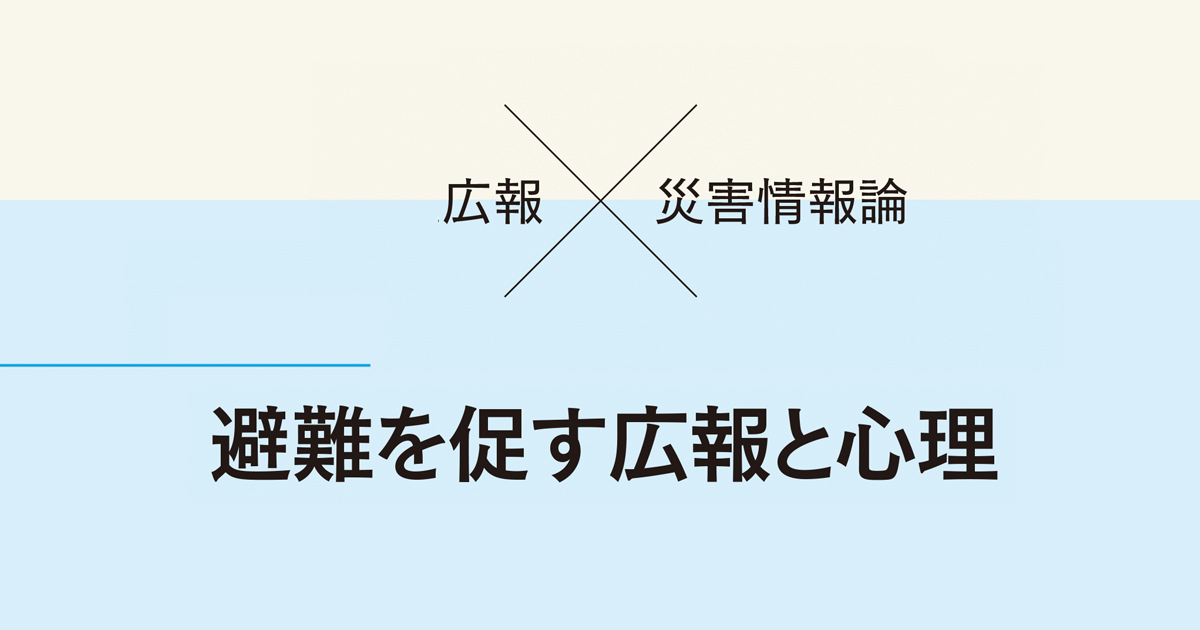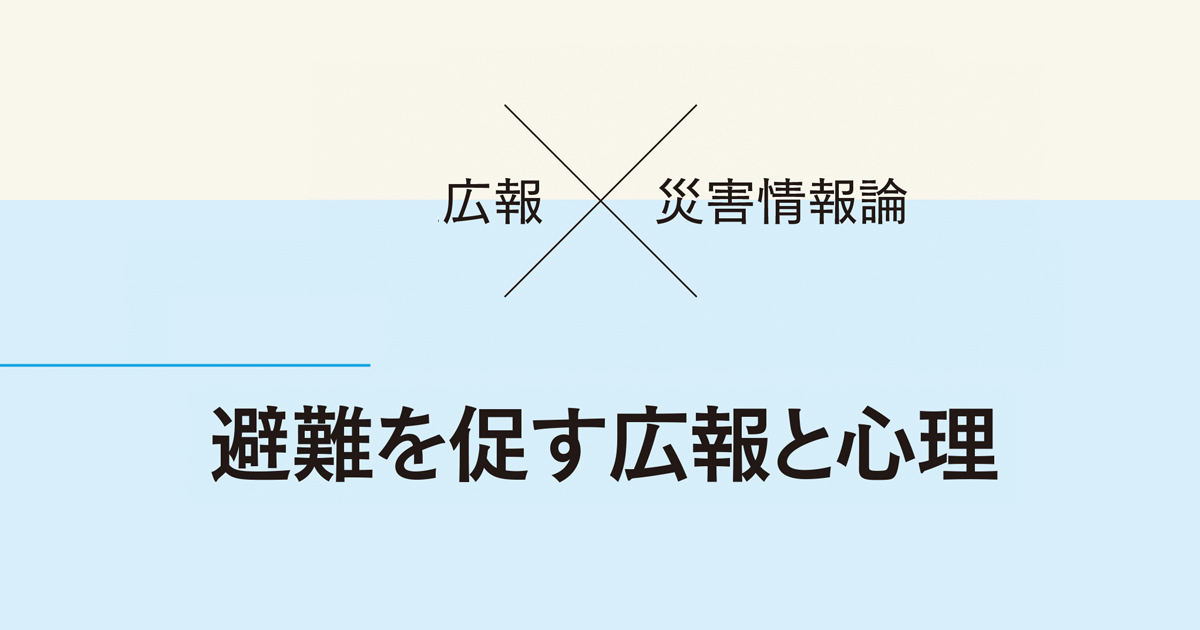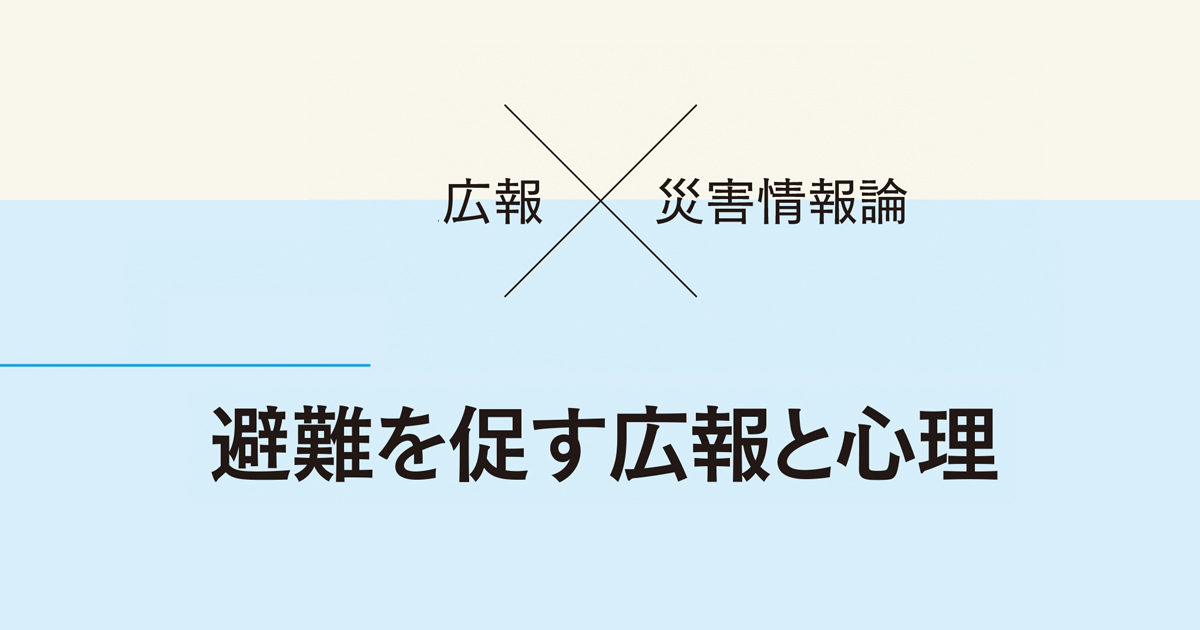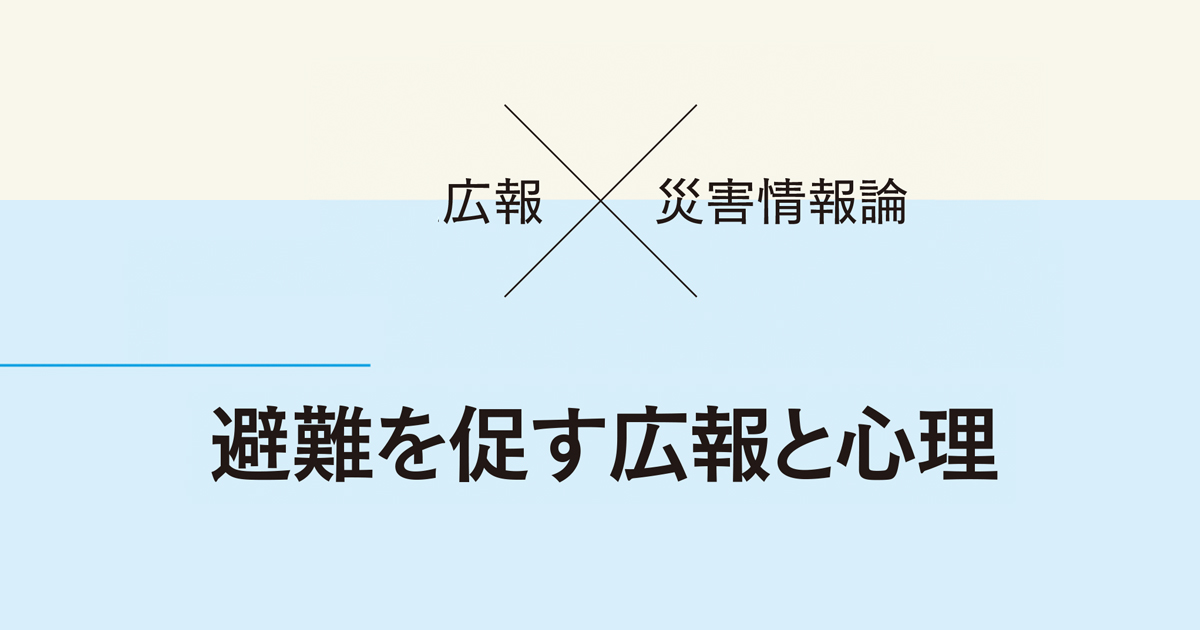迅速な行動喚起が必要な避難指示。その伝達が一刻を争うこともあります。災害情報論の視点から、情報の受け手の心理について考えます。
過去の災害経験がかえって避難の妨げになることを「経験の逆機能」といいます。以前の災害はあの程度だったから今回も大丈夫だろうという判断がそれです。東日本大震災、西日本豪雨など、こうした心理が避難を妨げた例が少なくありません。その背景には、小さな被害をもたらす災害はしばしば起きるものの、大災害発生の頻度は少ないという、災害の特性があります。
また超高齢社会においては、高齢者が「経験の逆機能」に陥りやすい傾向があり、特に注意が必要です。実際、2019年台風19号による福島県本宮市の洪水時のアンケートでは、「昭和時代の経験があだとなって避難が遅れた」とした人は、特に60・70代の人に多く見られました。
高齢者は苦手 とっさの判断
老年心理学によると、高齢になると人は言語など学習によって獲得された「結晶性知能」は維持できるものの、新たな情報を処理する「流動性知能」は低下するといいます(ワーキングメモリー等の低下)。避難の判断は、とっさに多くの情報を処理する「流動性知能」が要るので、そもそも高齢者には苦手な分野といえます。こうしたとき高齢者は、一部の情報だけで直感的に判断したり、過去の経験に頼ろうとしたりします。それゆえ高齢者は「経験の逆機能」に陥りがちなのです。最近問題となっているオレオレ詐欺も、多くの情報を処理しきれず直感でものごとを判断しがちな高齢者の「流動性知能」の低下を悪用したものと...