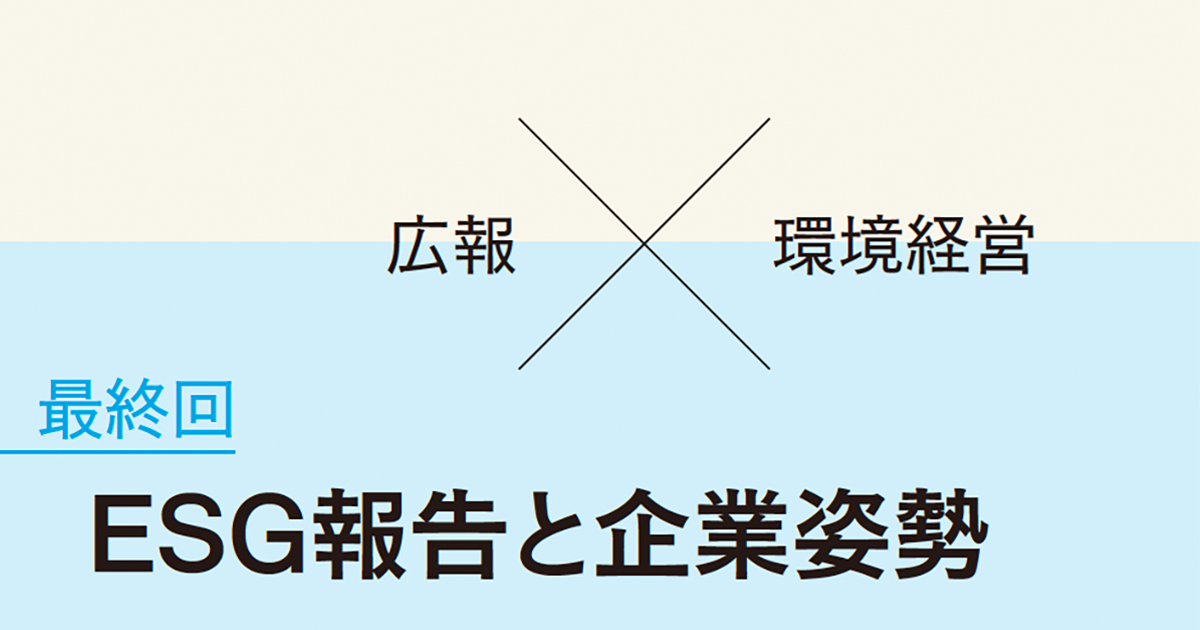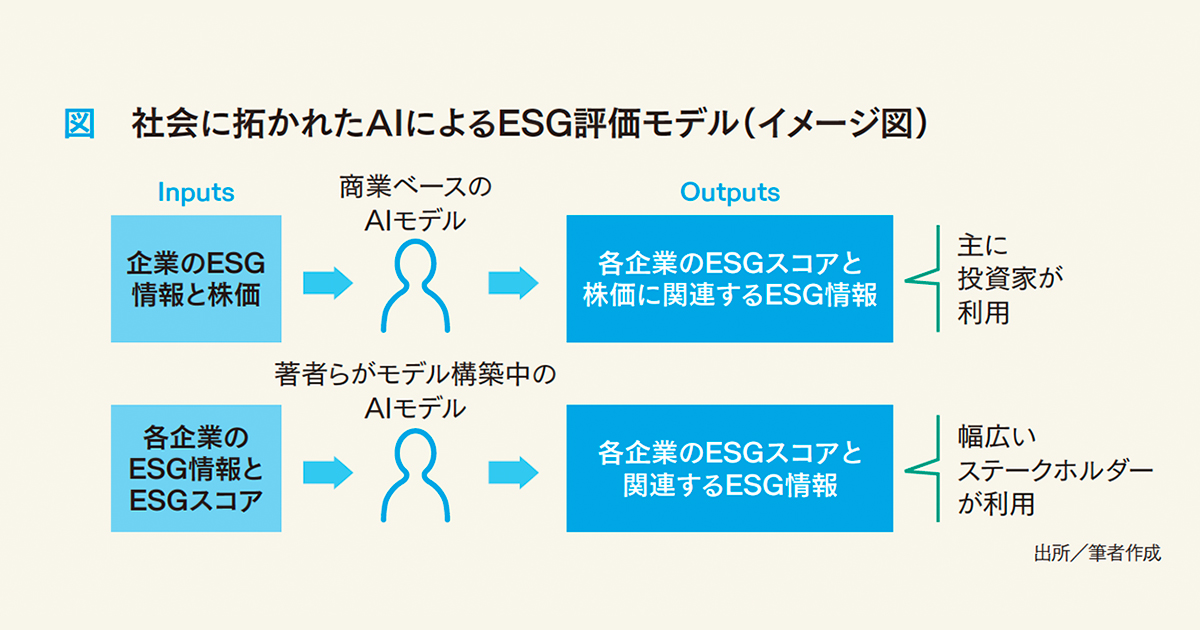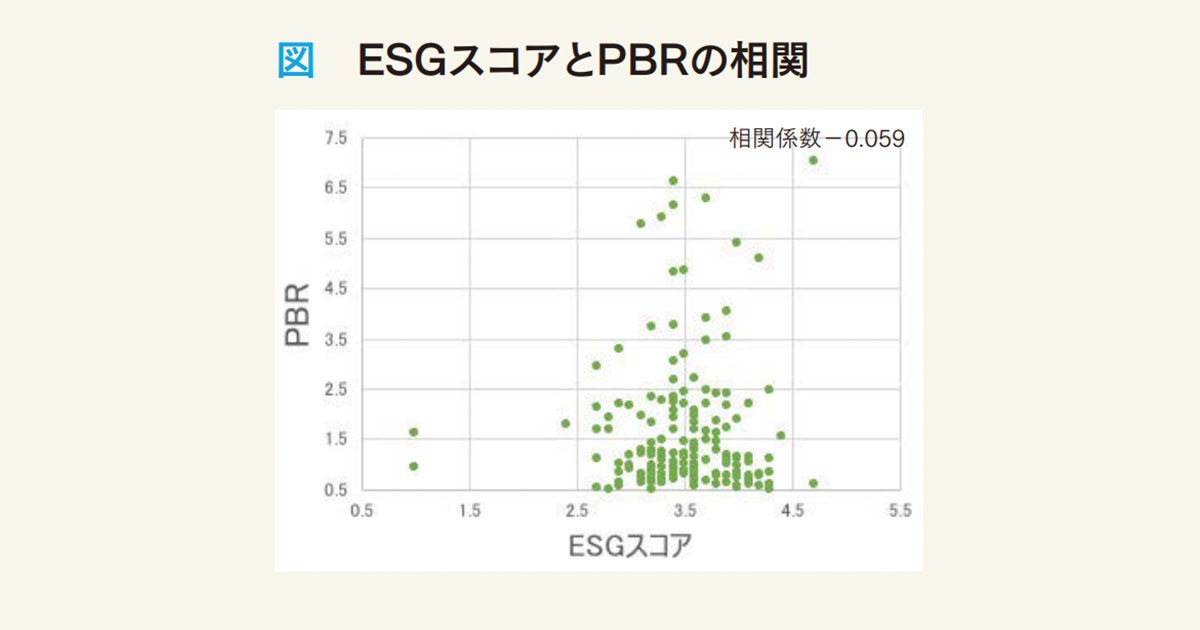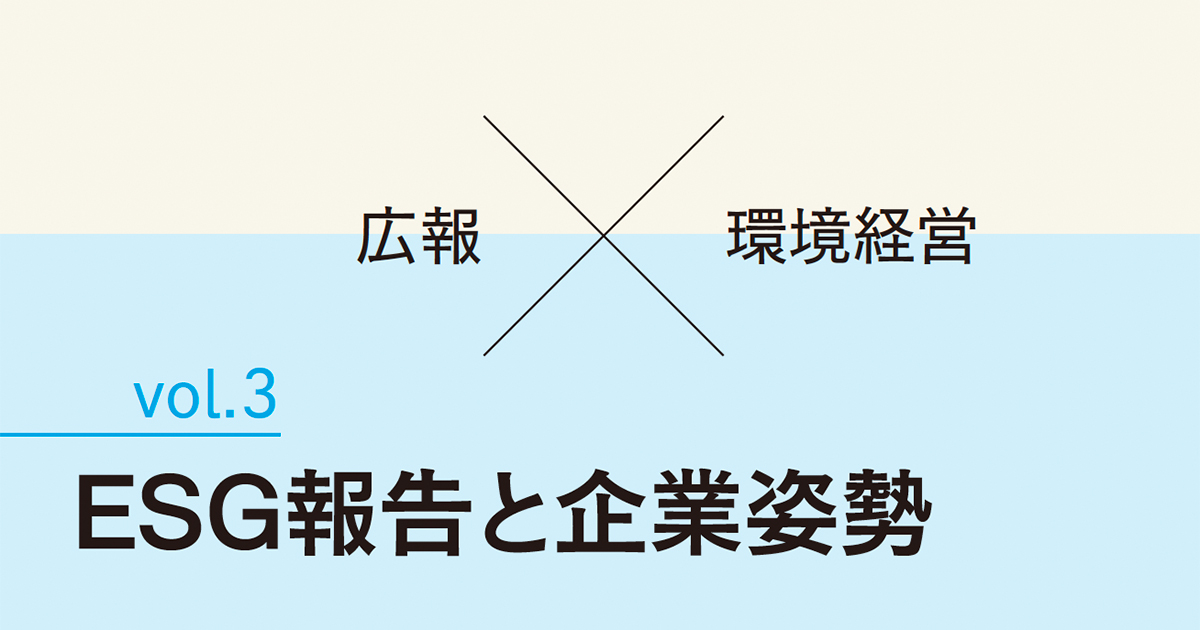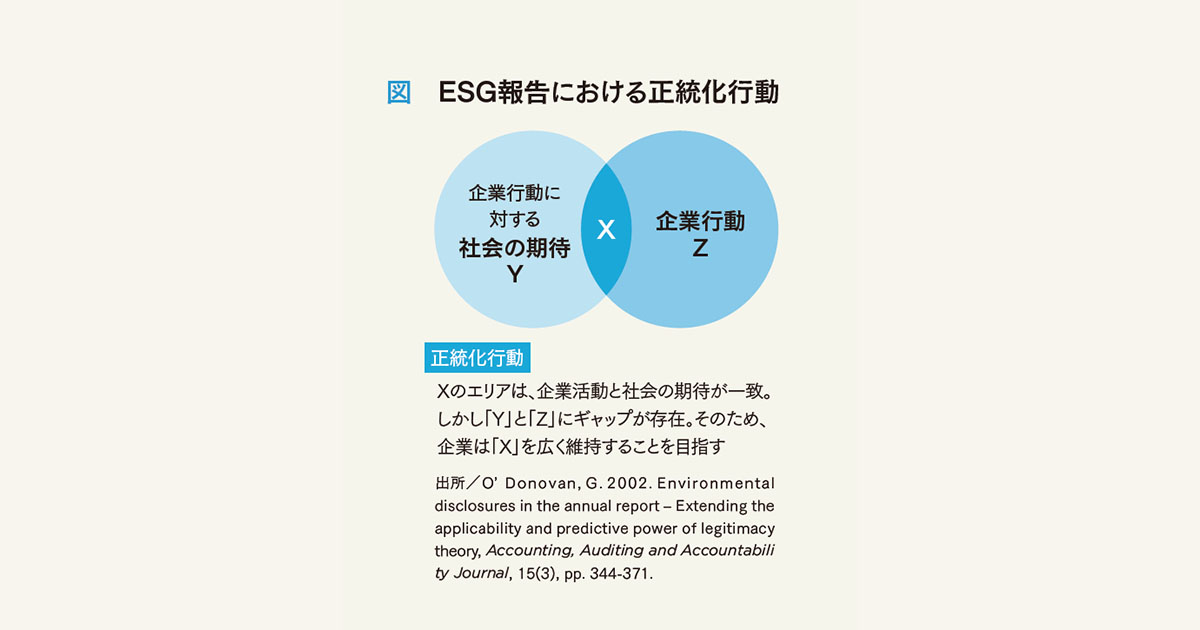ESG報告の温室効果ガス排出量や女性管理職比率などの数値情報の一律な解釈基準は存在しません。では開示情報からはどのような企業姿勢が読みとれるでしょうか。
ESG報告の中でも、投資家の関心が高いものに「気候変動のリスクと機会」の情報があります。気候変動リスクは、社会環境の変化によって投資額の回収が難しくなる座礁資産(Stranded Assets)として注目が集まっています。国際決済銀行も2020年に発表したレポ―トで、気候変動による極めて不確実で、物理的、社会的、経済的現象が伴うリスクを安定的にモニタリングする困難さを指摘しています。
このような気候変動リスクを金融システムに機能的に組み込むために、2017年、金融安定理事会から、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の最終報告書が公表されました。報告書では、企業等に対し、気候変動関連リスクおよび機会に関する項目として(1)ガバナンス(2)戦略(3)リスク管理(4)指標と目標の開示を推奨しています。2021年7月現在、TCFDに賛同する企業・機関は世界全体で2350、日本は451にのぼります。
しかしTCFDはあくまで企業の自主的開示であるため、推奨される開示項目で果たして気候変動のリスクは管理できるのでしょうか。Binglerら(2021)の研究では、各社のTCFDへの賛同は、ほとんどが口先だけで重要でない気候リスク情報を選んでいる(チープトークでチェリーピッキング*1)と批判しています。Binglerら(2021)は、TCFD賛同企業800社の6年間のアニュアルレポートを対象とし、AIを活用し、TCFD賛同後の内容を解析しています。その結果、特に、気候変動問題で重要な戦略や指標・目標の開示が不十分だと指摘しています。