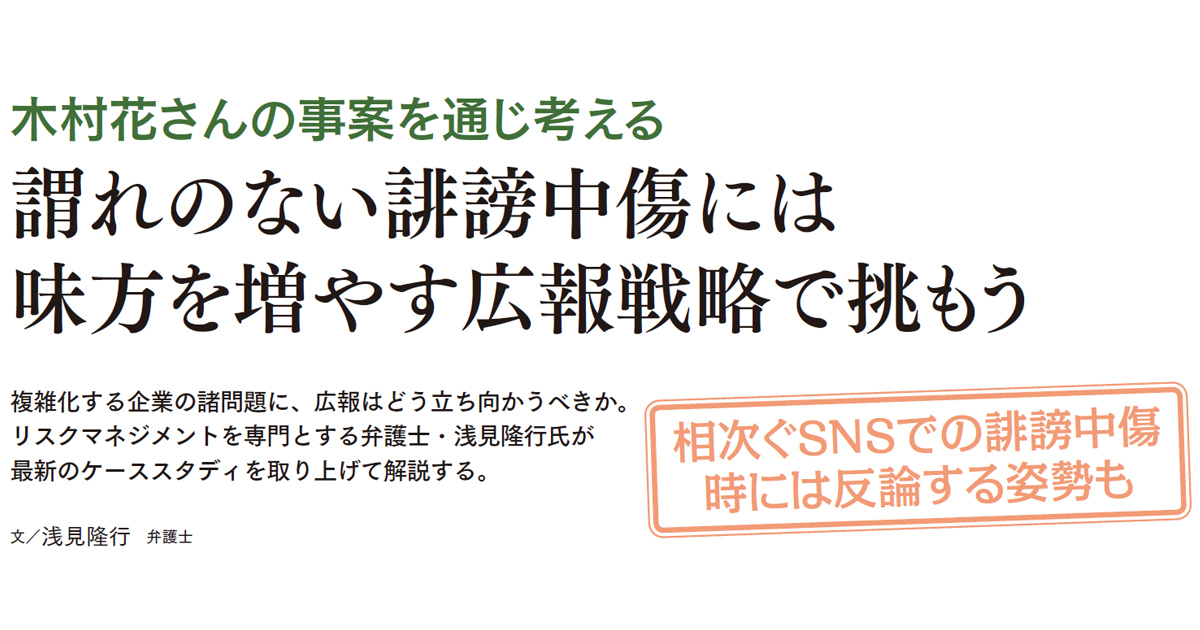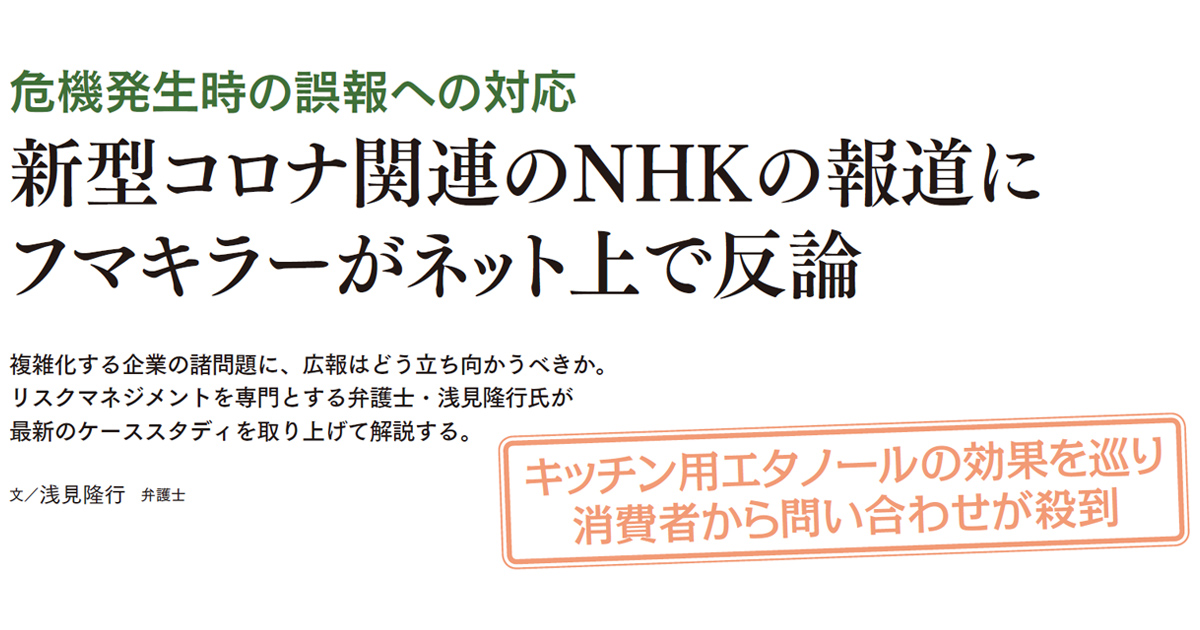複雑化する企業の諸問題に、広報はどう立ち向かうべきか。リスクマネジメントを専門とする弁護士・浅見隆行氏が最新のケーススタディを取り上げて解説する。
問題の経緯
2020年6月17日

商品の効能については、証拠資料に基づく正確な情報開示が求められる(写真はイメージです)。
自社の提供するタンポポ茶が新型コロナウイルスの予防に効くと宣伝したとして、大阪府警は6月17日、医薬品医療機器法違反(未承認医薬品の広告)容疑で、兵庫県内にある健康食品輸入会社の社長ら2人を逮捕した。他にも、インフルエンザなど様々な病気に効用があるとホームページ上で宣伝。消費者庁から指導を受けていたという。
医薬品ではないのに「タンポポ茶が新型コロナウイルスに有効」などと宣伝したため、タンポポ茶の製造輸入会社と販売会社の社長が薬機法違反(未承認医薬品の広告)にもとづき、6月17日に逮捕されました。新型コロナウイルスを商機到来と考える企業、新型コロナウイルスのダメージから回復しようとする企業、そのいずれもが、売上を伸ばすために広報の内容や方法を試行錯誤しているはずです。しかし、広報の内容や方法のいきすぎを理由に逮捕や行政処分を受けてしまっては企業としての信用を失います。
そこで、今回は、新型コロナウイルス関連商品に限らず、企業が行う商品・サービスの広告・宣伝などの広報に関して、広報部門が注意しておくべきポイントを解説します。
コロナで増えた「予防」うたう広告表現
3月以降、新型コロナウイルスを商機到来と捉えた企業は、自社の商品やサービスを新型コロナウイルスの予防に効果的であることを強調して広告宣伝していました。実際に、タンポポ茶などの健康食品やサプリメントのほか、「新型コロナウイルスに有効」などと表示するマイナスイオン発生器やイオン空気清浄機、「身に付けるだけで空間のウイルス除去・除菌」などをうたった、首につり下げて使用する携帯型の空間除菌用品や除菌・抗菌スプレーなどが現れました。
しかし、医薬品ではないのにサプリメントや健康食品に医薬品であるかのような効能を表示することは薬機法違反であるほか、それ以外の商品やサービスも一般消費者に品質や効果を誤認させるような表示をすることは禁じられています。消費者を騙すことになるからです。
消費者庁は、これらの「新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品等の表示」に対して、景品表示法違反(優良誤認表示)や健康増進法(虚偽誇大広告)を理由に3月以降繰り返し改善要請をするほか、5月15日には、首につり下げて使用する携帯型の空間除菌用品の販売業者5社に行政指導を行いました。
こうした行政指導・行政処分の対象となるのは、新型コロナウイルスの関連商品に限りません...