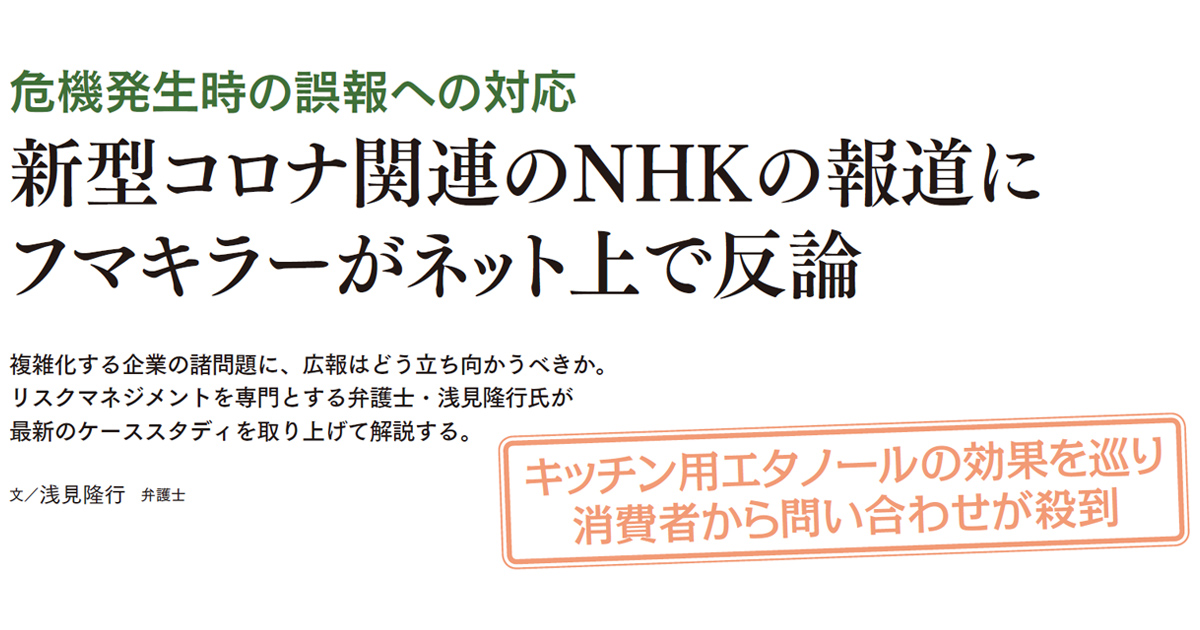複雑化する企業の諸問題に、広報はどう立ち向かうべきか。リスクマネジメントを専門とする弁護士・浅見隆行氏が最新のケーススタディを取り上げて解説する。
端緒となったニュース
2020年3月23日

在宅勤務を導入する企業が増加したのに伴い、顕在化した「ハンコ問題」。
文具メーカーのシヤチハタは同社の電子印鑑での決裁サービスを期間限定で無料開放することを発表。同社のサービスは、自宅でパソコンやスマートフォンから開いた稟議書や請求書といった書類に電子印鑑で押印、その書類を自社のみならず、取引先も閲覧できる仕組みだ。通常であれば一つの電子印鑑の登録に月額100円かかるサービスを、6月30日まで無料で開放。緊急事態宣言下で在宅勤務をする人が増える一方、書類に印鑑を押すためだけに出社する、などの非効率性の解消につながった。
また、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、社会貢献を行った企業は他にもある。例えば、島津製作所や、東洋紡、シャープ、資生堂などがあった。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、在宅勤務体制に移行した会社が多くなってきました。しかし、いまだに稟議書や決裁書などに「ハンコ」を押さなければならない場面も多く、「ハンコを押すためだけに出社する」などと揶揄される事態も生じています。そうした中、文具メーカーのシヤチハタが、3月31日から6月30日まで期間限定で、クラウド捺印サービスを無料開放することを発表。在宅勤務体制への大きな後押しとなりました。
そこで、今回は、シヤチハタの事例を題材に、新型コロナウイルスと企業の社会的責任という観点から危機管理広報を検討していきたいと思います。
企業の社会的責任を果たした好事例
3月中旬から在宅勤務体制に移行する企業が見られるようになり、4月7日の緊急事態宣言後には在宅勤務体制が本格化しました。それは、新型コロナウイルスがあることを前提とした上で、ウイルスとどうつき合って業務を継続していくか、いわゆる「ウィズコロナ/with COVI D-19」のフェーズに移行したとも言えるでしょう。
このフェーズになって明らかになったことは以下の2つです。ひとつは、テレワークなど業務の遂行方法を変化せざるを得ない、ということ。もうひとつは、企業の事業目的の変化です。事業目的の変化とは、何のために企業が事業を行っているのか、企業の存在価値の変化、という意味です。ビフォアコロナのときには、企業は売上・利益を上げればそれで良いと、ややもすると数字一辺倒になりかけていたことは否定できません。
しかし...