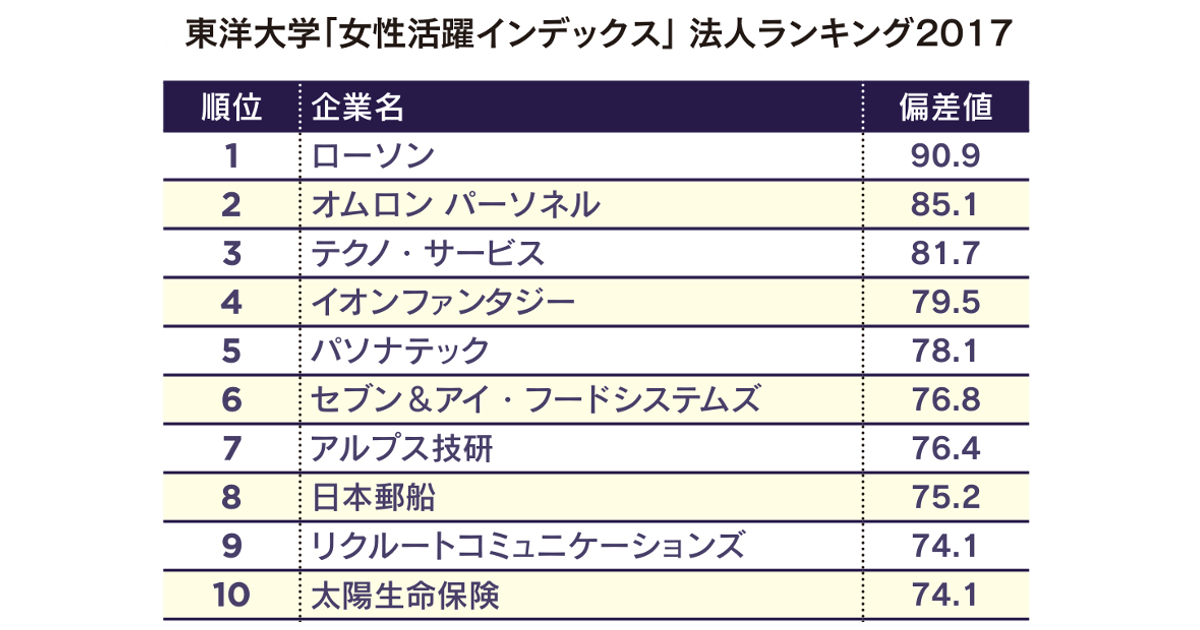800近くある国公私立大学が受験生や資金を求めて競争する教育現場。スポーツ選手を多く輩出する東洋大学で広報を務める榊原康貴氏が、現場の課題や危機管理などの広報のポイントを解説します。

8月1日に開かれた「国産カヌー開発発表会」の様子。前日に行われた試乗テストの動画なども上映した。
リオオリンピックの感動から早1年。2020年の東京大会に向けて様々な取り組みが盛り上がりを見せています。大学ではアスリート学生の育成はもちろん、各国と協定を結び体育施設を貸し出したり、通訳やボランティアを育成したりと多方面から大会に貢献しようと働きかけをしています。
そんな中、東洋大学では理系の研究リソースでオリンピックに貢献することを目的としたプロジェクトが進行中です。今回はこうした研究プロジェクトを起点に、理系イメージの定着を目指す過程について書きたいと思います。
東洋大学=文系?
そもそも、大学のイメージはどのようにして定着するのでしょうか?伝統校は成り立ちの学問系統のイメージが定着していますし、大学名に「工業・電気」などと入っていれば名前を見ただけで何をする大学か分かります。
しかし、東洋大学の名前にはそれら専門を意味する言葉も入っていませんし、哲学を発祥として⋯⋯という「建学の精神」を出しても、なかなかご理解いただけない場面が多くあります。また、体育学部はないのですが、箱根駅伝での活躍やオリンピック選手が多数存在するためスポーツが盛んなイメージに拍車をかけています。
現在、東洋大学の全13学部のうち5学部は理系なのです。しかし、世間では文系の総合大学というイメージがあるのではないでしょうか。実に3分の1以上の学問のテーマが理系であることはあまり世間に知られていないと実感しています。
大学全体でもこうした理系イメージアップは幾度となく広報の課題として挙がってきましたが、なかなか機会に恵まれませんでした。
一方、文部科学省の大型補助金事業「私立大学研究ブランディング事業」というものがあります。各大学の研究を大学のブランドイメージ向上に結びつけることを目指しているものです。国としても、研究成果を適切に広報することの重要性を感じている証です。ともすると、専門用語ばかりで分かりにくいのが理系の研究成果。これを広報することの難しさを痛感している大学関係者もたくさんいらっしゃると思います。
東洋大学ではこうした中、理系イメージの定着を図る取り組みをスタートさせました。
日の丸カヌーで金メダルを
昨年のリオオリンピックでは、羽根田卓也選手がカヌーで日本人初のメダルを獲得した快挙は記憶に新しいと思います。
しかし実は、選手たちが使う競技用カヌーのほとんどが東欧製。日本製を使用している選手はいないのです。海外選手に合わせて作られている競技用カヌーは、日本人選手の体格に合わず成績に影響が出るとも言われています ...