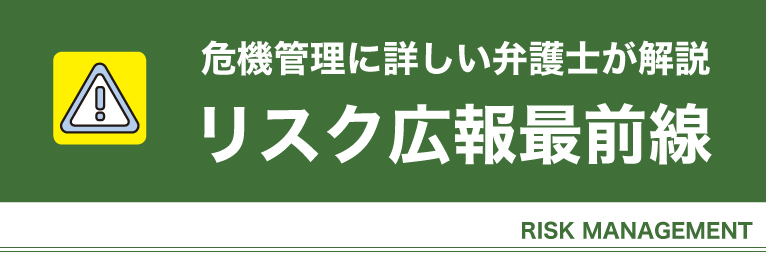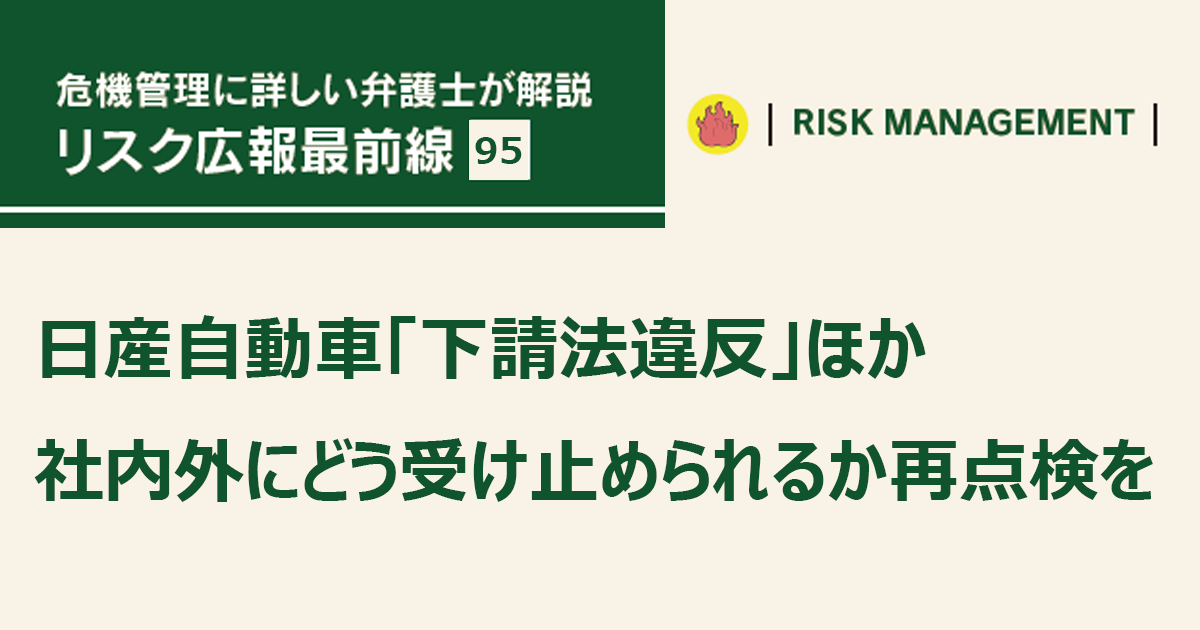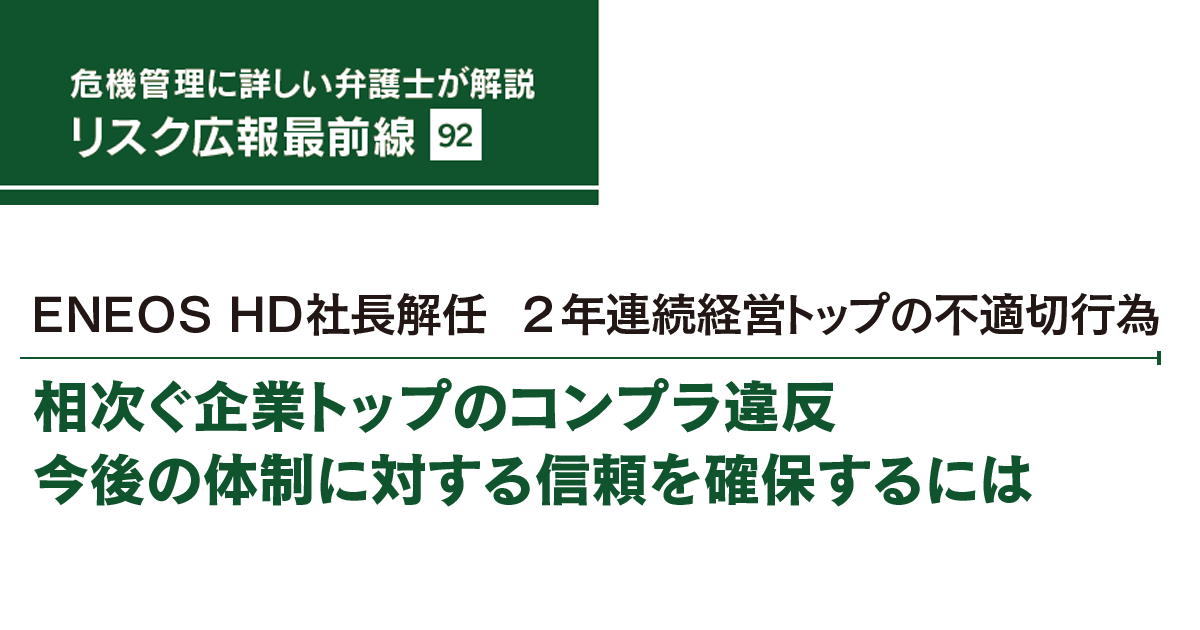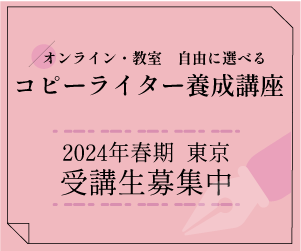あの不祥事は、なぜあれほど世間から批判されたのか─?顧客情報漏えいからフードテロ、取引先・子会社の不祥事まで、2014年の危機管理広報の誤りを専門家と振り返りながら、広報の視点で会社を守り、評判を高めるためのポイントを徹底解説します。

2014年4月9日に開かれた小保方晴子氏の記者会見。
入院中でドクターストップも懸念されていたが、2時間半記者の質問に対応した。
事件の経緯
4月9日、理化学研究所の小保方晴子ユニットリーダー(当時)は英科学誌ネイチャーに掲載されたSTAP細胞をめぐる論文に不正があったとされる問題で記者会見を開き、あらためて論文の正当性を主張した。会見は、理研の調査委員会は4月1日、小保方氏の論文に捏造と改ざんの不正があったと認定したことを受けて開かれたもの。理研ではSTAP細胞の存在を明らかにするため、検証を進めている。
 |
調査会社社長 古野啓介氏はこう見る
|
本件はやはり初動対応が致命傷となった。不正疑惑が浮上した段階で、リスクの本質と危機のインパクトが理解できず、理事らに現状の正しいリスク認識を周知できなかったコンプライアンス担当部門の知見のなさ、グループ内のコミュニケーションが機能しておらず、危機管理の経験に乏しい広報対応の未熟さが大きな要因だろう。
理事らのリスク意識の低さも問題だった。当初、研究者個人の責任問題として、理研としては「(コンプライアンスの)教育が行き届いていなかった」という認識に留まった。当事者意識が欠落し、論文の社会的インパクトと、それに伴うアカウンタビリティの大きさにも目をつむろうとしたと思われる表現からも顕著である。
理研としては研究者が当然の倫理観を持って研究成果を発表し、ネイチャー誌も相応の審査をしていることを前提としていたことは多少の理解ができる。しかし、最初の会見で、理研としての管理・監督体制に問題がなかったかを適切に把握せず発言したことは、説明責任を果たそうとせず、責任の転嫁などと評されても仕方ない。
危機管理対応の基本は ...