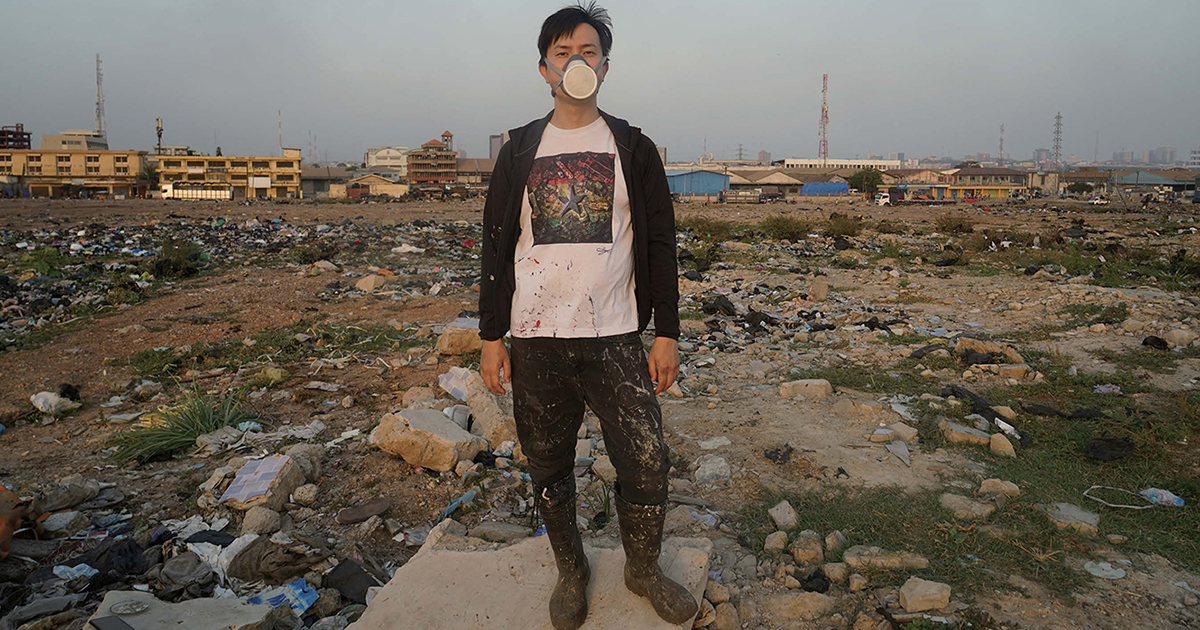暮らしのなかでの不思議との出会いを短歌で届けている歌人の小島ゆかり氏。限られた形式のなかでメッセージを伝える短歌と広告にはどのような共通点があるのか、話を聞いた。

小島ゆかり(こじま・ゆかり)さん
1956年愛知県に生まれる。早稲田大学文学部卒業。コスモス短歌会選者。歌集に『憂春』(迢空賞)、『純白光 短歌日記2012』(小野市詩歌文学賞)、『泥と青葉』(齋藤茂吉短歌文学賞)、『馬上』(芸術選奨文部科学大臣賞)、『六六魚』(詩歌文学館賞)、『雪麻呂』(大岡信賞)など。歌書に『和歌で楽しむ源氏物語』『短歌入門~今日よりは明日』などがある。産経歌壇選者。短歌甲子園特別審査員。2017年紫綬褒章。
科学では言い表すことができない「気持ち」や「体感」を表現する
「五・七・五・七・七」の詩形のなかで言葉を紡ぎ、数々の名作短歌を生み出してきた、歌人の小島ゆかり氏。これまでに15冊もの歌集を上梓しているほか、選者・審査員、各地での講演活動、日本経済新聞にてエッセーを連載するなど、言葉を軸に多彩な活動を行っている。
小島氏が短歌と出会ったのは大学生時代。当時、“文語体”の奥ゆかしさに惹かれていたことから、学内で偶然見かけた「短歌創作と鑑賞の会」と書かれたビラに興味を持ち、参加したことがきっかけであったという。
「短歌に限らず、人生で大切なこととの出会いは、不思議な偶然というか何か巡りあわせのように起こることが多いように思います。私と短歌の出会いも、そのような偶然から始まりました」と微笑みながら小島氏は話す。普段は気恥ずかしくてなかなか口にできないようなことも、歌にすれば表現できる。このような短歌の魅力に面白さを感じ、作品づくりをスタートさせたという。
日常のなかでの出会いを、やわらかな言葉で綴る小島氏の作品は、世代を超えて多くの人の心にやさしく沁み込んでいく。小島氏は作品を考える際、科学的なものの見方とは異なる、説明できないような気持ちや体感を大切にすることを心がけていると話す。
「様々なことが科学的に証明されていき、仕組化されたのが現在の世界の姿。もちろん、それにより暮らしは便利になっているので必要なものだとは思います。ただ、私が歌を詠む時は、そのような理論立ったものではなく、ある種の直感のようなものを大事にしたいと考えています。例えば1日は24時間ですし、月までの距離も決まっていますが、生きていると1日が過ぎるスピードがものすごく速い日や遅い日もあれば、月が近く感じたり果てしなく遠く感じたりといったこともあります。夏の夕暮れの切なさや、夜真っ暗なのになぜか安心感があったりして。このようなものの見方や感じ方を大切にして、世界に触れていたいと考えています」。
このような感覚は、言葉にするのが難しいことも往々にしてある。小島氏は、感じたことを「ありのまま」に表現することは不可能で、言葉にしようとした段階で「創作」となり、説明しようとすればするほど「ありのまま」の気持ちとは...