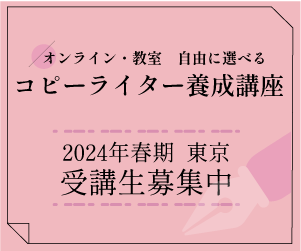「買ってくれた人も、現地の人も、地球も喜ぶ。文化、経済、環境全てが動く」。この思いを胸にアーティストとして活動し、絵画作品の売上をガーナ共和国のスラム街の社会支援に役立てる取り組みを行っている長坂真護氏。アートビジネスの観点から垣間見た現在の広告・マーケティングの在り方について問題提起する。

長坂真護(ながさか・まご)さん
1984年生まれ。2009年、自ら経営する会社が倒産し路上の画家に。2017年6月“世界最大級の電子機器の墓場”と言われるガーナのスラム街“アグボグブロシー”を訪れ、先進国が捨てた電子機器を燃やすことで生計を立てる人々と出会う。アートの力を使って、“我々先進国の豊かな生活は、このスラム街の人々の犠牲のもとに成り立っているという真実”を先進国に伝えることを決意。「サスティナブル・キャピタリズム」を提唱し、これまでに1000個以上のガスマスクをガーナに届け、2018年にはスラム街初の私立学校『MAGO ART AND STUDY』を設立。2019年8月アグボグブロシー5回目の訪問で53日間滞在し、彼らの新しい希望と生活のために、スラム街初の文化施設『MAGO E-Waste Museum』を設立した。この軌跡をエミー賞授賞監督カーン・コンウィザーが追い、ドキュメンタリー映画“Still A Black Star”を制作し、2021年アメリカのNEWPORT BEACH FILM FESTIVALで「観客賞部門 最優秀環境映画賞」を受賞。現在、公開へ向けて準備中。
先進国のゴミで埋もれた街 アグボグブロシーとの出会い
「先進国の豊かな生活は、スラム街の人々の犠牲のもとに成り立っている」。この事実を、電子機器の廃材を用いてアートを制作することで発信し続けているアーティストの長坂真護氏。持続可能性と資本主義は必ずしも相反するものではないとの考えから、「文化」「経済」「社会貢献」の3つの歯車が持続的に回る形態、「サスティナブル・キャピタリズム(持続可能な資本主義)」を掲げ、活動を行っている。
長坂氏はこれまでに、作品の販売により得た売上で、ガーナ共和国へのガスマスクの寄付や私立学校の設立を実施。生み出す作品を人々が所有すればするほど、現地のゴミが減り、経済に貢献し、文化性も高まるという仕組みだ。2030年までに100億円以上集め、現地に最先端のリサイクル工場を建設し、現地の人々が自活可能な場とすることを目標にしているという。
長坂氏はどのような経験を経て、現在の活動を始めるに至ったのか。
アパレル企業の経営者として活躍していた矢先の2009年、同氏は突然の会社倒産という不運に見舞われた。その後、幼少から親しんでいた絵を描こうと路上で絵を描き始めたという。そんな中、長坂氏は2016年にある1枚の報道写真を偶然見かける。そこには両手いっぱいに電子ゴミを抱えたひとりの少女の姿が。それは世界最大級の電子機器廃棄物の墓場と言われる、ガーナのスラム街「アグボグブロシー」の風景だった。
実際に自分の目で確かめたいと、翌年現地に赴いた長坂氏。アグボグブロシーに足を踏み入れると、そこには日本を含む先進国から廃棄された電子機器を燃やし、それにより排出される有毒ガスを吸いながら1日わずか500円の日当で生きる若者たちの姿があった。そんな現状を目の当たりにして強い衝撃を受けたという。
「あの風景は自分の人生観を180度変えるほどの大きなインパクトでした。そして何ができるか分からないけれど、自分が動かないとダメだと、強い衝動に駆られたんです」と話す。
そしてこの不条理な現実を自らが...