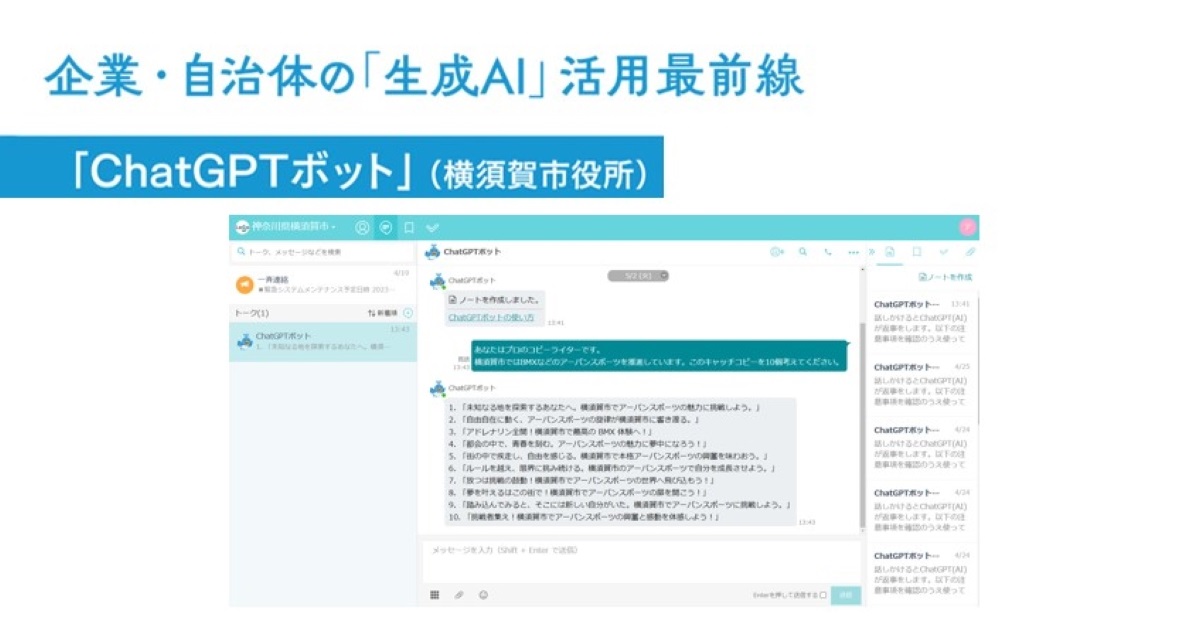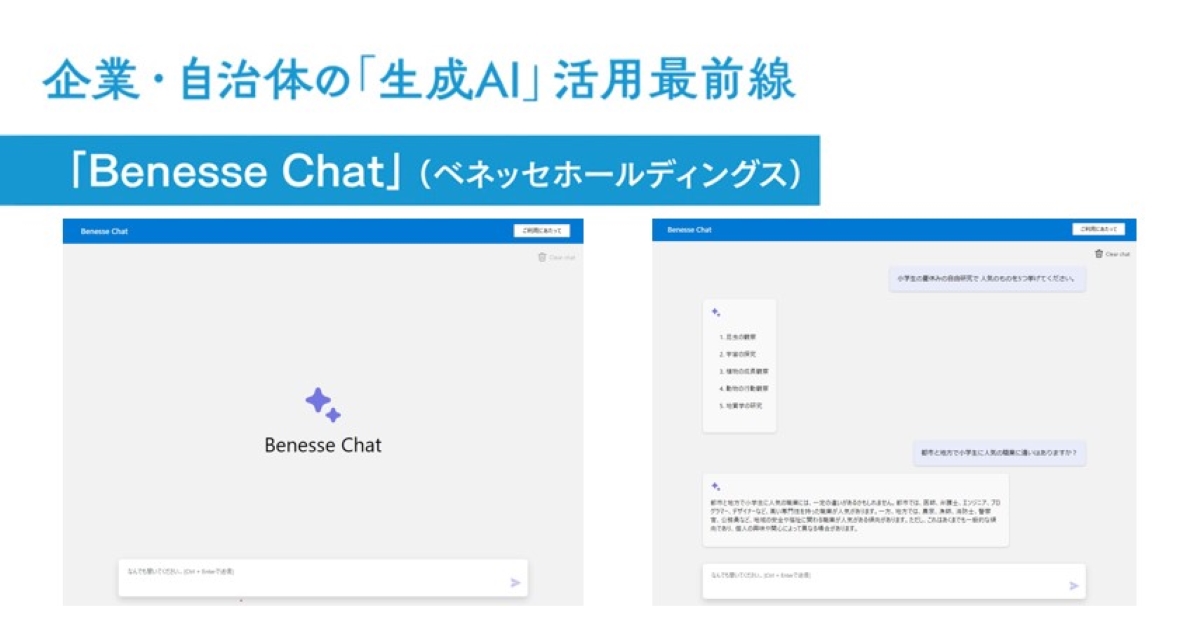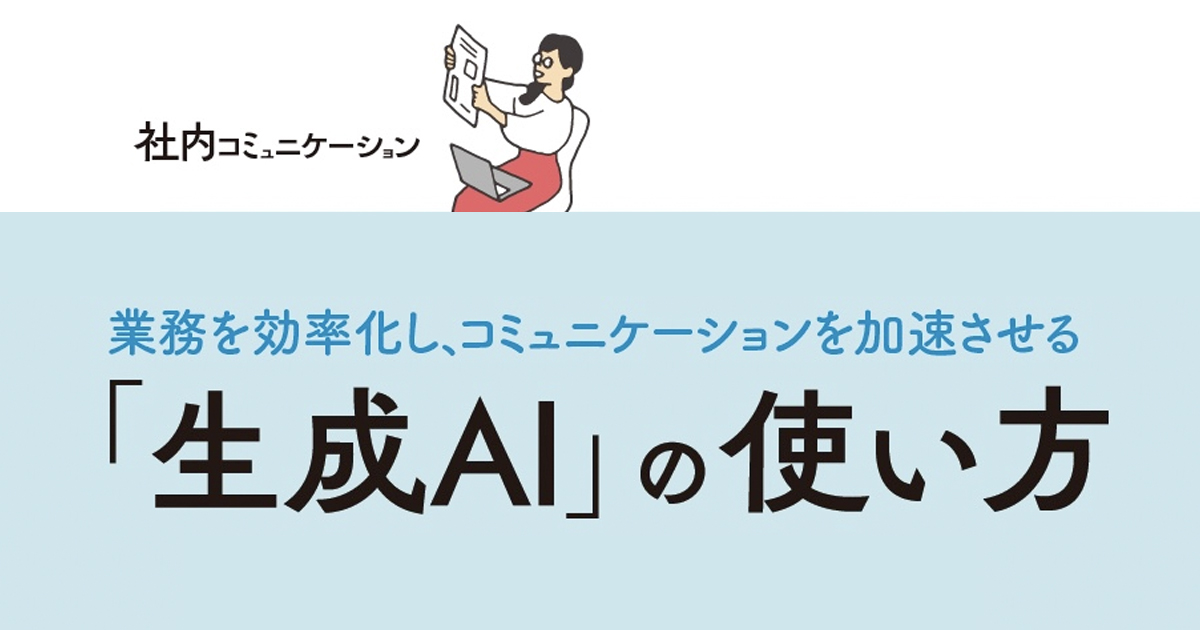社内報の作成にAIはいかに活用できるのでしょうか。「人員不足で作成に手が回らない」「せっかく書いても、なかなか読まれない」など、広報担当者の課題解決をサポートする活用アイデアを聞きました。「企画」「執筆」「画像生成」の3フェーズに分けて紹介します。
取材した人

note
CXO
深津貴之氏

日本マネジメント
総合研究所
理事長
戸村智憲氏

日本リスクコミュニケーション協会
代表理事
レイザー
代表取締役
大杉春子氏
生成AIを使い始める前の注意点
● ツール、サービスについて使用前に規約などを調べ、入力した情報が学習・サービス改善などへ二次活用されることがあるのか(情報漏洩のリスク)、生成コンテンツの著作権侵害の可能性などを理解した上で使用しよう。
● 出てきた情報を鵜呑みにせず、ファクトチェックや法規範、社会規範などを人間の目でチェックしてから公開しよう。
執筆編
Q. 本文をAIに考えてもらう際のコツはありますか
A. 構成案をつくってから、文章の作成に取り掛かりましょう
書いてほしい「テーマ」や文字数といった情報を指示することはもちろんですが、それだけで文章を書かせても、求めている内容とのズレが大きくなる可能性が高いです。そのため、私はまず、テーマから構成案をつくり、構成案についてのやり取りを何往復かしてブラッシュアップした上で、文章作成を指示するケースが多いです。
例えば、下記のようなステップを踏みます。
[ステップ1]「〇〇というテーマについて社内報記事の構成案をつくってください」と指示
[ステップ2]構成案をもとに「もっと社員が満足する社内報にするために追加した方がいい内容の案はありますか」と指示
[ステップ3]「提案してくれた内容を全て網羅した記事構成案をつくってください」と指示
[ステップ4]出てきた記事構成案に基づいて、「この記事の見出しをつくってください」と指示
[ステップ5]「生成した見出し●●に基づいて、本文を書いてください」と指示
構成案をつくる際、「この情報も入れてほしい」というものがある場合は、参照元の文章も入力すれば、織り込んでくれます。参照元の情報を入力する場合は、冒頭に「###」を入れるとよいです。その場合の指示は、例えば「あなたは社内報を執筆する広報の専門家です。以下の情報を参考にしながら、ESGコミュニケーションを軸...