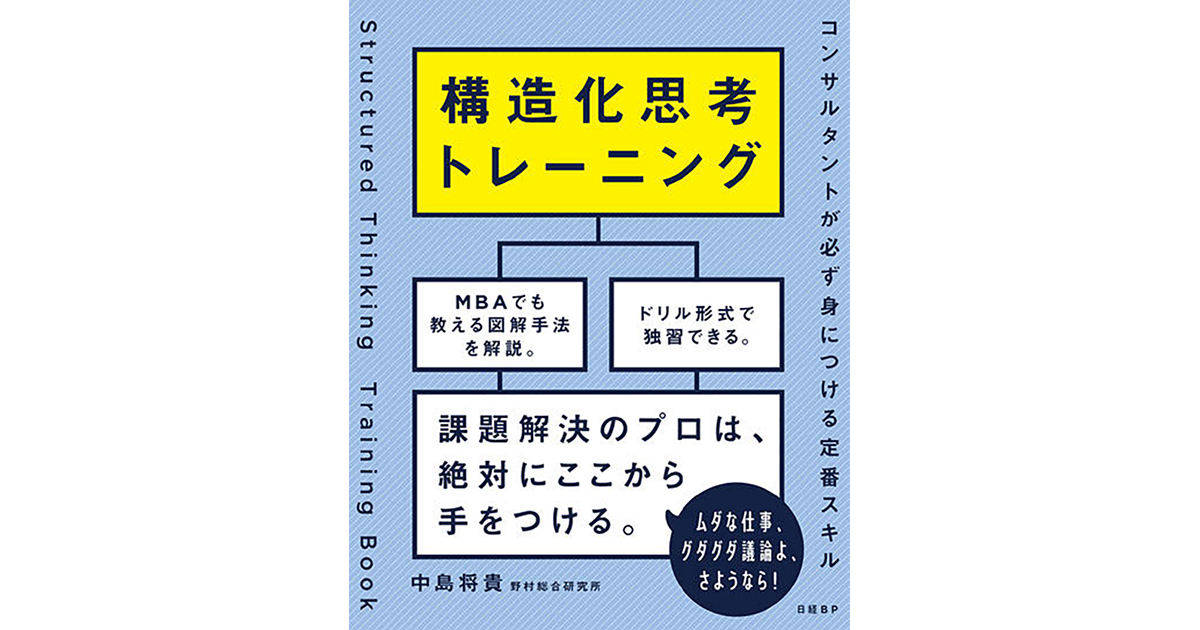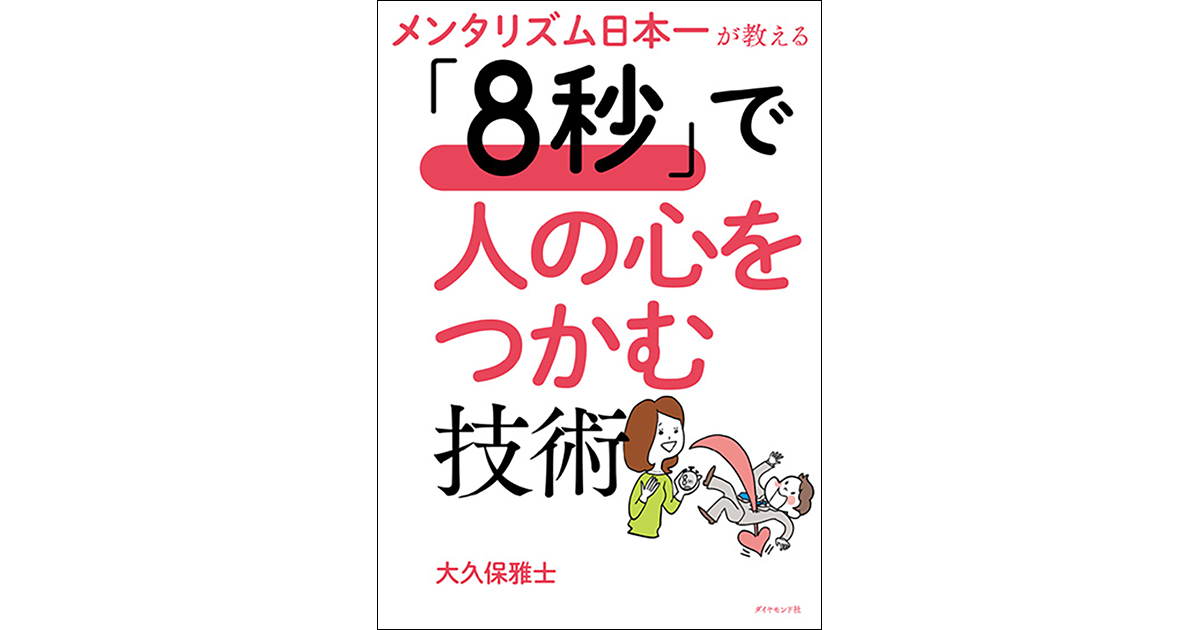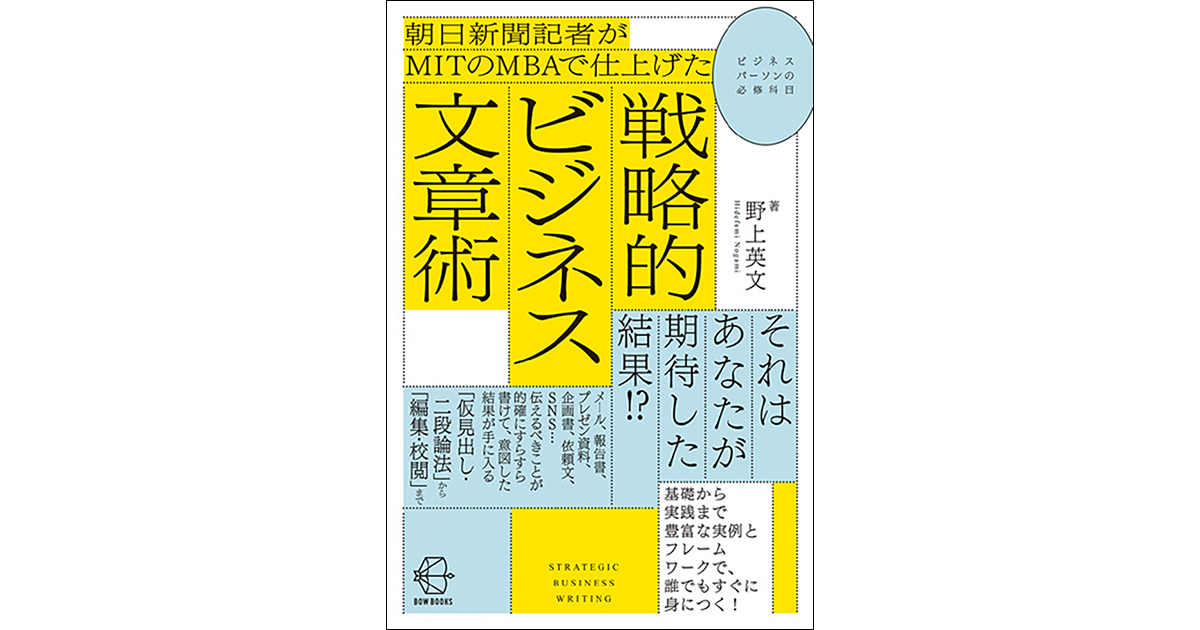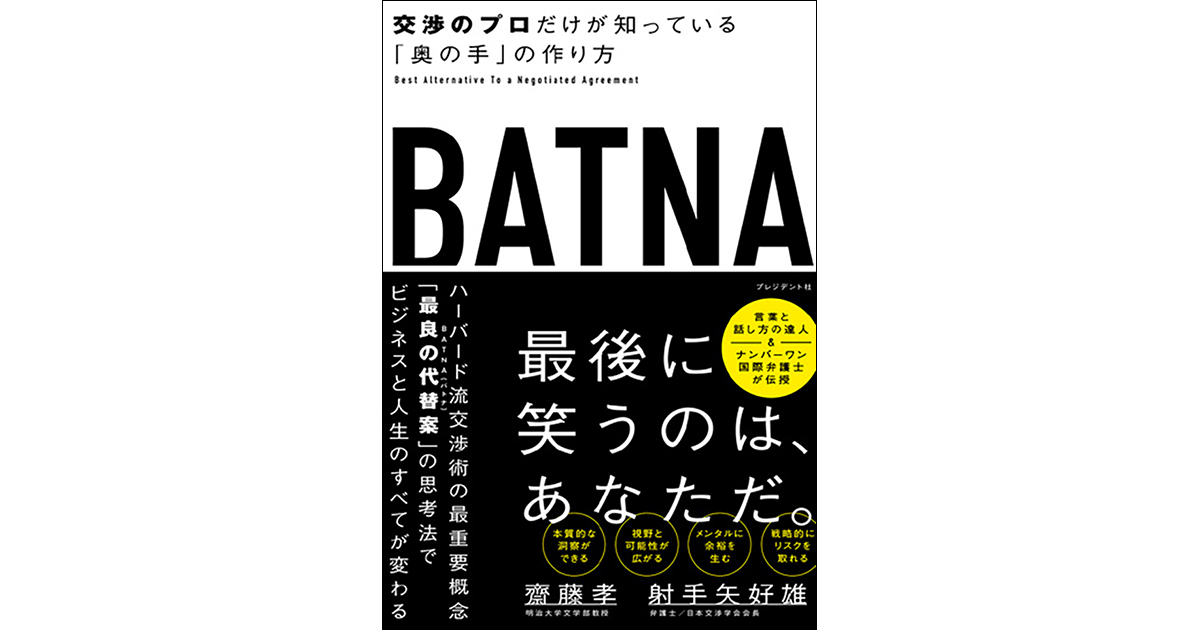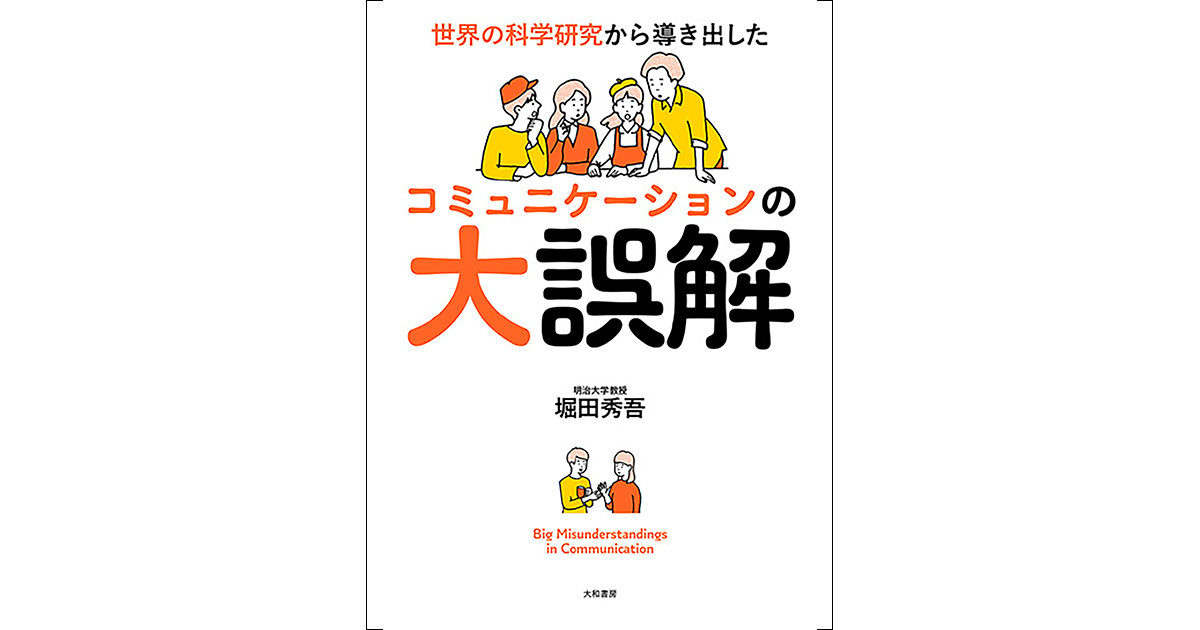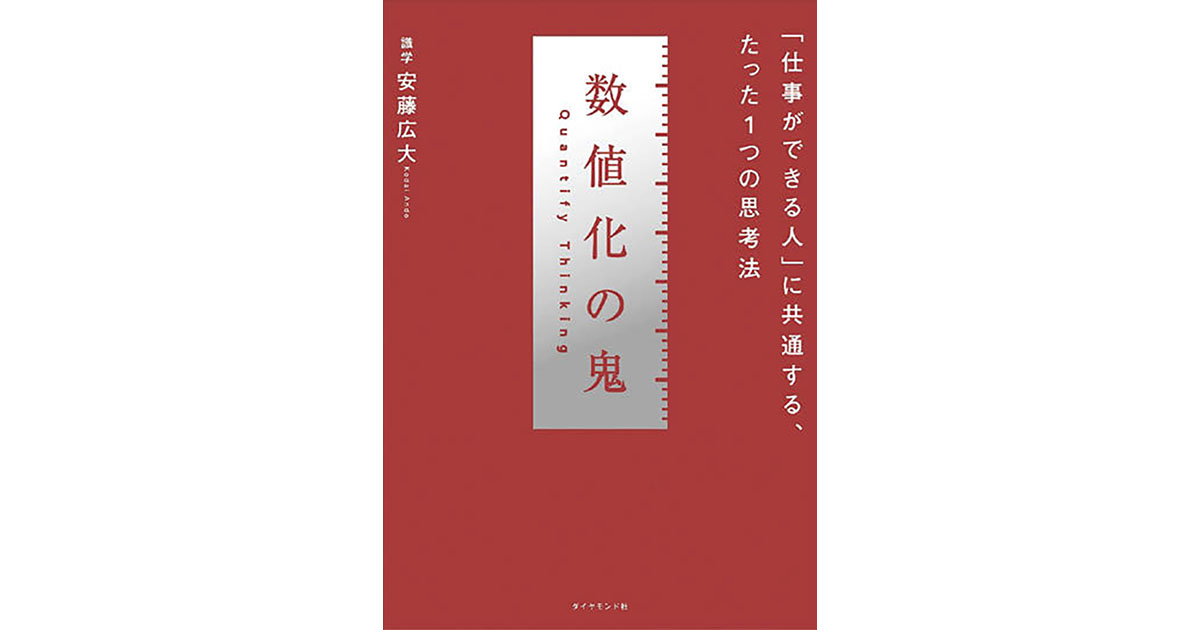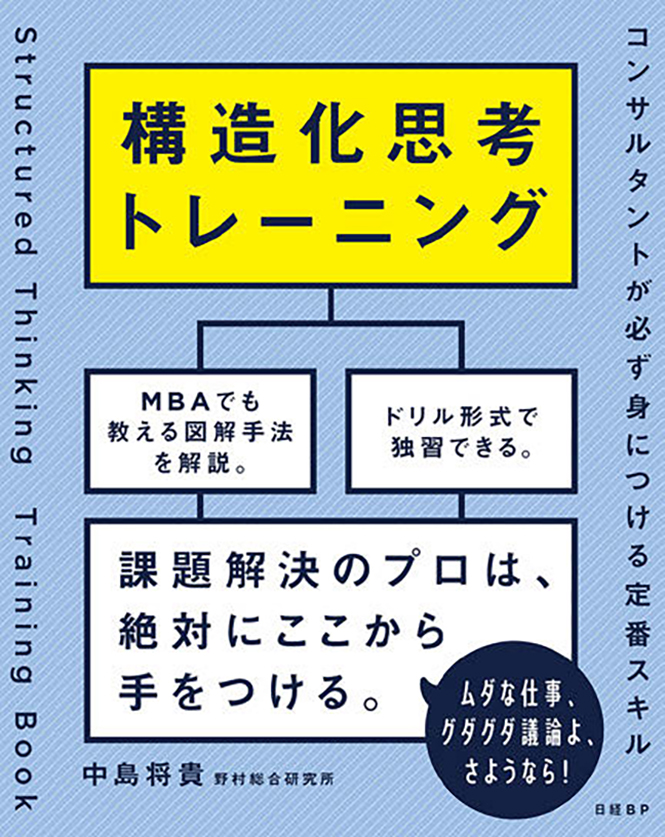
構造化思考トレーニング
コンサルタントが必ず身につける定番スキル
中島将貴/著
日経BP
160ページ、1760円(税込)
本書は単なるロジカルシンキングのテクニック本ではない。イシューとも呼ばれる「重要な論点」を見極め、論点の構造化を軸に意思決定する方法が記されている。もし、広報担当者のあなたが社内で依頼を受け、その背景から広報施策とゴールを設定し、イシューを見極めようとしたとき、高精度の仮説が立てられるだろうか。きっと多くの方が難しいと答えるはず。
本書では、コンサルタントとして活躍してきた筆者が、思考プロセスをより分かりやすくする手法として「キークエスチョンの設定」と「論点の構造化」の2ステップを取り入れることを提唱している。
キークエスチョンで論点構造化
「はじめに取りかかるべきは、キークエスチョンの設定です。これは、依頼主が理想とするゴールを疑問形に言い換えたもの。本書の“構造化思考”とは、この問いを出発点に論点を洗い出し、全体像を描いた後に、重要な論点を見極める問題解決のプロセスを指します」。キークエスチョン設定のポイントは、背景を踏まえ「誰が」「どのような状態になっているか」の達成水準を、可能な限り具体化することにある。
例えば、社内で役員から広報担当者へ「顧客の高齢化が顕著なので、若年層の認知を向上させる施策を検討し、次回の社内会議でその施策と見込み効果を発表してほしい」と依頼があったとしよう。その時のキークエスチョンは一般的に「若年層の認知を向上させるためにどのような施策を打つべきか」と設定されるケースが多い。しかし、真に求められているのは「広報担当者が、若年層の認知向上のための具体的な施策について腹落ちし、社内会議で自分の言葉で語れる状態」だ。
そして、次のステップでは、ロジカルシンキングを用いて論点を構造化する。先ほどのキークエスチョンであれば、論点は「実施したとして競合他社との差別化ができるのか?」「効果をどのように測るのか?」「依頼主である経営陣の判断軸はどこにあるのか?」などに分解できるだろう。それら一つひとつの論点に答えを積み上げていくなかで、重要な論点が見えてくる。
ここで注意したいのは、この論点を「市場分析」「競合分析」などの実施事項として記載しないこと。すべてを“論点”で表現することで、論点の全体像と関係性が見え、イシューの特定が容易になる。
この例のように本書は具体例を交え、その良し悪しまで説いているほか、複数の実践問題とその解説が全ページの半分以上を占めている。これらの具体例と自身のプロセスを比較することで「何が足りなかったのか?」が明確になり、自分ゴトとして腹落ちできるよう設計されているのだ。理解の領域にとどまるのではなく、実践の場でのアウトプットを踏まえたトレーニングが積めるというわけだ。
経営と広報の関連を見える化
この構造化思考は、広報担当者が抱える予算・人員・情報などのリソース不足の問題を解決し得るインパクトを秘めている。経営観点でキークエスチョンを設定し、論点を構造化することで、経営課題と広報施策との繋がりが見える化できるため、社内理解を得られやすくなるためだ。上層部を中心としたプレゼンテーションにも役立つうえ、広報部の施策に指標と優先順位をつけられるようにもなるだろう。視座を高く持つが故に、「私たちのアクションは経営課題に貢献しているのか?」とモヤモヤを抱えている人にこそ、手にとってほしい一冊だ。

中島将貴(なかじま・まさたか)氏
早稲田大学卒業後、野村総合研究所入社。2022年ブライアリー・アンド・パートナーズ出向。2019年、米国エモリー大学にてMBA取得(修了時にマーケティング分野でトップのMBAに贈られる「米国マーケティング協会賞」を受賞)。βΓΣ(ベータ ガンマ シグマ)会員。中小企業診断士。