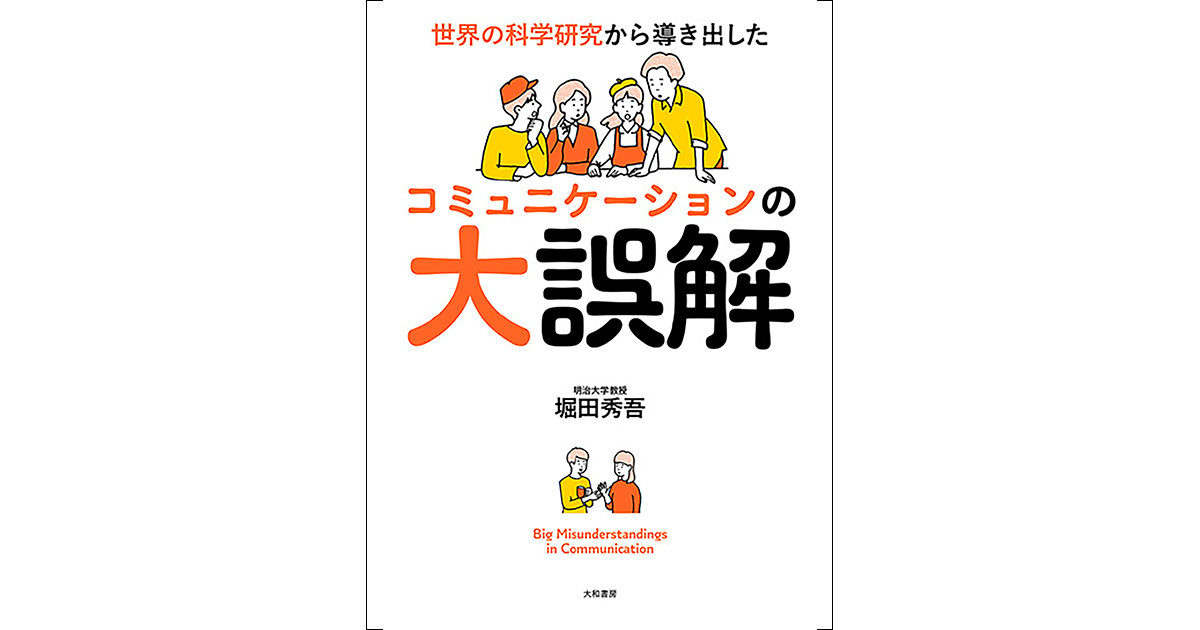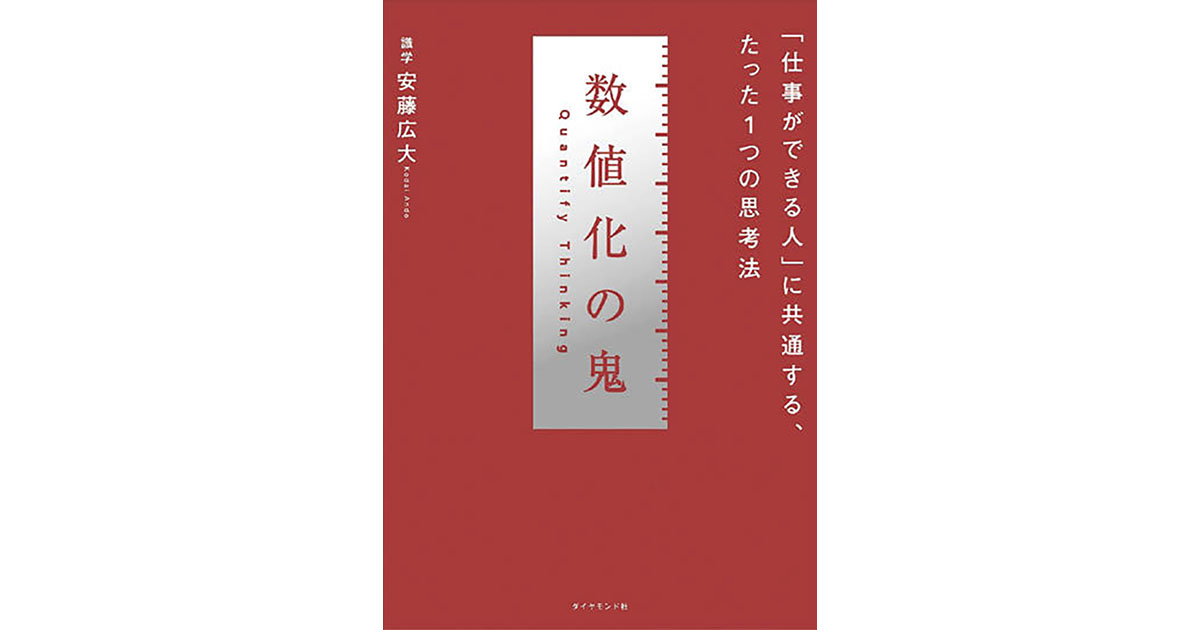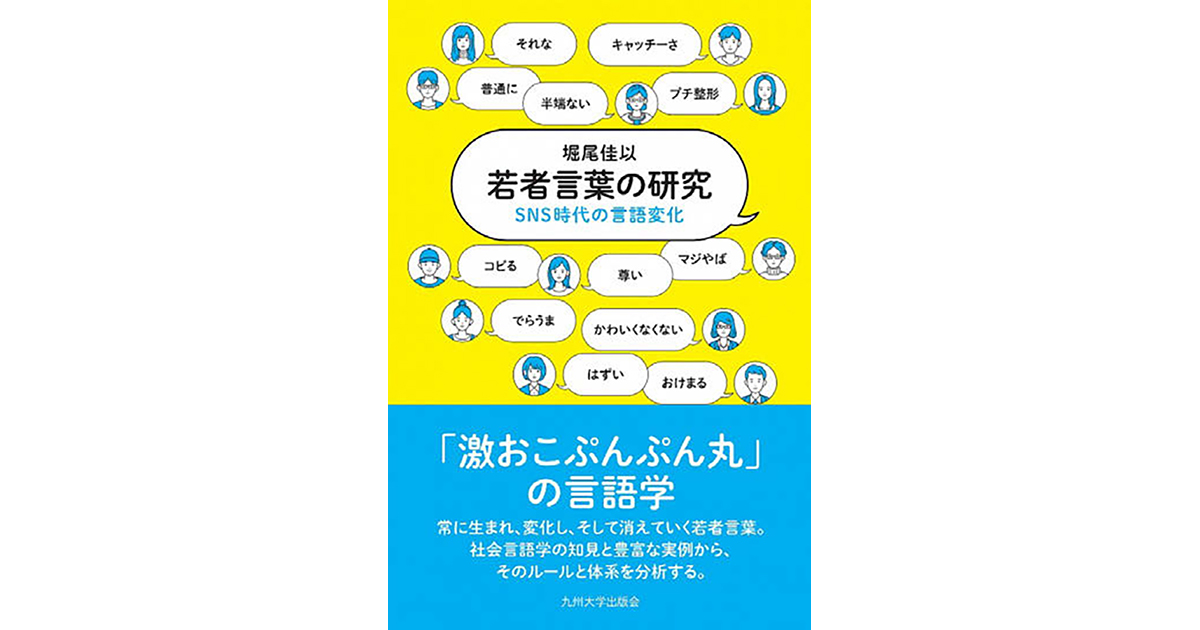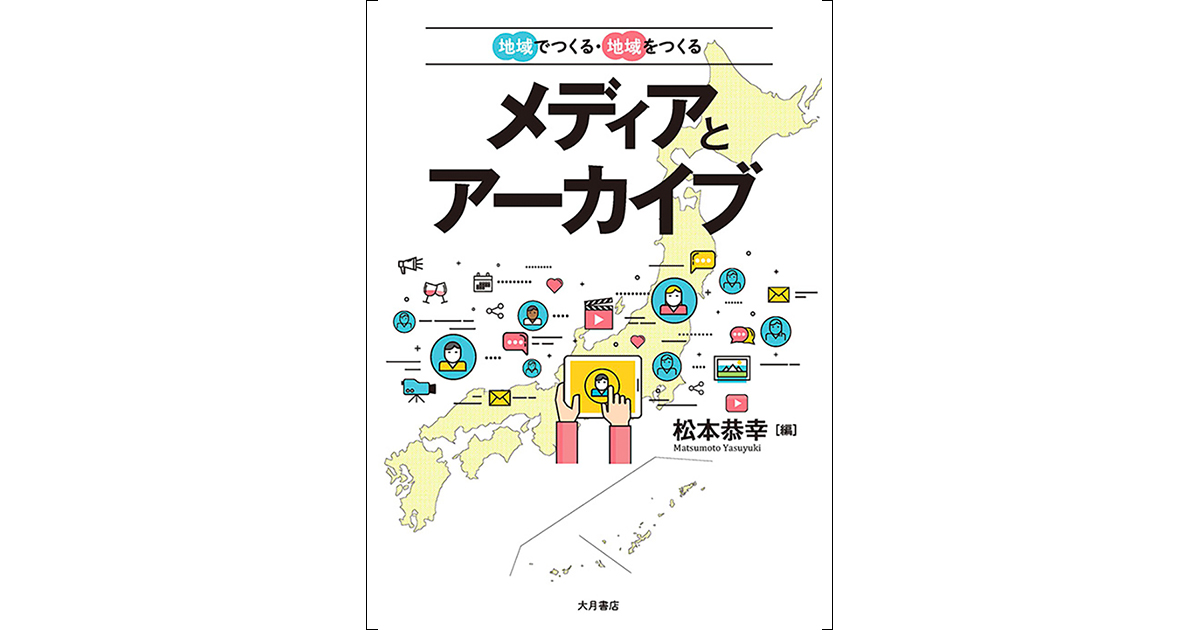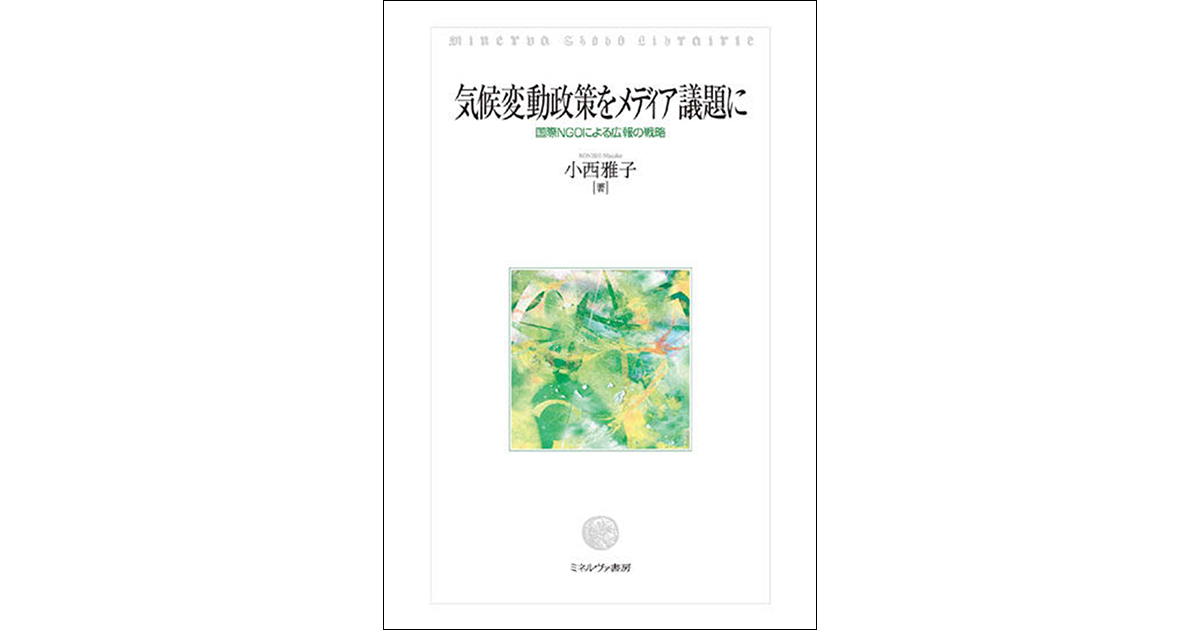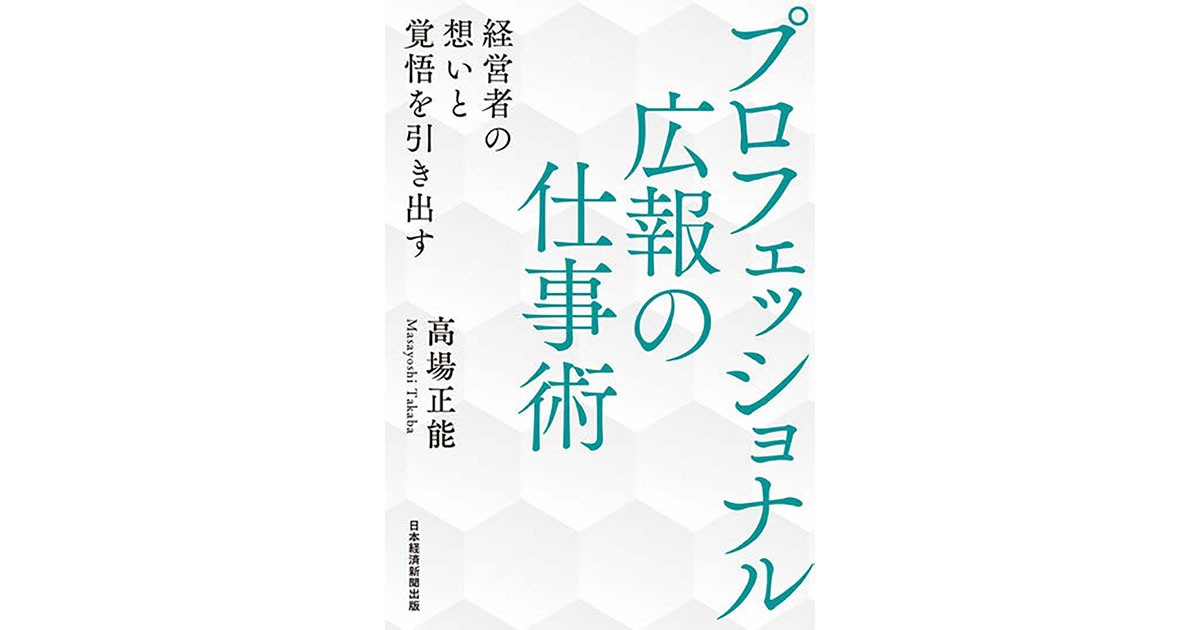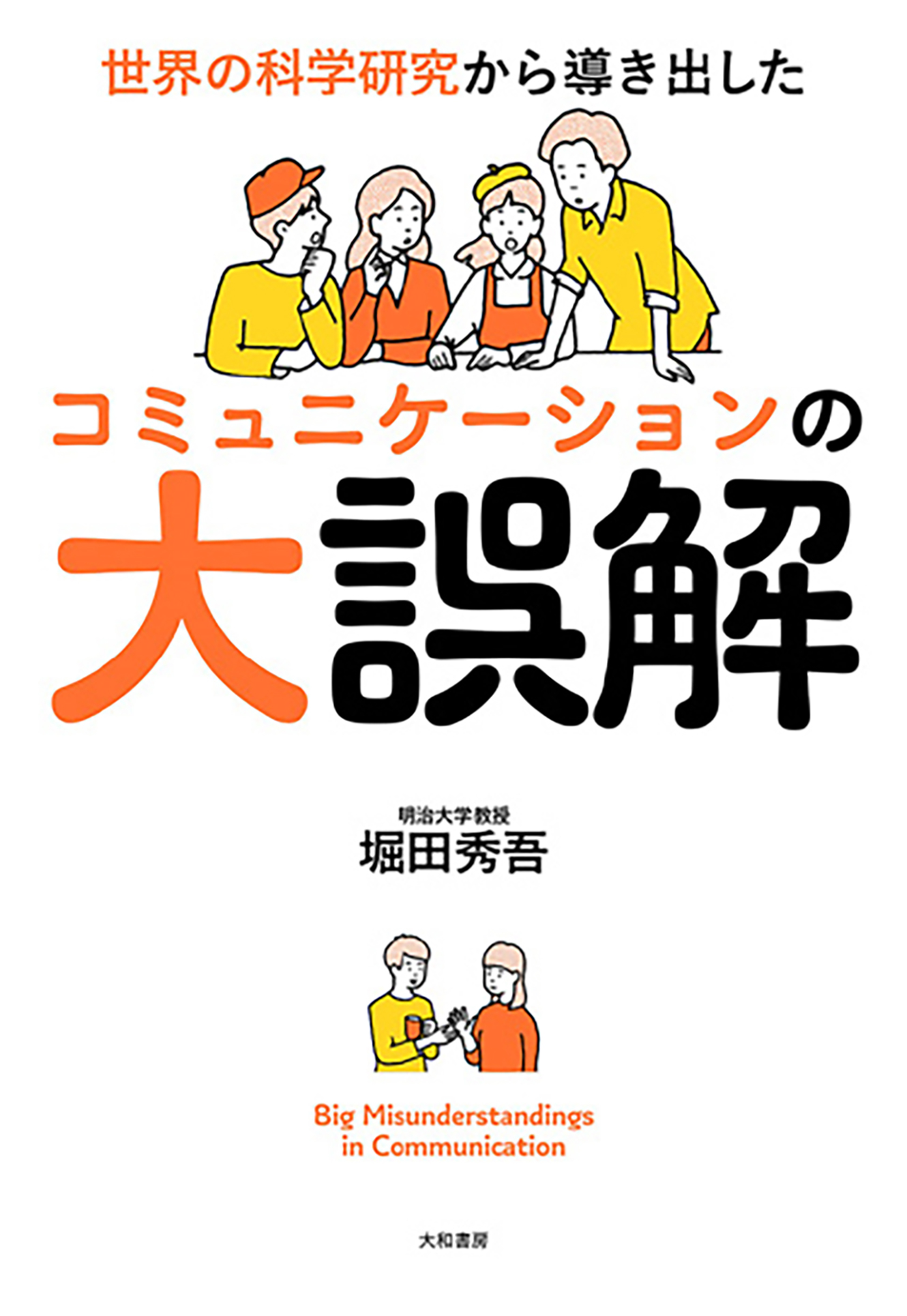
世界の科学研究から導き出した
コミュニケーションの大誤解
堀田秀吾/著
大和書房
240ページ、1650円(税込)
昨今、社員採用時に“コミュニケーション能力”を重要資質とする企業があるように、コミュニケーションは社会の中で重要視されている。しかし、深く考えてコミュニケーションを行っている人は、ほとんどいないのではないだろうか。そこで本書では、コミュニケーションに対する“一般的な思い込み”と“研究が明らかにした真実”のギャップを解き明かした。言語学・心理学が導き出したコミュニケーションの原理とは──。
言葉を発する際のルール
コミュニケーションはあくまで相手がいて初めて成立する“相互行為”である、と強調する堀田氏。
「話し上手は聞き上手というように、真にコミュニケーション能力が高い人は『受け方』も巧みです。また、自分の当たり前が相手の当たり前であるという前提が、間違っているということに注意する必要があります。バイアスを色眼鏡に例えると、人間は一人ひとり異なる組み合わせの色眼鏡を何重にもかけて世の中を見ています。だからこそ、自分と相手は住む世界が異なるのだと、前提をアップデートする必要があるでしょう。コミュニケーションには、相手が解釈する余白があり、その解釈は当事者の経験や知識により変わるため、自分の伝えたいことを100%思った通りに相手へ伝えることは難しいのです」。
しかし、できる限りコミュニケーションの齟齬は避けたい。そんな時に役立つのが、イギリスの言語学者が提唱した「協調の原理」にある4つのルールだ。情報は多すぎず少なすぎない適切な量で伝える「量のルール」、明らかに嘘だと思うことを言わない「質のルール」、話題に沿った話をする「関連性のルール」、曖昧さや分かりにくさを含む伝え方をしない「様態のルール」。
記者会見を例に挙げると、嘘をつかないのは当然だが、冗長的な説明、記者の質問への的外れな回答、明言を避ける発言など思い当たるシーンが浮かぶはずだ。この4つのルールは、それらの場面でも活かせるだろう。
事前のチェックとツールの研究
広報として事柄を正しく伝えるために、メッセージを研ぎ澄まし、細部の表現にまでこだわることは大切だ。ただ、発信前に工夫できることは他にもある。
「プレスリリースなどを発信する前に、広報のメンバーはもちろん、他部署や社外の人など、より受け手に近い人に確認してもらいましょう。また、効果的かつ効率的にコミュニケーションを図るためには、オフラインやオンライン、メール・社内報などの『媒体』と、テキスト・デザイン・写真・動画などの『伝達手段』への理解を深めるべきです。テキストでは情報の7%しか伝わらない*と述べられているように、ポイントは非言語情報をいかに活用するのか。媒体の性質により失われている可能性がある情報を意識して、それをカバーするために伝達手段の特性を活かす必要がありますね」。
*メラビアンの法則
一方で、昨今はSNSの炎上事例も数多く、言葉にはたった一言でも大きな力がある。「自分が思っているほど、またはそれ以上に、言葉には影響力があることを忘れないでほしい」と堀田氏は述べる。言葉の使い方やコミュニケーションの取り方は、まさに企業の人格を表し、アイデンティティを形成し得るものだ。今一度、媒体と伝達手段を研究し、コミュニケーションの実態を掴みながら、言葉の影響力を問い直したい。

堀田秀吾(ほった・しゅうご)氏
明治大学教授。専門は法言語学・心理言語学・コミュニケーション論。専門書に加え、研究活動において得られた知見を活かして、科学という切り口から自己啓発、ストレスコントロール、自己管理、コミュニケーション、ことわざなどに関連する書籍を刊行している。