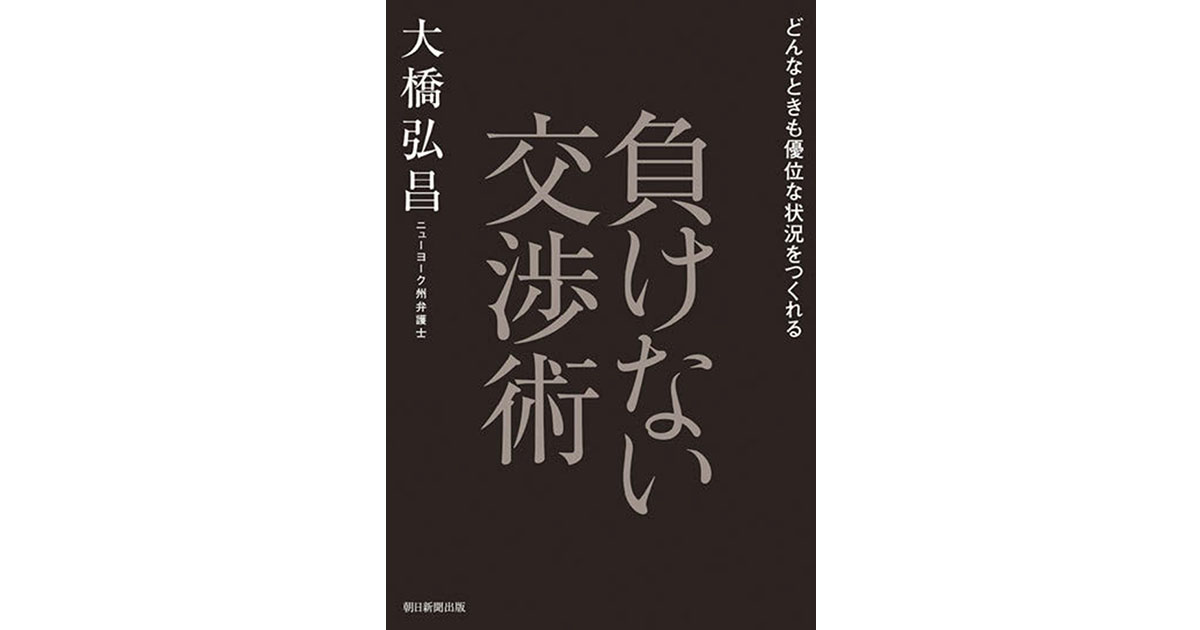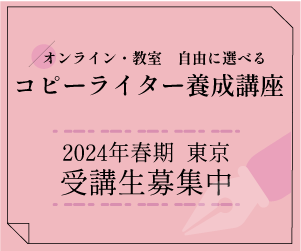共感という病
永井陽右/著
かんき出版
240ページ、1430円(税込)
NPO法人アクセプト・インターナショナル。ソマリアなどの紛争地でギャングやテロリストなどの社会復帰を支援している団体だ。本書著者が2011年、アフリカへの訪問を契機に、前身となる組織を設立。この10年、国際協力に身を置く中で、より頻繁に耳にするようになった「共感」。概して好意的に捉えられる、その“耳当たりの良い言葉”に違和感を抱くようになったという。その違和感の正体、そして、その脱却の方法を説いたのが本書『共感という病』だ。
共感されやすい表象
違和感の正体。それは、共感があれば排斥される存在もいる、という事実だ。本書でも冒頭、①道端に力なく座り込む、餓死しそうな中年男性 ②内戦に追われ難民となり、今にも餓死しそうな女の子、どちらに共感するかを問うている。この質問から、共感しやすい「表象」が存在することが分かる。それは、国際協力の領域においても例外ではない、と同氏。
「紛争地域への支援に関しても、“なんとなく共感しやすい” “かわいそうだと思える” “問題がシンプルで心にグッとくる問題”が注目されがちです。一方で、(テロリストの社会復帰など)賛否両論あり、共感しにくい問題は注目されにくい。そういった偏りを感じていたのです」。
ビジネス界隈でも使われる
そして、共感が使われるのは国際協力の領域のみではない。ビジネスの世界でも、共感の重要性は繰り返し述べられてきた。「SNS広告ひとつとっても、共感の獲得を目指し、ターゲットが10~20代ならこのインフルエンサーを使って、こういう文体にして⋯⋯と、今や形式的に決まっている印象です。プロモーション施策の、そうした思考停止の状態に一石を投じたい、との思いもありました。発信する側とユーザー側、双方が単純化された社会はどう見ても良いとは言えませんから」。
では、その解決策は。「それは理性的であることです」。共感には「認知的共感」と「情動的共感」の2種類が存在する。前者が相手の思考や感情を理性的に理解しようとする一方、後者は相手の感情を自分の感覚のように捉える。「どちらが良い悪いではない」と前置きしつつ、理性をいかに働かせて、情動的に共感してしまう“自分”を自覚することが重要だ、と著者。
「しかし、私にとってもそれは難しい。私もこの仕事の中で寄付のお願いをします。そこで、ウェブサイトを開設し、クリエイティブを制作する。その過程でデザインのレイアウト指示を行いますが、安易に共感を獲得しようとする風潮には加担したくない。例えば、共感されやすそうな写真を大きく見せて、フォトショップで加工する、といったことはやりたくありません」。
それは、実際の支援の現場でも意識していることだという。共感の輪からあぶれてしまった元テロリストたち。その背景を知ることが解決への第一歩だが、対話を拒む人もいる。そうした中で、理性的・情動に流されない「戦略的対話」を行うための経験上の心得なども本書には盛り込まれている。
広報担当者に対しては、目標数値などが予め決められた中で、ついつい共感を軸に広報してしまう、その“ままならなさ”は理解できる、と著者。しかしながら、情動的共感のみならず、理性的共感を引き出すPRの方法を模索してほしい、と語った。

永井陽右(ながい・ようすけ)氏
1991年、神奈川県生まれ。NPO法人アクセプト・インターナショナル代表理事。国連人間居住計画CVE(暴力的過激主義対策)メンター。London School of Economics and Political Science紛争研究修士。「Forbes 30 Under 30」や「King Hamad Award」など、国内外で受賞や選出多数。著書に『僕らはソマリアギャングと夢を語る「テロリストではない未来」をつくる挑戦』(英治出版)などがある。