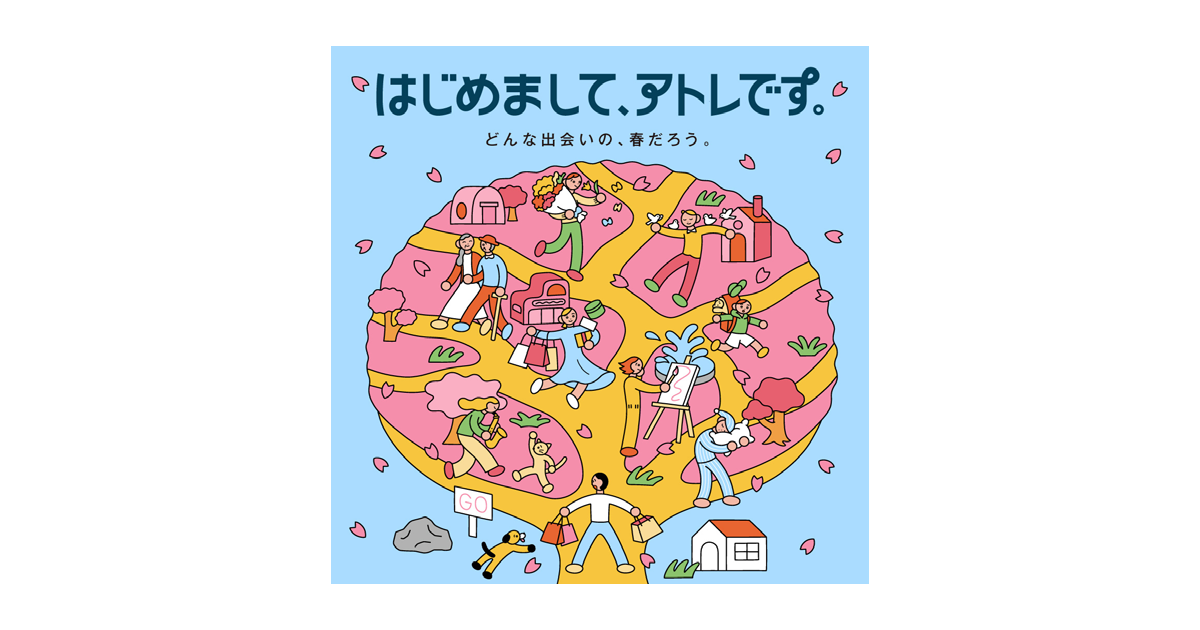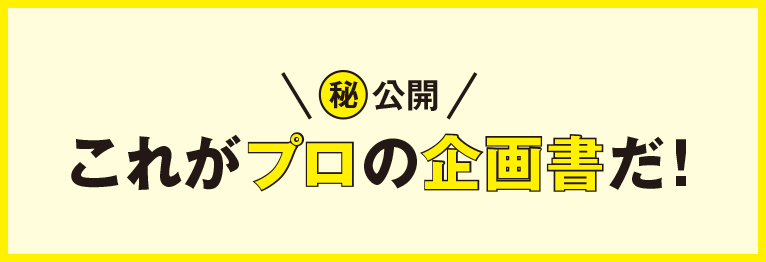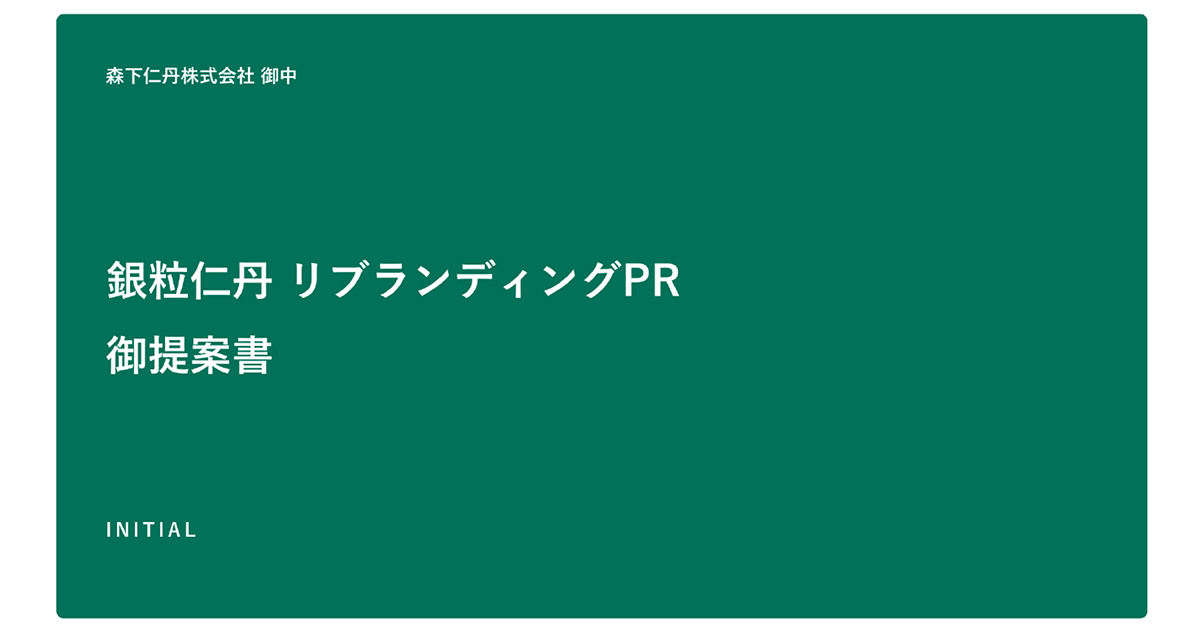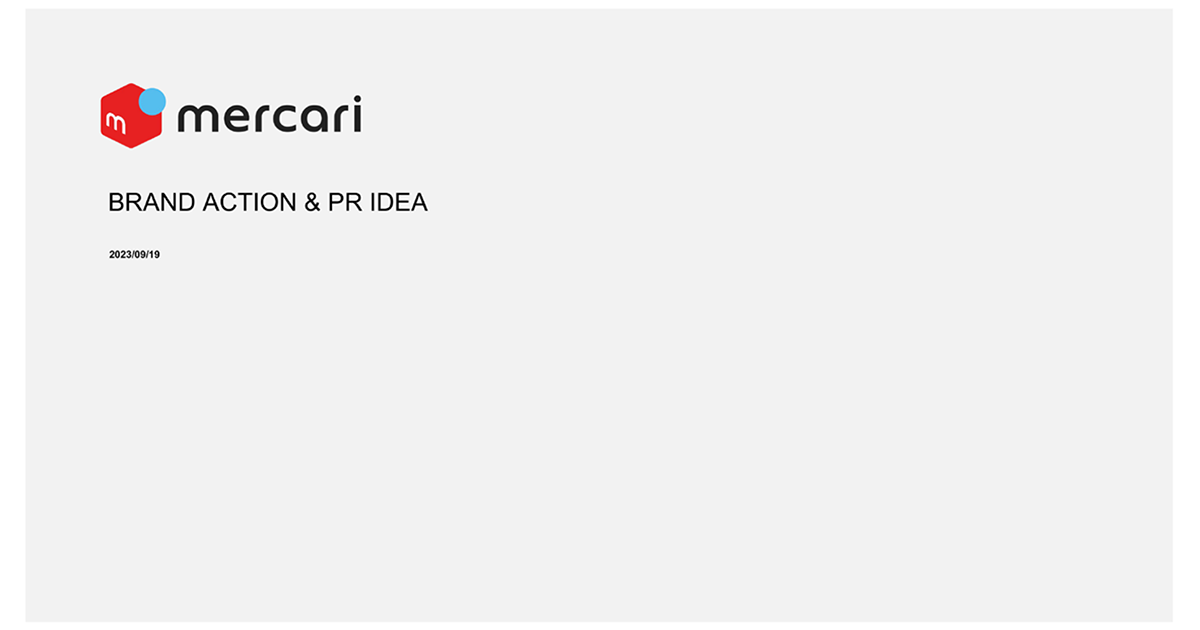顧客へ価値ある情報を発信し、いかに自分たちのサイトを魅力的に感じてもらうか。通販企業で雑誌編集に始まり、自社サイトや「楽天市場」「Yahoo!ショッピング」でEコマースに携わったのち、「All About」でメディア運営を手がけたスケールアウトの小林秀次氏に、「編集」×「EC」=メディア運営、広告運用の視点を持から、これからのECサイトのコンテンツ戦略で重要な点を聞いた。
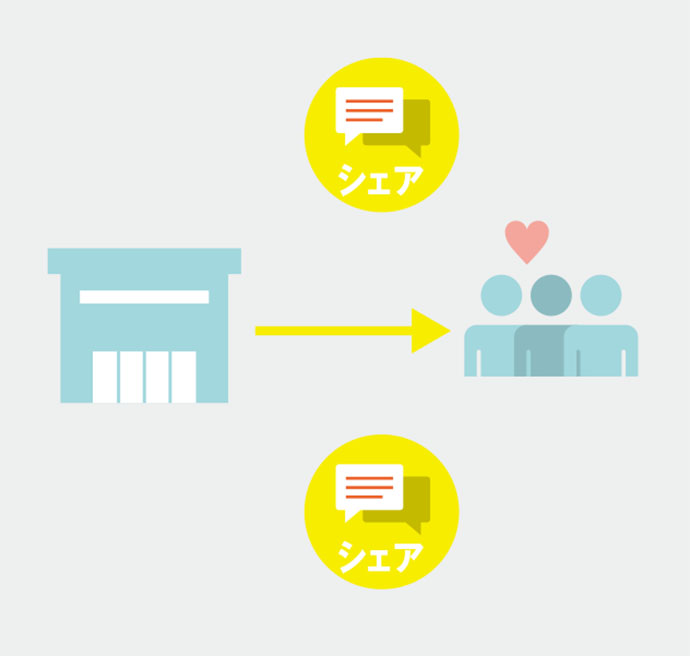
ユーザーの反応を確認
ソーシャルメディアの投稿に対する反響で、顧客の好みを知るのが最もハードルの低い方法。「A/Bテスト」を行うようにさまざまな切り口の投稿を試して反応を見る。
─Eコマースサイトでも、コンテンツを多用するケースが増えてきました。
Eコマース(EC)サイトがコンテンツを用い始めたのは、独自色を出すことが自店で買ってくれるファンづくりにつながるから、そして、そのファンを可視化しやすくなったから、ということが挙げられると思います。
モノがあふれている現在、商品を手に取ってもらうには、何か心を動かすしかけが必要です。それは実店舗でもECでも変わりません。たとえば以前、楽天市場では「店長」のキャラクターを前面に出していました。人となりがわかるメールマガジンを発行したりして、店長自身に共感を抱いてもらう取り組みでした。
さらには、店舗自体に帰属意識、ロイヤリティを感じてもらうほうが後々にとってもいい。他店舗にはないサービスや、自分たちしか持ちえていない情報などを提供するなど、店舗の特徴を生かしたコンテンツを出そうという気運が高まってきます。
他方で、テクノロジーが発展し、ユーザー分析が簡単にできるようにもなりました。いくら「親近感を持ってほしい」と考えていても、相手の顔を見ないのではコミュニケーションにはなりません。独自コンテンツを出そうというトレンドと共に、「データを見て、どんな人が来店しているのかを分析しよう」というインサイト分析のマインドも高まりはじめたのです。
なかでも最もハードルが低いのはソーシャルメディアです。既存の顧客層や新たに顧客として得たい層のことを知るのに使えます。投稿ごとに反応を見て、コンテンツの「A/Bテスト」を楽に繰り返せるようになりました。顧客に伝わりやすい、情報の切り口を探すのにうってつけのツールだと思います。
─顧客の視座に立つことが重要なのは分かるが、なかなか実現できない、という声も聞こえてきます。
人に着目しよう、顧客を起点に発想しようという考え方は、さして新しいものではありません。象徴的なフレーズが「マーケット・イン」ですが …