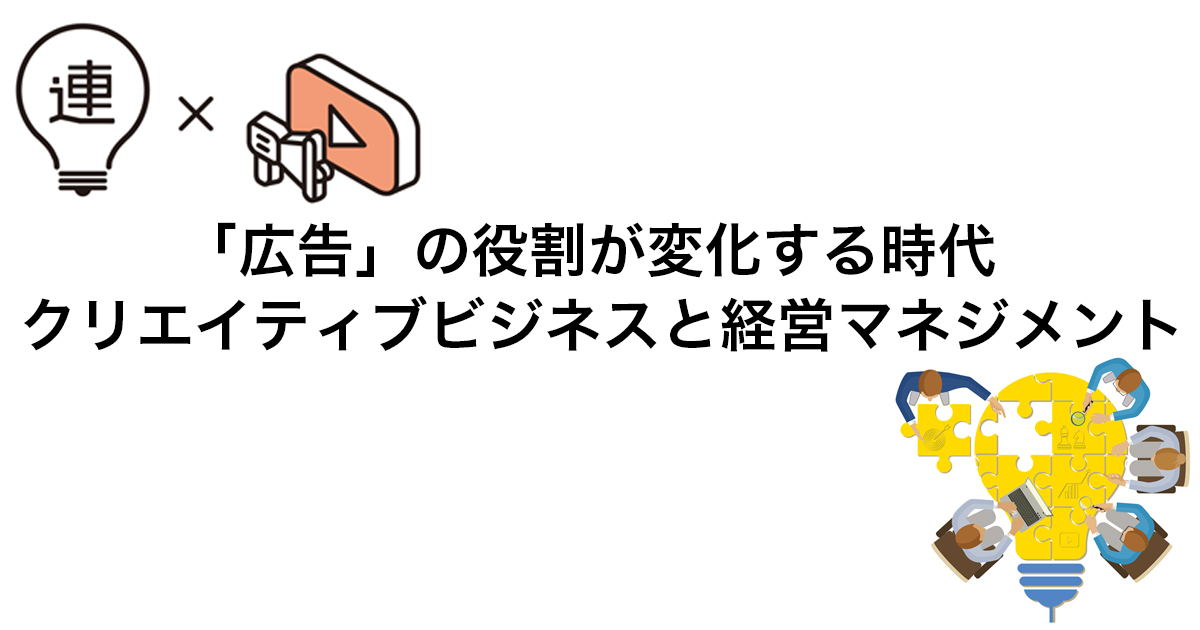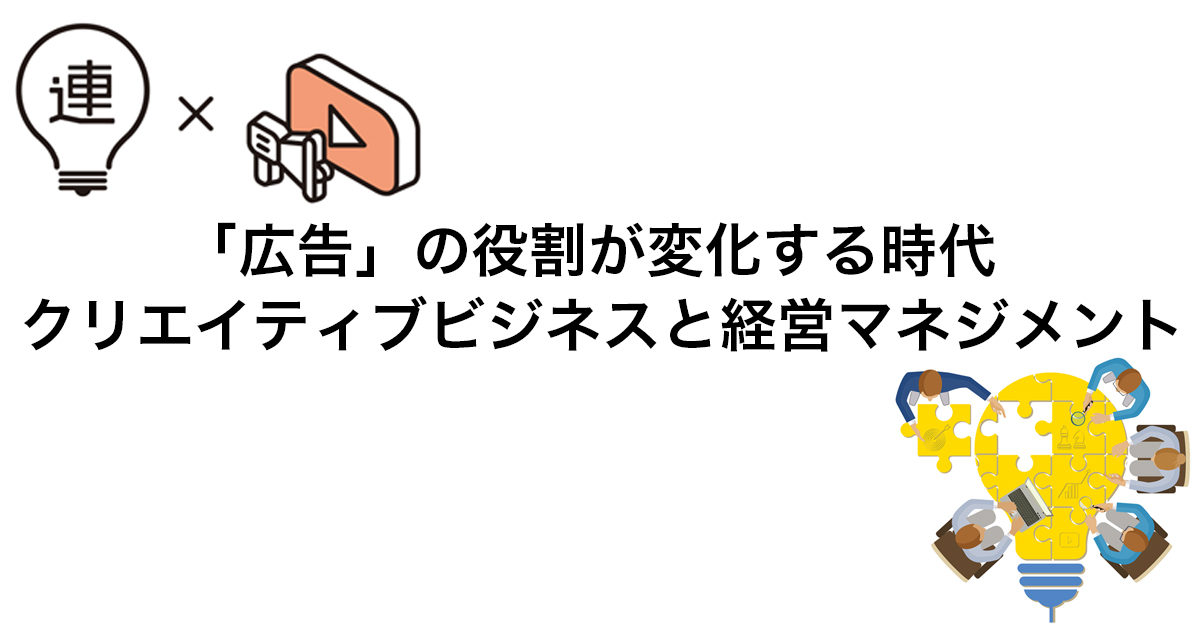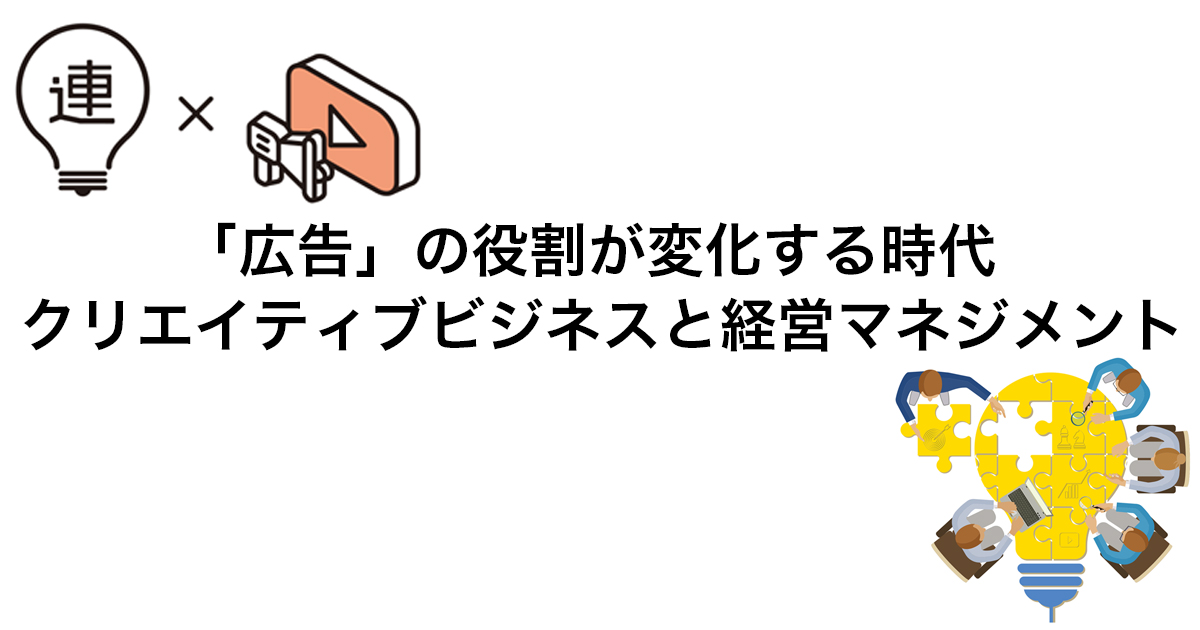マス・マーケティング全盛時代と比べると、クライアントがパートナー企業に期待する機能や役割は変化しています。「メディア枠」の提供からマーケティング課題を解決する「ソリューション」の提供へ。「広告代理店」から「マーケティング支援会社」へと進化が始まっています。広告業界のビジネスモデルが変化をしていく中で、広告業界の経営や人材マネジメントはどうあるべきなのでしょうか。
本連載は、自らイベント会社を経営し、広告産業におけるプロジェクトマネジメントの課題に直面した若村和明氏が創業した、その課題解決につなげようと開発された案件収支管理システム「プロカン」を提供するシービーティーと宣伝会議の共同企画。3回目は、デジタルマーケティング支援会社MOLTSの松尾謙吾氏に話を聞きます。
パートナーとして真価を問われる日本の広告会社
──広告業界に起きている変化をどのように捉えていますか。
いろいろ変化は起きていますが、大きく2つあると思います。ひとつは事業者側の広告に対するかかわり方です。デジタルマーケティングだと特に、広告会社に多くを任せてしまう場合とインハウスで運用するケースがあります。外注か、インハウスか⋯。これは、一定周期でトレンドが行き来していると思います。
なぜ、2つの運用方法で揺れ動くのか。その原因は人材にあります。ネット系の広告に携わる人は転職が多く、大体3年スパンで人が入れ替わります。広告会社で一定のスキルを身につけたのち、事業者側に転職するパターンが多い印象です。
もちろん、スキルが高い人は事業会社でも広告会社でも必要とされますので、激しい人材の奪い合いが起きています。デジタルマーケティングにかかわる人のすそ野は広がっていますが、優秀な人材の比率は大きくは変わっていない。常に人材不足の状況が続いているので、事業会社側でも良い人材が獲得できればインハウス化を目指しますし、それが実現しない時には、広告会社に任せる。一定周期で揺れ戻しがある背景には、業界に慢性的にある人材不足の問題があると思います。
もうひとつの変化が、クライアントである事業会社の方たちが、広告会社に対して、よりパートナーとしての立場を求めていること。そして我々は、パートナーとしての真価がより強く問われている状況にあります。
コロナ禍で多くの企業が、従来の顧客接点が失われる中で、「事業を継続させるために、いかに自社のビジネスを変化させられるか」という課題に直面しました。我々としても、これまでだったらクライアントに説明する時、例えば「こういう広告をやって、こういう集客をしたら売上が伸びる」というようなお話をさせていただくことが多かったです。しかし、コロナ禍では前例が通用しませんでした。消費者がこれまでになかったような動きをするからです。
これまでの経験だけに頼ることができず、予測も立たない環境の中で、「一体、この先どうしたらよいのか?」という課題に対し、真に相談できるパートナーを求めるクライアントが増えました。正解が分からない中でも、共に知恵を出し合えるか。広告会社には、パートナーとしての真価が問われるようになった...