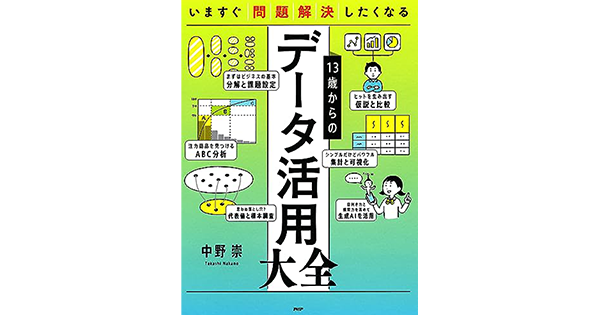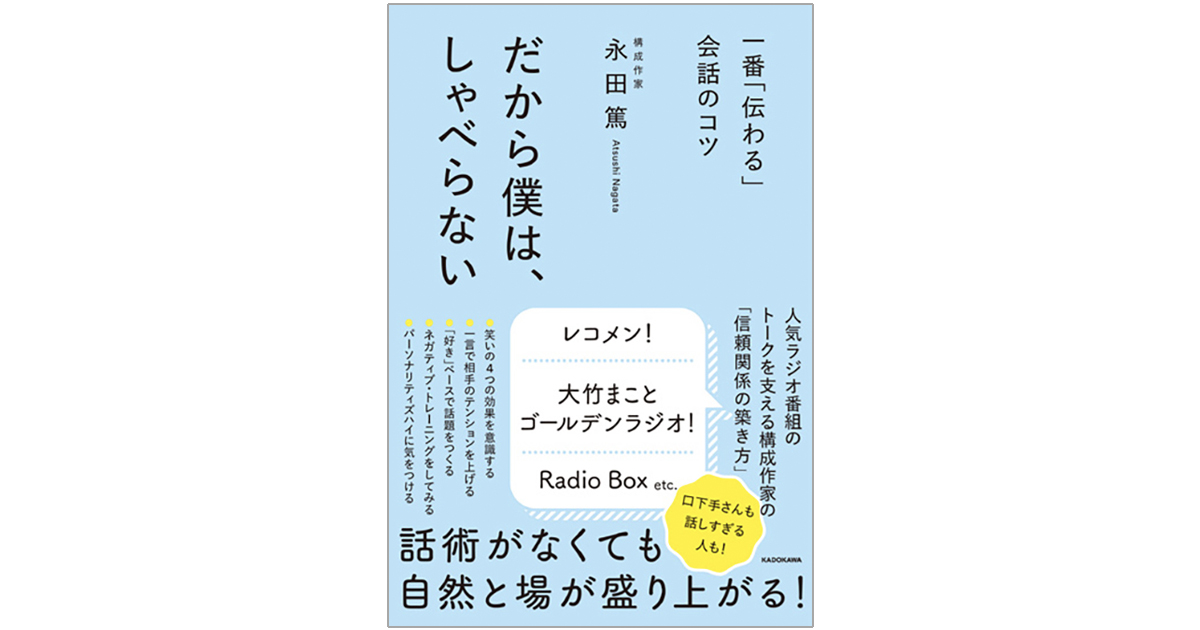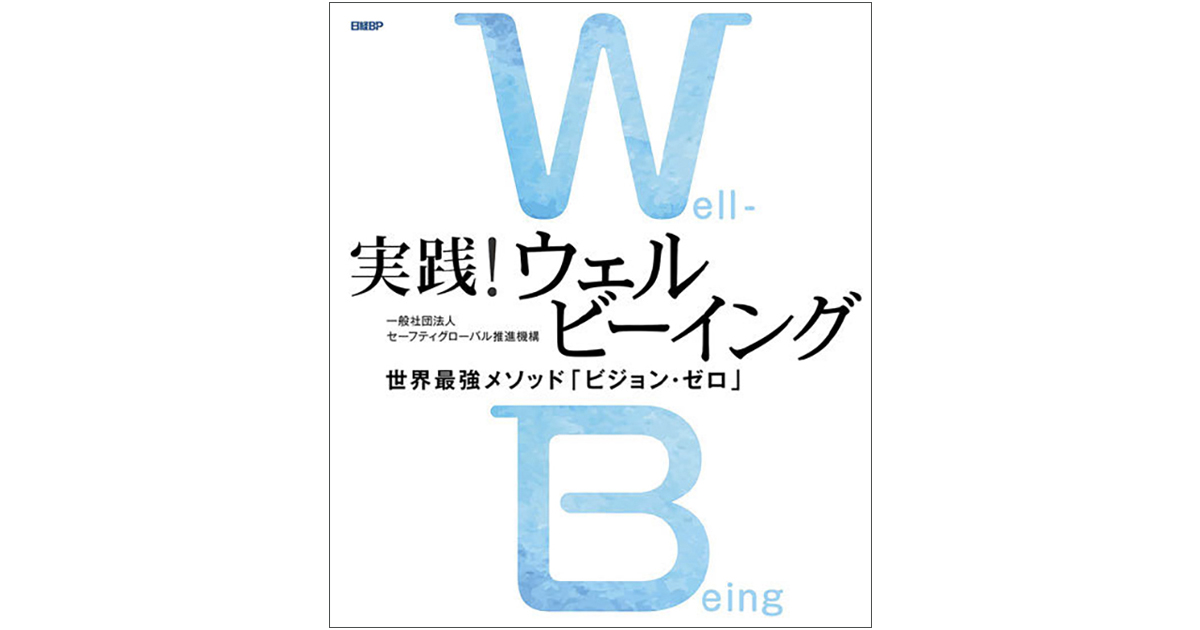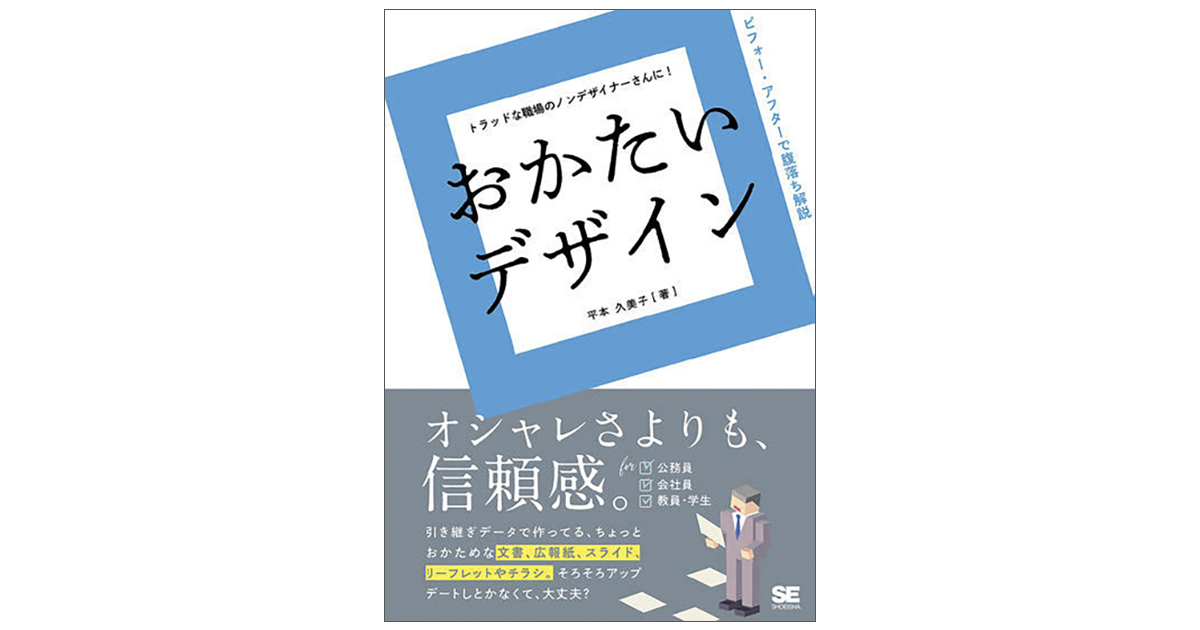いますぐ問題解決したくなる
13歳からのデータ活用大全
PHP研究所
中野 崇/著
336ページ、2640円(税込)
DXという言葉が連日聞かれる昨今。さまざまな業務がデータと連動し、データに基づき数値で語るスキルは、全ビジネスパーソンに求められるようになってきた。事実、今や小中学校ではプログラミングやデータ活用の授業が必修化している。小学4年生がクロス集計表を学ぶ時代なのだ。本書の著者であり、データ活用を軸に事業を推進してきた中野崇氏は「『数字に強い=仕事ができる』ではなく、『数字に弱い=話にならない』と判断される時代が来る」とコメントする。
この半面、「データ活用」への漠然とした苦手意識から、いまだに敬遠している人も多いのが現状だ。「ビジネスシーンで課題を迅速に解決するには、数字で語るのが最も効率的なはず。それでも数字に苦手意識のある人は、『データ活用』の効果を実感した経験が少ないからだと考えました」。そこで本書では、小中学生でも理解できる知識をベースに、「データ活用」を身近な課題の解決と結びつけて解説。その有効性を示している。
「どう生きるか」をデータで改善
中でも、最も身近な課題が「時間の使い方」だろう。何に時間を費やしているかを把握し改善するアプローチは、業務だけでなく人生の改善にも通ずる。「人生における時間の使い方は、いわば命の使い方。これを数値化すると『理想の生き方』をするために必要なアプローチが見えてきます」。
本書では、データ活用で「『楽しくない時間』を減らし『楽しい時間』を増やす」実践法を紹介。まず時間の使い方を可視化するため、時間を使っている主な行動を項目化。「楽しい時間/楽しくない時間」に分類し、1週間で各項目に費やしている時間を集計する。現状をデータ化することで、「楽しい時間を1.5倍にする」といった具体的なアプローチも見えてくるのだ。
「データ活用の基本は、このように理想と現実を数値化して客観的視点から比較し、ギャップがあればそこから課題を設定し最適化を図る。単純な構造ですが、身近な物事の改善に役立てられることを実感いただきたいです」。
グラフの精度は企業への信頼度
また広報担当者にとって、データ活用と結びつくのが「調査リリース」の発信だろう。アンケート結果などを掲載したリリースは、データを通じて状況を把握したいメディアの関心に刺さりパブリシティ獲得につながりやすい。
だが精度の低い情報を出すと、むしろ企業への不信感に直結するリスクもある。例えば、アンケートの設問設定に問題があるケースを挙げる。「お客様満足度」に関する調査なのに、有効回答数が100以下であり、また回答の母集団も「自社商品の購入経験がある人」と偏っていて、満足度が高いと謳うことを前提とした調査になっている。このような精度の低い調査の掲載は、企業の信頼性を下げかねない。
調査の信頼性を高めるためには、適切な調査対象者や回答者数の設計が欠かせない。また恣意的にならずにメディアへ訴求できる調査結果を得るためには、自社の強みを多面的に分析して、アピールする切り口を考える力、つまり「仮説構築力」が重要となる。アンケートでは、質問や選択肢に落とし込めた回答しか導き出せないのだ。
「広報担当者が発信する情報の質は、会社イメージを左右するほどの影響力があります。質を高めるためにデータの効果的な活用法を身に付け、企業価値の向上に役立てて下さい」(中野氏)。

Zoku Zoku Consulting
代表
中野 崇(なかの・たかし)氏
データドリブンな新規事業開発×組織開発の伴走型コンサルティングを提供。著書に『いちばんやさしいマーケティングの教本』等。宣伝会議の講座講師。