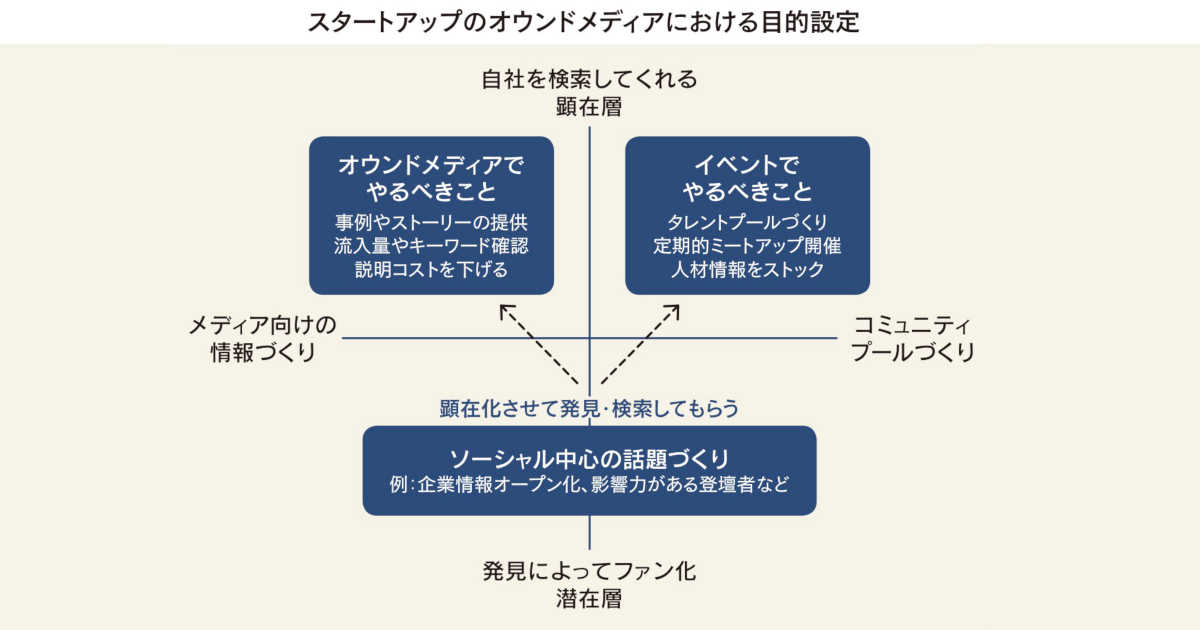オンラインの情報流通構造が複雑化し、広報の手法も変化しています。デジタルPRの基本と戦略に活かすヒントを専門家がお届けします。
今回のポイント
(1)機能より「ストーリー」で関係性を深化
(2)「主語」を意識してストーリーを考える
(3)ペルソナ設定で巻き込む関係者を決める
近年、「PRにはストーリーが重要だ」「ストーリーテリングで差別化を図ろう」といった声が聞かれるようになりました。企業や商品、ブランドに対する共感を呼ぶためには、機能性だけでなく独自のストーリーが求められます。また、認知の獲得だけではなく、中長期的に当事者意識を醸成し、ファンや応援者を増やすために欠かせない要素であるといえるでしょう。
特にネット上では感情に訴えかけるような知られざるエピソードやコンテンツは相性が良いこともあり、受け手の琴線に触れるストーリーを用いたコミュニケーションの設計が求められているのです。
一方で、それが時に「ストーリー先行」になり、実が伴っていないのではと思われるケースもしばしば見受けられます。PRに寄与する素材や行動といった事実がなければストーリーは成立しないので、その抽出が広報担当の腕の見せどころです。そこで今回は、ストーリーに必要な要素とは何か、事例を用いて考えていきたいと思います。
グリコ「液体ミルク」の場合
ひとつ目の事例は、2019年3月に発売された江崎グリコの乳児用液体ミルク「アイクレオ赤ちゃんミルク」です。競合他社からも同様の製品が発売されており、「液体ミルク」というカテゴリー自体が上半期のヒット商品にも選出されました。
液体ミルクはこれまで国に販売が認められていませんでしたが、2018年8月に規制が緩和されました。背景には、災害時の活用ニーズの高まりや父親たちの子育て参画サポート促進のためという社会的要因があります。
加えて日本ではかつて“母乳信仰”が根強く残っていましたが、働き方や子育てを取り巻く環境は大きく変化しました。「お湯や水に溶かすことなく飲める液体ミルクは、いざという時に乳児を助けることになる」というメリットとともに、その正しい使い方を広く啓蒙していく必要がありました。
特に同社の場合「子どものココロとカラダの健やかな成長」に寄与するという、創業時から受け継がれているテーマがあります。社会的背景とともに、企業姿勢とプロダクトへの理解を促すPRを展開する好機でもあったのです。実際に2019年2月には、夫婦で取り組む育児を応援する「Co育てPROJECT」も始動させていました …