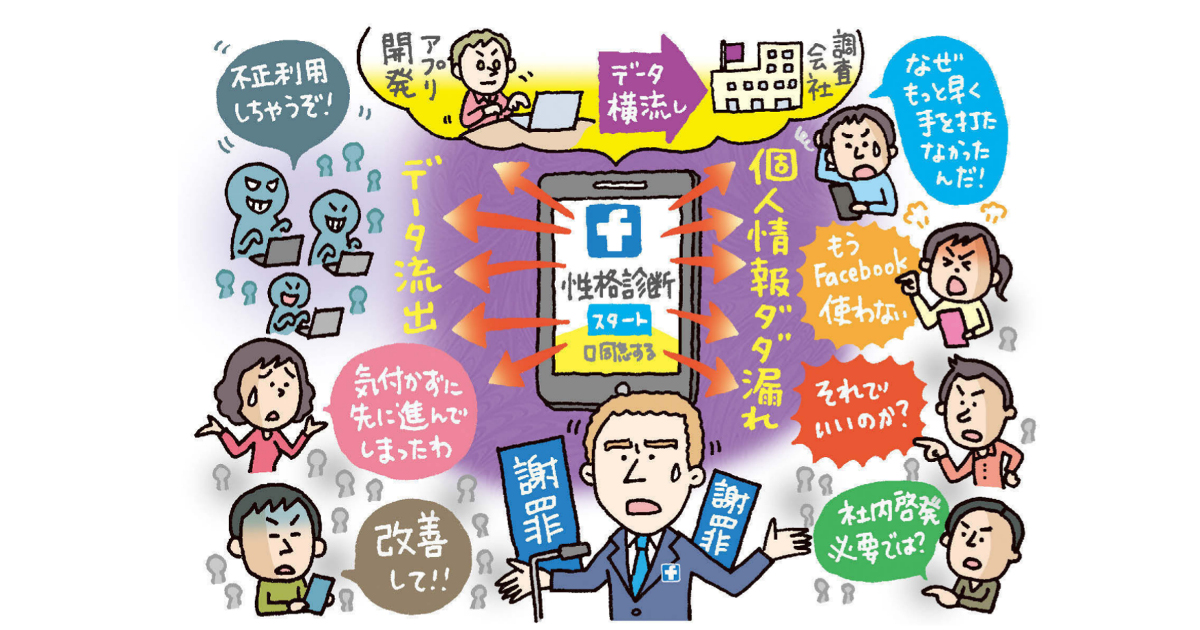ブログや掲示板、ソーシャルメディアを起点とする炎上やトラブルへの対応について事例から学びます。

イラスト/たむらかずみ
災害時に問われる企業広報
台風21号の暴風でドミノ・ピザの配達バイクが道路で立往生する動画が「さすがにこの台風での配達は無謀です」というツイートとともに、ネット上で拡散した。
明らかに危険な暴風雨の中で、ドミノ・ピザの配達バイクが立往生する動画が拡散した。数年前までならスタッフへの同情や応援メッセージが広がっていたのかもしれないが、災害の続く昨今は、安全性に対する企業姿勢を問う声の方が目立つ。災害時の企業姿勢と広報のあり方が問われたケースだった。
警戒感の中での動画拡散
6月の大阪北部地震、7月の西日本豪雨、9月の台風21号や北海道胆振東部地震などの発生により、大きな自然災害が繰り返し起きた夏だった。台風情報が出ると、企業ではスタッフに帰宅指示を出したり、学校では早期に休校を決めたりといった対応が見られた。そんな中、9月4日に猛烈な勢力の台風21号がやってきた。テレビは台風情報一色とも言える状況で、ネットには、身近な台風被害の様子がリアルタイムに次々と投稿されていた。
拡散された問題の動画も、そのひとつだった。ドミノ・ピザの配達スタッフが暴風にあおられ、乗っているバイクが前に進めず横転、道路で立ち往生する様子を捉えたものだ。ネット上では、「スタッフが気の毒」「頼む方もおかしい」「従業員の方が命知らず」など様々なコメントが見られた。
一方で、宅配ピザ店にとって、荒天時は稼ぎ時なのだという。それに加えてフランチャイズ型の場合、オーナーや店長に判断を委ねる要素も大きいのかもしれない。しかしそれも理解した上で、それぞれのレベルでしっかりとした災害時の方針を持ち、見直しを続けながらスタッフの安全配慮に十分注意した最適な運用の形を模索していく必要性が高まっている。
危機対応時こそ積極的な発信を
今回のケースでもうひとつ注目したいのは、同業他社の対応を比較する記事が出たことだ。ピザチェーン各社に台風時の方針と台風21号における実際の対応について3つの質問をし、その結果をまとめたものだった。読むと、企業の方針はもちろん、広報コメントが生む印象の差も小さくなかった。
記事内で、渦中のドミノ・ピザは「『安全基準に則り各店舗を営業しています』とのみ回答」と記載されたのに対して、ピザーラ、ピザハット、ナポリの窯、シカゴピザは情報量には差があるものの、自社の対応と考え方について3つそれぞれの質問にコメントしたものが掲載されていた。いずれも広報が返信した表現のままと思われる。
冷静に考えれば、ドミノ・ピザにとっては、動画が拡散する中で少しでも情報をアップデートして伝えたい状況だろう。あの配達員は無事なのか、店の安全管理についての考え方はどうなのか。企業としてのメッセージを伝える極めて限られた重要なタイミングではなかっただろうか。
リスクに際し、広報はできるだけそれを小さな扱いの報道に留めたいという意識が働くが、今回のように他社と比較されたとき、それが裏目に出るリスクも踏まえておく必要がある。
社会情報大学院大学 客員教授・ビーンスター 代表取締役社会情報大学院大学客員教授。米コロンビア大学院(国際広報)卒。国連機関、ソニーなどでの広報経験を経て独立、ビーンスターを設立。中小企業から国会までを舞台に幅広くコミュニケーションのプロジェクトに取り組む。著書はシリーズ60万部のベストセラー『頭のいい説明「すぐできる」コツ』(三笠書房)など多数。個人の公式サイトはhttp://tsuruno.net |