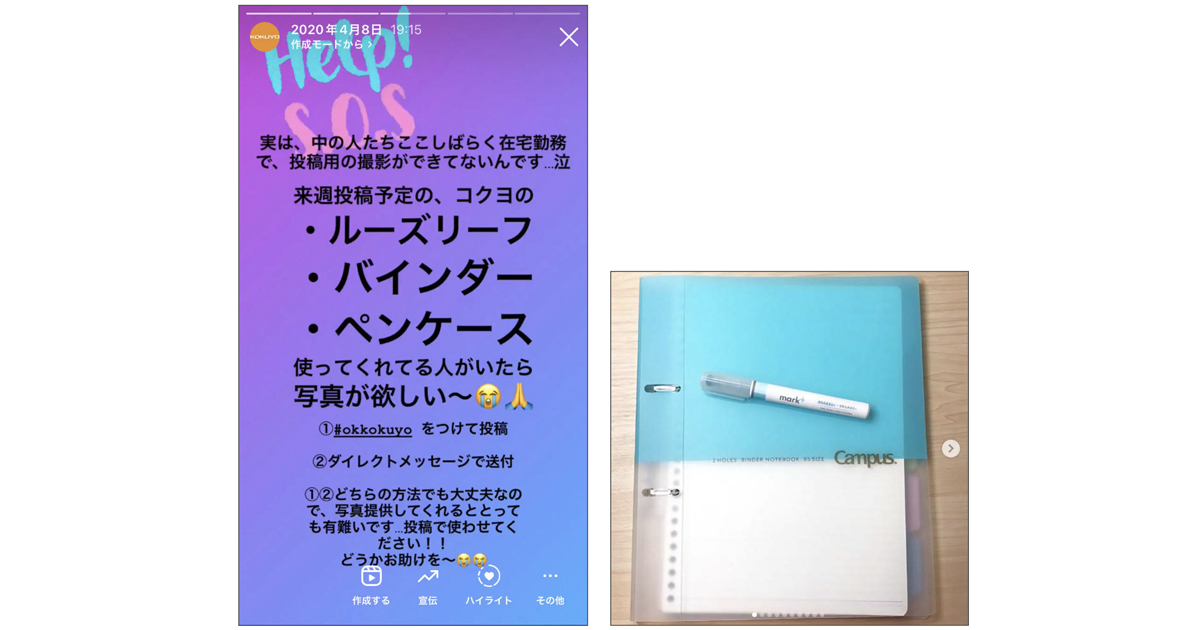ファンとの直接的なつながりを求めて開設したものの、運営し続けることが難しく、数年でクローズしてしまうオウンドメディアも少なくない。キリンホールディングスの平山高敏氏が「持続的なオウンドメディア」のポイントを話す。
自社で情報のコントロールができ、かつ生活者をはじめとするステークホルダーとの直接的な接点を築くことができるオウンドメディアに、BtoC、BtoB問わず企業からの注目が集まっている。しかし、それぞれ企業によって運用目的が異なるため、いざオウンドメディアを始めようと、運用の参考例を探そうとしても自社と近しいものはなかなか見つからなかったり、「始めたものの、コンテンツがつくれず更新頻度が上げられない」といった悩みを持つ担当者もいるのではないか。
キリンホールディングス コーポレートコミュニケーション部に所属する平山高敏氏は、同社のオウンドメディア「KIRINto」「note 公式アカウント」などを運営し、インハウスエディターの育成も実施。1月には書籍『ステークホルダーを巻き込みファンをつくる!オウンドメディア進化論』(宣伝会議)を刊行し、そこではオウンドメディア立ち上げの「適切なアプローチ」から、持続的なオウンドメディア運用、オウンドメディアが果たすことのできる役割について綴っている。

「KIRIN公式 note」の記事は、インターナルブランディングや採用など、副次的な効果も生み出している。
社会的潮流とオウンドメディア
オウンドメディアは現在、大きく分類すると2つの方向へ向かっていると平山氏は話す。ひとつは新規顧客の獲得や、既存顧客との深い絆づくりのために行われる「マーケティング的活用」。そしてもうひとつが、企業への信頼醸成やイメージ獲得を目的とした「コーポレートコミュニケーション的活用」だ。
2010年代前半にオウンドメディアが“ブーム”となった時期には、マーケティング的活用のメディアが多く生まれたが、2019年に始まったトヨタ自動車の「トヨタイムズ」やユニクロの「LifeWear magazine」などを契機に、企業の「インターナル(内側)」をオープンにするメディアが現れ、「コーポレートコミュニケーション的活用」としてのオウンドメディアが見られ始めた。
この背景にはSDGsやソーシャルイシューへの関心の高まりという社会的潮流があり、「社会の一員としての振る舞い」が企業にも求められるようになったことが影響していると平山氏は話す。
従来のオウンドメディアが「企業・商品起点」だったのに対し、新しいオウンドメディアは「社会・個人起点」であることが特徴だという。
「続くメディア」の理想形とは
平山氏が考えるオウンドメディアの役割とは、「企業の中にある資産を、お客さまに...