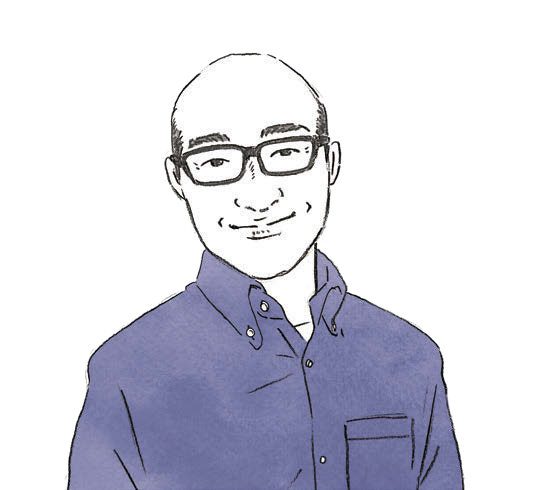"
共同行為において「タダ乗り」はさせない
私は現在、1年間の予定でイタリアに居住している。楽しみのひとつは、ドラマ『VIVANT』を鑑賞することだ。10年前に流行った『半沢直樹』もU-NEXTで観た。非常に面白い。
大手銀行を舞台にして、腹黒上司とその取り巻きに敢然と立ち向かう半沢直樹とその仲間たち。一難去ってまた一難。その過程で仲間の信頼と結束は強まっていく―。このコラムのテーマと何の関係があるのか?『VIVANT』や『半沢直樹』の演出などを手掛けたのは福澤克雄という人物。実は、彼は福澤諭吉の子孫で、幼稚舎から大学まで慶應義塾で学んだ塾員だ。歴史と伝統を受け継ぐために、この世に生を受けた「生ける慶應義塾」である(ように私には思える)。『半沢直樹』原作者の池井戸潤もまた慶應の塾員で、慶應閥の三菱銀行に勤務していた。波乱万丈の物語は現実世界にもある。
明治初頭の慶應義塾は、小規模ながら全国から塾生を集め、主に福澤諭吉の資産と授業料収入で運営されていた。1877年に西南戦争が起きると、その余波で塾生が激減。当時は脆弱な経営基盤だったために、慶應は廃塾の危機に直面した。諭吉は幾度も政府に資金援助を要請。
その中には、当時大蔵卿(現在の財務大臣のような存在)で親交があった大隈重信も含まれる。直筆の書簡の中には、慶應義塾が社会に果たす役割の有…
あと57%