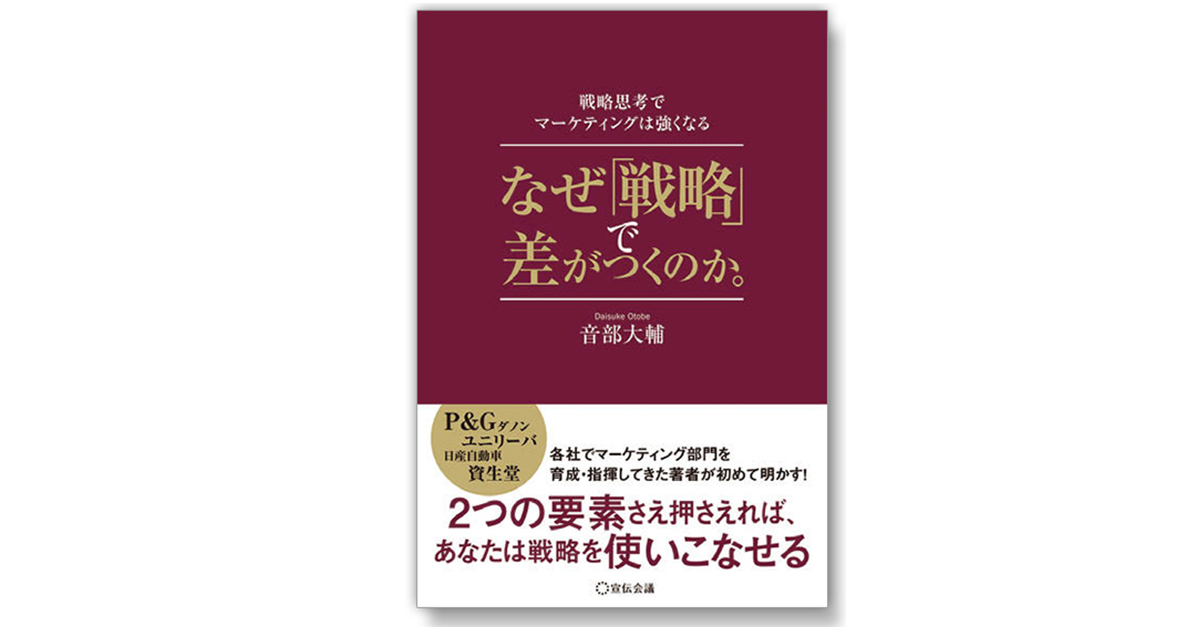約300社の有力な広告主企業・団体が参加する、日本アドバタイザーズ協会は2016年11月、新たに「デジタルメディア委員会」を設立した。本委員会の活動を通じて見えてくる、広告主、そして広告業、メディアが知るべき課題と未来展望とは。
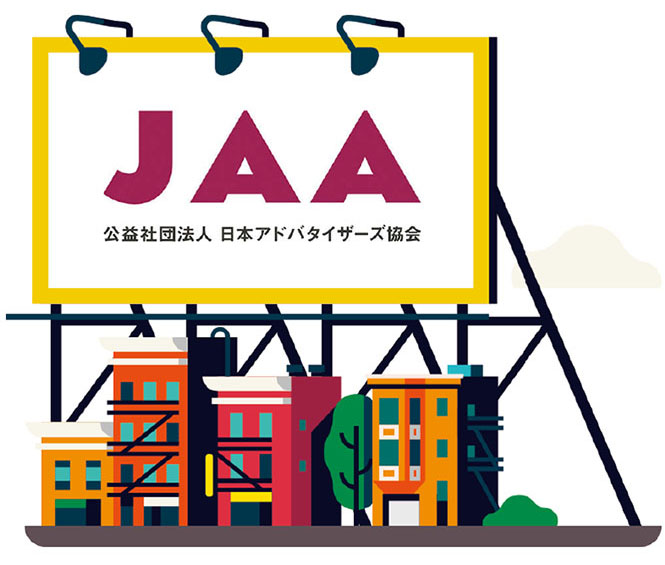
コミュニケーション量の理解にズレ デジタル投資も含めた商談を
連載1回目では、2017年の春に「デジタルメディア委員会」内に立ち上がった「取引適正化・透明性」と「効果の可視化」の2つのワーキンググループについて紹介しました。今回は「効果の可視化」チームの新たな動きについて取り上げます。本チームは発足以来、特に消費財メーカーの小売流通企業に対する棚割り交渉の際のコミュニケーションギャップの解消に向けた活動に力を入れてきました。
小売流通企業が仕入れ量や棚割りを決める際には、消費財メーカーのコミュニケーション投資の量がひとつの判断基準に使われてきました。しかし、ここでのコミュニケーション投資とは、テレビが中心。消費財メーカーがデジタル広告への投資も増やしている環境下で、小売流通企業と消費財メーカーとの間でコミュニケーション規模の認識にズレが生まれていました。
今のままだとデジタル広告の施策が効果を発揮して店舗への送客につながったとしても、商品が陳列されていないことも想定され、メーカーにとっても小売流通企業にとっても、機会損失につながりかねません。この課題を解決するために、テレビだけではなく、デジタルも含めてコミュニケーション投資と捉えてもらう認識を広げていく活動が必要となっていました。
しかし、この活動を進める上では世帯視聴率ベースのテレビと、到達人数ベースのデジタル広告を同じ指標で表現できるようにしなければなりません。昨今、テレビ局各社もネット配信に力を入れ、テレビの世界にも個人ベースでのカウントの方法が浸透していくだろうという環境下ですので、最終的にテレビもデジタルも「ターゲットに対して何人に、何回表示するか」の実数ベースでの表現に統一することになりました。
ただ、この場合のデジタル広告は動画広告のみを対象にし、尺の長さ、視聴デバイスの違いは考慮しないことにしました。
また世帯GRP量を到達人数と回数ベースに換算する方法が、会社によって異なっては、新しいスタイル(指標)の定着につながりません。そこでJAAとして換算表を作成して、2018年1月にJAA加盟各社に配布する予定です。商談における新しい方法を浸透させる上では、広告主がデジタルの量把握の考え方を統一し、共通の換算表を皆で採用するなど、足並みを揃えることが必要です。だからこそJAAが取り組むべき重要な活動だと考えています。

デジタルメディア委員会 委員長
資生堂ジャパン コミュニケーション統括部長
小出 誠氏