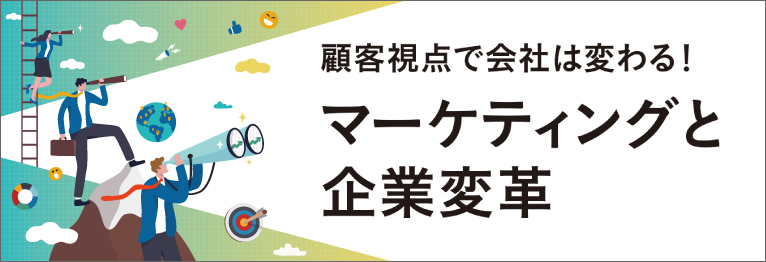時代の逆風を受け、一時は売上がピーク時の3分の1まで低迷したという岩下食品。先代から同社を継承した岩下和了氏は、SNSを駆使したコミュニケーションを実践している。岩下氏が描いた戦略について話を聞いた。

岩下食品
代表取締役社長
岩下和了氏
モノが余る時代にマーケティングの必要性を痛感
「岩下の新生姜」をはじめとする食品の製造・販売を行う岩下食品。1990年代後半に歴代売上のピークに達した同社であったが、2004年に社長業を継承した岩下和了氏は、就任時の様子を次のように語る。
「先代社長の時代は、『つくれば売れる』高度経済成長期ならではの売り手市場でした。ところが時代が変わり、モノが余るように。漬物市場の縮小という課題もあり、売上は下降傾向にありました」(岩下氏)。
伝統食品である漬物は、主要な消費者の高年齢化や若者離れが起こっていた。このような状況下でこれまでと同様の戦略は通用せず、顧客とのコミュニケーションを工夫しなければならないと岩下氏は考えた。
「従来の『送り手こそが商品を一番よく知るプロなのだから、いいものを送り出しさえすればよい』というプッシュ型のビジネスから、『お客さまこそが購入を決定するのだから、買いたいと思われるものをつくらなければいけない』というプル型のビジネスへと方向転換しなければならないという危機感がありました。そのために立ち戻ったのが、『お客さまの立場で考える』という、マーケティングの基本でした」。
岩下氏は「お客さまの立場で考える」ためには、顧客の生の声を聞く必要があると考えた。しかし、当時顧客の声を集める手法は、同社のお客さま相談室への電話か、折り込みハガキによるアンケート調査などしか存在しなかった。それらの手法に関しても、問い合わせなどを除く純粋な商品への感想の数はとても少なく、収集にも時間がかかり、声を施策に落とし込むまでにタイムラグが発生してしまう状態であった。
Twitterアカウントを始動 1日1000件を超える声が集まる
顧客とのコミュニケーション方法を模索していた岩下氏だったが、その後、世の中にSNSが普及。SNS内では「岩下の新生姜」に対しても自然とユーザーからのコメントが発生していることに気づいたという。
岩下氏は2010年に...