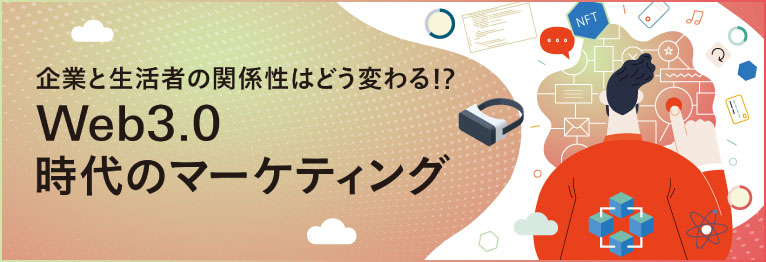トークンを活用したマーケティング施策は、ハイファッションブランドやアートなど、モノの「所有」そのものに意味がある業界で進んでいる印象がある。しかし、企業が現在注力するポストクッキー時代のデータ利活用においても有効な手段となり得ることは知っておきたい。ここでは、SUSHI TOP MARKETING代表取締役CEO徳永大輔氏にマーケティングにおけるトークン活用の可能性を聞く。
世界が模索するトークン活用マーケティング
NFTやWeb3.0という言葉は2021年頃から世に出て、多くの人が知る言葉となりました。しかし、NFTやFT(=仮想通貨)の総称である「トークン」や大元のブロックチェーン技術をどのように活用して私たちの生活にインパクトを生むのかという問題に対しては、多くの企業がいまだに模索し続けています。
そんな中、2022年後半に世に出た「スターバックスオデッセイ」に端を発するロイヤルティマーケティング手段としてのNFT施策は、企業がトークンを活用する上で、ひとつの方向性を示しました。
本施策は、スターバックスからNFTを受け取った消費者が店舗などで「ジャーニー」と呼ばれる特別な体験を受けることができます。「ジャーニー」は店舗でコーヒーを淹れる体験からコーヒー豆の産地の農場へ旅するものまで様々。トークンを所有する消費者はこれらの「ジャーニー」を通じてロイヤルティの高いファンへと醸成されるのです。
トークン活用のメリットは、消費者が受け取ったトークンを他人へ譲渡・転売できることや、企業が後付けでコンテンツを増やせること。エアドロップでのトークン送付など、従来では難しかったことが可能になることです。スターバックスは顧客コミュニケーションにトークンを介在させることで、「体験」を通じたロイヤルティが高いファン醸成に成功したのです。
「デジタルオーナーシップ」と「トークングラフ」とは
マーケティングにおけるトークン活用の可能性を考える前提として、トークン、ひいてはブロックチェーンが介在することで私たちとインターネットの間にどのような関係性が生まれたのかを考えてみます。
「Web3.0」は、一言で表すと「市民が分割所有するインターネット」と言えます。従来はGAFAMのような巨大プラットフォーマーが私たちのデータを独占的に彼らのデータベース内で支配していましたが、ブロックチェーンといういわば、オープン/透明/パブリックなデータベースの登場により、個人は本当の意味でデジタルデータを所有できるようになりました。これが「デジタルオーナーシップ」です。
例えばソシャゲに100万円課金したとして...